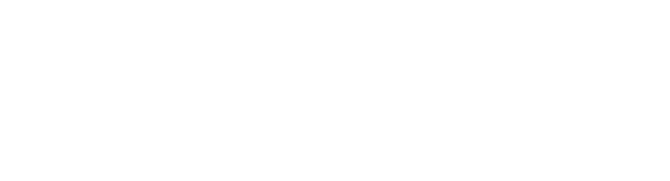大学の農系学部が研究・開発した製品と、その製品化までの道のりを紹介します。
第17回
都市に環境にやさしい木造建築を
純木造建築を実現する
東京農工大学の耐火集成材

日本で古くから親しまれてきた木造建築。近年は、森林循環や脱炭素という観点からも建築物への木材利用が見直されています。しかし、都市で見かける大規模建築物の多くは、鉄鋼や鉄筋コンクリートを主要な資材として造られています。それは、建物が密集する都市部において、木造建築物は耐火性能に課題があるというこれまでの経験から敬遠されてしまったことが理由のひとつです。このため、耐火性能を有する新木造技術の開発が期待されてきました。こうした課題に対し、東京農工大学、(有)ティー・イー・コンサルティング、森林総合研究所、鹿島建設(株)の産学官連携の研究によって誕生したのが、国産スギ材を利用した耐火集成材「FR ウッド®︎」です。今回は、その開発までの道のりを紹介します。
純木造建築を実現する
耐火集成材
2001年から服部順昭名誉教授を中心にはじまった東京農工大学の耐火集成材の研究は、同名誉教授のもとに、(有)ティー・イー・コンサルティングから、木材のみで構成された耐火集成材を作るには難燃薬剤を均一に注入する必要があるので、それに使えそうなレーザインサイジング技術(レーザで木材に穴を開ける手法)を用いて開発しないかという相談を持ちかけられたことがきっかけでした。
大規模な建築物や不特定多数の人が利用する建築物を建築するためには、防火の観点から一定の耐火性能を満たすことが必要になります。
森林総合研究所も耐火の基本技術で開発に加わり、約10数年もの開発期間を経て、国内唯一の国産スギだけで構成される耐火集成材の開発に成功し、特許取得後に、「FR ウッド®」として使われることになりました。

ラミナへのレーザインサイジング
耐火集成材の種類
まず、耐火集成材にはどんな種類があるのでしょうか。現在、国内で普及している耐火集成材は、主に以下の3タイプに分けられます。
a
集成材被覆型

集成材被覆鉄骨
断面(mm):240×240
荷重支持部となる鉄骨構造材の周りを、木材で被覆した耐火集成材。荷重を受ける部分は鉄骨となるため、建築構造上は木造ではなく鉄骨造となります。
b
被覆(メンブレン)型

強化石膏ボード被覆
断面(mm):244×244
木材の周りを耐火性能のある石膏ボードで被覆した耐火集成材。表面が木材ではなく、見た目が木造に見えないため、化粧板を貼っています。
c
燃え止まり型

モルタル板挿入
断面(mm):472×472
荷重支持部となる木材の周囲に、難燃薬剤を注入した木材(難燃処理層)やモルタルの挿入等による燃え止まり層を配置することで、耐火性能を確保しています。発熱源の量を抑えて白華を防止するために、所定厚さの無処理木材を化粧材として表面に貼ることで、「FRウッド®︎」は見た目も構造上も100パーセント木造となります。
次に、耐火集成材が、耐火性能を満たすためには、どのような条件が必要なのでしょう?
「1時間耐火構造の場合、耐火試験炉の中に入れた耐火集成材をISOに規定されている温度曲線に従って炉内で1時間加熱します。そして加熱終了後は、自然鎮火しなければいけません。また、耐火集成材の中心となる荷重支持部のいちばん外側の温度が260度を超えないこと、そして荷重支持部の表面が変色していないことが条件となります」と服部名誉教授。
では一体、「FR ウッド®︎」はどんな技術を用いて木材のみの構成で耐火性を確保したのでしょうか?
「FR ウッド®︎」が
火災に強い理由とは?
「FR ウッド®︎」は、難燃薬剤を注入したラミナ(板)で普通の集成材を被覆し、無処理の化粧板で仕上げた耐火集成材です。そして「FR ウッド®︎」の開発においてポイントとなっている技術が、木材の加工に適した炭酸ガスレーザを用いて、ラミナの広い面に所定の間隔でピンホールを開ける“レーザインサイジング”と呼ばれる加工です。なお、レーザインサイジングで開けられるピンホールに近い穴を細いドリルで開けるドリルインサイジング技術も開発され、実用化されています。

レーザインサイジングの準備
レーザインサイジングによって開けた穴に、木材の炭化促進と発泡効果で熱を内部に伝わり難くする“ポリリン酸カルバメート“という難燃薬剤を均一に注入することで、耐火性が付与されています。国内の人工林のうち大きな面積を占めているスギは、他の木材に比べて薬剤の注入が容易な木材組織で構成されていることから、耐火集成材に適しており、採用されています。

FRウッド®︎内部構造
耐火性能を満たすまで
薬剤を注入するためのインサイジング(ラミナの厚さを貫通する穴開け)は、耐火性能を発揮するためにある程度の数が必要となりますが、建築材としての強度も維持しなければなりません。そのための最適なインサイジングの密度や縦横の間隔を見つけるまでが、開発を成功させるまでに乗り越えなければならない壁だったといいます。

FR ウッド®︎の加熱試験の様子。左から、加熱試験前、加熱試験中、加熱試験後。
「『FR ウッド®︎』が国土交通大臣認定を取得するまで30回以上の加熱試験を行っていますが、そのうち初期の10数回は燃えてしまいました。何が原因だったかを都度確認して、確実に耐火性を維持したインサイジング密度にたどり着くまでが最も困難なことでした」と服部名誉教授は話します。
そして、鹿島建設(株)が実用化に向けて産学官連携の共同開発に参入し、2013年には遂に、1平方メートルあたり1600個の穴開けをした「FR ウッド®︎」が最初の大臣認定を取得しました。この呼称は鹿島建設(株)の登録商標です。同年には、日本初の「FR ウッド®︎」を使った「野菜倶楽部 oto no ha Café」の建物が建設され、2018年には神田神社に文化交流館EDOCCOが竣工しています。


野菜倶楽部 oto no ha Café(左:完成外観、右:1階)
野菜倶楽部 oto no ha Café(上:完成外観、下:1階)


神田神社の文化交流館EDOCCO(左:外観、右:2階ホールのホワイエ)
神田神社の文化交流館EDOCCO(上:外観、下:2階ホールのホワイエ)
さらに、住友林業(株)も共同開発に加わり、穴開けの数を1平方メートルあたり800個に減らすなどしてコストダウンを図った「FR ウッド®︎」の改良耐火集成材が、2016年に新たに国土交通大臣認定を取得することに成功しました。
また、ライフサイクルアセスメント(環境負荷計算の手法:以下LCA)の専門家でもある服部名誉教授は、木造の建築物が都市に増えることで以下のようなメリットがあると話します。
「LCAの計算上、我々が開発した『FR ウッド®︎』による木造は、同等の鉄骨造あるいは鉄筋コンクリート造よりも2割程度環境負荷が低いということがわかっています。また、木材は大気中のCO₂を貯蔵しているため、燃やしたりしない限りは温室効果ガス削減への効果が期待できるのです」
\学生の声/

東京農工大学 農学部
環境資源科学科 生活環境分野
長田 拓巳 さん
ラミナと呼ばれるひき板を接着することで集成材と呼ばれる建材を製造することができます。そのラミナに難燃薬剤を注入することで火に強い集成材を作ることができ、私たちはこの耐火集成材についての研究を行っています。木材には材ごとに個体差があり、それによって薬剤の注入量にも差が生じます。この差のあるラミナを集成材にするときに、並べ方によって耐火性能にどう影響を及ぼすのかを調べることが私の研究テーマです。
多くの気付きと学びを与えてくれる先生方と、共に切磋琢磨できる仲間の存在もあり、充実した日々を過ごすことができています。この素晴らしい環境で自己研鑽に励み、将来の役に立てていきたいです。
今後の研究について
服部名誉教授によれば、国産スギは、薬剤の注入が容易で耐火集成材に適した木材であるという利点がありますが、密度が低く、その分燃えやすいため、耐火性を付与するには不利な面があります。その国産スギで耐火性の技術が確立できたということは、密度がそれより少し高い国産ヒノキでは、注入性もあまり変わらないので、大臣認定取得が同じように可能ではないかと考えられるそうです。そのため、いずれは、国産ヒノキを使用した純木製の耐火集成材が誕生する可能性も秘めています。しかし、耐火性能は2時間も確認出来ているものの、「FR ウッド®︎」の需要を高めるためにはコスト面がネックになっているとのこと。それを解決するために、使用する薬剤をさらに減量するための効率的な集成材の組み方など、50パーセントのコストダウンを目指した研究を進めているそうです。

東京農工大学
東京都府中市晴見町3丁目8-1
042-367-5504
https://www.tuat.ac.jp/
|今回 教えてくれたのは・・・|

東京農工大学
服部 順昭 名誉教授
農学博士。専門は木材加工機械、木材のレーザ加工、木材製品のライフサイクルアセスメント(LCA)。「帯鋸盤における鋸走行位置制御に関する研究」で学位取得。1988年よりレーザインサイジング技術の開発に着手、2001年より耐火集成材の開発に応用。2002年より木材製品や木造建築物の環境影響評価(LCA)を開始。

東京農工大学
安藤 恵介 講師
博士(農学)。専門は木材加工機械、木材のレーザ加工。「レーザインサイジングの構造用木材への応用に関する研究」で学位取得。1991年よりレーザインサイジング技術の開発に従事、2005年より耐火集成材の開発に関する研究を開始。

この記事のPDF版はこちら
(PDF : 1,165KB)
お問合せ先
大臣官房広報評価課広報室
代表:03-3502-8111(内線3074)
ダイヤルイン:03-3502-8449