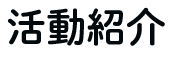食事は食べごと(食べごと)であるという考えのもと、和食に宿る日本の文化を箱膳の食事体験を通して伝えている。つい50年ほど前までの普通の日本人の暮らしと、長い歴史の中で育まれた食文化である「和食」を次の世代に受け継ぐための活動が主たる取組である。箱膳体験は(1)座学(食べごとについての講義)、(2)調理実習(食事体験用の和食、一汁三菜を調理する)、(3)箱膳での食事体験の3つのメニューがあり、適宜組み合わせて実施している。
活動紹介 | 箱膳を使って『食べごと』を伝える
概要

信州ひらがな料理普及隊
「箱膳を使って『食べごと』を伝える」
取り組みの成果
食育、食文化を伝えるツールとして、「箱膳」を使ったことで、本来、食育目的でなかった人も参加をしてくれる機会が増えたということが大きな効果である。箱膳の会には大人や観光客、外国の人も申込をしてくれ、信州の食に触れ、和食を堪能し、リピーターも多い取組となっている。
今後の取り組み
箱膳を使った食育、信州の食文化の継承を続けていくと共に、後継者(語り部)に育成にも力を入れていく予定。すでに3つの会では、独自に指導者養成講座を開いている。地域の郷土料理、伝統料理をその時代に生きていた人からヒアリングしていくのも、だんだんと難しくなってきているが、「食の風土記」つくりも進めていく。
団体・企業概要
| 団体名 |
信州ひらがな料理普及隊 |
|---|---|
| 事務局 |
長野県農村文化協会(長野市小柴見) |
| 取組内容 |
和食アドバイザー(群馬県に本部のある一般 社団法人日本実務能力協会和食アドバイザー検定協会認定)の資格を持ったメンバーで構成された、長野県内に拠点を持つ11の組織により構成されている。(2020年現在)和食、特に信州人の伝統的な食文化の推進と、食事に対する考え方(食べごとの心)を、伝えることを目的としている。伝えるための手段として昭和30年代まで一般的であった食事スタイル(箱膳)を活用し、子供から大人まで、広い世代に参加をしてもらえる取組になっている。 |
取組事例
松代箱膳の会
- 長野市有形文化財である「寺田商家(旧金箱家住宅)*」で箱膳体験が定期的に開催され、松代の風情と季節の味覚を楽しむ会は観光にも一役買って人気のイベントとなっている。「着物de箱膳体験会」など、城下町の松代で、「着物を着る」、「人力車に乗る」という体験との組み合わせにより、観光目的の人にも食育に触れてもらうことができた。また、地元の小学校で3年生になった生徒は、毎年箱膳体験を通じて食育を学びに来てくれるほか、アメリカ・ミズーリ州からは、令和元年5月まで3回連続、和食体験に学生が訪れている。
- *寺田商家:真田十万石の城下町である松代で、江戸末期から昭和初期まで質屋等を営んでいた商家・金箱家の旧宅で敷地内には、明治から大正までの商家の営みを伝える歴史的建造物と、泉水路と池をもつ庭園が現存しており、松代における明治期を中心とした豊かな商家の暮らしぶりを伝える貴重な屋敷として、2012年に長野市の有形文化財に指定された。

食の風土記・レシピ集の発行
- 日本の食の形が残っていると言われる昭和30年代に焦点をあて聞き取り調査に取組んでいる。これらは「信州ながの食の風土記」や「レシピ集」としてまとめ、食育推進活動のテキストとして活用。食のレシピの料理は、箱膳体験のメニューとしても取り入れられている。書物の発行はいずれも長野農文協が行っている。

後継者(語り部)の育成
- 日本の「食べごと」を継承していく新たな指導者を育成するために、「いただきますの会」「四方気の会」「朔の会」では独自に指導者育成用の講座を開催している。
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
代表:03-3502-8111(内線4601)
ダイヤルイン:03-3502-5723