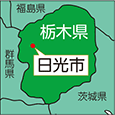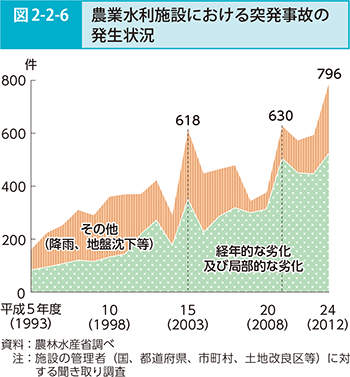第2節 農業生産基盤の整備・保全
良好な営農条件を備えた農地や農業用水等の農業生産基盤の整備・保全管理は、我が国の農業生産力を支える上で重要な役割を担っており、農業競争力の強化に向けた農地の大区画化・汎用化の推進、老朽化の進行や防災・減災への対応が課題となっています。
以下では、農地の大区画化・汎用化、農業水利施設(*1)の適切な保全管理、防災・減災の取組について記述します。
(農業生産基盤の整備による農業競争力の強化)
農業従事者の減少や高齢化等が進行する中、我が国の農業生産力の向上を図り、農業の有する多面的機能を将来にわたって発揮していくためには、生産効率の向上を図る農地の大区画化・汎用化、収益性の高い農業経営を実現する畑地かんがい等の農業生産基盤の整備が不可欠です。
平成25(2013)年における水田の整備状況をみると、30a程度以上の区画に整備済みの水田は156万haで水田面積全体の6割を占めており、1ha程度以上の大区画化も進められています。畑については、畑面積全体の7割において幅員3m以上の末端農道が整備されているとともに、2割において畑地かんがい施設が整備されています(図2-2-1)。
一方、水田の排水性についてみると、30a程度以上の区画に整備済みの水田の3分の2(107万ha)では排水が良好で畑としても利用可能な汎用田となっていますが、残り3分の1(49万ha)は排水が良好でない状態にあります(図2-2-2)。
農業競争力の強化を図るためには、担い手への農地集積・集約化に向け、農地中間管理機構とも連携した農地の大区画化・汎用化や担い手の労力を軽減する生産基盤の整備を推進する必要があります。
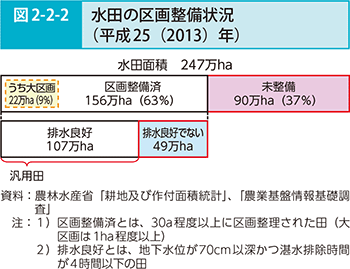
また、大区画化・汎用化や担い手への農地集積、新規需要米への取組、気候変動による影響等により、作期の変化による農業用水の利用形態の変化や作業時期の分散が生じてきています。このような農業構造や営農形態の変化に対応した水管理の省力化や水利用の弾力化を図るため、用水路のパイプライン化、ICT(*1)や地下水位制御システム等の新たな技術の導入、水利用の運用方法や管理体制の見直し等による新たな農業水利システムの構築が求められています。
地下水位制御システムについては、暗渠(きょ)排水と地下かんがいを両立させ、地下水を作物の生育状況に適した水位に制御し、自在に田畑輪換を行うものであり、平成25(2013)年度末時点で全国約1万3千haのほ場に導入されています(図2-2-3)。このシステムの整備により、水田の有効活用による麦・大豆の生産拡大、水管理の作業時間の削減や大区画化との相乗効果による生産コストの低減が期待されています(図2-2-4)。

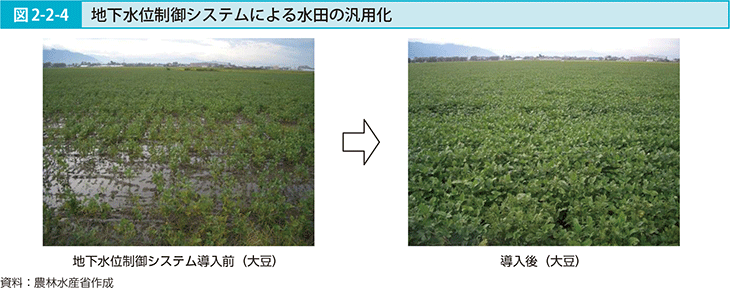
事例:ほ場整備を契機とした集落営農組織の法人化と地域の活性化
栃木県日光市(にっこうし)の芹沼(せりぬま)地区は、水田が狭小及び不整形で、水路は用排水兼用であったことから、平成10(1998)年度から平成17(2005)年度までほ場整備事業に取り組みました。大区画化や大型機械の導入等により労働時間が短縮されたほか、水路や農道の整備により利便性が向上し、排水機能も改善され、水稲のほか大豆、そば等を作付けしています。
また、事業実施を契機として、若い農業後継者や女性、高齢者も参加して農地集積のビジョンを策定し、担い手への農地集積を進めるとともに、平成13(2001)年に認定農業者による作業受託組織を設立しました。事業実施後の平成18(2006)年には特定農業団体となり、経理の一元化や資材の一括購入による経費削減を進め、平成23(2011)年に「農事組合法人日光アグリサービス」として法人化しました。組合員は水田経営を同法人に委託することで土地利用型農業の合理化を図り、いちごや花き等の施設園芸に労力を転換しています。
同法人では、「協同の力で地域農業を守り、豊かな生活の確立を目指す」という基本理念の下、観光地である日光を活かした地域ブランドの確立や6次産業化(*)により、付加価値の高い農業と地域づくりを展開していくこととしています。
(農業水利施設の適切な保全管理の推進)
農業水利施設については、かんがいや排水のための農業用用排水路は地球10周分に相当する40万km以上、ダムや取水堰(せき)、用排水機場等の点的な基幹的施設は7千か所に整備されており、このような農業水利ストック全体の資産価値は、再建設費ベースで32兆円、このうち基幹的水利施設(*1)は18兆円に達すると算定されています(*2)。
基本的に、基幹的水利施設は、国、地方公共団体、土地改良区により保全管理が行われる一方、地域に密着した農地周りの水路、農道、ため池等は、集落の共同活動等により保全管理が行われており、良好な営農条件を確保する上で重要な取組となっています。
しかし、近年、農地集積の進展や営農体系の多様化に伴い水管理等の高度化・複雑化が求められる一方、土地改良区は農家数の減少や職員の高齢化により組織の脆弱(ぜいじゃく)化が進行しており、効率的な事業実施や技術継承のための体制を整備する必要があります。
また、基幹的水利施設の多くは、戦後から高度経済成長期にかけて整備されてきたことから、現在、老朽化が急速に進行し、更新等が必要な時期を迎えています。
このうち、耐用年数を迎えるものについて再建設費ベースでみると、既に標準耐用年数を超過している基幹的水利施設は全体の2割を占め、また、今後10年間で標準耐用年数を超過する基幹的水利施設を含めると、全体の3割に達します(図2-2-5)。
さらに、経年的な劣化による水路の漏水等の突発的な事故も増加傾向にあるなど、施設の将来にわたる安定的な機能の発揮に支障が生じることが懸念されています(図2-2-6)。
このため、機能の監視・診断等によるリスク管理を行いつつ、劣化の状況に応じた適時適切な補修・更新等を行うことにより、施設の長寿命化とライフサイクルコスト(*3)の低減を図る戦略的な保全管理を推進しています。
一方、農地周りの農業用用排水路等については、農家数の減少や土地持ち非農家の増加により、水管理体制の脆弱化や施設の保全管理に向けた共同活動力の低下が懸念されていることから、多面的機能支払(*4)により、農地、農業用水等のきめ細かな保全活動や施設の長寿命化のための活動への支援が行われています。
コラム:歴史的なかんがい施設の遺産登録
「かんがい施設遺産」は、かんがいの歴史・発展を明らかにし、理解醸成を図るとともに、かんがい施設の適切な保全に資することを目的として、国際かんがい排水委員会(ICID(*))が登録・表彰する制度で、平成26(2014)年に創設されました。
建設から100年以上経過し、かんがい農業の発展に貢献したもの、卓越した技術により建設されたもの等、歴史的・技術的・社会的価値のあるかんがい施設が対象で、平成26(2014)年は5か国から17施設が登録され、我が国から以下の9施設が登録されました。
登録により、かんがい施設の持続的な活用・保全方法の蓄積、研究者・一般市民への教育機会の提供、かんがい施設の維持管理に関する意識向上に寄与するとともに、かんがい施設を核とした地域づくりに活用されることが期待されています。
(農村地域における防災・減災の取組の推進)
我が国は、年間を通して降雨が多く台風の常襲地帯であり、特に近年においては、豪雨の発生回数が増加傾向にあるほか、地形が急峻(きゅうしゅん)で変化に富むことから、災害が発生しやすい自然条件にあります。
これまで、農地や農業水利施設は、農地が持つ保水・貯留機能による洪水・土砂災害の防止、避難場所としての役割、農業用排水機場による農地及び周辺の宅地や公共施設等の湛水被害の防止等、多面的な機能を発揮し、地域住民の安全の確保に寄与してきました。
しかし、農業水利施設の老朽化、農業従事者の減少や高齢化に伴う地域の防災力の低下等により、自然災害に対する脆弱性が高まっています。
また、東日本大震災では、農地の浸水や農業水利施設の破損等が発生し、農業生産や農村生活に様々な影響を及ぼしたほか、将来、発生する可能性が高い大規模地震として、南海トラフ地震等が想定されており、防災・減災の取組が重要となっています。
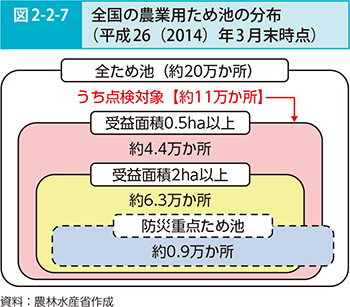
例えば、農業用水の水源として利用されているため池は全国に約20万か所ありますが、このうち受益面積が0.5ha以上のため池又は下流に人家や公共施設等があり決壊した場合に影響を与えるおそれのある防災重点ため池約11万か所を対象に、平成25(2013)年度、平成26(2014)年度の2か年で豪雨や地震に対する一斉点検を実施しました(図2-2-7)。今後、点検結果を基に防災重点ため池を優先して詳細な調査を行い、その結果に応じてハザードマップの作成や対策工事等を実施します(図2-2-8)。

一方、土地改良施設管理者が有事に備えた業務継続計画(BCP(*1))を作成し、事前準備や初動体制の強化に取り組むとともに、地域住民が土地改良施設の保全管理活動や避難訓練等への参加を通じて防災意識を高めることも重要です。
このような中、平成25(2013)年12月に国土強靱化基本法(*2)が公布・施行されるとともに、国土強靱化に係る国の他の計画等の指針となるものとして、平成26(2014)年6月に「国土強靱化基本計画」が策定されました。同計画に基づき、農業水利施設等についても老朽化対策や耐震化等のハード対策とハザードマップの作成や監視・管理体制の強化等のソフト対策の両面から国土強靱化に取り組むこととしています。
また、平成26(2014)年6月に「海岸法」が改正され、切迫する南海トラフ地震等による大規模な津波、高潮等に備え、海岸の防災・減災対策を強化するとともに、高度成長期等に集中的に整備された海岸保全施設の老朽化に対応し、海岸の適切な維持管理を推進することとされました。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883
FAX:03-6744-1526