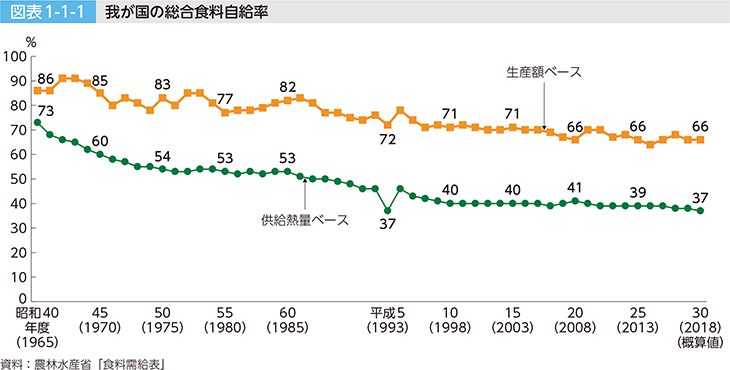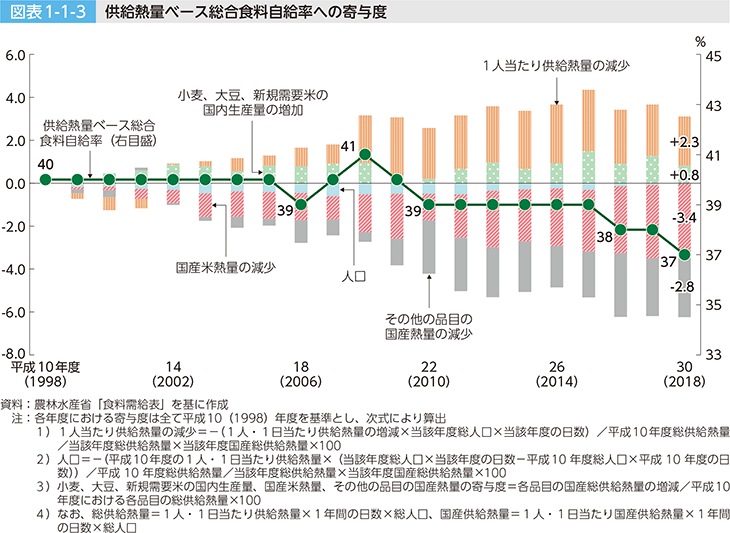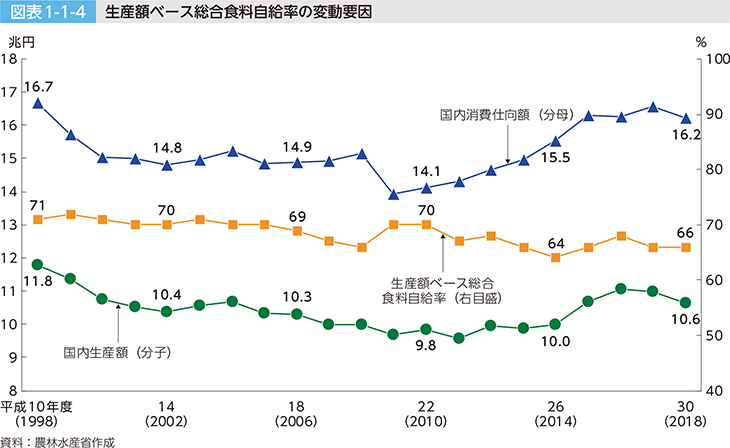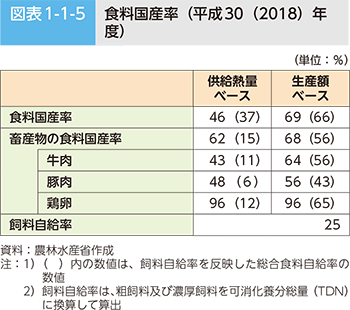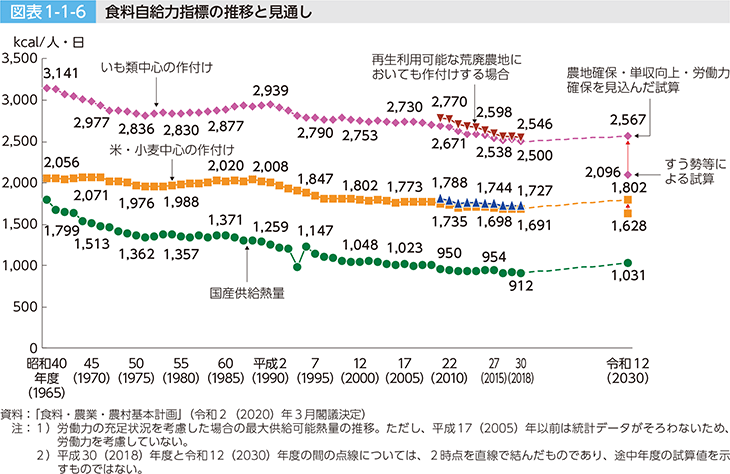第1節 食料自給率と食料自給力
令和2(2020)年3月に閣議決定された食料・農業・農村基本計画においては、令和12(2030)年度を目標年度とする総合食料自給率(*1)の目標が設定されるとともに、新たに国内生産の状況を評価する食料国産率(*2)の目標が設定されました。また、我が国の食料の潜在生産能力を評価する食料自給力指標(*3)について、新たに農業労働力や省力化の農業技術を考慮するよう指標が改良され、さらに、今後の農地や農業労働力の確保、単収の向上等を踏まえた令和12(2030)年度の見通しが示されました。
*1~3 用語の解説3(1)を参照
(1)食料自給率の目標と動向
(供給熱量ベースは1ポイント低下の37%、生産額ベースは前年同の66%)
総合食料自給率の目標は、令和12(2030)年度を目標年度として、供給熱量(*1)ベースで45%、生産額ベースで75%と定められました。平成30(2018)年度の供給熱量ベースの総合食料自給率は、天候不順により、小麦、大豆、飼料作物等の生産量が減少したこと、これに伴う飼料自給率の低下等から、前年度に比べ1ポイント低下し、平成5(1993)年度に並び、過去最も低い37%となりました。生産額ベースの総合食料自給率は、野菜や鶏卵の生産量増加により単価が下落した一方、ホタテ貝等の輸出増加による国内仕向量減少、国産てんさい由来の砂糖の製造量増加等から、前年度と同じ66%となりました。
我が国の食料自給率は、長期的には低下傾向で推移してきましたが、近年では、供給熱量ベースの総合食料自給率は平成8(1996)年度以降おおむね40%前後とほぼ横ばいで、生産額ベースの総合食料自給率は平成8(1996)年度以降60%台後半から70%台前半までの範囲で、それぞれ推移しています(図表1-1-1)。
長期的に食料自給率が低下してきた主な要因としては、食生活の多様化が進み、国産で需要量を満たすことのできる米の消費が減少した一方で、飼料や原料の多くを海外に頼らざるを得ない畜産物や油脂類等の消費が増加したことによるものです(図表1-1-2)。
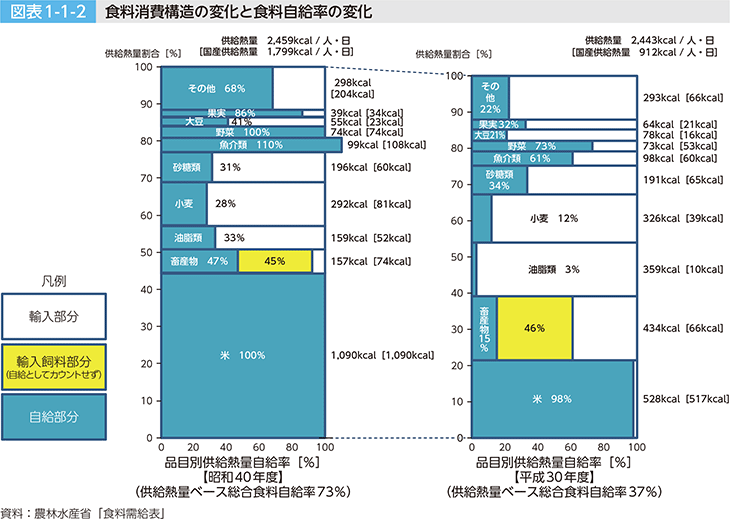
また、近年供給熱量ベースの総合食料自給率は40%前後で推移してきましたが、これは、マイナス要因である国産米熱量の減少、水産物や野菜等その他品目の国産熱量の減少の寄与が拡大する一方で、プラス要因である高齢化等に伴う1人・1日当たり供給熱量の減少、小麦、大豆、新規需要米(*2)の国内生産量の増加等の寄与が一定にとどまっていることによります(図表1-1-3)。
一方、生産額ベースの総合食料自給率は緩やかな低下で推移してきましたが、平成25(2013)年度以降は国内消費仕向額(分母)と国内生産額(分子)がともに増加していることから、横ばいで推移しています。国内消費仕向額の増加は、景気回復や輸入品も含めた食料価格の上昇によると考えられ、国内生産額の増加は、和牛やシャインマスカット等の高付加価値品目の取組の進展や生産量の微減傾向等による価格の上昇に伴い、畜産物、野菜、果実を中心に増加傾向にあることによると考えられます(図表1-1-4)。
総合食料自給率のうち供給熱量ベースは、生命と健康の維持に不可欠な基礎的栄養価であるエネルギー(カロリー)に着目したものであり、消費者が自らの食料消費に当てはめてイメージを持つことができるなどの特徴があります。一方で生産額ベースは、食料の経済的価値に着目したものであり、エネルギーが比較的少ない一方で高い付加価値を有する畜産物、野菜、果実等の生産活動をより適切に反映させることができます。
供給熱量ベースよりも生産額ベースの方が相対的に高いのは、我が国の農業構造が諸外国と比べて、カロリーの高い土地利用型作物よりも畜産物、野菜、果実等の付加価値の高い作物の生産に比較優位があることを示唆しています。
このため、諸外国の経済発展による海外市場の拡大や食生活の多様化等国際環境の変化に積極的に対応し、比較優位のある品目を生産・輸出していくことは、生産額や所得の確保を図り、農地の保全や就業者の確保等を図っていく上で重要となります。一方で、食料の安定供給のためには、国内生産の増大を図ることを基本としつつ、国内生産では十分に賄うことのできない食料を安定的に輸入することも必要となります。
*1 用語の解説3(1)を参照
*2 主食用米、加工用米、備蓄米以外の米穀で、飼料用米、米粉用米、稲発酵粗飼料用米等がある。
(食料自給率向上に向けて生産基盤の強化と消費拡大の推進が重要)
総合食料自給率目標は、令和12(2030)年度の食料消費の見通しと生産努力目標を前提として示されています。生産努力目標は、国内外の需要の変化に的確に対応できる農業生産を推進するとの方針の下、品目ごとに農業生産に関する課題が解決された場合に実現可能となる生産量として設定されています。令和12(2030)年度の生産努力目標について、小麦は108万t(平成30(2018)年度76万t)、大豆は34万t(平成30(2018)年度21万t)となっており、目標達成に向けては、耐病性や加工適性等に優れた新品種の開発導入の推進や、排水対策の更なる強化等が課題となっています。また、野菜は1,302万t(平成30(2018)年度1,131万t)、果実は308万t(平成30(2018)年度283万t)となっており、目標達成に向けて、労働生産性の向上等を図ることが必要です。この他の品目でも、畜産物については、国内外の需要に応える供給を確保するための生産基盤強化が課題であるなど、生産努力目標達成に向けては、品目ごとに課題を克服していく必要があります。
人口減少、農業従事者(*1)の高齢化、農地面積の減少等が進む中で、食料自給率を向上させるためには、国内生産基盤の強化等により我が国農業を持続可能なものとすることが重要です。このため、品目ごとのきめ細かな対策とともに、担い手への農地の集積・集約化(*2)、新規就農の促進等による担い手の確保、スマート農業の導入、農地の大区画化・汎用化等を推進する必要があります。また、食の外部化(*3)等による加工・業務用需要の拡大や、近年増加している訪日外国人旅行者によるインバウンド需要、健康志向の高まり等による食料消費の変化に適切に対応するとともに、旺盛な海外需要を取り込むため、輸出向け産地の形成や流通加工体制の整備等を通じて輸出を促進するなど、需要の変化に応じたマーケットイン型の取組を推進する必要があります。
このような生産面での取組に加え、消費面においても、消費者が食料・農業・農村の持つ役割を理解することを促し、国産農産物の消費拡大につながる主体的な行動を引き出していくことや、安定的な取引関係の確立による農業と食品産業の連携強化等により国産農産物の需要拡大を図ることも重要です。
*1 用語の解説1、2(4)を参照
*2、3 用語の解説3(1)を参照
(食料国産率と飼料自給率)
新たな基本計画において、新たに目標に位置付けられた食料国産率は、飼料が国産か輸入かにかかわらず、畜産業の活動を反映し、国内生産の状況を評価するものです。需要に応じて増頭・増産を図る畜産農家の努力が反映され、また、国産畜産物を購入する消費者の実感に合うという特徴があります。
一方、飼料の自給度合いによって畜産物の自給率は大きく影響を受けるため、国産飼料基盤に立脚した畜産業を確立する観点から、新たな基本計画においても飼料自給率の目標が設定されています。食料自給率は輸入飼料による畜産物の生産分を除いているため、食料国産率と飼料自給率の双方の向上を図りながら、食料自給率の向上を図ることが必要です(図表1-1-5)。
(2)食料自給力指標の動向
(いも類中心の作付けでは、推定エネルギー必要量を上回る)
食料の多くを海外に依存している我が国では、食料安全保障(*1)の観点から、国内の農地等を最大限活用することで、どの程度の食料が得られるのかという食料の潜在生産能力(食料自給力)を把握し、その維持・向上を図ることが重要です。
食料自給力指標は、我が国の食料の潜在生産能力を評価する指標であり、栄養バランスを一定程度考慮した上で、農地等を最大限活用し、熱量効率が最大化された場合の1人・1日当たり供給可能熱量を、米・小麦中心の作付けといも類中心の作付けの2パターンについて試算したものです。新たな基本計画では、農業労働力や省力化の農業技術も考慮することとし、また、令和12(2030)年度の見通しも併せて示しています(*2)。
平成30(2018)年度の食料自給力指標の試算では、442万haの農地面積、9万haの再生利用可能な荒廃農地(*3)面積、実際に投入されている臨時雇用を含む延べ労働時間等を前提として試算を行っています。平成30(2018)年度の労働力の充足状況を考慮した食料自給力指標は、「米・小麦中心の作付け」で1,727kcal/人・日、「いも類中心の作付け」で2,546kcal/人・日となりました(図表1-1-6)。
日本人の平均的な1人当たりの推定エネルギー必要量2,169kcal/人・日と比較すると、より私たちの食生活に近い「米・小麦中心の作付け」ではこれを下回る一方、供給熱量を重視する「いも類中心の作付け」ではこれを上回ります。なお、いも類中心の作付けにおいては、農地を最大限活用した場合の供給可能熱量では、その作付けに必要な労働力が不足するため、作付けの一部を米・小麦等の省力的な作物に置き換え、労働力も併せて最大限活用されるよう試算を行っています。
また、食料自給力指標の推移については、農地面積の減少、単収の伸び悩み等により平成30(2018)年度まで低下傾向にありますが、農地確保、単収向上、労働力確保、生産性向上を今後図っていくことにより、供給可能熱量を押し上げていくことが可能です。
将来における世界の食料需給に不安定要素が存在する中、需要に応じた生産や海外需要の獲得等により、平素から我が国における農業生産の振興を図ることで優良農地が確保され、食料自給力の維持向上につながります。このため、担い手の確保や担い手への農地の集積・集約化を進め、荒廃農地の発生防止と再生を図るとともに、新品種・新技術の開発・導入、輪作体系の適正化や排水対策等の基本技術の励行により単収の高位安定化を図る必要があります。
*1 用語の解説3(1)を参照
*2 新たな食料自給力指標については、特集1を参照
*3 用語の解説3(1)を参照
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883
FAX番号:03-6744-1526