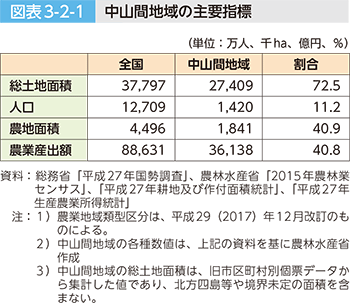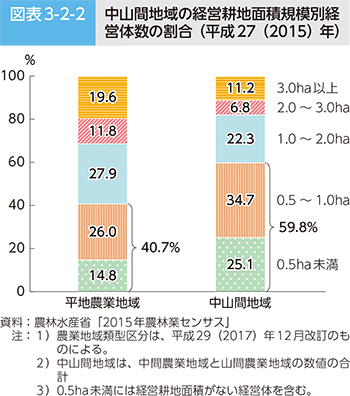第2節 中山間地域の農業の振興
中山間地域は、農業生産条件が不利である一方、農業生産活動を通じ、国土の保全、水源の涵養(かんよう)、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等、様々な機能を有しています。農林水産省では、施行された棚田地域振興法の枠組みによる取組を始め、中山間地域の振興に向けて必要な支援を進めています。
(地域資源を活かすことで収益力のある農業を実現)
中山間地域は、我が国の人口の1割、総土地面積の7割、農地面積と農業産出額では4割を占めており、我が国の食料生産を担うとともに、豊かな自然や景観を有し、多面的機能の発揮の面でも重要な役割を担っています(図表3-2-1)。
一方で、傾斜地が多く存在し、ほ場の大区画化や大型農業機械の導入、農地の集積・集約化(*1)等が容易でないため、生産性の向上が平地に比べて難しく、人口減少、高齢化による担い手不足等とあいまって、営農条件面で不利な状況にあります。
1経営体当たりの経営規模で見ると、経営耕地面積規模が1.0ha未満の経営体の割合は、平地農業地域(*2)で4割であるのに対し、中山間地域では6割となっています(図表3-2-2)。
また、中山間地域は、野生鳥獣の生息地となる山林と農地が隣接することから、平地に比べて農作物の鳥獣被害を受けやすく、荒廃農地(*3)が発生しやすい環境にあります。
このような不利な営農条件下にあるものの、中山間地域特有の冷涼な気候や清らかな水を活かして良食味の米や伝統野菜を栽培するなど、地域資源を活かすことで収益力のある農業を実現する地域もあり、今後も特色ある農業や6次産業化(*4)の取組が展開されることが期待されています。
*1、3、4 用語の解説3(1)を参照
*2 用語の解説2(6)を参照
事例:レタス等の高収益作物の生産と担い手の経営規模の拡大(群馬県)
群馬県昭和村(しょうわむら)、沼田市(ぬまたし)ほかからなる赤城西麓(あかぎせいろく)地区は、地域の一部が特定農山村地域にも指定されています。同地区では降水量が少なく、常に干ばつ被害を受ける不安定な農業経営を余儀なくされていました。
このような状況の中、昭和56(1981)年度から始まった国営かんがい排水事業等によって、頭首工(とうしゅこう)や用水路の整備、農地の区画整理等が行われ、農業用水の安定的な供給が可能となるとともに、担い手への農地の集積や経営規模の拡大が進展しました。これにより、レタスやほうれんそうの作付面積が増加したほか、こんにゃく収穫量が全国シェアの上位を占めるようになり、高収益作物の生産拡大が進みました。
その結果、昭和村における1戸当たりの農業所得は約2倍に増加しました。
(農業生産基盤強化プログラムにより中山間地域の基盤整備と活性化を推進)
令和元(2019)年12月に農業生産基盤強化プログラムが策定され、棚田を含む中山間地域の基盤整備と活性化を推進することとされました。
これを受けて、農林水産省では、中山間地域における所得向上に資する農産物の生産・販売等の促進、基盤整備と生産・販売施設等の整備の一体的な推進、棚田地域の景観修復等の棚田保全・振興の取組開始に必要な環境整備の推進により、令和6(2024)年度までに地域資源を活用した取組等を行う地区を250地区創出することとしています。
(山村地域の特性を活かした産業の育成による雇用と所得の増大)
国土面積の47%を占める振興山村(*1)は、国土の保全、水源の涵養(かんよう)、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等に重要な役割を担っていますが、人口減少、高齢化等が他の地域より進んでいることから、国民が将来にわたってそれらの恵沢(けいたく)を享受することができるよう、地域の特性を活かした産業の育成による就業機会の創出を図ることが重要です。
このため、農林水産省は、農山漁村振興交付金の山村活性化対策により、振興山村の山菜やくり、ゆず、木工品等の特色ある地域資源を活かした新商品の開発や販路開拓等を支援し、地域の雇用と所得の増大を図っています。
*1 山村振興法に基づき指定された地域
事例:6次産業化で中山間地域の課題解決に取り組む地域(福島県)
福島県三島町大登(みしままちおおのぼり)地区は特定農山村地域、過疎地域、振興山村地域に指定される中山間地域で、鳥獣被害と耕作放棄地の発生に悩まされていましたが、これらの課題解決に取り組むため、町が出資し、農地所有適格法人桐(きり)の里産業(さとさんぎょう)株式会社を設立しました。町、桐の里産業、民間企業がコンソーシアムを形成し、農地中間管理事業を活用して、大規模農地を復元し、エゴマの栽培を開始することとなりました。エゴマは、必須脂肪酸であるα-リノレン酸を豊富に含んでおり、美肌、健康等に効果があることに加え、独特のにおいがあることから鳥獣の被害を受けにくいものです。また、生産したエゴマの搾油(さくゆ)、瓶詰め等を行うことで、地域の雇用創出にも寄与しています。
桐の里産業が販売するエゴマ油は、一般財団法人都市農山漁村交流活性化機構(としのうさんぎょそんこうりゅうかっせいかきこう)が運営する里の物語オンラインショップで1本(100g)2千円と高値で販売されています。スーパー等で低価格帯で販売されている外国産エゴマと異なり、良質な国産エゴマ油として、消費者から好評を博し、リピーターもついています。
エゴマ油を販売した利益の一部は、地域の鳥獣被害対策のために用いられ、地域の課題解決に貢献しています。
(棚田保全に向けた動きと棚田地域振興法の施行)
山の斜面や谷間の傾斜地に階段状に作られた水田のことを棚田といいます。棚田は、農産物の供給にとどまらず、国土の保全、水源の涵養(かんよう)、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等の多面的機能を有しています。しかし、地形的に条件が厳しい棚田の保全には多大なコストを要するのが実情であり、高齢化の進展等により、棚田が荒廃の危機に直面しています。
一部の棚田地域では、棚田の美しい景観を活かした観光や、棚田オーナー制度、農泊や農業体験学習を通じた都市住民との交流、棚田米やその加工品の販売等、棚田の持つ多様な魅力を活かした取組が行われていますが、そのような地域は限定的です。また、棚田の保全や地域振興に活用できる各府省庁の既存の施策があるものの、十分に周知・活用されていないという状況があります。
このような背景の下、令和元(2019)年8月、棚田地域振興法が施行され、市町村や都道府県、農業者、地域住民等の多様な主体が参画する地域協議会による棚田を核とした地域振興の取組を、関係府省庁横断で総合的に支援する枠組みが構築されました。新たな枠組みの中で、棚田地域の振興に関する事業を取りまとめて毎年度公表するとともに、関係府省庁の職員からなる棚田地域振興コンシェルジュが、地域協議会の体制づくりから活動の実施まで、幅広い相談に応じながら、様々な施策の活用促進を図っていくこととしています。
(棚田カードプロジェクトチームを立上げ)
農林水産省では、棚田地域を盛り上げ、棚田の保全につなげる取組の第一歩として、都道府県に呼びかけ、棚田カードプロジェクトチームを立ち上げました。棚田の持つ魅力と棚田で行われている保全活動の実態を知ってもらい、棚田に馴染みのない人でも棚田を訪れるきっかけになるよう棚田カードを作成し、令和元(2019)年7月からそれぞれの棚田地域で配布を開始しました。また、棚田地域全体を盛り上げるために「棚田に恋」をキャッチコピーとしたポスター等を作成し、棚田に関心を持ってもらえるよう情報発信を行っています(図表3-2-3)。
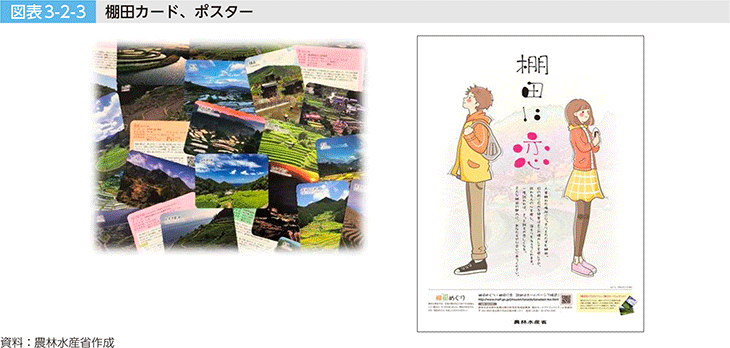
事例:棚田を核に地域おこし(長崎県)
長崎県平戸市(ひらどし)の春日(かすが)集落は、平成22(2010)年に文化庁の重要文化的景観に選定されました。これをきっかけに、市の農業部局にとどまらず、文化財部局のサポートも得て、集落で議論を重ね、集落の全世帯(約20世帯)が参加した協議会「安満(やすまん)の里(さと) 春日講(かすがこう)」が立ち上げられました。
協議会では、文化庁事業も活用した歩道整備や案内看板の設置等、歴史や景観に配慮した環境整備のほか、石積みの修理、災害の復旧等の棚田の維持管理を行っています。また、耕作放棄地を活用した農業体験や棚田米を使った日本酒やお菓子の商品化等の取組を進めています。
平成30(2018)年には、棚田を含む集落が世界文化遺産に登録されたこともあり、メディアの取材等が増加した結果、平成29(2017)年度まで年間1,500人だった観光客は、平成30(2018)年度には2万人にまで増加しました。
このような中、文化庁事業を活用して空き家を改修した集落拠点「かたりな」では、地域の高齢者がスタッフとして来訪者をもてなすことにより、住民と来訪者が相互に刺激を受ける、理想的な文化観光の形ができつつあります。
今後、持続的な仕組みづくりと農泊や農家カフェ、6次産業化等に更に取り組むことにより、訪ねる人との交流を核とした経済活動を含む取組につなげていくこととしています。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883
FAX番号:03-6744-1526