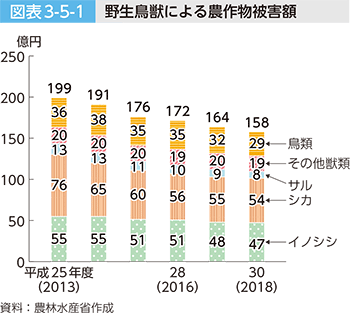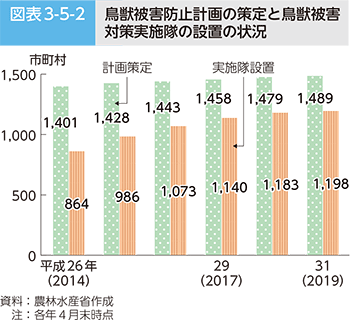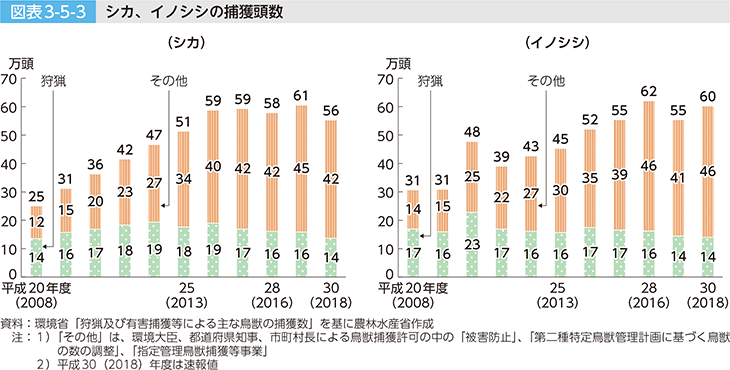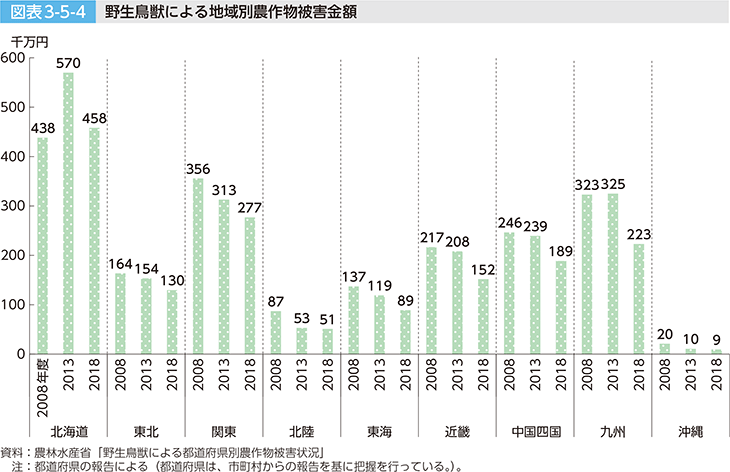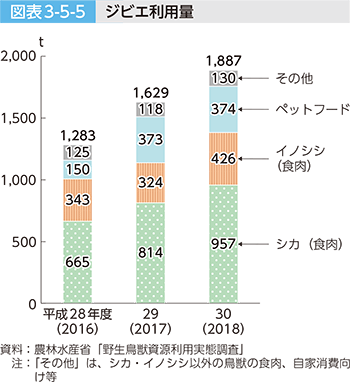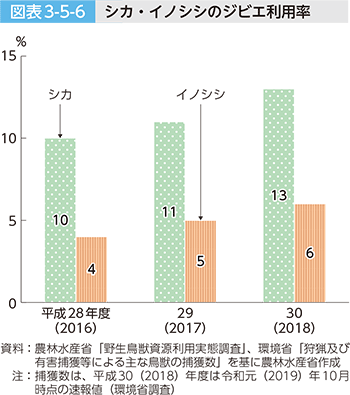第5節 鳥獣被害とジビエ
野生鳥獣をめぐっては、生息数の増加等により深刻な農作物被害が全国的に発生しており、また、車両との衝突事故や住宅地への侵入等の被害も問題となっています。一方で、捕獲した有害鳥獣をジビエ(*1)として利用していくことで農山村における所得向上等が期待されており、マイナスの存在であった有害鳥獣をプラスの存在に変えていく取組が進められています。
*1 フランス語で野生鳥獣肉のこと
(1)鳥獣被害の現状と対策
(野生鳥獣による農作物被害額は158億円)
平成30(2018)年度の野生鳥獣による農作物被害額は158億円で、多いものから、シカ、イノシシ、鳥類、サルによるものとなっています(図表3-5-1)。また、その推移を見ると、被害防止対策の推進等により、年々減少傾向が続いています。しかしながら、野生鳥獣による被害は営農意欲の減退をもたらし、耕作放棄や離農の要因になることから、数字として表れる以上に農山村に深刻な影響を及ぼしています。
(ICTを利用した「スマート捕獲」の展開)
野生鳥獣による被害防止のため、鳥獣被害防止特措法(*1)に基づき、平成31(2019)年4月末時点で1,489市町村が鳥獣被害防止計画を策定しています。そのうち1,198市町村が鳥獣被害対策実施隊(*2)を設置しており、各市町村において様々な対策が行われています(図表3-5-2)。
このような中、近年では、ICT(*3)を利用した「スマート捕獲」が注目されています。例えば、わなにカメラを取り付け、その映像をパソコンやスマートフォンで確認することにより、わなの見回り労力の軽減につなげています。また、わなに取り付けたセンサーによって頭数や獣種を判別することにより、狙った獲物だけを捕獲することが可能となります。これにより、1頭よりも複数頭を、幼獣よりも成獣を捕獲することができるようになることから、作業効率が向上しています。
シカとイノシシの捕獲頭数は平成20(2008)年度からの10年間で2倍に増加しており、特に被害防止等を目的とした市町村長等の許可に基づく捕獲が増えています(図表3-5-3)。継続的な対策により、全体として被害金額は減少傾向にあるものの、被害金額を地域別に見ると、鳥獣の生息域の拡大や地域における対策の取組状況等により、被害が増加している地域もあることから、引き続き、地域の実情に合わせた対策が必要となっています(図表3-5-4)。
*1 正式名称は「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」
*2 市町村長が任命または指名した隊員で構成され、鳥獣被害防止計画に基づく捕獲、防護柵の設置等の実践的活動を実施する組織
*3 用語の解説3(2)を参照
(2)消費の広がるジビエ
(ジビエ利用量は前年度から15.8%増加)
捕獲した有害鳥獣を地域資源と捉え、ジビエとして有効活用することで、農山村の所得が増加するとともに、捕獲意欲が向上し、農作物被害や生活環境被害の低減につながることが期待できます。
平成30(2018)年度に食肉処理施設において処理された野生鳥獣のジビエ利用量は、前年度に比べ15.8%増加の1,887tとなりました(図表3-5-5)。
一方で、ジビエ利用率(*1)は、年々増加傾向にあるものの、平成30(2018)年度はシカで13%、イノシシで6%となっており、依然として低い水準にとどまっています(図表3-5-6)。
また、野生イノシシのCSF(*2)感染が確認されている地域ではジビエ利用ができなくなっていることにより、食肉処理施設への影響も生じているため、シカの利用への転換等の対策を進めるほか、野生イノシシにおける感染拡大防止の取組を進めています。
*1 捕獲頭数全体に占める、ジビエ利用のために食肉処理施設で処理された野生鳥獣頭数の割合(シカ、イノシシ)
*2 用語の解説3(2)を参照
(処理加工体制の整備や関係者間の情報共有が重要)
ジビエ利用量を増加させるためには、食肉処理施設の増設による受入れや処理加工能力の拡大のほか、車内で一次処理を行うことができ、遠方からでも肉質を落とさずに搬入できるジビエカーの導入、捕獲・搬送段階で適切な衛生処理ができる捕獲者の育成等が重要です。また、未利用部位の活用や、ペットフード等の食肉用途以外の活用の推進等によって、新たな需要が生まれることや処分コストが低減されることが期待されています。
また、ジビエは畜産物とは異なり、供給量や品質が安定しないことから、需要者が希望するロットを確保できない場合もあるなど、その不安定さが流通の阻害要因となることがあります。このため、捕獲、受入れ、処理加工、販売の各段階の情報を関係者が共有できるシステムを構築することにより、円滑な流通の実現を図る必要があります。例えば、長野県長野市(ながのし)の長野市(ながのし)ジビエ加工(かこう)センターでは、ICTを活用し、識別番号による個体管理を行うシステムによって、受入れ、処理加工、販売までのトレーサビリティの確保と在庫管理を実現しています。
農林水産省では、ジビエ利用を更に拡大させるため、令和元(2019)年10月にジビエ利用拡大フォーラム及びジビエペットフードシンポジウムを開催し、ジビエ利用モデル地区における我が国の先導的モデルや、ジビエのペットフード利用に取り組む事業者等の優良事例を行政機関や食肉処理施設、ペットフード業界等の関係者に広く紹介しました。
(消費者の安心確保に向けた国産ジビエ認証制度の運用)
ジビエの安全性の向上と透明性の確保を通じて、ジビエに対する消費者の安心と信頼を確保するため、農林水産省は平成30(2018)年5月に、国産ジビエ認証制度を開始しました。
同制度は、厚生労働省が定める「野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針(ガイドライン)」に基づく衛生管理の遵守や、流通のための規格・表示の統一を図る食肉処理施設を認証するもので、認証された食肉処理施設は、生産したジビエ製品等に認証マークを表示して安全性をアピールすることができます。令和元(2019)年度末時点では、14施設が認証を取得しており、更なる拡大が期待されます。
(需要拡大に向けてジビエプロモーションを展開)
シカ肉は低カロリーかつ高栄養価の食材として注目されており、アスリート食としての消費の拡大も期待されています。
農林水産省は、ジビエの全国的な需要拡大に向けたプロモーションとして、ジビエを提供している飲食店やイベント情報、国内消費者やインバウンド向け動画等の様々な情報をWebサイト「ジビエト」で紹介しています(図表3-5-7)。
また、消費者がジビエ料理を食べる機会を創出するため、前年度に引き続き、令和元(2019)年度も、全国の飲食店等でジビエメニューを提供する全国ジビエフェアを実施しました(図表3-5-8)。


事例:ジビエを地域の特産品に(石川県)
捕獲したイノシシを処分するだけではなく、収入につなげられないかとの思いから、石川県羽咋市(はくいし)では、平成27(2015)年に食肉処理施設を整備し、捕獲したイノシシを地域資源として活用する「のとしし大作戦」を開始しました。平成29(2017)年には合同会社のとしし団(だん)を設立し、ジビエの本格的な生産が始まりました。
ジビエを地域の特産品にするという目標の下、精力的な営業により、地域の飲食店やスーパーといった通年の出荷先を確保しているほか、同社によるぼたん鍋用の精肉はふるさと納税返礼品として登録され、好評を博しています。このような活動が評価され、平成30(2018)年度には「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」のジビエグルメ賞を受賞しました。
事例:野生鳥獣の全頭搬入を目指して(鳥取県)
鳥取県若桜町(わかさちょう)の食肉処理施設わかさ29工房(にくこうぼう)は、地域で捕獲された野生鳥獣の全頭搬入を目指しており、捕獲者の研修や山中への保冷車での集荷に取り組んでいます。全国の食肉処理施設の9割では、シカの年間処理頭数が500頭以下にとどまっていますが、平成30(2018)年度には、同施設では約2,300頭の処理を実現しています。
また、鳥取県内のジビエの食肉処理施設として、平成29(2017)年6月には、初めて鳥取県HACCP(*)適合施設の認定を受け、令和元(2019)年7月には国産ジビエ認証を受けるなど、施設の衛生管理の高度化を図っています。さらに、新たにジビエに取り組む食肉処理施設担当者に対し、解体処理の研修を実施するなど、食肉処理施設をけん引する存在として期待されています。
* 鳥取県食品衛生条例に基づくHACCPによる工程管理を行う施設、食品を認定する制度。HACCPは用語の解説3(2)を参照
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883
FAX番号:03-6744-1526