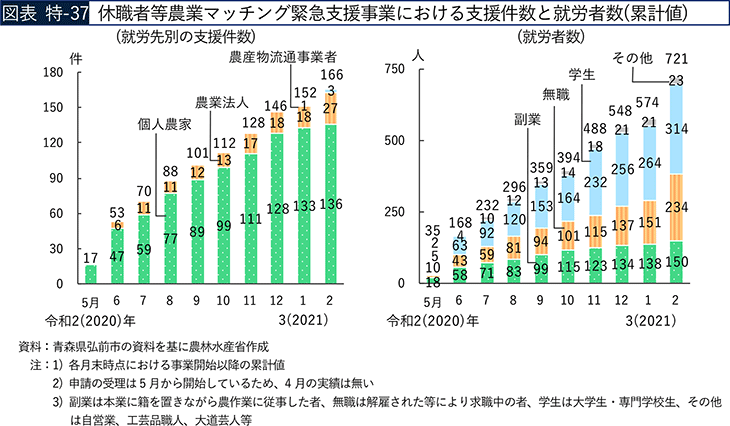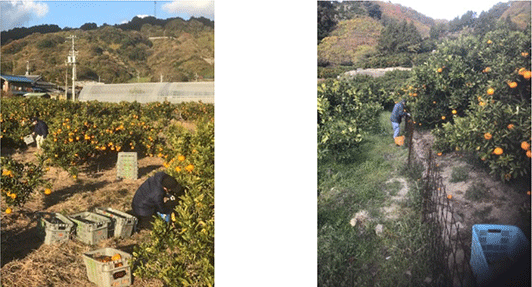(2)農業生産・販売面での影響と新たな動き エ 労働力確保に向けた動き
(他産業との連携により労働力を確保)
新型コロナウイルス感染症の影響により、営業自粛や客数減少等による事業活動の縮小を余儀なくされた宿泊業・飲食業等においては、多数の休業者・失業者が発生しましたが、このような中、農業経営体(*1)がこれらの産業からの労働者を雇用する動きが見られました。
長野県の佐久浅間(さくあさま)農業協同組合では、地元の軽井沢(かるいざわ)旅館組合と協力し農繁期を迎えるレタス農家等の農業経営体と訪日外国人旅行者の減少や外出自粛の影響で従業員の雇用継続が困難であった宿泊施設の従業員等のマッチング支援を令和2(2020)年4月に開始しました。この取組によって、同年11月までに7人の人材が農業現場で雇用されました。
青森県弘前市(ひろさきし)では、休業を余儀なくされた旅館業や、飲食業、製造業等の休職者等と、農繁期を迎えるりんご農家等の農業経営体を、農協等と連携しマッチングを図り、雇用した農業経営体に対して、1日当たりの賃金の半額(上限3,000円)を助成する「休職者等農業マッチング緊急支援事業」を令和2(2020)年4月に開始しました。
同事業の実施により、調理師がりんご等の食材の生産に携わることができたほか、一時的な雇用から継続雇用へと進展した事例が見られるなど、副次的な効果も生じています。令和3(2021)年2月末時点での支援件数は166件、就労者数は721人となっています(図表 特-37)。
また、JA全農は旅行会社の株式会社JTBと連携し、観光業で働く人に農業の現場で働いてもらうための「農業労働力支援事業」に取り組み始めました。JAグループが農家の労働力需要を取りまとめ、株式会社JTBがホテルや旅館、バス会社から人材を募り、アルバイト雇用した上で、労働力を提供する取組です。
令和2(2020)年12月から愛媛県内でモデルケースとして開始し、6軒のみかん農家に36人の労働力を提供し、収穫作業等の作業を行いました。
JA全農は、今後、同様の事業を全国に広げていくことを目指しており、株式会社JTBのようなパートナー企業の発掘に取り組むとともに、県単位のJAグループで事業スキームを周知していくこととしています。
*1 用語の解説1、2(1)を参照
(農福連携による障害者の賃金や就労意欲の更なる向上と農業労働力の確保)
新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けた宿泊業や飲食業等に従事していた障害者が、農作業等に従事することで、賃金や就労意欲の更なる向上につながる取組も見られます。
北海道七飯町(ななえちょう)のJA新はこだて七飯(ななえ)基幹支店は、パート職員の高齢化により、従来から繁忙期における作業員の確保が課題となっていました。一方で、障害者の就労継続支援を行う函館恵愛(けいあい)会では、新型コロナウイルス感染症の拡大により運営するホテルの売上げが減少し、ホテル内で客室清掃等に従事していた障害者の賃金確保が困難となりました。
そのため、函館恵愛会とJA新はこだて七飯基幹支店が連携し、令和2(2020)年5月から、9人の障害者が同JAの花き共選場で、カーネーションの選別作業を行うこととなりました。花き共選場では、JA職員の支援の下、障害者が作業に取り組み、ホテル内での清掃等に従事していた障害者の賃金は、令和2(2020)年には月平均で前年の約2倍に増加しました。職を失っていた障害者が、農業という新たな分野に挑戦することで、安定して職を確保できるようになったことは、就労意欲の更なる向上にもつながっています。
(スマート農業で人手不足に対応)
人手不足をスマート農業機械の導入によりカバーするとともに、作業効率を向上させる動きも見られます。
静岡県静岡市(しずおかし)の株式会社鈴生(すずなり)は、100haを超える農地で枝豆やレタス等を生産し、販売しています。令和2(2020)年は、ブロッコリーの生産を本格的に開始するため、タイ等から技能実習生11人の受入れを予定していましたが、入国が困難となったことを契機として、同年8月に自動操舵トラクターや全自動移植機、自動収穫機等のスマート農業機械を導入しました。
導入した自動操舵トラクターにより耕起や畝立てに要する作業時間が72%削減されたほか、全自動移植機により、それまで5~8人必要だった定植作業を3人で行うことが可能になるなど、スマート農業機械の導入により、作業効率を向上させることができました。今後は、これを機に更なる機械化を進めるとともに、施肥の管理や品種改良等も積極的に行い、更なる収益の拡大を目指す予定です。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883