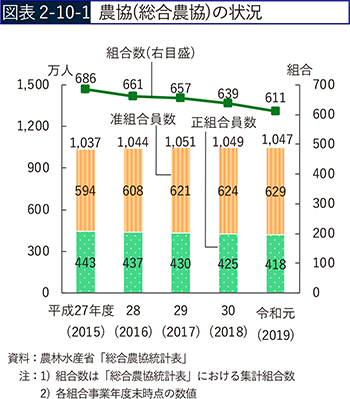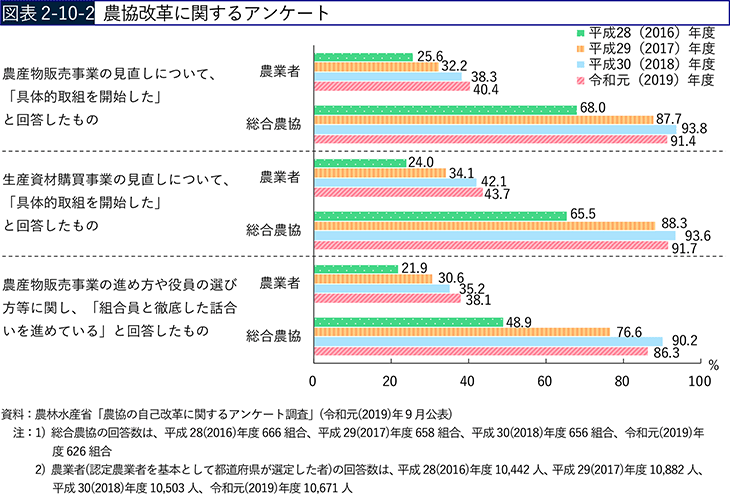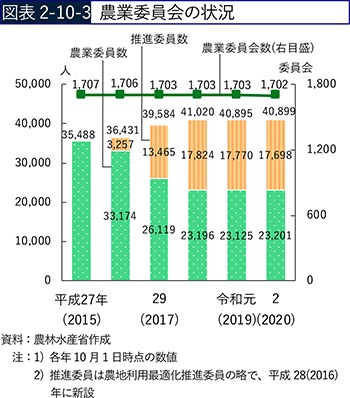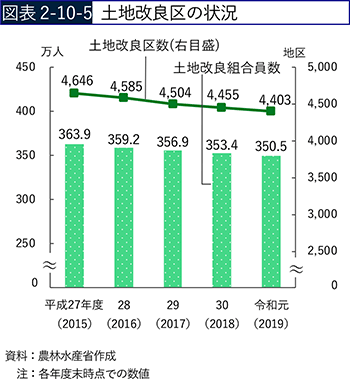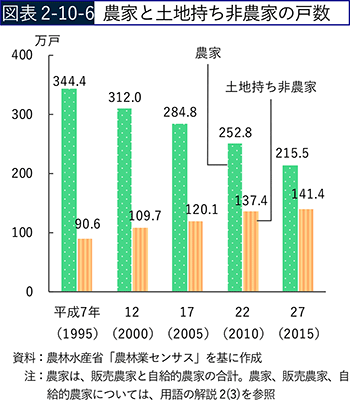第10節 農業を支える農業関連団体

各種農業関連団体については、農業経営の安定、食料の安定供給、農業の多面的機能の発揮等において重要な役割を果たしていくことが期待されています。
本節では、各種農業関連団体へのそのような期待に対応した取組の動向について紹介します。
(1)農業協同組合系統組織
(各地の農協で自己改革の取組が進展中)
農協は協同組合の一つで、農業協同組合法に基づいて設立されています。農業者等の組合員により自主的に設立される相互扶助組織であり、農産物の販売や生産資材の供給、資金の貸付けや貯金の受入れ、共済、医療等の事業を行っています。
近年の総合農協(*1)の組合数は減少傾向、組合員数は横ばいで推移しており、令和元(2019)年度の組合数は611組合、組合員数は1,047万人となっています(図表2-10-1)。組合員数の内訳を見ると、農業者である正組合員数は減少傾向で推移していますが、非農業者である准組合員数は増加傾向にあります。
農林水産省が実施した令和元(2019)年度のアンケート調査によると、地域の農協が農業者の所得向上に向けた農産物販売事業や生産資材購買事業の見直しについて、「具体的取組を開始した」と回答した総合農協、農業者双方の割合は、年々増加傾向にあり、各地の農協において、農業者の所得向上を目的とした農産物の有利販売や生産資材の有利調達、組合員との徹底的な話合い等の自己改革の取組は着実に進展していることがうかがわれます(図表2-10-2)。一方で、総合農協と農業者の評価には2倍以上の差があり、各地の農協においては、引き続き自己改革の取組を進めていくことが期待されています。販売事業や購買事業以外にも、例えば地域農業の担い手の育成等、地域の課題を踏まえた取組が各地の農協で工夫して展開されており、農林水産省としても、それらの具体的な取組をWebサイトで公表し横展開を図るなど、自己改革の取組を促進しています。
1 農業協同組合法に基づき設立された農協のうち、販売事業、購買事業、信用事業、共済事業等を総合的に行う農協
(事例)新規就農者の育成により野菜事業の黒字化を実現(福岡県)
福岡県柳川市(やながわし)の柳川(やながわ)農業協同組合では、野菜生産の担い手確保に向けて新規就農者を育成することにより、野菜事業利益の黒字化を実現しています。
同農協では、新規就農者の確保・定着を図るため、農協と柳川市、南筑後普及指導(みなみちくごふきゅうしどう)センターが連携して、定期就農相談会を行うほか、就農準備段階から現役生産者がアドバイスを行う体制を整えています。また、新規就農者は販売実績がなく、融資を受けることが難しいため、農協がハウスや農業機械を購入し、リースしています。
こうした支援により、平成24(2012)年度から令和元(2019)年度の間にいちごの生産者は53人から65人に増加し、アスパラガスの生産者は33人から46人に増加しました。その結果、野菜の販売・取扱高は平成24(2012)年度の25.6億円から令和元(2019)年度には28.9億円となり、3.3億円増加しました。
同農協では、令和3(2021)年度には販売・取扱高を30億円とすることを目指し、引き続き新規就農者を支援していくこととしています。
(コラム)新型コロナウイルス感染症対応に取り組む厚生連病院
JAグループでは、医療や保健(健康管理)、高齢者福祉等の厚生事業も行っています。都道県郡単位で設置されている厚生農業協同組合連合会(以下「厚生連」という。)では、病院・診療所等の医療施設の運営や、高齢者福祉のサービス等の提供により、組合員や地域住民の生活を支えており、全国に105の厚生連病院、60の診療所(令和3(2021)年3月末時点)を有しています。厚生連病院については、その43%が人口5万人未満の市町村に立地し、農山村を始め地域における基幹施設としての役割を果たしています。
厚生連病院では、感染症指定医療機関に指定されている病院を始めとして、令和2(2020)年1月以降の新型コロナウイルス感染症の発生初期から感染者の受入れを行ってきました。一部の厚生連病院では大型クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号において発生した感染者を受け入れました。その後も各地の厚生連病院では感染者を受け入れており、同年1~12月までの間で受入実績がある病院は67、受け入れた患者は3,049人に上ります。
こうした厚生連に対して、日本中央競馬会からは5億円の寄附が行われたほか、全国農業協同組合連合会(全農)からは食事サポート、全国共済農業協同組合連合会(全共連)や農林中央金庫、農協等からはマスク等の寄贈が行われています。
(事例)各地の農協等における新型コロナウイルス感染症拡大を受けた取組
(通販による応援消費の取組)

送料無料キャンペーンのバナー画像
資料:JA全農
JA全農は、平成13(2001)年から、全国の農協や生産者が農畜産物や加工品等を産地直送するインターネット販売サイト「JAタウン」を運営してきました。新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、農産物の売り先に困っていた生産者を支援するため、令和2(2020)年5月から、和牛、果実、乳製品、花きを対象に、送料をJAグループが負担する「さんち直送おうちごはん 送料無料キャンペーン」を実施しました。開始後1か月間で対象アイテム数は1,000アイテムまで増加し、畜産物の販売拡大を継続的に支援しています。このような産地支援や旺盛な巣ごもり需要の影響を受けて、キャンペーンの効果もあり、令和2(2020)年のJAタウンの売上高は前年比で約2倍に増加しました。
(他産業とのマッチングによる人材確保の取組)
長野県の佐久浅間(さくあさま)農業協同組合では、地元の軽井沢(かるいざわ)旅館組合と協力し、レタス農家等の農業経営体と訪日外国人旅行者の減少や外出自粛の影響で雇用継続が困難であった宿泊施設の従業員等のマッチング支援を、令和2(2020)年4月に開始しました。この取組によって、同年11月までに7人の人材が農業現場で雇用されました。
また、JA全農は旅行会社の株式会社JTBと連携し、観光業で働く人に農業の現場で働いてもらうための「農業労働力支援事業」に取り組み始めました。JAグループが農家の労働力需要を取りまとめ、株式会社JTBがホテルや旅館、バス会社から人材を募り、アルバイト雇用した上で、労働力を提供する取組です。令和2(2020)年12月から愛媛県内でモデルケースとして開始し、6軒のみかん農家に36人の労働力を提供し、収穫作業等の作業を行いました。
(2)農業委員会系統組織
(農地利用の最適化に向けてより一層の取組を推進)
農業委員会は、全国の市町村に設置され、農地法等の法令業務(農地の権利移動の許可や農地転用案件への意見具申)を行う行政委員会です。農業委員会の業務は、平成28(2016)年4月に施行された改正農業委員会法において、従来の農地法等の法令業務に加え、農地利用の最適化業務(担い手への農地の利用集積、遊休農地(*1)の解消、新規参入の促進)が必須化されました。これに伴い、農業委員とは別に、各地域において農地利用の最適化を推進する農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)が新設され、令和元(2019)年度から、新体制の2期目がスタートしました。令和2(2020)年における農業委員数は2万3,201人、推進委員数は1万7,698人で合わせて4万899人となっています(図表2-10-3)。
令和2(2020)年4月に施行された改正農地中間管理事業法に基づき、地域の将来的な担い手・農地利用の青写真を定めた「人・農地プラン」を見直すことで、担い手への農地の集積率を8割に引き上げるという目標の実現に向け、農業委員会はもとより、市町村、農地バンク、土地改良区、農協等が課題解決策を持ち寄り、地域の関係者が一丸となって取り組んでいくこととしています。農業委員会は、農地のコーディネーターとして、農地の保有・利用状況や所有者の意向等、農地の利用集積に向けた有益な情報を提供することで、農地利用の最適化の一層の推進に資することが期待されています。
1 用語の解説3(1)を参照
(3)農業共済団体
(1県1組合化等による業務効率化、農業保険への加入促進の取組が進展中)
農業共済制度は、農業保険法の下、農業共済組合及び農業共済事業を実施する市町村(以下「農業共済組合等」という。)、 県単位の農業共済組合連合会、国の3段階で運営されてきました。近年、業務効率化のため、農業共済組合等の合併により県単位の農業共済組合を設立するとともに、農業共済組合連合会の機能を県単位の農業共済組合が担うことにより、農業共済組合と国の2段階で運営できるよう、1県1組合化を推進しています。令和2(2020)年4月1日時点では41都府県で1県1組合化が実現しており、まだ実現していない道県にある農業共済組合等においては、引き続き1県 1組合化等による業務の効率化を進めることとしています(図表2-10-4)。
また、平成30(2018)年4月に全国農業共済組合連合会が設立され、平成31(2019)年1月から始まった収入保険(*1)の業務を実施しています。その業務の一部は、農業共済組合等又は農業共済組合連合会に委託されています。近年多発する自然災害や価格低下等の様々なリスクに備えるためには、収入保険への加入が重要となっています。令和2 (2020)年における青色申告を行っている農業経営体のうち収入保険に加入している割合は10.2%であることから、農業共済団体においては、引き続き収入保険への加入を促進していくことが期待されています。
1 第2章第5節を参照
(4)土地改良区
(土地改良区の組織運営基盤の強化に向けた取組が進展中)
土地改良区は、圃場(ほじょう)整備等の土地改良事業を実施するとともに、農業水利施設(*1)等の土地改良施設の維持・管理等の業務を行っており、令和元(2019)年度末時点で4,403地区となっています(図表2-10-5)。
農業者の高齢化による離農や農地集積の進展等に伴い、土地持ち非農家(*2)が増加しています(図表2-10-6)。このような中、土地改良区においても組合員の中での土地持ち非農家の割合が増加していることや組合員数の減少等が課題となっています。今後も、土地持ち非農家が増加すれば、土地改良施設の管理や更新等に関する土地改良区の意思決定が適切に行えなくなるおそれがあります。
このような状況を受けて、実際に農業を行っている耕作者の意見が適切に反映される事業運営体制への移行を進めるため、平成31(2019)年4月に改正された土地改良法では、土地改良区の准組合員制度の導入や、農地の所有者から耕作者への組合員資格交代手続の簡素化等により、耕作者が事業運営により参加しやすい仕組みが作られました。また、将来にわたって土地改良施設等の維持・管理や更新を適切に進めるために、同法では、財務状況の透明性を高め、計画的な施設更新を図ることを目的とする貸借対照表の作成・公表を令和4(2022)事業年度から行うこととされました。
農林水産省としても、土地改良区の規模・組織体制の違いにより準備の進捗に差が生じることのないよう、小規模な土地改良区に対する巡回指導等の支援を行っています。
1 用語の解説3(1)を参照
2 用語の解説2(3)を参照
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883