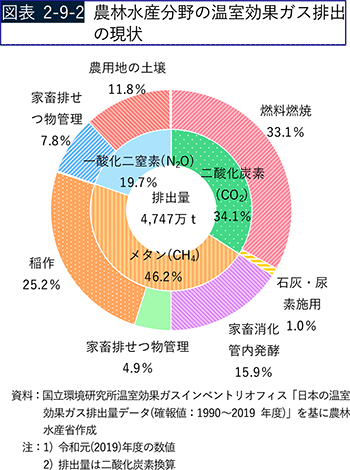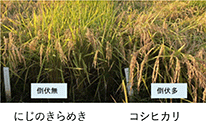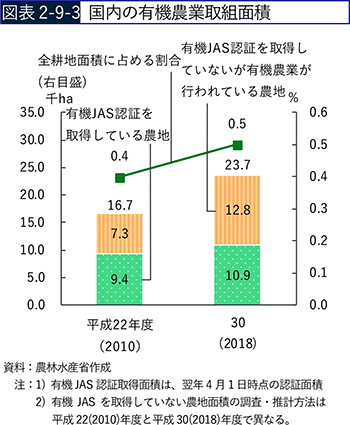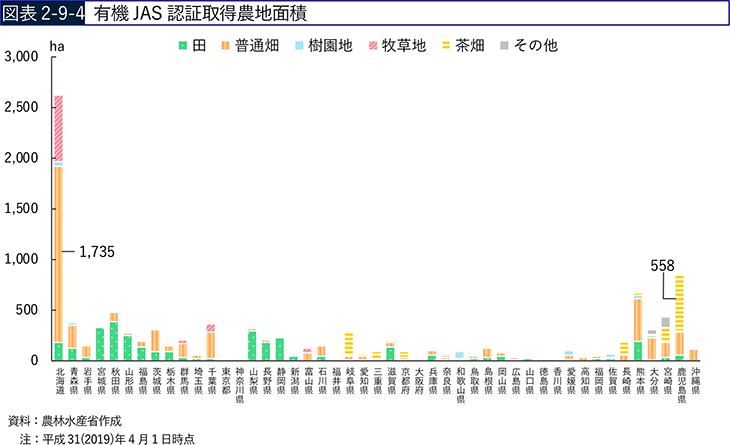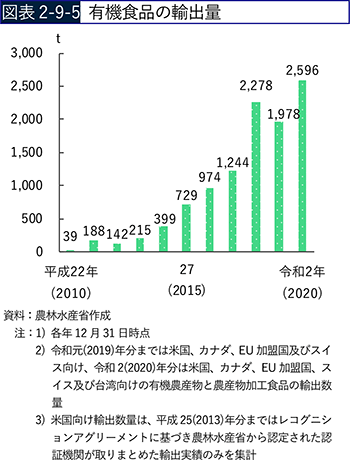第9節 気候変動への対応等の環境政策の推進
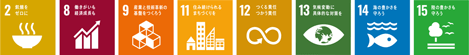
令和2(2020)年、京都議定書に代わる地球温暖化対策の国際ルールであるパリ協定(*1)が実行段階に入り、また、同年10月には、総理所信表明演説において、令和32(2050)年までに我が国の温室効果ガス(*2)の排出を全体としてゼロ(*3)にすること(「カーボンニュートラル」)が宣言されるなど、気候変動への対応の加速化が求められています。
国内では、このような動きを受け、持続可能な食料システムの構築に向けて、食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現するため「みどりの食料システム戦略」(*4)の策定に向けた検討を進めています。
本節では、食料・農業・農村分野における気候変動に対する緩和・適応策や、生物多様性の保全に向けた取組を示すとともに、有機農業の推進状況や企業・消費者とのコミュニケーションについて紹介します。
1 平成27(2015)年の国連気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)で採択された、地球温暖化対策の国際ルール。パリ協定は世界の平均気温の上昇を工業化以前に比べ2℃未満に抑えることを目指し、1.5℃を努力目標としている。さらに全ての締約国は自国が決定する温室効果ガスの削減目標を提出し、その目標に向けた取組の実施状況を報告する必要がある。
2 用語の解説3(1)を参照
3 二酸化炭素を始めとする温室効果ガスの排出量から、森林等による吸収量を差し引いてゼロを達成すること
4 トピックス2を参照
(1)気候変動に対する緩和・適応策の推進
(パリ協定の目標達成に向けて)
近年、気候変動に伴う気温の上昇や、気候変動による強度や頻度の増大が懸念されている大雨、台風等の異常気象や気象災害が世界各地で生じており、気候変動対策は喫緊の課題となっています。
我が国では令和元(2019)年6月に策定した「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」において、最終到達点として掲げた脱炭素社会の実現に向け、令和32(2050)年までに温室効果ガスの排出を80%削減することとしています。このため、令和2(2020)年1月に官房長官を議長とする統合イノベーション戦略推進会議で決定した「革新的環境イノベーション戦略」を踏まえ、農林水産分野では、農地・森林・海洋による二酸化炭素の吸収・固定、農畜産業からのメタン・一酸化二窒素の排出削減、再生可能エネルギーの活用とスマート農林水産業の推進等、イノベーションを創出するための新たな技術開発に取り組んでいます(図表2-9-1)。
また、令和2(2020)年7月には、革新的環境イノベーション戦略を着実に実施し、最大限の成果を生み出すことを目的として「グリーンイノベーション戦略推進会議」を設置し、革新的環境イノベーション戦略のフォローアップ等の議論を行いました。
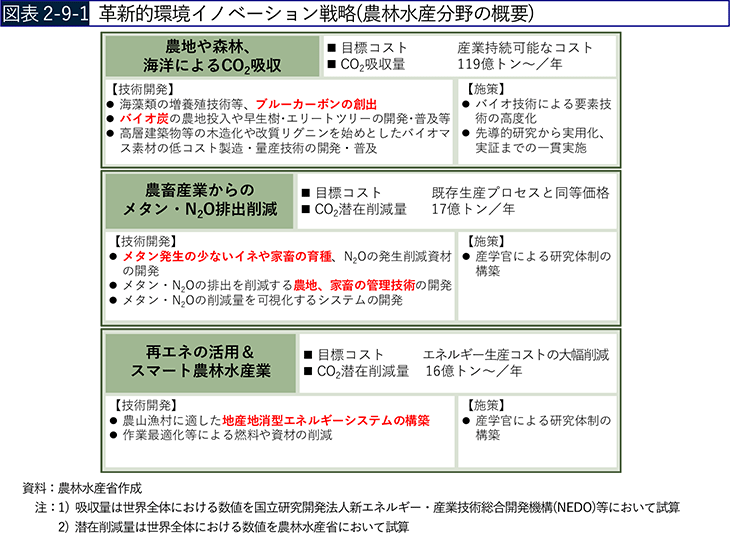
(総理所信表明演説で、令和32(2050)年までにカーボンニュートラルの実現を宣言)
令和2(2020)年10月に行われた総理所信表明演説で、令和32(2050)年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすること(「カーボンニュートラル」)が宣言され、より早期に脱炭素社会を実現することが求められています。
このため、令和2(2020)年10月、農林水産省と環境省は、気候変動に直面する中で顕在化している課題の解決に向けて、大臣間で連携を強化することで合意しました。今後、農林水産業における令和32(2050)年までのCO2ゼロエミッション化を目指し、農山漁村における再生可能エネルギーの導入の促進等について連携・協力するほか、食品ロスや海洋プラスチックごみ削減等の循環経済への移行に向けた取組や、国連気候変動枠組条約締約国会議等の国際交渉において、連携していくこととしています。
また、令和2(2020)年12月、経済と環境の好循環を作っていく産業政策として、経済産業省等の関係府省と連携の下、グリーンイノベーション戦略推進会議の意見も踏まえて「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を策定しました。本戦略の中で、今後の産業としての成長が期待され、温室効果ガスの排出削減の観点からも令和32(2050)年にカーボンニュートラルを目指す上で取組が不可欠な14分野について、現状と課題、今後の取組方針等をまとめた「実行計画」を策定しており、「食料・農林水産業」分野もその一つとなっています。
具体的には、みどりの食料システム戦略を策定し、スマート農林水産業等の実装の加速化による化石燃料起源のCO2ゼロエミッション化、森林及び木材・農地・海洋における炭素の長期・大量貯蔵の技術等の確立、スマートフードチェーンの活用、持続可能な消費の促進等の取組等を推進することとしています。
さらに、令和2(2020)年12月、脱炭素社会の実現に向けて、政府と地方自治体との連携の在り方等を議論する「国・地方脱炭素実現会議」を官房長官を議長として設立し、農林水産大臣も政府側メンバーとして参加しています。同会議では、農山漁村・里山里海等の地域の取組と国民のライフスタイルに密接に関わる主要分野において、国と地方が協力して、令和32(2050)年までに、脱炭素、かつ持続可能で強靱(きょうじん)な活力ある地域社会を実現する行程を「地域脱炭素ロードマップ」として描くこととしています。
(緩和策と適応策を一体的に推進)
地球温暖化の要因である温室効果ガスは、化石燃料の燃焼によってその多くが発生していますが、農林水産業においても、燃料の燃焼、稲作、家畜の消化管内発酵(げっぷ)など営農活動に伴い温室効果ガスが排出されています。我が国の農林水産分野における令和元(2019)年度の排出量は4,747万t(二酸化炭素換算)で、我が国の総排出量の3.9%を占めています(図表2-9-2)。
農林水産省では、森林吸収源対策や温室効果ガスの排出削減対策など地球温暖化を防止するための「緩和策」と、高温でも品質低下が起きにくい生産安定技術や品種の開発・普及など気候変動による被害を回避・軽減する「適応策」に取り組んでいます。
さらに、緩和策と適応策を一体的に推進するため、令和2(2020)年11月には大臣政務官をチーム長とする「農林水産省地球温暖化対策推進チーム」の体制を拡充しました。気候変動による影響の評価に関する最新の知見や、政府の地球温暖化対策計画及び適応計画の改定、みどりの食料システム戦略の検討状況等を踏まえ、令和3(2021)年度中に緩和策としての「農林水産省地球温暖化対策計画」(平成29(2017)年3月決定)と適応策としての「農林水産省気候変動適応計画」(平成30(2018)年11月改定)の改定に向け、検討を進めています。
(フードサプライチェーンにおける脱炭素化の実践とその可視化を推進)
農林水産省は、令和2(2020)年3月に新たな「農林水産省環境政策の基本方針」を策定し、農林水産業・食品産業の成長が環境も経済も向上させることを理念として掲げました。基本方針の中では、カーボンニュートラルを実現するため、フードサプライチェーン全体を通じて温室効果ガスの排出削減と吸収を推進するとともに、その取組を可視化し、気候変動対策への投資等のESG投資(*1)や環境と調和した生産方法で作られた農林水産物・食品の消費等の持続可能な消費行動を促すこととしており、基本方針の理念はみどりの食料システム戦略の中間取りまとめへも反映させています。
このことを踏まえ、農林水産省では、同年9月から「フードサプライチェーンにおける脱炭素化の実践とその可視化の在り方検討会」を開催しました。検討会では、令和3(2021)年4月までにTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)提言(*2)に基づく取組事例を調査し、食品事業者向けに分かりやすい手引を作成するとともに、新たな脱炭素化技術や定量化等の情報を基に、農林水産業・食品産業等の関係者向けの脱炭素技術の紹介資料を作成し、農林水産省Webサイトにおける情報発信や食品関連事業者への周知等により、サプライチェーンを通じた脱炭素化の実践とその可視化の取組を促すこととしています。
1 従来の財務情報だけでなく、環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)要素も考慮した投資のこと
2 第1章第3節参照
(顕在化しつつある気候変動の影響に適応するための品種や技術の開発・普及を推進)
農業生産は一般に気候変動の影響を受けやすく、各品目で生育障害や品質低下等の地球温暖化によると考えられる影響が現れており、この影響を回避・軽減するための品種や技術の開発・普及が進められています。
農林水産省では、「農林水産省気候変動適応計画」(平成30(2018)年11月改定)に基づき、都道府県の協力を得て農作物等の地球温暖化の影響や適応策の導入状況について調査を行い、「地球温暖化影響調査レポート」を公表しています。令和2(2020)年10月に公表したレポートにおいて、水稲は高温でも品質低下が起こりにくい高温耐性品種の導入が進められており、令和元(2019)年産における作付面積は、前年産に比べ0.9万ha増加し、13.6万haとなったことが報告されています。
また、気温の上昇による栽培地域の拡大を活用し、これまで輸入に依存していた亜熱帯・熱帯果樹等の導入も行われており、例えば愛媛県でブラッドオレンジやアボカドの普及が進められています。
(2)生物多様性の保全と利用
(次期生物多様性国家戦略の策定に向けて)
平成22(2010)年に愛知県で開催された生物多様性条約第10回締約国会議(COP10(*1))で、世界目標である「生物多様性戦略計画2011-2020及び愛知目標」が採択されました。これを受け、我が国では生物多様性国家戦略2012-2020を策定し、愛知目標を踏まえた国別目標を設定しました。令和3(2021)年に開催予定の生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)では、愛知目標の達成状況等を踏まえ、今後10年間に達成すべき新たな世界目標が決定される予定です。それに伴い、我が国では同目標の達成に向けて、次期生物多様性国家戦略(以下「次期国家戦略」という。)を策定することとしています。
次期国家戦略の策定に向けて、農林水産省では、農林水産業と農山漁村における生物多様性に関する「農林水産省生物多様性戦略」(平成24(2012)年2月改定。以下「戦略」という。)を見直すため、令和2(2020)年度に有識者による戦略検討会を開催し、愛知目標の達成に向けた農林水産分野の取組状況と次期戦略の改定の方向性について整理を行いました。次期戦略は、みどりの食料システム戦略を踏まえて検討することとしており、国民と共有できる未来像として令和12(2030)年のビジョンを設定し、農山漁村が育む自然の恵みを生かし、環境と経済の向上の両立を目指していく旨を記載することとしています。
1 COPは締約国会議(Conference of the Parties)の略。10は第10回を指す。
(3)有機農業の更なる推進
(有機食品の市場規模が拡大)
世界の有機食品市場は、欧米を中心に拡大しており、平成20(2008)年から平成30(2018)年までの10年間で倍増しています。これに対応する形で世界の有機農業(*1)の取組面積も、同期間に2倍に拡大しており、例えば、平成30(2018)年の欧州における取組面積は1,560万ha、欧州全体の耕地面積に占める割合は3.1%となっています(*2)。
我が国においても有機食品の市場規模は拡大しており、平成21(2009)年の1,300億円から平成29(2017)年には1,850億円(*3)と、8年間で1.4倍になったと推計されています。
これに対応し、我が国の有機農業の取組面積も平成22(2010)年度から平成30(2018)年度にかけて4割拡大し2.4万ha(*4)、全耕地面積に対する割合は0.5%となっています(図表2-9-3)。我が国では、有機食品の日本農林規格(JAS)に適合した生産が行われていることを認証された事業者のみが「有機JASマーク」を貼ることができ、この有機JASマークがない農産物、畜産物、それらの加工食品に、「有機」、「オーガニック」等の名称の表示を付すことはJAS法(*5)で禁止されています。平成31(2019)年に有機JAS認証を取得している農地は1.1万haとなっており、普通畑(*6)では北海道で1,735ha、近年増加している茶畑は鹿児島県で558haと面積が大きくなっています(図表2-9-4)。
1 化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減するとともに、生物多様性の保全等、生物の生育・生息環境の維持にも寄与するもの
2 FiBL&IFOAM「The World of Organic Agriculture Statistics & Emerging Trends 2020」
3 農林水産省「平成29 年度有機食品マーケットに関する調査」を基に推計
4 有機JAS認証取得農地面積に有機JASを取得していないが有機農業が行われている農地面積(農林水産省推計)を加えた数値
5 正式名称は「日本農林規格等に関する法律」
6 畑のうち樹園地及び牧草地を除いた畑
(有機食品の輸出は増加傾向)
国内外での有機食品市場の拡大に伴い、我が国で生産された有機食品の輸出量は増加しており、令和2(2020)年は2,596tとなりました(図表2-9-5)。主な輸出品目は茶、しょうゆ、味噌等です。
諸外国の多くは「有機」の表示を規制しており、自国の制度により有機認証を受けた食品でなければ「有機」の表示はできませんが、国・地域間で有機認証制度の同等性が認められている場合には、自国で有機認証を受けた食品を輸出先に「有機」の表示を付して輸出することが可能です。我が国の有機JAS認証は、EU、米国、カナダ、スイス及び台湾の有機認証制度と同等性が認められており(*1)、これらの国・地域では我が国の有機JAS認証を受けた農産物・農産物加工食品に「有機」の名称(Organic等)を表示して輸出することができます。
また、令和2(2020)年7月16日以降は、有機JAS認証を受けた畜産物・畜産物を含む加工食品について、米国、カナダ及びスイスに「有機」と表示して輸出することができるようになりました。有機食品の輸出促進の観点から、引き続き、各国から我が国の有機JASが同等性を認められるよう推進していくこととしています。
1 令和2(2020)年10月時点
(有機農業の取組拡大に向けて)
「有機農業の推進に関する法律」に基づき令和2(2020)年4月に定められた「有機農業の推進に関する基本的な方針」では、今後の国内外の有機食品市場の拡大を見通し、我が国の有機農業の取組面積を令和12(2030)年までに6.3万haとすることを目標としています。また、令和3(2021)年3月に公表されたみどりの食料システム戦略の中間取りまとめにおいては、令和32(2050)年までに、有機食品市場を拡大しつつ、耕地面積に占める有機農業(*1)の取組面積割合を25%(100万ha)に拡大することを目指すこととしています。
農林水産省では、有機農業の取組拡大のため、生産面では人材育成や産地づくり、消費面では販売機会の多様化や消費者の理解の増進等を推進しています。令和2(2020)年度からは、都道府県による有機農業指導員の育成、有機農業に新たに取り組む者の技術習得支援や有機農地の試行的な取組等に対する支援を開始しました。さらに、全国27地区で、有機農業者グループの技術習得や販路開拓の取組への支援により有機農業の産地づくりを推進し、一部では、生産した有機食品が学校給食の食材として活用されています。
このような産地づくりに資するため、水田や畑地の雑草対策技術の実証支援や、点在する有機農業者と消費地間の物流の合理化に向けた実証の支援を行い、令和3(2021)年3月には、取組の成果を共有するセミナーを開催しました。
また、令和元(2019)年8月に立ち上げた「有機農業と地域振興を考える自治体ネットワーク」において、耕作放棄地を活用した有機農業の取組事例を共有するセミナーを令和2(2020)年9月に開催し、自治体間での情報共有も推進しています。
1 国際的に行われている有機農業
(4)農業の自然循環機能の維持増進とコミュニケーション
(民間企業等を巻き込んだ持続可能な生産・消費の拡大への取組)
SDGs(*1)のゴール12(生産・消費)には「つくる責任つかう責任」が位置付けられており、農林水産業の持続的な発展のためには、環境と調和した持続的な生産とともに、消費についても持続可能なものとしていくことが求められています。
このため、農林水産省では消費者庁、環境省と連携し、食品や農林水産物の持続的な生産・消費を達成するため、令和2(2020)年6月、生産から消費に至るサプライチェーン全体に関わる事業者等の連携を促す「あふの環(わ)2030プロジェクト~食と農林水産業のサステナビリティを考える~」を立ち上げました。令和3(2021)年3月現在、116企業・団体が参画しています。本プロジェクトでは、令和2(2020)年9月17~27日に「サステナウィーク~未来につながるおかいもの~」を実施し、本プロジェクトに参画する企業等による持続可能な取組の発信や、生産現場での体験イベントが行われ、持続可能な消費について多くの消費者が気付を得られるイベントになりました。
また、生物多様性等に効果の高い有機農業を国内で更に拡大していくため、令和2(2020)年9月、国産の有機食品を取り扱う小売事業者等の協力の下、国産の有機食品の需要喚起を推進するためのプラットフォーム「国産有機サポーターズ」を立ち上げ、国産の有機食品の需要拡大に取り組んでいます。
1 用語の解説3(2)を参照
(コラム)EUのFarm to Fork戦略
令和2(2020)年5月20日、欧州委員会は欧州グリーンディールの一環として、「Farm to Fork戦略」 (政策文書:Communication)を公表しました。
持続可能な食料システムの構築に向けたEUの戦略であり、有害性の高い農薬や肥料の使用の削減、抗菌剤の販売の削減、有機農業の割合の上昇、食品ロスの削減といった数値目標が定められました。
詳細内容は、今後の欧州議会及び理事会での議論を踏まえ、令和5(2023)年の立法化までに明らかになる予定です。
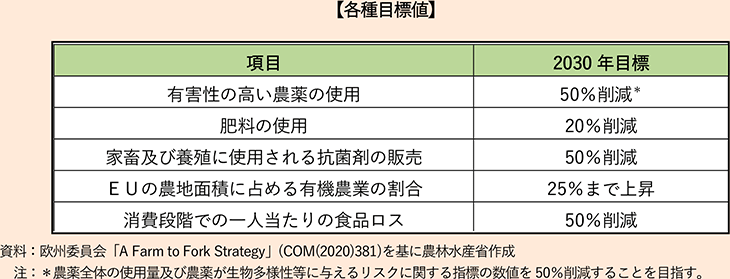
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883