トピックス2 みどりの食料システム戦略~食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現~

食料・農林水産業は、自然災害や気候変動に伴う影響、生産者の減少等による生産基盤の脆弱(ぜいじゃく)化や農山漁村の地域コミュニティの衰退等の課題に直面しています。また、SDGs(持続可能な開発目標)(*1)への対応や令和32(2050)年までのカーボンニュートラルの実現に向けて、食料・農林水産業の分野においても貢献が求められています。
諸外国では、持続的な生産・消費が活発化するとともにESG投資(*2)が拡大しています。中でも、EUは令和2(2020)年5月に環境や健康に関する「Farm to Fork戦略」(*3)を発表し、これを国際ルールに反映させようとする動きが見られます。このような中、同年10月から、我が国の食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現させるための「みどりの食料システム戦略」の検討を開始し、令和3(2021)年3月に中間取りまとめを公表しました。以下では、中間取りまとめで示された戦略の基本的な考え方を紹介します。
1 平成27(2015)年9月の国連サミットにおいて全会一致で採択された、令和12(2030)年を期限とする国際社会全体の開発目標
2 従来の財務情報だけでなく、環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)要素も考慮した投資のこと
3 第2章第9節を参照
(策定に当たっての考え方)
戦略においては、革新的な技術・生産体系を順次開発し、社会実装することにより、令和32(2050)年までに農林水産業のCO2ゼロエミッション化の実現を図ることとしています(図表トピ2-1)。また、同年までに化学農薬や化学肥料の使用量の低減、有機農業の取組面積の拡大、食品製造業の労働生産性の向上、持続可能性に配慮した輸入原材料調達の実現等を目指すこととしています。
実現に向けては、食料システムを構成する農林漁業者・食品企業・消費者の行動変容が必要不可欠です。そのため、食料システムが抱える課題に対する関係者の理解の促進を図るとともに、意欲的な取組を後押しする必要があります。さらに、令和3(2021)年9月に開催予定の国連食料システムサミット等において、この戦略をアジアモンスーン地域の持続的な食料システムのモデルとして我が国から発信することとしています。
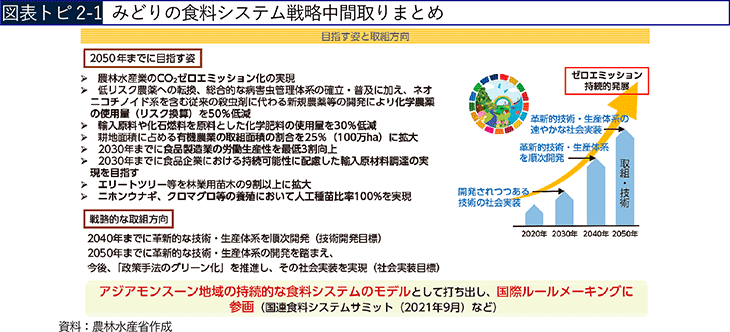
(資材・エネルギー調達における脱輸入・脱炭素化・環境負荷軽減の推進)
新型コロナウイルス感染症の影響により、複数の穀物の輸出国等において輸出規制が行われるなど、サプライチェーンの混乱が発生しました。我が国では、食料生産を支える肥料等の資材原料やエネルギーの調達を輸入に依存していることから、資材原料やエネルギーを国内で調達する割合を増やすことが重要です。
このため、営農型太陽光発電等による地産地消(*1)型エネルギーマネジメントシステムの構築といった持続可能な資材やエネルギーの調達等を推進していくこととしています。
1 用語の解説3(1)を参照
(イノベーション等による持続的生産体制の構築)
我が国の農業生産の担い手は年々高齢化、減少していることから、労働力不足等の生産基盤の脆弱化が深刻な課題となっています。そのため、スマート農林水産業や農業機械の電化等を通じて、高い労働生産性と持続性を両立する生産体系への転換を推進することとしています。
(ムリ・ムダのない持続可能な加工・流通システムの確立)
加工・流通段階では、データ・AI(*1)の活用による流通の合理化や、食品製造・加工、小売、外食の労働生産性の向上等が課題となっています。電子タグを活用した商品・物流データの連携や需給予測システムの構築、ロボットを活用した加工・調理の自動化・非接触化により、流通・加工の効率化とともに、食品ロスの削減を目指すこととしています。
1 用語の解説3(2)を参照
(環境にやさしい持続可能な消費の拡大や食育の推進)
環境にやさしい消費の実現に関しては、外見ではなく、持続性を重視した消費の拡大、消費者と生産者の交流を通じた相互理解の促進等に取り組んでいくこととしています。
→第2章第9節を参照
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883








