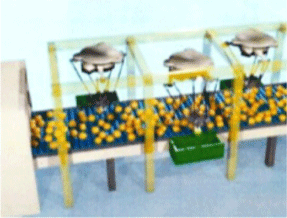トピックス3 令和元(2019)年度スマート農業実証プロジェクト
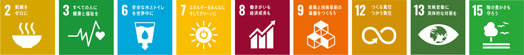
労働力不足等に直面している我が国の農業生産の現場では、ロボット、AI(*1)、IoT(*2)等の先端技術を活用した「スマート農業」の社会実装の加速化がますます重要になっています。
このため、農林水産省では、令和元(2019)年度から「スマート農業実証プロジェクト」を、初年度は69地区において各地区2年間の事業期間で実施し、農作業の自動化、情報共有の簡易化、データの活用等を実際に行い、導入コストと経営改善効果の分析や成果の情報発信をすることとしています。以下では、スマート農業実証プロジェクトの初年度の成果(中間報告)と、これを踏まえた今後の対応方針について紹介します。
*1、2 用語の解説3(2)を参照
(水田作では労働時間の削減効果を確認)
水田作では、(1)大規模水田作、(2)中山間水田作、(3)輸出水田作の3事例について、慣行農法と比較した労働時間の削減効果等を検証しています(図表トピ3-1)。
労働時間については、無人で作業ができるロボットトラクタ、水管理を遠隔・自動制御できる水管理システム、ドローンによる農薬散布等、多くの技術で削減効果が確認され、いずれの事例でも全体の労働時間が減少しました。また、収量についても、いずれの事例でも増加しました。一方、経営収支については、高額なスマート農業機械を限られた面積で実証し、機械費が大きく増加したこと等により、いずれの事例でも利益が減少しました。

(畑作等では品目により効果に差異)
畑作(小麦、大麦)、露地野菜(キャベツ、ほうれんそう、さといも、すいか)、施設園芸(ピーマン)、果樹(温州みかん)、地域作物(茶)についても、水田作と同様に営農面のデータを収集し、検証しています(図表トピ3-2)。
労働時間については、新しい省力栽培技術と組み合わせたトラクターの自動操舵システムやロボットハンドによる腐敗果の自動選別技術等のスマート農業技術の導入により、ほぼ全ての事例で、削減効果が確認できました。一方、増収に伴い収穫時間が増加した施設園芸等、労働時間が増加した事例もありました。
経営収支については、施設園芸では、環境制御装置等の導入による収量の増加により、利益が増加しましたが、その他の事例では、実証規模が限られていた中で、スマート農業機械の導入によって機械費が大きく増加したこと等により、利益が減少しました。

(今後の対応方針)
令和元(2019)年度の実証プロジェクトの成果により、スマート農業による労働時間の削減効果等のメリットや、スマート農業機械の初期投資の負担等の課題が明らかになりました。
農林水産省では、これらの課題に対して、令和2(2020)年10月に策定した「スマート農業推進総合パッケージ」(令和3(2021)年2月改訂)を踏まえた取組を推進しています。今後は、適正な最大稼働面積を見極め、スマート農業機械導入後の機械費等の削減方策の検討や、シェアリング等の農業支援サービスによる初期投資の軽減方策の検証、地域の実情に応じたスマート農業技術の導入効果の情報提供の充実等を実施していきます。
→第2章第8節を参照
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883