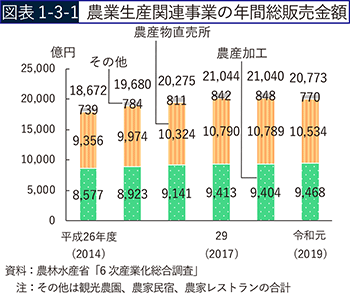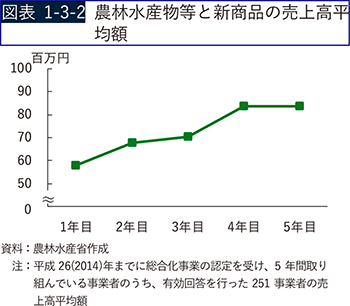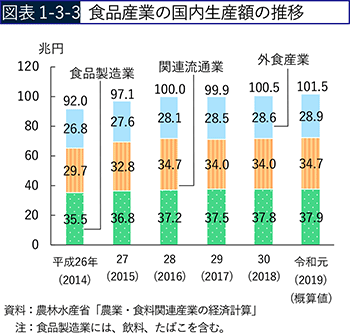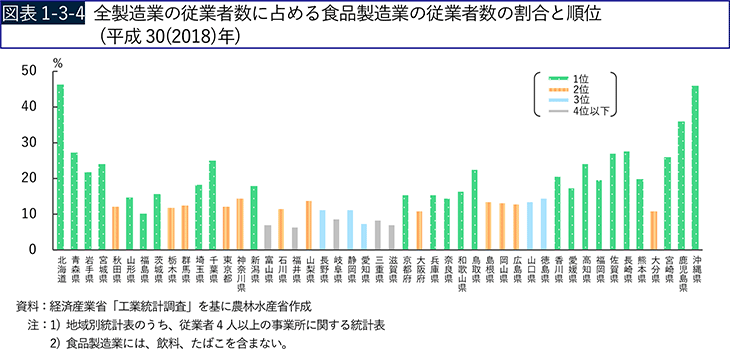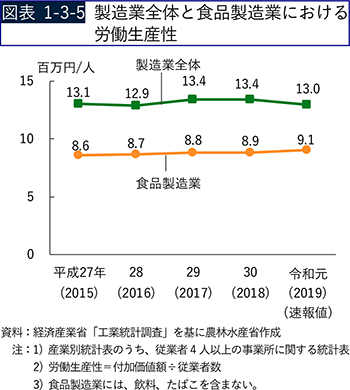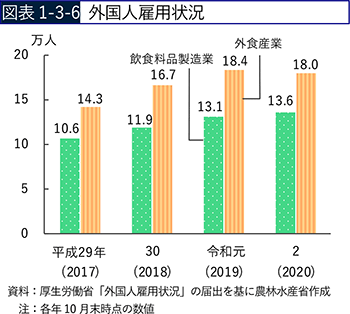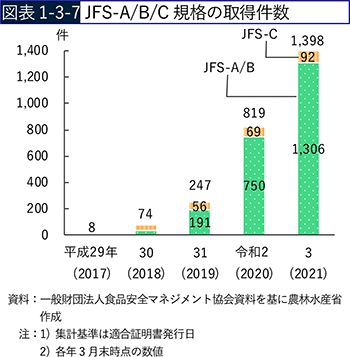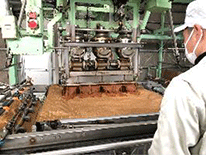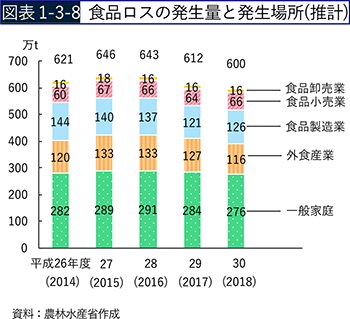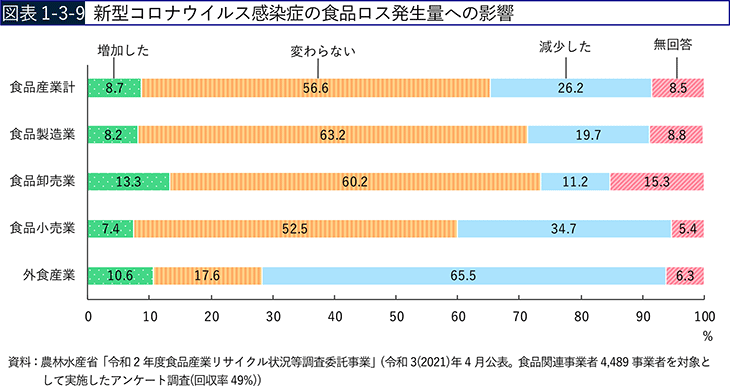第3節 新たな価値の創出による需要の開拓
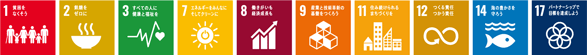
農業の成長産業化に向けて、農業生産の現場では、農産物を始めとする地域の多様な資源を有効に活用した6次産業化(*1)等の取組が重要となってきています。また、食品産業においても、多様化する食の需要を背景としたフードテック(*2)等の研究開発のほか、労働生産性の向上に向けた先端技術の導入や食品ロスの削減に向けた取組等が重要となっています。
本節では、これらの取組に係る動向について紹介します。
1 用語の解説3(1)を参照
2 フードテックについては、トピックス7を参照
(1)需要に応じた新たなバリューチェーンの創出
(6次産業化による農業生産関連事業の年間総販売金額は2兆773億円)
6次産業化に取り組む農業者等による加工・直売等の農業生産関連事業の年間総販売金額は、近年増加傾向で推移していましたが、令和元(2019)年度の年間総販売金額は、前年度と比べ268億円減少し、2兆773億円となりました(図表1-3-1)。
(6次産業化に取り組む事業者の売上高平均額は増加傾向)
六次産業化・地産地消法(*1)に基づく総合化事業計画(*2)認定件数の累計は、令和2(2020)年度末時点で2,591件となりました。農林水産省が行った認定事業者を対象としたフォローアップ調査によると、5年間総合化事業に取り組んだ事業者の総合化事業で用いる農林水産物等と新商品の売上高平均額は、増加傾向となっています(図表1-3-2)。
6次産業化に取り組む事業者に対しては、付加価値の高い6次産業化の取組の創出に向けて、都道府県段階で6次産業化プランナーを派遣し、経営改善の取組を支援するとともに、全国段階でエグゼクティブプランナーを派遣して6次産業化の事業拡大や発展に向けた支援を行っています。
1 正式名称は「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」
2 用語の解説3(1)を参照
(事例)地元生産物にこだわった農産加工からコト消費まで行う地域観光拠点型の6次産業化(長崎県)
長崎県大村市(おおむらし)の有限会社シュシュは、社員73人で、ぶどう、なし、いちごの生産・加工を行うとともに、約200戸の地域の生産者を抱える直売所を経営しています。また、農家レストランやアイス・パン等の工房、観光農園、食育体験施設等を敷地内に配置した地域観光拠点として「おおむら夢ファームシュシュ」を運営し、年間49万人を集客しています。
農産加工品の販売だけでなく、収穫体験や食育体験教室等の体験型のサービスプログラムを充実させるとともに、農家レストランで結婚式を実施するなど、コト消費にも積極的に取り組んでいます。
また、規格外農産物の加工も受託しており、地域の生産者は新たな設備投資を行うことなく所得を向上させることができています。
さらに、地域生産者と連携した農業体験や、定年帰農者を対象とした農業塾の開設等、地域農業の活性化に貢献しています。
(2)食品産業の競争力の強化
ア 食品産業の現状
(食品産業の国内生産額は101.5兆円)
食品産業は、農業と消費者の間に位置し、食品の生産、流通、消費の各段階において品質と安全性を保ちつつ食品を安定的に供給するとともに、消費者ニーズを生産者に伝達する役割も担っています。食品産業の国内生産額は、近年増加傾向で推移しており、令和元(2019)年は、前年と比べ1.0兆円増加し、101.5兆円となりました(図表1-3-3)。食品製造業ではそう菜・すし・弁当、パン類、めん類等の工場出荷額、関連流通業では小売業のマージン額(*1)、外食産業では飲食店の売上高等がそれぞれ増加しました。なお、全経済活動に占める割合は前年と比べ0.1ポイント増加し、9.7%となりました。
1 マージン額とは、販売額から売上原価を差し引いた額
(地域の雇用において重要な役割を果たす食品製造業)
各都道府県の全製造業の従業者数に占める食品製造業の従業者数の割合を見ると、多くの都道府県で1割を超えており、特に北海道と沖縄県では4割を超えています(図表1-3-4)。また、全製造業の従業者数に占める食品製造業の従業者数の割合の順位を見ると、1位が25道府県、2位が12都府県、3位が5県と、42都道府県において1位から3位に入っており、食品製造業が地域の雇用において重要な役割を果たしていることがうかがえます。
(労働生産性の向上に向けて先端技術の活用等が重要)
食品製造業の労働生産性を見ると、緩やかな上昇傾向にはあるものの、依然として製造業全体に比べて低い水準にとどまっています(図表1-3-5)。食品製造業は、小さく、柔らかく、形状が不安定な食品を取り扱うことや、高い安全性やそのための衛生管理が求められること等から機械の導入が困難な場合が多く、多くの人手に頼らざるを得ない面があります。しかし、労働力不足が顕在化する中、現状を打破するためには、従業員が働きやすい環境の整備に努めるとともに、近年発展著しいIoT(*1)等の先端技術の活用による省力化・省人化に取り組むことが重要となっています。
このため、農林水産省では、令和2(2020)年度に実際の現場において自動で食品の製造や包装作業等を行うロボット、AI(*2)を活用した検査装置等の先端技術の活用実証を行うとともに、その成果について動画によりWebサイト等で情報発信することにより、食品産業全体の生産性向上に向けた取組を支援しています。
1、2 用語の解説3(2)を参照
(事例)AIを活用した生産性向上の取組
キユーピー株式会社では、ベンチャー企業等との連携により、AIを活用した食品原料検査装置を開発しました。この装置を導入し、これまで人手・目視に頼っていた原料の検査工程を効率化することで人手を削減でき、同工程の労働生産性が25%向上しました。
多くの人手と熟練の技を必要とする食品原料検査工程の効率化は食品製造業に共通する課題ですが、既存の海外製の異物検査装置は価格が高く、性能面でも、種類や色、形が様々な野菜の原料検査へ活用するには十分ではなかったことから、同社は食品製造事業者でありながら自ら装置の開発を行いました。
さらに同社は、当該装置についてオープンイノベーションによる検知感度の改善やコスト削減、電磁波を活用した野菜内部の虫の検出技術の研究開発にも取り組んでおり、将来的には、他の食品製造事業者に低価格で広く提供し、食の安全・安心を業界全体に広げることを目指しています。
(我が国の食品産業で雇用されている外国人は年々増加)
我が国の食品産業で雇用されている外国人の主な受入れ対象は、特定技能や技能実習、身分に基づく在留資格、資格外活動許可を受けた留学生のアルバイトです。
これらの資格により我が国の食品産業において雇用されている外国人は年々増加していますが、令和2(2020)年10月末時点では、前年同月と比べ飲食料品製造業では4,926人増加の13.6万人、外食産業では3,940人減少の18.0万人となっています (図表1-3-6)。
また、特定技能制度(*1)により、我が国で雇用されている外国人は、令和2(2020)年12月末時点で、前年同月と比べ、飲食料品製造業分野で5,207人増加の5,764人、外食業分野では898人増加の998人となっています。
1 平成31(2019)年4月に改正された出入国管理及び難民認定法により創設。飲食料品製造業及び外食業等の14の特定産業が受入れ対象分野
イ 食品流通の合理化等
(食品流通の合理化を推進)
トラックドライバーを始めとする食品流通に係る人手不足が深刻化する中で、国民生活や経済活動に必要不可欠な物流の安定を確保するには、サプライチェーン全体で合理化に取り組む必要があります。特に生鮮食品や花きの輸送は、荷物の手積み、手降ろしといった手荷役作業が多い、小ロット・多頻度での輸送が多いなどの事情から、取扱いが敬遠される事例が出てきています。このような中、農林水産省、経済産業省、国土交通省は、令和元(2019)年より食品流通合理化検討会を開催し、統一規格輸送資材(パレット等)の導入による手荷役から機械荷役への転換、集出荷拠点の集約等や共同配送による効率化、トラック輸送から船舶・鉄道へのモーダルシフト、電子タグ(RFID(*1))等を活用した商品・物流情報のデータ連携等の現場実装に向けた取組を進めています。
また、卸売市場については、市場の実態に応じて、商物分離等取引ルールの設定が可能となったところであり、食品流通における卸売市場のハブ機能の強化、低温物流センターの整備等によるコールドチェーンの確保や情報通信技術等の利用による効率的な商品管理等に取り組んでいます。
1 Radio Frequency Identificationの略。電子タグに記憶された生産・流通履歴等の情報を、無線通信によって読み取ることで、移動追跡等を可能とする情報通信技術
(事例)コールドチェーン化により青果物の品質安定化・有利販売を図る(大分県)
大分県のJA全農おおいたは、令和元(2019)年より、広域で荷物を集荷する拠点となる「大分青果センター」を稼働しました。
大分青果センターは県内のストックポイントとしての役割を担い、同センターを中継することで、これまで課題とされてきた効率的な物流体制を構築するとともに、近年の物流業界を取り巻く厳しい環境による運賃コストの増嵩(ぞうすう)を抑え、生産者の所得向上につながることが期待されています。
また、産地から集荷した荷物は最低12時間以上予冷庫で冷やして品質を保ち、予冷庫の搬入口とトラック等を隙間なく密着させるドックシェルター方式を採用することで、青果物を外気に触れさせず、温度を一定管理した状態で卸売市場へ出荷することが可能なコールドチェーン化を実現しました。
これにより従来の2日目販売から3日目販売に移行したことで延着防止にもつながりました。加えて、青果物の鮮度を保つことで品質の安定化を図るとともに、販売先に正確な出荷情報を提供することで市場評価も向上しています。
令和元(2019)年度は県内の約40か所から集荷しており、同年6月から令和2(2020)年3月までの青果物の取扱実績は11,275tとなりました。令和3(2021)年度の同センターにおける取扱量は14,300tを計画しています。
ウ 規格・認証の活用
(HACCPの制度化への対応を支援)
HACCP(*1)(危害要因分析及び重要管理点)は、食品の製造・加工の工程ごとに微生物汚染等の危害要因を分析し、それらを防止する観点から、特に重要なリスク管理の工程を継続的に監視・記録する衛生管理システムです。
HACCPを導入することで、安全性に問題のある食品の出荷が未然に防止される効果等が期待されており、世界的にHACCP導入の制度化の動きが広がっています。
令和2(2020)年6月に施行された食品衛生法等の一部を改正する法律により、令和3(2021)年6月までに原則として全ての食品等事業者(食品製造、調理、販売等)に、一般衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施が求められることになっています。このうち食品製造事業者では、令和元(2019)年10月時点で、HACCPに沿った衛生管理を導入済み又は導入途中の割合は4割程度にとどまっています。このため、食品等事業者の大部分を占め、特に導入が遅れている中小事業者においてもHACCPに沿った衛生管理の制度化に円滑に対応できるよう、農林水産省は、HACCPの知識を普及する研修や業界団体によるHACCP導入の手引書作成等に対するきめ細かな支援を行っています。
さらに令和2(2020)年度は、実際の製造現場に入り、手引書を使ったHACCP導入モデルの実証や、多くの事業者に学ぶ機会を広く提供できるよう、オンライン学習教材の作成等への支援を行っています。また、中小規模の食品等事業者を対象に、HACCP等の導入や加工食品等の輸出に際しての施設整備に対する金融措置を実施しています。
1 用語の解説3(2)を参照
(食品製造業の安全管理に関する認証規格(JFS規格)の国内取得件数は年々増加)
JFS(*1)規格は、一般財団法人食品安全(しょくひんあんぜん)マネジメント協会(きょうかい)が策定した、日本発の食品安全管理に関する認証規格です。JFS規格の特徴は、生食や発酵食等が認証可能で、我が国の食文化に馴染む規格にあります。加えて、JFS規格の製造セクターでは、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理を包含するJFS-A規格、HACCPに基づく衛生管理を包含するJFS-B規格、国際取引にも通用する高水準のJFS-C規格(*2)が設けられており、経営規模等に応じて段階的に取り組みやすい仕組みとなっています。JFS-A/B/C規格の国内取得件数は、平成28(2016)年の運用開始以降、年々増加してきており、令和3(2021)年3月末時点で1,398件(*3)となりました(図表1-3-7)。今後、JFS規格の更なる普及により、我が国の食品安全レベルの向上や食品の輸出力強化が期待されます。
1 Japan Food Safetyの略。用語の解説3(2)を参照
2 平成30(2018)年10月に、GFSI(世界食品安全イニシアティブ)に国際規格として承認された。GFSIについては用語の解説3(2)を参照
3 製造セクター以外の規格を含めた国内取得総件数は1,465件
(事例)JFS規格を取得し、輸出に取り組む(石川県)
石川県の大野醤油醸造協業組合(おおのしょうゆじょうぞうきょうぎょうくみあい)は、県内の醤油醸造業者数社によって設立された醤油醸造工場を運営する組合であり、組合員が販売する醤油をまとめて製造しています。醤油の輸出に取り組みたいという組合員の声に応え、平成30(2018)年に、国際取引にも通用する高水準のJFS-C規格を取得しました。
以前、出荷先から取得を求められたFSSC22000(*)の取扱い範囲には、醤油等一部の発酵食が含まれていなかったため、日本の食文化に配慮した食品安全管理規格であるJFS規格を取得することとしました。JFS-C規格取得に向けて取り組む中で12人の従業員の食品安全管理に対する意識も向上し、定期的に従業員同士が現場の課題等について議論を行い、積極的に改善案が提案されています。
令和元(2019)年は、30万L以上の醤油を組合員経由で、主に北米とヨーロッパに向けて輸出しています。
オランダ発の食品安全管理規格で、GFSI承認規格の1つ
(多様なJASを推進)
JAS制度は、これまで、農林水産大臣が制定した農林物資の品質に関する規格(JAS)に基づき、第三者機関が農林水産物・食品の品質を認証・保証する公的制度として、市場に出回る粗悪品の排除や商品の品質の改善に寄与してきました。
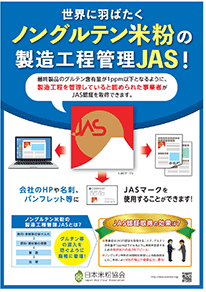
ノングルテン米粉JAS制定のポスター
資料:日本米粉協会
近年、輸出の拡大や市場ニーズの多様化が進んでいることから、農林水産省では、農林水産物・食品の品質だけでなく、事業者による農林物資の取扱方法、生産方法、試験方法等について認証する新たなJAS制度を推進しており、令和2(2020)年度には、ノングルテン米粉の製造工程管理のJAS等3規格を制定しました。これらのJASによって、事業者や産地の創意工夫により生み出された多様な価値・特色を戦略的に活用でき、我が国の食品・農林水産分野の競争力の強化につながることが期待されています。
また、農林水産省は、我が国産品の国際市場における付加価値向上のため、試験方法JASを基礎とした機能性成分の定量試験方法に関する規格を令和2(2020)年4月にISO(国際標準化機構)に提案し、我が国主導による国際規格の制定を目指しています。
(3)食品ロス等をはじめとする環境問題への対応
(我が国の食品ロスの発生量は年間600万t)
我が国の食品ロスの発生量は、近年、減少傾向にあり、平成30(2018)年度においては、前年度より12万t減少し、年間600万tと推計されます。
食品ロスとは、本来食べられるにもかかわらず捨てられてしまう食品のことを指しますが、食品ロスの発生量を国民1人当たりに換算すると年間47kgとなり、我が国の1人当たりの米の年間消費量54kgに近い量です。また、1日当たりに換算すると130gとなり、茶碗1杯のごはんの量に相当します。
平成30(2018)年度における食品ロスの発生場所を見ると、一般家庭における発生(いわゆる「家庭系食品ロス」)が276万t、食品産業における発生(いわゆる「事業系食品ロス」)が外食産業116万t、食品製造業126万t、食品小売業66万t、食品卸売業16万tとなっています(図表1-3-8)。
さらに食品ロスを削減するためには、食品産業における発生を抑えるとともに、一般家庭からの発生も抑えなければなりません。このためには、食品ロス削減を国民運動として取り組んでいくことが必要です。
(新型コロナウイルス感染症の影響により外食産業の約7割が食品ロスが減少したと回答)
令和2(2020)年12月から令和3(2021)年1月に食品関連事業者に対して実施したアンケート調査において、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和2(2020)年3月以降に食品ロス発生量に変化があったかを質問した結果、食品産業全体では、「変わらない」との回答が56.6%と最も多く、次いで「減少した」との回答が26.2%、「増加した」との回答が8.7%となりました(図表1-3-9)。業種別に見ると、食品製造業、食品卸売業、食品小売業それぞれにおいて、最も多くの事業者が「変わらない」と回答した一方で、外食産業については、「減少した」という回答が65.5%と最も多い結果となりました。
(食品産業界全体の取組により食品ロス発生を抑制)
食品ロスの問題については、個別企業等の取組では解決が難しくフードチェーン全体で解決することが必要なことから、平成24(2012)年度から食品関連事業者、有識者等を構成員とする「食品ロス削減のための商慣習検討ワーキングチーム(以下「商慣習検討ワーキングチーム」という。)」において継続して検討が行われてきました。
その検討の中で、食品産業から発生する食品ロスの一つの要因として、食品小売業者が賞味期間の3分の1を経過した商品の納品を受け付けない、いわゆる3分の1ルールや、多くの加工食品の賞味期限が年月日表示されているといった商慣習が指摘されたことを踏まえ、農林水産省では、製造・配送・販売にまたがる商慣習の見直しの取組を推進しています。
令和元(2019)年10月に施行された「食品ロスの削減の推進に関する法律」において、10月が「食品ロス削減月間」、10月30日が「食品ロス削減の日」と定められていることを受けて、農林水産省は、令和2(2020)年10月30日を「全国一斉商慣習見直しの日」として、食品小売事業者における納品期限の3分の1ルールの緩和や食品製造事業者における賞味期限表示の大括り化(年月表示、日まとめ表示)の取組を呼びかけました。その結果、同年10月時点で納品期限の3分の1ルールの緩和に取り組む食品小売事業者は、同年3月時点と比べて34事業者増の142事業者、賞味期限表示の大括り化に取り組む食品製造事業者は36事業者増の156事業者となりました。
農林水産省としては、こうした取組を食品産業界全体に波及させ、食品ロスの発生を抑えていくことを目指しています。
(事例)賞味期限表示を大括り化することで食品ロスの発生を抑制

年月表示への移行イメージ
資料:アサヒ飲料株式会社
多くの商品の賞味期限は年月日で表示されていますが、納品しようとする商品の賞味期限が、既に納品済みの商品の賞味期限より先に来るものは納品しないという商慣習があります。
例えば、物流拠点間で在庫商品を転送しようとする場合や小売業者に追加の納品をしようとした場合に、転送しようとする商品の賞味期限が、転送先で既に納品している商品よりも1日でも先にくる場合は、賞味期間がまだ十分に残っていても転送できず、結果としてそれらが食品ロスになる場合があります。このような事態を防ぎ食品ロスを発生させないため、農林水産省では、賞味期限表示について、年月表示や日まとめ表示(年月日表示のまま、日の表示を例えば10日単位で統一)といった大括り化を推進しています。
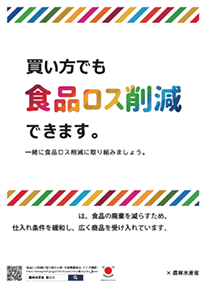
自社(店舗)の食品ロス削減の取組を紹介する啓発資材
また、平成29(2017)年度に、商慣習検討ワーキングチームにおいて啓発資材の効果の検証を行ったところ、店頭への啓発資材の掲示が、消費者の共感や食品ロスに対する社員の意識向上へとつながり、実験店舗における廃棄率が改善したことが確認されました。
この検証結果を踏まえ、農林水産省は、令和2(2020)年10月の「食品ロス削減月間」において、食品小売事業者・外食事業者が店舗等で消費者に食品ロス削減の啓発を行うための各種ポスター等啓発資材を提供するとともに、これに取り組む79の事業者名を公表しました。
さらに、令和2(2020)年12月から令和3(2021)年1月にかけて、年末年始の会食における飲食店等での食べ残しへの対策として、関係省庁や全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会と共同で、「食べきり運動」や「30(さんまる)・10(いちまる)運動(*1)」を紹介するポスターの提供や、外食時のおいしく「食べきり」ガイド、飲食店等の食品ロス削減のための好事例集の周知等による啓発活動を実施しました。参加した事業者からは、初めて「30・10運動」を実施したところ、料理が残ることなく食品ロスを防ぐ効果を感じたとの声も寄せられています。
外食産業については、環境省、消費者庁、農林水産省及びドギーバッグ普及委員会は、飲食店等において、消費者が食べきれずに残した料理を持ち帰ることを身近な習慣として広める取組として、令和2(2020)年10月に「Newドギーバッグアイデアコンテスト」を開催しました。持ち帰る行為のネーミングとして「mottECO(もってこ)」を大賞として選定し、消費者や飲食店等に広く普及を図っています。
1 乾杯の後の30分間とお開き前の10分間は自分の席について料理を楽しむことを推進することで、宴会時における食べ残しを減らす運動
(プラスチックの使用削減のためプラスチック製買物袋の有料化義務化を開始)
プラスチックは、軽量で破損しにくいことや加工・着色が容易であること、水分や酸素を通しにくく食品を効果的に保護できること等から、農林水産業や食品産業において幅広く活用されています。一方で、海岸での漂着ごみやマイクロプラスチック等の海洋プラスチック問題の顕在化を受け、国内におけるプラスチックの資源循環の体制整備が必要となっています。
このため、令和元(2019)年5月に環境省、経済産業省、農林水産省を始めとする関係省庁が策定したプラスチック資源循環戦略において、使い捨てのプラスチック製容器包装・製品が不必要に使用・廃棄されることのないよう、消費者のライフスタイル変革を促すこととされ、令和2(2020)年7月には、排出抑制の手段としてプラスチック製買物袋(いわゆるレジ袋)の有料化が義務化されました。
(気候変動リスクへの対応を解説したガイダンスを策定)
平成27(2015)年12月に採択されたパリ協定を受け、気候変動が投融資先の企業の事業活動に多大な影響を与える可能性があることから、保有資産に対する気候変動の影響を評価する動きが広まっています。TCFD(*1)(気候関連財務情報開示タスクフォース)が平成29(2017)年に公表したTCFD提言(*2)に沿った情報開示を進めるため、TCFDコンソーシアム(*3)は、令和2(2020)年7月、食品産業を含む関連産業の望ましい戦略の示し方や推奨する開示のポイント・視点等を解説した「TCFDガイダンス2.0」を策定しました(図表1-3-10)。
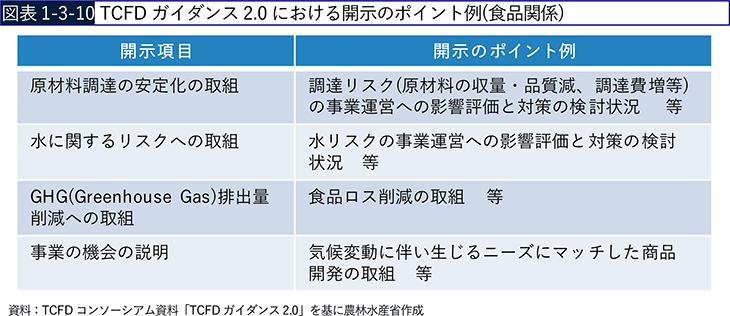
1 Task Force on Climate-related Financial Disclosuresの略。G20の要請を受け、FSB(金融安定理事会)により、気候関連の情報開示及び金融機関の対応をどのように行うかを検討するため、平成27(2015)年12月に設立された組織
2 企業に求められる気候関連財務情報開示の内容について、TCFDが取りまとめた報告書
3 金融機関、食品関連事業者等が協力して、効果的な情報開示等について議論する場として、令和元(2019)年5月に設立
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883