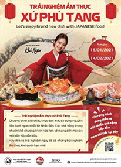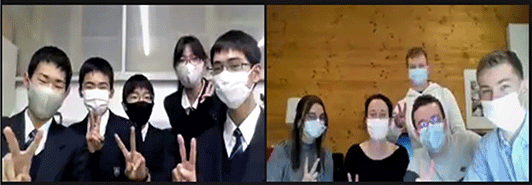第4節 グローバルマーケットの戦略的な開拓

国内においては、消費者の低価格志向に加え、今後、人口減少や高齢化により、農林水産物・食品の消費の減少が見込まれます。農業・農村の持続性を確保し、農業の生産基盤を維持していくため、輸出を拡大していくことが重要です。令和2(2020)年3月に閣議決定した食料・農業・農村基本計画等において、令和7(2025)年に2兆円、令和12(2030)年に5兆円とする農林水産物・食品の輸出額の目標が設定されました。
本節では、輸出の状況や輸出環境の整備、輸出に向けた海外への商流構築やオールジャパンのプロモーションの取組、食産業の海外展開の動向、地理的表示(GI(*1))保護制度や家畜遺伝資源(*2)の保護について紹介します。
1 Geographical Indicationの略
2 用語の解説3(1)を参照
(1)農林水産物・食品の輸出促進
ア 輸出の状況
(農林水産物・食品の輸出額は8年連続で過去最高額を更新)
令和2(2020)年の農林水産物・食品の輸出額は、世界的な新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、上半期は前年同期比で8.2%減少しましたが、年間では前年に比べ1.1%(96億円)増加の9,217億円となり、8年連続で過去最高額を更新しています。また、少額貨物等を含む輸出額は、前年に比べ1.5%(148億円)増加の9,860億円となっています(図表1-4-1)。特に、鶏卵やぶどうといった家庭食向けの輸出が増加したほか、上半期は低迷した牛肉や日本酒が、販売方法の改善等により下半期は回復したことにより、農林水産物・食品の輸出が増加しました。国・地域別には、中国で日本酒や日本産ウイスキー等のアルコール飲料が人気となったほか、ベトナム向けに粉乳やかつお・まぐろ類の輸出額が増加しました。
イ 輸出阻害要因の解消等による輸出環境の整備
(輸入規制に対して政府一体となって戦略的に取り組む体制を構築)
農林水産物・食品の輸出に関しては、これまで、輸出先国による食品安全等の規制について、担当省庁が複数にまたがることにより、輸出先国との協議や証明書発行、施設認定に時間を要し、輸出に取り組む事業者の負担となっていました。
このような課題に対応するため、令和2(2020)年4月に輸出促進を担う司令塔として、農林水産大臣が本部長を務める農林水産物・食品輸出本部が農林水産省に創設されました(図表1-4-2)。同本部では、輸出を戦略的かつ効率的に促進するための基本方針や実行計画(工程表)を策定し、進捗管理を行うとともに、関係大臣等が一丸となって、輸出先国に対する輸入規制等の緩和・撤廃に向けた協議、輸出証明書発行や施設認定等の輸出を円滑化するための環境整備、輸出に取り組む事業者の支援等を実施しています。

(動植物検疫協議により7つの国・地域の7品目で輸出が解禁又は検疫条件が緩和)
農林水産省では、実行計画に基づき、農林水産業及び食品産業の持続的な発展に寄与する可能性が高い輸出先国及び品目から優先的に協議を進めています。
輸出解禁の取組は、産地の要望を踏まえ、農林水産省が相手国・地域への解禁要請を行うことから始まります。その後、相手国・地域において疾病や病害虫のリスク評価がなされ、さらに、検疫条件の協議が行われることで輸出解禁へと至ります(図表1-4-3)。このような一連の協議の結果、令和2(2020)年度は、マカオ向けの牛肉について30か月齢の月齢制限が撤廃され、長期肥育による最高級牛肉の輸出が可能となるなど、7つの国・地域の7品目で輸出が解禁又は検疫条件が緩和されました(図表1-4-4)。

(放射性物質による輸入規制措置の緩和・撤廃)
東京電力福島第一(とうきょうでんりょくふくしまだいいち)原子力発電所(以下「東電福島第一原発」という。)の事故に伴い、多くの国・地域において、日本産農林水産物・食品の輸入停止や放射性物質の検査証明書等の要求・検査の強化といった輸入規制措置が実施されています(図表1-4-5)。
これらの輸入規制を実施している国・地域に対し、我が国が実施している安全確保のための措置やモニタリング結果等の科学的データ等の情報提供を行ってきた結果、令和2(2020)年度において、モロッコ、エジプト、レバノン、アラブ首長国連邦、イスラエル等で輸入規制措置が緩和・撤廃されました。この結果、輸入規制措置を設けた54か国・地域のうち、39か国・地域で輸入規制措置が撤廃されました。
(投資円滑化法改正案を国会に提出)
農林水産物等の輸出を始めとする、農林水産・食品分野での新たな取組にチャレンジする事業者にとっては、リスクに対応した十分な資本装備が必要となっています。
このため、農林水産省は、農業法人だけでなくフードバリューチェーンに携わる事業者全てを投資対象にすること等を内容とする「農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律案」を令和3(2021)年2月に国会に提出しました。これにより、農林水産・食品分野における資金調達の選択肢を増やし、民間主体からの資金供給をより得られやすい環境を整備することを目指しています。
(GFPグローバル産地計画)
海外市場のニーズや輸出先国の求める農薬規制・衛生管理等に対応した生産・加工体制を構築するため、農林水産省は、JETRO(独立行政法人日本貿易振興機構)等と協力して、農林水産物・食品輸出プロジェクトであるGFP(*1)を通じ、グローバル産地づくりや、輸出に意欲的な農林漁業者や食品事業者等のサポートと連携に取り組んでいます。令和2(2020)年度には、「GFPグローバル産地」として63産地を採択しています(図表1-4-6)。農林水産省では、これらの産地においてGFPグローバル産地計画の達成に向けた取組等を支援しています。

1 Global Farmers/Fishermen/Foresters /Food Manufacturers Projectの略称
(2)海外への商流構築等と食産業の海外展開の促進
ア海外への商流構築、プロモーションの促進
(GFP等を通じた輸出支援)
GFPのWebサイトを通じて登録すると、専門家による無料の輸出診断や輸出商社の紹介、登録者同士の交流イベントへの参加等のサービスを受けることができ、その登録者数は令和2(2020)年度末時点で4,572件となっています。このうち輸出診断の対象者である農林水産物・食品事業者は2,622件となっており、令和2(2020)年度においては、261件に輸出診断(うち、訪問診断76件)を行いました。また、オンラインによる交流会を開催し、海外バイヤー等から登録者に対し現地マーケット情報等を共有したほか、GFPによる農林水産物・食品事業者と商社等のマッチングを行いました。
さらに、JETROによる国内外の商談会の開催や、海外見本市への出展支援等において、輸出者への総合的な支援を行ったほか、日本食品海外プロモーションセンター(JFOODO)により、国・地域及び品目を絞り込み、売り込むべきメッセージを明確にした重点的・戦略的なプロモーションを実施しました。また、団体・民間事業者等により、輸出拡大が期待される具体的な分野・テーマについて、欧米やアジアでの花き等の海外市場の開拓・拡大に向けた取組を支援しました。
(事例)GFPで輸出診断が行われ輸出が実施された事例(鹿児島県)
鹿児島県薩摩半島(さつまはんとう)の最南端に位置する指宿市(いぶすきし)にある大吉農園(だいきちのうえん)では、キャベツを中心に生産するほか、裏作の枝豆を出荷・加工しています。輸出に関心があり、平成30(2018)年11月にGFPに登録しました。
GFPのサポートのうち輸出診断を活用して、輸出商社に係る助言や輸出商社の紹介等を受けたことをきっかけに、マカオの百貨店で開催された鹿児島物産展でのフリーズドライ枝豆の出展やシンガポール、香港、タイの小売店でのキャベツの販売が決まるなど、輸出への道が急に開けました。「大吉農園のキャベツは、果物を思わせるほど甘くておいしい」との評判が現地で広まり、令和2(2020)年には新たに台湾や香港で引き合いがありました。更に輸出を拡大するため、近隣農家と連携するなどして、キャベツの農地面積の拡大を図っています。
今後はキャベツを含めた他の産品の更なる海外販路の開拓を目指しています。
(日本産食材や日本食の普及)
海外における日本食レストランの数については、令和元(2019)年は約15万6千店と、平成25(2013)年の3倍近くに増加しており、近年、海外での日本食・食文化への関心が高まっていることがうかがわれます。
農林水産省は、急増している海外の日本食レストラン等を日本産食材の輸出拠点として継続的に活用していくため、民間が主体となり日本産食材を積極的に使用する海外の飲食店や小売店を「日本産食材サポーター店」として認定する制度を平成28(2016)年度に創設しました。令和2(2020)年度末時点で、前年度に比べて1,293店増加の6,069店が認定されています(図表1-4-7)。
また、令和2(2020)年には、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、海外における日本産食材を取り扱っている飲食店等が一時閉店等の対応を強いられ、海外における日本産食材の需要が激減しました。このため、農林水産省の補助事業により、JETROが日本産食材サポーター店等と協力して日本産食材の魅力を訴求するプロモーションを実施しました。
(日本食・食文化の発信の担い手を育成)
農林水産省は日本食・食文化の海外発信を強化するため、海外の外国人料理人の日本料理に関する知識・調理技能を習得度合いに応じて認定する「日本料理の調理技能認定制度」を平成28(2016)年度に創設しました。令和2(2020)年度末時点で、前年度に比べて344人増加の1,719人が認定されています。
また、海外の外国人料理人が日本料理の知識や調理技能、おもてなしの精神等を日本国内で学ぶ研修を支援しており、本研修では、「日本料理の調理技能認定制度」の認定も行っています。なお、本年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、研修生を招聘(しょうへい)することが困難であったことから、海外在住の多くの料理人等を対象にオンラインによる研修を実施しました。これまでの本研修の修了生の一部は、母国で日本料理講習会や日本食イベントを開催するなど、日本食・食文化の普及に寄与しています。
さらに、日本食・食文化の魅力を広く国内外に効果的にPRするため、平成26(2014)年度から、海外の日本食レストラン等に対してアドバイスを行う国内外の日本料理関係者を「日本食普及の親善大使」として任命しており、令和2(2020)年度末時点で145人が任命されています。「日本食普及の親善大使」は、独自で行う日本食・食文化の普及活動のほか、令和2(2020)年度はオンライン開催となった外国人による日本料理コンテストの審査員等を務めました。
(訪日外国人旅行者の日本滞在時の食に関する体験を促進)
訪日外国人旅行者の日本滞在時の食に関する体験をきっかけとした日本産食材の需要拡大・輸出促進を目的として、農林水産省は平成30(2018)年に「食かけるプロジェクト」を立ち上げました。本プロジェクトでは、食と芸術や歴史等、異分野の活動を掛け合わせた体験を通じて、訪日外国人旅行者の日本食への関心を高めるとともに、帰国後も我が国の食を再体験できる環境の整備を推進しています。本プロジェクトの一環として、食と異分野を掛け合わせた食体験を募集・表彰する「食かけるプライズ」を実施し、令和2(2020)年10 月に大賞等15件を決定しました。表彰事例については、旅行商品Webサイトへの掲載や体験商品としての磨き上げを支援しています。
イ 食産業の海外展開の促進
(広く海外需要を獲得し、「稼ぎ」の機会を増加)
成長著しいアジア地域等で、農林水産物・食品の輸出のみならず、食産業の戦略的な海外展開を通じて広く海外需要を獲得していくことは、国内生産者の販路や稼ぎの機会を増やしていくことにつながります。このため、農林水産省では、平成26(2014)年度に、民間企業や関係機関・団体等からなるグローバル・フードバリューチェーン(GFVC)推進官民協議会を設置し、農林水産物の生産から製造・加工、流通、消費に至る付加価値の連鎖をグローバルに構築すべく、諸課題の検討や情報の共有、ビジネスマッチング等を行っています。
令和2(2020)年度においては、11月に同協議会に中南米部会を新設し、世界最大の約210万人の日系人社会を有する同地域への日本産農産物・食品の輸出促進の加速化や、我が国の穀物等の安定的供給元であるブラジルに関し、ブラジル政府が優先的な開発地域としている北東部の生産・流通体制の構築に向けた課題等について、農林水産省、国内企業が意見交換を行いました。
国際的にもデータを活用した農業への注目が高まっていることや、スマート農業が環境対策としても期待されていることから、令和3(2021)年2月には、同協議会に分野別研究会「スマートフードチェーン」を立ち上げ、稲作や施設園芸等、我が国が強みを有する分野のスマート農業技術の海外への導入や、生産から加工、流通、消費までのデータ連携の構築等について官民で議論を行いました。日本企業が海外展開していくことを通じ、更なる技術の改善や量産化によるコスト低減等が図られれば、こうした技術の活用等を通じて国内のスマート農業の発展にも貢献するものと期待されます。同日開催されたアフリカ部会でも、令和4(2022)年開催予定の第8回アフリカ開発会議(TICAD8)を見据えて、ICT(*1)技術を活用したアフリカ農業のイノベーションの具体的な進め方等について議論を行いました。
また、令和2(2020)年度には、6か国と二国間対話等を実施しており、例えば、同年8月には、大洋州のパラオ共和国との間で農業協力に関するテレビ会議を開催、同国内に日本の民間企業等の技術を活用して新鮮な野菜や果物の供給体制を構築できないかという観点から意見交換を行いました。同年10月に開催された第6回日仏農政ワーキンググループにおいては、日本企業によるフランスへの投資促進に係る一元的な相談窓口の設置や、両国の農業高校が参加するオンライン会議の開催、フランスで開催予定の魚の活け締め普及セミナーへのフランス政府関係者の招待等、今後とも農業・食品産業分野における協力を進めることで一致しました。
さらに、同年12月には、日ベトナム両国の農業大臣の出席の下、第5回日越農業協力対話ハイレベル会合及び官民フォーラムをテレビ会議方式で開催し、民間企業の投資促進を図る観点から、園芸作物産地での食品加工分野の協力や、ハノイ、ホーチミン等の大都市近郊での物流インフラ整備や農産物の規格認証に関する協力等を深化させていくことを確認しました。
1 用語の解説3(2)を参照
(3)知的財産の保護
ア 地理的表示(GI)保護制度
(GI保護制度の登録産品は106産品となり着実に増加)
地理的表示(GI)保護制度は、地域ならではの特徴的な産品の名称を知的財産として保護する仕組みです。同制度に産品を登録することで、模倣品が排除されるほか、登録生産者団体が自らの産品の価値を再認識することができるなどの効果が期待されています。
令和2(2020)年度は、新たに12産品が同制度に登録され、これまでに登録された産品は、同年度末時点で、40都道府県と2か国の計106産品となりました(図表1-4-8)。
また、日EU・EPA(*1)により、日本側GI72産品、EU側GI89産品が、令和3(2021)年1月1日に発効した日英EPAにより日本側GI47産品、英国側GI3産品が相互に保護されています。

1 用語の解説3(2)を参照
イ 家畜遺伝資源保護
(和牛遺伝資源の管理・保護のための新制度が開始)
和牛は、関係者が長い年月をかけて改良してきた我が国固有の貴重な財産であることから、国内の関係団体等は「和牛遺伝資源国内活用協議会」を設立し、和牛遺伝資源の輸出自粛等の取組を行ってきました。
しかし、平成30(2018)年6月、和牛遺伝資源である家畜人工授精用精液や受精卵が輸出検査を受けずに中国に持ち出され、中国当局において輸入不可とされた輸出未遂事案が確認されたことから、我が国における和牛遺伝資源の保護を求める声が高まりました。
このような情勢を踏まえ、農林水産省は、学識経験者や関係団体等から構成する「和牛遺伝資源の流通管理に関する検討会」を開催し、流通管理の在り方や知的財産としての価値の保護の可能性について検討を進め、令和元(2019)年7月には中間とりまとめが示されました。また、同年10月には、同検討会の下に、法曹実務家、知的財産に関する専門家、オブザーバーとして関係省庁を加えた「和牛遺伝資源の知的財産的価値の保護強化に関する専門部会」が開催され、保護強化に向けた課題・対策と知的財産制度上の位置付けの可能性について検討し、令和2(2020)年1月に中間とりまとめが示されました。これらの中間とりまとめの内容を踏まえ、同年3月に改正家畜改良増殖法案と家畜遺伝資源法案(*1)が国会に提出され、同年4月に可決・成立し、同年10月に施行されたことにより、和牛遺伝資源の管理・保護のための新制度が開始されました(図表1-4-9)。
改正家畜改良増殖法により、家畜人工授精所等以外で保存されている家畜人工授精用精液等の他人への譲渡が禁止されるなど、家畜遺伝資源の不適正な流通を防止するための関係規程が整備されました。また、家畜遺伝資源法により、和牛遺伝資源について、知的財産としての価値の保護を図るため、契約に違反した使用や譲渡等に対して差止請求や損害賠償請求を行うことが可能となるとともに、悪質な不正行為に対しては刑事罰が適用されるようになりました。

1 正式名称は「家畜改良増殖法の一部を改正する法律案」と「家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律案」
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883