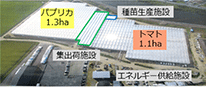第1節 東日本大震災からの復旧・復興
平成23(2011)年3月11日に発生した東日本大震災では、岩手県、宮城県、福島県の3県を中心とした東日本の広い地域に東京電力福島第一(とうきょうでんりょくふくしまだいいち)原子力発電所(以下「東電福島第一原発」という。)の事故の影響を含む甚大な被害が生じました。
政府は同年7月に策定した「東日本大震災からの復興の基本方針」において、復興期間を令和2(2020)年度までの10年間と定め、被災地の復興に向けて取組を行ってきました。また、令和2(2020)年7月の復興推進会議において、令和3(2021)年度から令和7(2025)年度までの5年間を新たな復興期間として、「第2期復興・創生期間」と位置付け、引き続き被災地の復興に向けて取り組むこととしています。
本節では、東日本大震災の地震・津波や原子力災害からの農業分野の復旧・復興の状況について紹介します。
(1)東日本大震災の発生
(未曾有の規模の被害をもたらした東日本大震災)
平成23(2011)年3月11日午後2時46分に、三陸沖を震源として、国内観測史上最大規模となるマグニチュード9.0の「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」が発生しました。この地震により、宮城県北部で震度7、宮城県、福島県、茨城県、栃木県で震度6強等、広い範囲で強い揺れが観測されました。また、太平洋沿岸を中心に高い津波が観測され、特に東北地方の太平洋沿岸地域では大規模な津波被害が発生しました。その後も規模の大きな余震が発生したほか、同年3月12日には、長野県北部を震源とする最大震度6強の地震が発生するなど、余震域の外側でも地震活動の高まりが見られました。さらに、東電福島第一原発の事故により、広い地域に立入制限が課されました。
東日本大震災による人的被害は、令和3(2021)年3月10日時点で死者1万5,899人、行方不明者2,526人(*1)に上り、大正12(1923)年に発生した「関東大震災」の死者・行方不明者10.5万人に次いで、多くの尊い生命が失われました。また、地震・津波による建物の全壊・半壊は約37万戸を超え、このうち全壊は約13万戸に及びました。このため、地震発生直後には、最大約47万人が公民館・学校等の避難所に避難し、以後、長期の避難生活を余儀なくされました。
また、東北地方では約440万世帯、関東地方では約405万世帯が停電するなど、電力、水道、ガス等のインフラに多大な支障が生じました。さらに、石油製品については、太平洋岸沿いの製油所が被災したことにより、ガソリンや灯油等の供給不足が発生しました。交通網では、高速道路が多くの路線で通行止めとなり、鉄道でも、JR東日本、私鉄等多くの路線で運転が休止しました。
*1 警察庁緊急災害警備本部広報資料「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の警察活動と被害状況」(令和3(2021)年3月10日公表)
(2)政府の復興方針
(政府の復興方針の策定)
政府は、平成23(2011)年7月に「東日本大震災からの復興の基本方針」を策定しました(同年8月に改定)。同方針では、復興期間を10年間とし、当初の5年間(平成23(2011)年度~平成27(2015)年度)を「集中復興期間」と位置付けました。農業分野の復興施策については、被災地の農業の復興を図り、日本全国のモデルとなるよう取組を進め、東北を新たな食料供給産地として再生することとしました。
また、平成28(2016)年3月には、「「復興・創生期間」における東日本大震災からの復興の基本方針」を閣議決定しました。同方針では、後期5か年の「復興・創生期間」(平成28(2016)年度~令和2(2020)年度)において重点的に取り組む事項として、農業分野の取組については、被災地の農林水産業の再生に向けた、農地の大区画化・利用集積を推進することとしました。
さらに、令和元(2019)年12月には、復興の進展に伴い、引き続き対応が必要となる事業や新たな課題も明らかになってきたことを踏まえ、「「復興・創生期間」後における東日本大震災からの復興の基本方針」を閣議決定しました。同方針における、復興・創生期間後(令和3(2021)年度以降)の農業分野の取組として、農地・農業用施設等の整備や、農業用機械・家畜の導入、鳥獣被害対策等これまで行ってきた被災農業者への支援を継続し、営農の再開を促進することとしています。
(3)地震・津波災害からの復旧・復興
(営農再開が可能な農地は94%に)
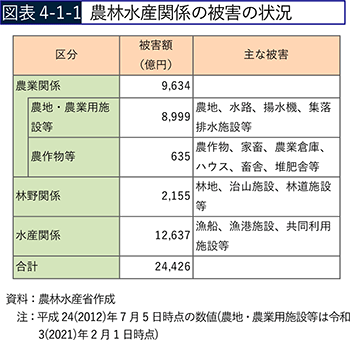
東日本大震災による農業関係の被害額は、平成24(2012)年7月5日時点(農地・農業用施設等は令和3(2021)年2月1日時点)で9,634億円、農林水産関係の合計では2兆4,426億円となっています(図表4-1-1)。津波により被災した農地2万1,480haから公共用地等への転用が見込まれるものを除いた復旧対象農地1万9,690haについては、除塩や畦畔(けいはん)の修復等の復旧が進められており、令和3(2021)年1月末時点では94%で営農再開が可能となりました(図表4-1-2)。
避難指示が解除された区域内の農地や、まちづくり等の他の復旧・復興事業との工程調整が必要な残りの農地についても、早期復旧に向けた取組が進められています。
(地震・津波からの農地の復旧に併せた圃場の大区画化が進展)
岩手県、宮城県、福島県の3県では、地域の意向を踏まえ、地震・津波からの復旧に併せた農地の大区画化(整備計画面積8,230ha(*1))に取り組んでいます。令和2(2020)年度末時点では、8,160haの大区画化が完了し、地域農業の復興基盤の整備が進展しています。
農地整備事業の区域内に、防災集団移転促進事業により市町村が買い上げた住宅等の移転元地が点在する場合、土地改良法の換地(*2)制度を活用することで、移転元地と農地をそれぞれ集団化することが可能となります。これにより、事業期間の短縮と効率的な土地利用を実現できます。防災集団移転促進事業と連携した農地整備事業は、宮城県と福島県の10市町15地区で進められており、令和2(2020)年度末時点で12地区の整備が完了しています。
*1 整備計画面積は、大区画化に取り組む地区の計画面積の総計であり、大区画化の取組を行わない農地(端部の狭小農地等)も一部含まれている。
*2 用語の解説3(1)を参照
(事例)震災からの復興のため、地域資源を活用した次世代施設園芸に取り組む(宮城県)

株式会社デ・リーフデ北上(きたかみ)は、従業員45人(うち正社員7人)でトマトとパプリカの周年栽培を行い、カット野菜等の加工業者やファストフード店、小売店に販売しています。
同社は、東日本大震災の津波により大きな被害を受けた宮城県石巻市(いしのまきし)の北上川下流域でオランダ式の施設園芸を始めるため、地域の農家と中小企業からの出資を受け、平成26(2014)年に設立されました。
平成28(2016)年には、農林水産省の事業「次世代施設園芸導入加速化支援事業」を活用して、最先端の環境制御設備を導入した約2.4haの大規模なガラス温室等「宮城県拠点」を整備しました。温室の加温にはLPGボイラーのほかに木質バイオマスボイラーや、地中熱を利用したヒートポンプ等を併用したハイブリッド運転を採用し、地域資源を有効活用することで化石燃料の使用量削減にも取り組んでいます。
高度な環境制御技術と地域エネルギーを活用した「次世代施設園芸」の全国モデルの一つとして、被災地での雇用創出を実現するとともに、拠点の成果の普及等により、今後、東北地域の施設園芸を牽引する存在としての活躍が期待されます。
(先端的農業技術の現地実証研究、情報発信等を実施)
農林水産省は被災地域を新たな食料生産基地として再生するため、産学官連携の下、農業・農村分野に関わる先端的で大規模な実証研究を行っています。
平成30(2018)年度から令和2(2020)年度にかけては、岩手県、福島県において7課題の農業分野に関わる現地実証研究を行うとともに、岩手県、宮城県、福島県の3県に、これまでの実証研究で得られた成果を現場に定着させるための拠点を設置しました(図表4-1-3)。各拠点では、それぞれオープンラボや展示圃場(ほじょう)を設置し、情報発信、技術指導等を行い、得られた研究成果の普及に取り組んでいます。
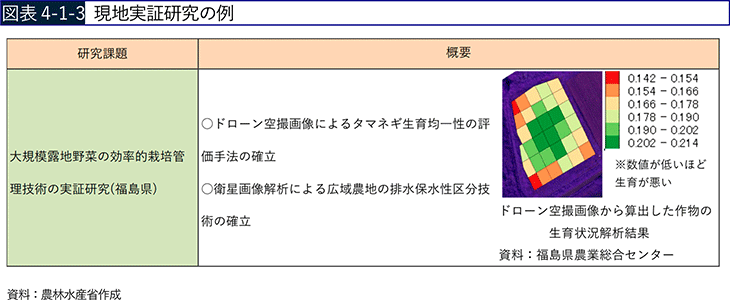
令和2(2020)年12月には、こうした取組の全体を共有するため、福島県福島市(ふくしまし)で研究成果発表会を開催し、被災地域の生産者・生産者団体、加工・流通関係者、普及・行政機関等を対象に、実証研究に取り組んだ生産者等とともに現地実証の研究成果を発信しました。今後は、現場指導や実証圃(ほ)における技術検証の実施により実用化された技術体系の迅速かつ広範な社会実装を図っていくこととしています。
(「新しい東北」の創造に向けた取組を推進)
復興庁では、復旧・復興に当たり、単なる原状回復にとどめるのではなく、地方公共団体、企業、大学、NPO(*1)等がこれまでの手法や発想にとらわれない新しい挑戦に取り組み、地域の諸課題の解決を進める、「新しい東北」の創造に向けた取組を推進しています。
平成26(2014)年度から開催している「新しい東北」復興ビジネスコンテストでは、被災地域における地域産業の復興や地域振興に資する事業の表彰を行っており、令和2(2020)年度においては、農業関係では、有害捕獲したニホンジカをジビエとしてオンライン販売をしている株式会社ソーシャル・ネイチャー・ワークス(岩手県大槌町(おおつちちょう))が優秀賞を受賞しました。このほか、農業関係では二つの取組が企業賞を受賞しました(図表4-1-4)。
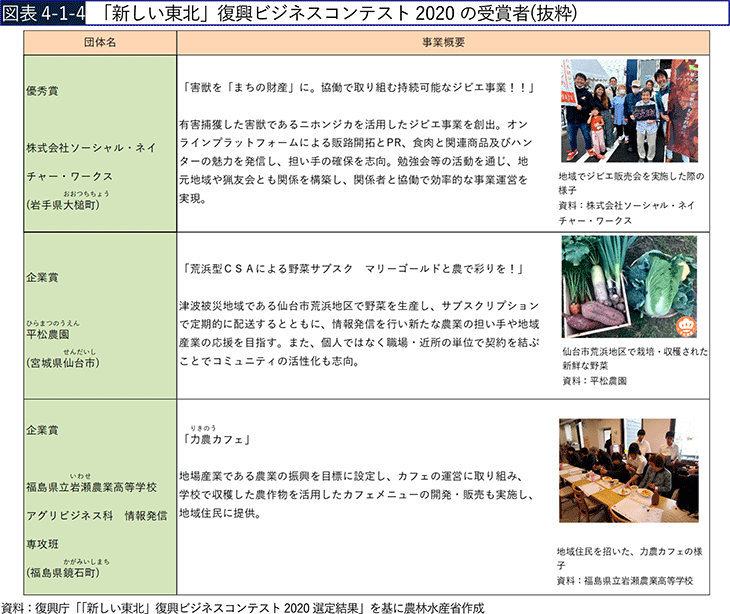
さらに、平成28(2016)年度から、被災地域で進む「新しい東北」の実現に大きな貢献をしている個人や団体を対象に「新しい東北」復興・創生顕彰を実施しています。令和2(2020)年度においては、農業関係では、消費期限が短い「甲子柿(かっしがき)」を1年中食べられるように加工し、6次産業化(*2)を軸とする地域活性化に取り組んだ釜石市甲子地区活性化協議会(かまいししかっしちくかっせいかきょうぎかい)と移住希望の新規就農者(*3)へ伴走型の就農支援を実施した一般社団法人イシノマキ・ファームが顕彰されました(図表4-1-5)。
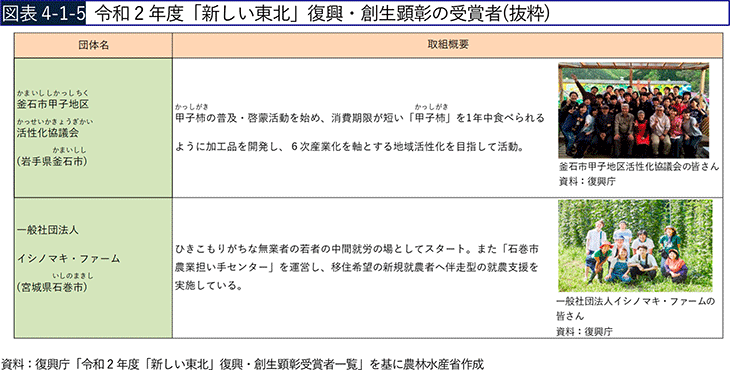
*1 用語の解説3(2)を参照
*2 用語の解説3(1)を参照
*3 用語の解説2(6)を参照
(4)原子力災害からの復旧・復興
ア 農畜産物の安全確保の取組
(安全性確保のための取組が進展)
生産現場では、市場に放射性物質の基準値を上回る農畜産物が流通することのないように、放射性物質の吸収抑制対策、暫定許容値以下の飼料の使用等、それぞれの品目に合わせた取組が行われています。このような生産現場における努力の結果、基準値超過が検出された割合は、全ての品目で平成23(2011)年以降低下しており、平成30(2018)年度以降では、全ての農畜産物において基準値超過はありません。
福島県では、米については、作付制限、放射性物質の吸収抑制等の対策とともに、これまで県全域で全量全袋検査を実施していましたが、放射性物質の吸収を抑制するカリウムの追加施用等を徹底した結果、平成27(2015)年以降、通算5年間基準値超過がないことから、令和2(2020)年産から旧避難指示区域等(*1)一部の地域を除き、モニタリング(抽出)検査に移行しています。
さらに、第三者認証GAP(*2)の取得も進められており、福島県の発表によれば、令和2(2020)年12月末時点で、GAP認証の取得件数は、GLOBALG.A.P.(*3)が29件、ASIAGAP(*4)が6件、JGAP(*5)が170件及びFGAP(*6)が92件となっています。
*1 田村市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村及び川俣町(旧山木屋村)
*2~6 用語の解説3(2)を参照
イ 原子力被災12市町村の復興
(原子力被災12市町村の農地の復旧・整備実施済面積は約1,830ha)
原子力被災12市町村の農地については、営農休止面積1万7,298haから、帰還困難区域(約2,040ha)と農地転用等(約1,440ha)を除いた約1万4千haのうち、令和元(2019)年度末時点で約1,090haは農地の復旧が実施・検討、約1,700haは農地の復旧に併せた整備が実施・検討、約3,590haは農地の整備が実施・検討されており、これらのうち、令和元(2019)年度末時点で約1,830haの復旧又は整備が実施されました(図表4-1-6)。
一方で、復旧又は整備が検討されているものの、帰還率が低い地域では、実施に向けた調整が必要となっています。
また、残りの約7,440haについては、条件の悪い農地で不在地主化が進んでいるとともに、担い手の不足等が課題となっています。
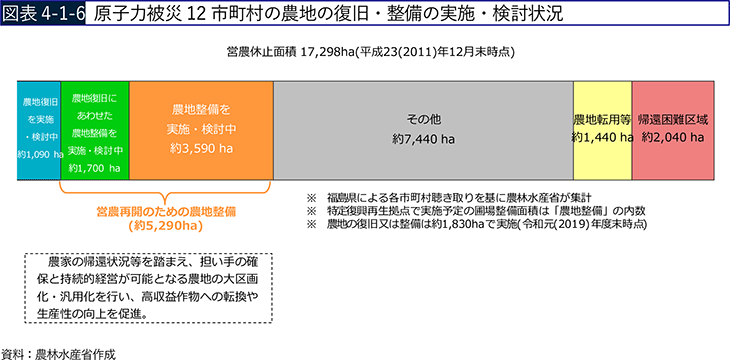
(営農再開済の回答が増加)
令和元(2019)年度末時点で、原子力被災12市町村(*1)においては、平成23(2011)年12月末時点で営農が休止されていた農地1万7,298haの32.2%に当たる5,568haで営農が再開されています(図表4-1-7)。
農林水産省は、福島相双復興(ふくしまそうそうふっこう)官民合同チームの営農再開グループに参加し、平成29(2017)年以降毎年、原子力被災12市町村の主に認定農業者(*2)以外の農業者を対象とした要望調査や支援策の説明を個別訪問により行っています。平成29(2017)年~令和2(2020)年までに実施した調査では、令和元(2019)年までの調査結果よりも2.9ポイント増加の32.1%が「営農再開済」と回答しています(図表4-1-8)。一方で、「再開未定又は再開意向なし」と回答した農業者の割合は55%であり、これらのうち「農地の出し手となる意向あり」と回答した農業者の割合は72%となっています。地域外も含めた担い手の確保や、担い手と農地のマッチングの取組を推進することが課題となっています。
なお、農林水産省と福島県が平成28(2016)年7~11月にかけて原子力被災12市町村の認定農業者に個別訪問を行った際に実施した要望調査の結果では、61.7%が「営農再開済」、23.4%が「営農再開を希望」と回答しています。
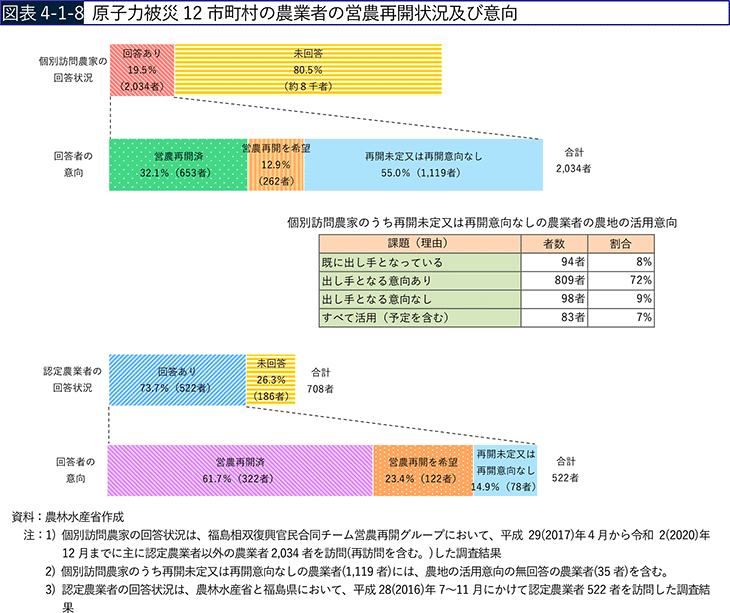
*1 田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
*2 用語の解説3(1)を参照
(農地の利用集積と大規模化に向けた取組)
このような課題を踏まえ、福島復興再生特別措置法の改正を含む、復興庁設置法等の一部を改正する法律が令和2(2020)年6月に成立しました。これにより、改正後の福島復興再生特別措置法においては、営農再開の加速化に向けて、農地の利用集積や6次産業化(*1)施設の整備を促進するための特例が措置されました。この改正法は令和3(2021)年4月に施行されます。こうした措置や関連予算により、担い手の意向に沿った農地の利用調整を円滑に進めるための体制を構築するとともに、農地中間管理機構(農地バンク)を活用して担い手への農地集積・集約化を図る取組等を支援していきます。
*1 用語の解説3(1)を参照
(営農再開支援のため原子力被災12市町村へ職員を派遣)
営農再開支援に際し、原子力被災12市町村の中で営農再開割合の比較的高い地域では、「人・農地プラン」の作成や農業委員会の活動が進んでおり、大規模で労働生産性の高い農業経営の展開を図ることができる一方で、営農再開割合の比較的低い地域では集中的な対策を講じていく必要があります。
このため、農林水産省は、令和2(2020)年度から、常駐職員を原子力被災12市町村へ派遣し、福島県、市町村、福島相双復興推進機構(ふくしまそうそうふっこうすいしんきこう)、農協と連携して、一筆ごとの土地利用調整に取り組むなど、市町村が行う営農ビジョンの策定から具体化までの支援を行っています。
(事例)被災市町村派遣職員が農業者の営農再開をサポート(福島県)

*田村市、南相馬市、川俣町、
広野町、楢葉町、富岡町、
川内村、大熊町、双葉町、
浪江町、葛尾村、飯舘村
農林水産省では、原子力被災地域での営農再開を加速するため、原子力被災12市町村に対して職員を派遣し、市町村や農協等の関係機関と一体となって支援しています。
また、技術職員(農学、農業土木)等によるサポートチームを設置して派遣職員のサポートにあたっています。12市町村ではそれぞれ復興のステージが異なることから、派遣職員は市町村ごとのステージに合わせて必要とされている業務に取り組んでいます。
避難指示解除が比較的早く、営農再開が進んでいる田村市(たむらし)、広野町(ひろのまち)、楢葉町(ならはまち)、川内村(かわうちむら)等では、圃場(ほじょう)や施設等の整備を進めるための交付金関連業務を始め、農地中間管理事業を活用した担い手への農地集積等に取り組んでいます。
一方、未だ町内の大半のエリアが帰還困難区域である双葉町(ふたばまち)や大熊町(おおくままち)では、営農再開ビジョンの策定や農業者の営農に対する意向確認等の業務に取り組んでいます。被災市町村からは、「震災以降、農政に詳しい職員が少なくなっており、農政に係る各種情報提供や、農地の保全管理から基盤整備事業につなげるための各地区の組合との調整、県と連携した基盤整備事業に取り組む際の助言等、派遣職員に頼っているところが大きい。」などの声も聞かれています。
しかしながら、依然として住民帰還が進んでいない市町村も多く、担い手不足等営農再開に向けて多くの課題を抱えています。こうしたことから農林水産省では、意見交換の場を定期的に設けるなど、市町村や派遣職員が抱える課題の共有と解決に向けたサポートを実施しています。
今後は、営農再開を加速させるため、圃場整備やICTの活用等による大規模で労働生産性の高い農業の展開、生産と加工等が一体となった高付加価値生産の広域的な展開に向け、関係者間の連携を更に深めながら、取り組んでいくこととしています。
(生産と加工等が一体となった高付加価値生産を展開する産地の創出)
原子力被災12市町村の営農再開率が3割にとどまっている中、営農再開の加速化に向け、地域外からの参入も含め農業者の再開意欲を高めていくためには、生産すれば売れる環境を形成し、将来に向けて被災地域の農業が産業として発展する姿を提示していくことが不可欠です。
このため、農林水産省は、福島県、農業者団体等関係機関との意見交換を行い、令和2(2020)年7月には、食品加工メーカー等の実需者等を現地に呼び込み、市町村の範囲を越えて農産物を供給する産地を広域的に形成する構想を取りまとめました。
構想を踏まえ、現地に進出する意向を有する実需者等と農産物を供給する農業者団体等関係機関との調整や、市町村との意見交換等、産地の形成に向けた取組を進めています。
(事例)福島県浪江町で震災後初めて米の販売会を実施(福島県)

福島舞台(ふくしまぶたい)ファーム株式会社は、福島県浪江町(なみえまち)で米を生産する農業生産法人です。
同社は、令和2(2020)年に東日本大震災の津波と原発事故で大きな被害を受けた浪江町で29haの水田に福島県のオリジナル品種「天のつぶ」の作付けを開始しました。
収穫した米は、浪江町の道の駅で震災後初めて開催された販売会において「浪江復興米」として販売しました。
この取組は、東京農業大学が福島イノベーション・コースト構想推進事業による担い手育成をテーマに、農作業体験や現地講習の取組の一環として、福島舞台ファーム株式会社と連携して、稲刈り、販売実習を行いました。
福島舞台ファーム株式会社の代表取締役志子田勇司(しこだゆうじ)さんは、「今後も作付面積を拡大し、地域農業の復興のために寄与していきたい。」と話しています。
また、東京農業大学の黒瀧秀久(くろたきひでひさ)教授は、「今後は、学生のインターンのためのプログラムを充実したいと考えており、従来の6次産業化支援、スマート農業推進に加えて、新たにイノシシ対策プロジェクトや復興米を使った復興酒(日本酒)づくりにも取り組んでいきたい。」と話しています。
(福島イノベーション・コースト構想に基づく先端農林業ロボット研究開発を実施)
福島・国際研究産業都市(イノベーション・コースト)構想研究会が平成26(2014)年6月に取りまとめた「福島・国際研究産業都市(イノベーション・コースト)構想研究会報告書」では、革新的な先端農林水産業を全国に先駆けて実施することを通じて、地域の農林水産業の復興・再生を実現することとしています。これを受け、農林水産省では、平成28(2016)年度から、福島イノベーション・コースト構想に基づく先端農林業ロボット研究開発事業を実施しており、令和2(2020)年度は、ブロッコリー自動選別収穫機、高品質米生産管理技術、農地地力の見える化技術、ICT(*1)活用による和牛肥育管理技術の研究・開発の取組を支援しました。
*1 用語の解説3(2)を参照
(「特定復興再生拠点区域」の復興・再生への取組を実施)
福島復興再生特別措置法においては、5年を目途に避難指示を解除し、住民の帰還を目指す「特定復興再生拠点区域」の復興・再生を推進するための計画制度の下、帰還困難区域が存在する全6町村(*1)が計画の認定を受けています。
6町村全ての復興再生計画で農業の再生を目指した区域が設定されており、本計画に基づき、インフラの復旧、生活環境の整備、産業の復興・再生、除染・家屋解体等が進められています。福島県双葉町(ふたばまち)では、特定復興再生拠点区域内の除染した農地で、令和2(2020)年6月から福島県営農再開支援事業による除草等の農地の保全管理が行われました。
*1 双葉町、大熊町、浪江町、富岡町、飯舘村、葛尾村
(事例)特定復興再生拠点区域内の除染した農地の保全管理作業を実施(福島県)
福島県双葉町(ふたばまち)の羽鳥(はとり)・長塚(ながつか)地区は、帰還困難区域内の一部に設定された特定復興再生拠点区域の耕作再開モデルゾーンです。同地区では、令和2(2020)年4月に地元農家等で農地保全管理組合が設立され、除染後の農地の保全管理が行われています。
令和3(2021)年度には、出荷制限を解除するための野菜の試験栽培と東電福島第一原発の事故後初めてとなる水稲の試験栽培が行われる予定です。
双葉町農業振興課では、「農業者へのアンケート結果では、震災から10年が経ち、営農を再開する予定はないという回答が多い中、双葉町でまた農業をやりたいという回答も少なからずある。こうした農業者の思いをつないで、地域外の力も借りながら、まずは羽鳥・長塚地区の田園風景を再生していきたい。」と考えています。
ウ 風評払拭に向けた取組等
(「風評払拭・リスクコミュニケーション強化戦略」に基づく取組のフォローアップを実施)
消費者庁が令和3(2021)年2月に公表した消費者の意識調査(*1)によると、放射性物質を理由に福島県産品の購入をためらう人の割合は8.1%となり、調査開始以来最低の水準となったものの、依然として一定割合の人が購入をためらうと回答しています(図表4-1-9)。
このような風評を払拭するため、復興庁その他関係府省庁は、平成29(2017)年12月に取りまとめた「風評払拭・リスクコミュニケーション強化戦略」に基づく取組のフォローアップとして、「知ってもらう」、「食べてもらう」、「来てもらう」の三つを柱とする情報発信を実施しています。
また、農林水産省では、福島復興再生特別措置法に基づき、関係省庁と協力し、平成29(2017)年度から福島県産農産物等の販売不振の要因と実態を明らかにするための流通実態調査と当該調査に基づく指導・助言等を行っています。
令和2(2020)年度調査では、福島県産農産物等の価格は回復傾向にあるものの、一部の品目で震災前の水準まで回復していないこと、仲卸業者等の納入業者が納入先の福島県産農産物等の取扱姿勢を実態よりも低く評価している認識の齟齬は、平成30(2018)年度調査と比べてやや改善傾向にあること等が明らかになりました。
このほか、「食べて応援しよう!」のキャッチフレーズの下、生産者、消費者等の団体や食品事業者等、多様な関係者の協力を得て被災地産食品の販売フェアや社内食堂等での積極的利用を進めています。
*1 消費者庁「風評被害に関する消費者意識の実態調査(第14回)」(令和3(2021)年2月公表)
(放射性物質による輸入規制措置の緩和・撤廃)
(東京電力による農林水産関係者への損害賠償支払)
原子力損害の賠償に関する法律の規定により、東電福島第一原発の事故の損害賠償責任は東京電力(とうきょうでんりょく)ホールディングス株式会社(以下「東京電力」という。)が負っています。
東京電力によるこれまでの農林漁業者等への損害賠償支払累計額は、令和3(2021)年3月末時点で9,509億円(*1)となっています。
*1 農林漁業者等の請求・支払状況について、関係団体等からの聴き取りから把握できたもの
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883