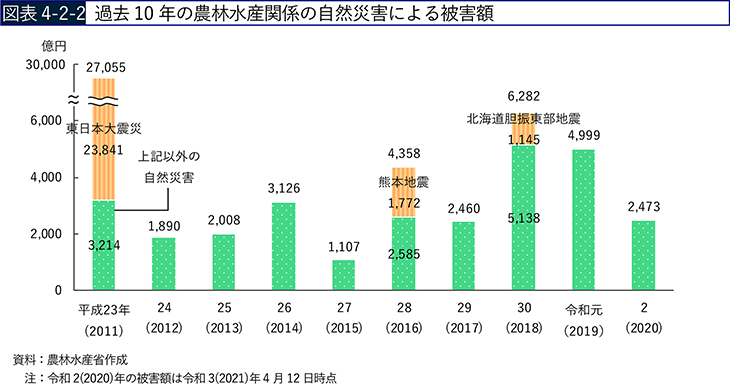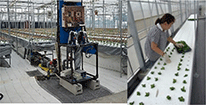第2節 大規模自然災害からの復旧

近年、日本各地で地震や異常気象に伴う豪雨等の大規模な自然災害が頻発しています。地震や豪雨等の自然災害により被災した農業者の早期の営農再開を支援するとともに、被災を機に災害への対応強化と一体的に、作物転換、規模拡大等、生産性の向上等を図る産地の取組を支援しています。本節では、近年の大規模自然災害による被害の発生状況やこれらの災害からの復旧に向けた取組について紹介します。
(1)近年多発する自然災害と農林水産業への被害
(平成30(2018)年や令和元(2019)年の農林水産関係の自然災害による被害額は過去10年で最大級)
近年、異常気象による猛烈な雨の発生回数(全国のアメダスによる観測値を1,300地点当たりに換算した数値)は増加傾向となっています。1時間降水量が80mm以上の「猛烈な雨」の年間発生回数を、10年間ごとの平均回数で見ると増加傾向で推移しており、平成23(2011)~令和2(2020)年は26回となっています(図表4-2-1)。
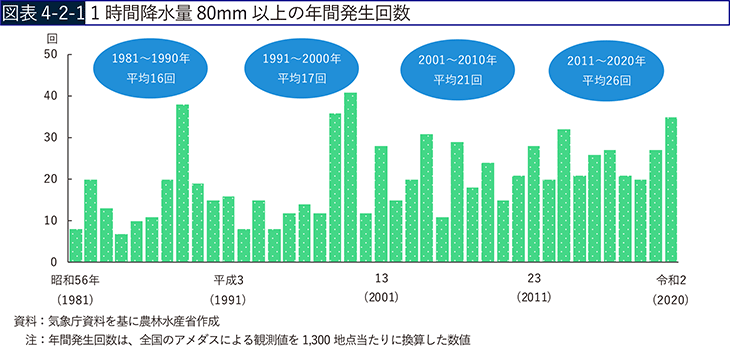
平成30年7月豪雨では西日本を中心に記録的な大雨となりました。また、令和元年房総半島台風及び令和元年東日本台風は強い勢力を保ったまま本州に上陸したことから、我が国の農林水産業は農作物や農地・農業用施設等に甚大な被害が発生しました。
この結果、平成30(2018)年や令和元(2019)年の農林水産関係の自然災害による被害額は、東日本大震災のあった平成23(2011)年を除くと過去10年で最大級の被害額となりました。なお、令和2(2020)年の被害額は、平成30(2018)年や令和元(2019)年よりも減少しました(図表4-2-2)。
(2)近年の大規模自然災害からの復旧状況
(熊本地震からの創造的復興が進展)
平成28(2016)年4月に発生した熊本地震では、熊本県を始めとする九州各県で大きな被害が生じました。熊本県では、同年12月に策定した「熊本復旧・復興4カ年戦略」に基づき復旧・復興の歩みを進めてきました。
農林水産分野では、農地及び営農施設の復旧等を着実に進めた結果、目標に掲げた「被災農家の営農再開100%」を達成しています。
大規模な地表面の亀裂やずれによる被害が発生した農地や農業用施設については、創造的復興の取組として、単に元の姿に戻すだけでなく、担い手への農地集積を図るために大区画化等の基盤整備を行いました。具体的には、熊本県熊本市(くまもとし)と熊本県益城町(ましきまち)にまたがる秋津(あきつ)地区で172ha、熊本県阿蘇市(あそし)の阿蘇谷(あそだに)地区で63ha、熊本県南阿蘇村(みなみあそむら)の乙ヶ瀬(おとがせ)地区で26haの農地において大区画化を進め、工事が完了した農地から順次、営農が再開されています(図表4-2-3)。
令和元(2019)年度に着手した熊本県西原村(にしはらむら)の大切畑(おおきりはた)ため池(通称、大切畑ダム)の復旧工事については、令和2(2020)年12月に河川の流れを切り替える転流工を行い、令和3(2021)年3月には仮排水トンネルを竣工しました。なお、大切畑ダムの復旧は令和5(2023)年度までの5年間で工事完了を目指しています。
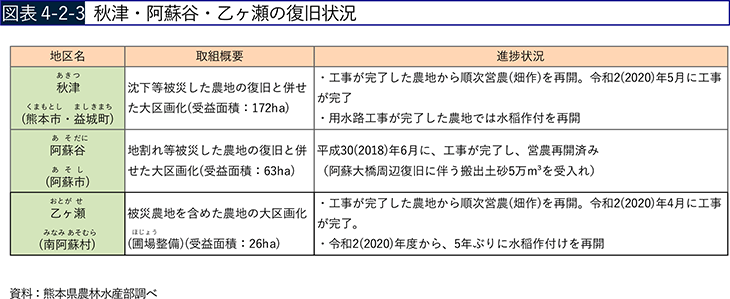
(北海道胆振東部地震からの復興)
平成30(2018)年9月に発生した北海道胆振東部(いぶりとうぶ)地震では、北海道全域に大きな被害が生じました。
北海道では、同年12月に策定した「北海道胆振東部地震災害からの復旧・復興に向けた取組のロードマップ」や平成31(2019)年3月に策定した「平成30年北海道胆振東部地震災害からの復旧・復興方針」に基づき復旧・復興に向けた取組を進めてきました。
被災した農地については、災害復旧事業の対象面積137.6haのうち、令和3(2021)年3月末までにおおむね100%に当たる137.3haが復旧しました。
被災により通水不能となった国営パイプラインの受益地約2,800haでは、直轄災害復旧事業で代替水路を整備し、平成31(2019)年4月から営農が可能となりました。被災したパイプラインは令和4(2022)年度の工事完了を目指し、復旧を進めています。
特に被害が大きかった北海道厚真町(あつまちょう)では、山腹崩壊により作付けが不能であった農地において、早期に作付けが可能となるよう、暫定的に堆積土砂を農地内の一部に集積したほか、倒木、土砂の撤去、畦畔築立(けいはんちくりつ)により復旧を図り、平成31(2019)年4月には一部の農地で営農を再開しました。
農地の復旧後は、生産力の回復に向け、町、農協、土地改良区と連携を図りながら、土壌診断、生育・収量調査、営農の指導・助言等のフォローアップを実施しています。
(令和元年東日本台風等からの復興)
令和元年東日本台風等で被災した農地・農業用施設の復旧について、農林水産省は、被災自治体に人的・技術的支援を行いながら、令和2(2020)年1月末までに災害査定を完了しました。順次復旧工事が進み、令和3(2021)年2月末時点で、災害復旧事業の対象となる9,061件のうち、4,931件で復旧が完了しました。
果樹の浸水被害については、長野県や福島県で土砂の撤去、樹体洗浄、ゴミの撤去、病害の発生・蔓延防止に向けた取組が実施されました。
(令和元(2019)年の台風等からの復旧のためスマート農業実証を支援)
令和2(2020)年度のスマート農業実証プロジェクトでは、被災地の速やかな復興・再生とともに新たな技術の導入に向け、令和元(2019)年に発生した台風等による被害を受けた地域での実証について、優先的に採択しました。宮城県、福島県、茨城県、千葉県等の被災地において、水田作や花き、養豚等の生産から出荷に関する各種先端技術の導入の実証を行っています(図表4-2-4)。
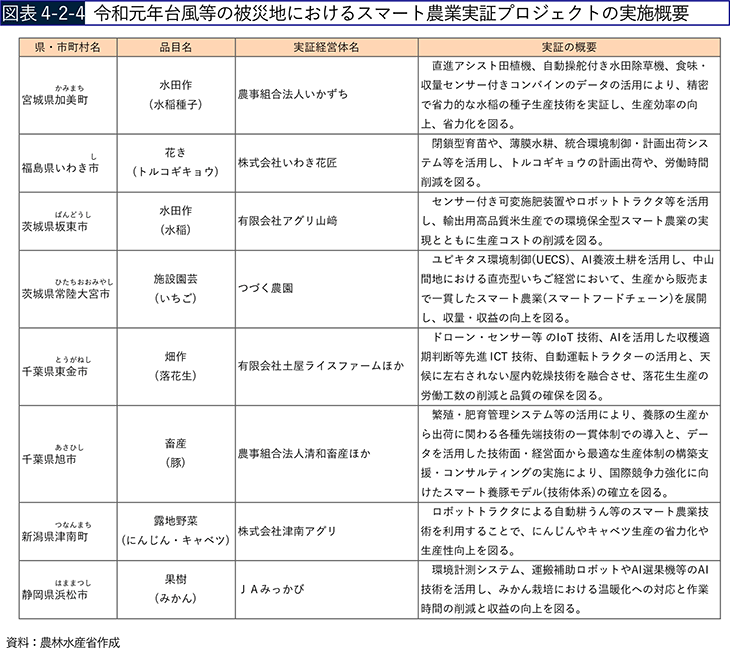
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883