第4節 防災・減災、国土強靱化と大規模自然災害への備え
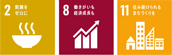
自然災害が頻発化・激甚化する中、今後も発生し得る災害に備えるため、農業・農村の防災・減災、国土強靱(きょうじん)化対策の推進が喫緊の課題となっています。農林水産省では、「国土強靱化基本計画」に基づき、国土強靱化対策を推進するとともに、農業保険への加入等農業者自身が行うべき災害への備え等を行うよう取り組んでいます。本節では、これらの取組状況について紹介します。
(1)防災・減災、国土強靱化対策の推進
(「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」等を推進)
国土強靱化対策を推進するため、令和2(2020)年度は関係予算を6,287億円(3か年緊急対策に係る臨時・特別の措置1,008億円を含む。)確保し、「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」(平成30(2018)年12月閣議決定)に基づき、農業水利施設(*1)・ため池の整備や農業用ハウスの災害被害防止等に取り組みました。
また、令和3(2021)年度から実施する「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」(令和2(2020)年12月閣議決定)の初年度予算として、令和2(2020)年度第3次補正予算において2,209億円を確保し、(1)流域治水対策(農業水利施設の整備、水田の貯留機能向上)、(2)防災重点農業用ため池の防災・減災対策、(3)農業水利施設等の老朽化、豪雨・地震対策、(4)園芸産地事業継続対策等に取り組むこととしています。
そのような中、農業者の減少に伴う管理体制の脆弱(ぜいじゃく)化や近年における豪雨・地震の頻発化・激甚化に早急に対応するため、令和2(2020)年10月に「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法」を施行しました。
このほか、農地・農業水利施設が持つ洪水調節機能を活用するため、農林水産省では、関係省庁や地方公共団体、農業関係者等と連携しながら、大雨により水害が予測される際に、(1)事前に農業用ダムの水位を下げて雨水を貯留する「事前放流」、(2)水田に雨水を一時的に貯留させる「田んぼダム」、(3)ため池への雨水の一時的な貯留、(4)農作物への被害のみならず、市街地や集落の湛水被害も防止・軽減させる排水施設の整備等、流域治水の取組を通じた防災・減災対策を強化しています。
*1 用語の解説3(1)を参照
(2)災害への備え
(農業者自身が行う自然災害への備え)
自然災害等の農業経営のリスクに備えるためには、農業用ハウスの保守管理、農業保険等の利用等に農業者自身が取り組んでいくことも重要です。
農林水産省では、近年、台風、大雪等により園芸施設の倒壊等の被害が多発している状況に鑑み、農業用ハウスの保守管理や補強等の台風や大雪による被害の防止に向けた技術指導のほか、農業用ハウスの資産価値に応じて新築時の資産価値の8割を上限に補償する園芸施設共済に加え、収量減少や価格低下等農業者の経営努力で避けられない収入減少を幅広く補償する収入保険への加入促進を重点的に行うなど、農業者自身が災害への備えを行うよう取り組んでいます。なお、園芸施設共済については、令和元(2019)年度の加入率は60%となっていますが、令和2(2020)年9月から、耐用年数を超えたハウスも新築時の資産価値まで補償できる特約を導入する等補償の充実を図るなど、農業者の幅広いニーズに応えられるよう見直しを行っています。
このほか、豪雨や台風等の風水害等に備えるための予防減災情報をWebサイト上で情報発信しています(図表4-4-1)。
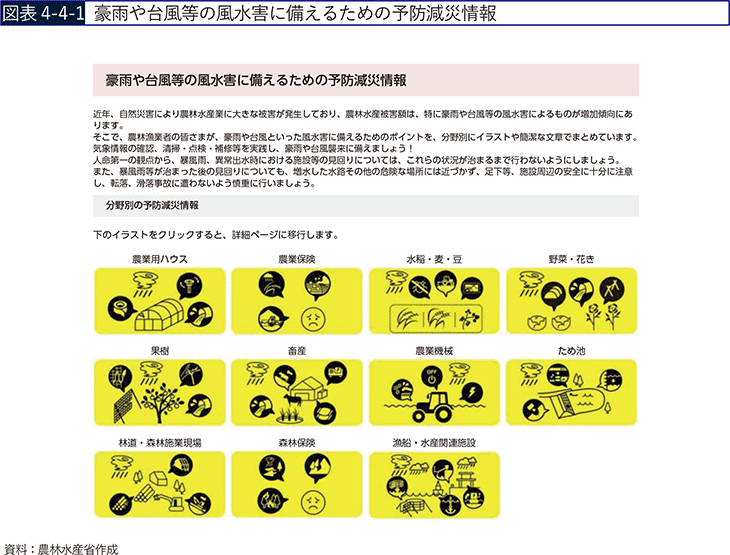
また、MAFFアプリでは、台風の接近時等に、災害への備えに関する情報や、農業者が作業時に留意すべき事項、被災した農林漁業者向けの支援策の情報を、農業者等ユーザーのスマートフォンにプッシュ通知でお知らせしています。
(「自然災害等のリスクに備えるためのチェックリスト」と「農業版BCP(事業継続計画書)」のフォーマットを策定)
農業者自身が行う自然災害等への備えの取組の定着に資するよう、令和3(2021)年1月に「自然災害等のリスクに備えるためのチェックリスト」と「農業版BCP(*1)(事業継続計画書)」のフォーマットを策定しました(図表4-4-2)。
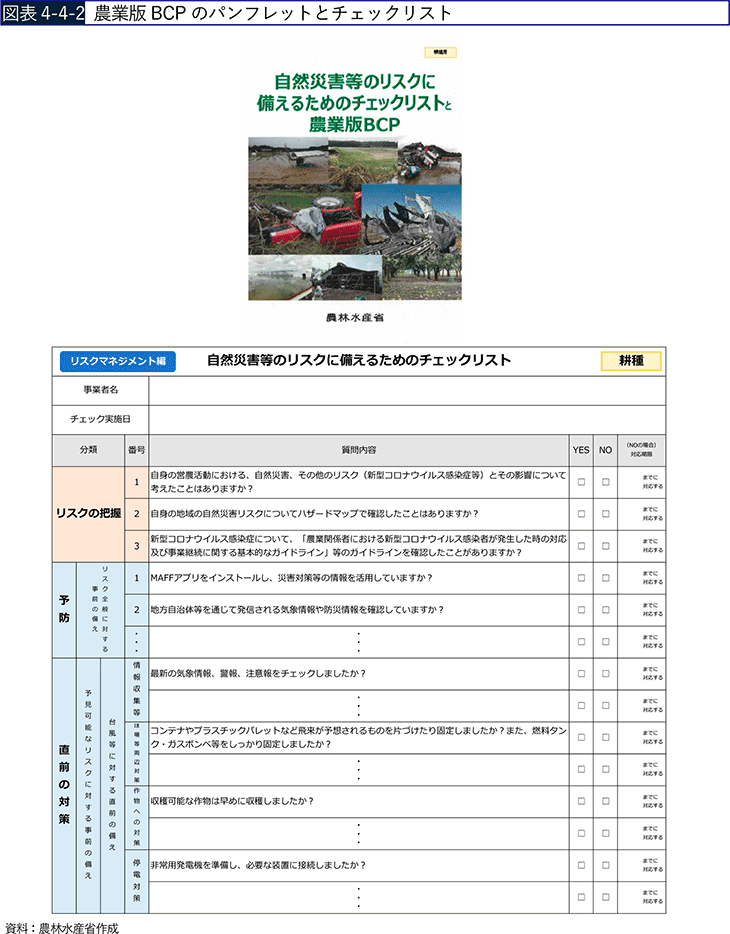
本チェックリストと農業版BCPは、耕種、園芸、畜産の3種類から構成され、自然災害等のリスクに対する備えの意識やMAFFアプリ等自然災害等に係る注意喚起システムへの関心を高めるとともに、台風被害等の軽減のための取組事例等(災害の教訓)の提供や農業保険等セーフティネットへの加入の契機となることを目的としています。
チェックリストは、平時からのリスクに対する備えや台風等の自然災害への直前の備えに関するチェック事項であるリスクマネジメント編と、被災後の早期復旧・事業再開の観点から対策すべき事項(ヒト、モノ、カネ/セーフティネット、情報等)である事業継続編から構成されています。
農業版BCPは、インフラや経営資源等について、被害を事前に想定し、被災後の早期復旧・事業再開に向けた計画を定めるものであり、決して難しいものではなく、農業者自身に経験として既に備わっていることも含め、「見える化」することで、自然災害に備えるためのものです。また、チェックリストや農業版BCPの作成を通じて、平常時における自らの経営の見直しや、改善にもつながるものであり、今後、農業者自身が自然災害等の備えに活かせるよう、活用を促進していくこととしています。
*1 用語の解説3(2)を参照
(家庭で行う災害への備え)
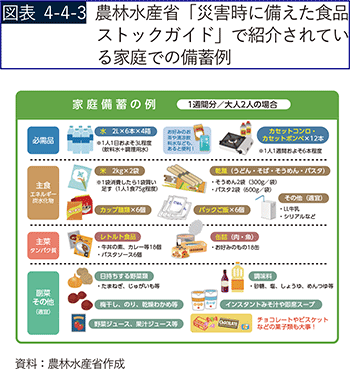
家庭では、大規模な自然災害等の発生に備え、自身の身を守る上で当面必要となる食料や飲料水を用意しておくことが重要です。家庭における備蓄量は、最低3日分から1週間分の食品を人数分備蓄しておくことが望ましいと言われています。
農林水産省では、平成31(2019)年3月に、ローリングストック(*1)等、平時から食料の家庭備蓄を実践しやすくする方法や、乳幼児や高齢者、食物アレルギー等の要配慮者がいる家庭での実践方法をまとめた「災害時に備えた食品ストックガイド」と「要配慮者のための災害時に備えた食品ストックガイド」を作成したほか、Webサイト「家庭備蓄ポータル」やBUZZ MAFFの動画、SNS等での情報発信を通して、家庭備蓄の定着に取り組んでいます(図表4-4-3)。
*1 普段の食品を少し多めに買い置きしておき、賞味期限を考えて古いものから消費し、消費した分を買い足すことで常に一定量の食品が家庭で備蓄されている状態を保つための方法
(コラム)災害等は忘れる前にやってくる~国はリスクに対して様々な支援を用意~
令和2(2020)年度は、令和2年7月豪雨や大雪等の自然災害、鳥インフルエンザ等の家畜伝染病が発生しました。
自然災害や家畜伝染病等の様々なリスクに対して、国は、現場の要望等を聴きながら、きめ細かな支援策を措置し、農業者の1日も早い経営再開に向けて対応しています。
今後も起こり得る様々なリスクに対し、平時から、農業者自身が農業用ハウスの保守管理・補強や、農業保険等への加入、飼養衛生管理基準の遵守等、取り組むべきことには取り組み、リスクに備えることが重要です。国としても、そうした農業者の営農継続の努力に対して全面的に協力していきます。
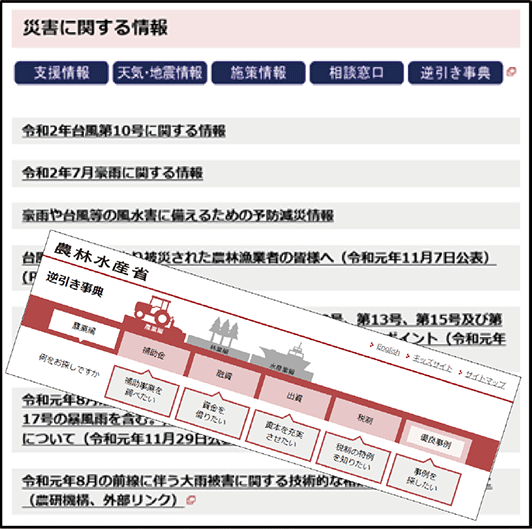
農林水産省Webサイトの「災害に関する情報」や「逆引き辞典」から防災・減災に関する支援策をチェック
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883




