(7)今後に向けて
今回、我が国の農業構造のこれまでの変化について分析を進めたところ、我が国農業の持続的な発展のためには、若年層等の農業従事者の確保・定着と併せて、それらの農業従事者一人一人がこれまでに比べてより大きな役割を担っていくことが必要となっていることがうかがえます。
このような中、経営耕地面積に占める主業経営体と法人経営体の割合が増加傾向であり、1経営体当たりの経営規模も拡大し、大規模層では農業所得も大きくなっていることから、基盤整備による大区画化や農地の集約化、経営データの活用等のスマート農業の取組を促進すること等と併せ、法人化・規模拡大の取組は今後とも重要であると考えられます。その一方で、経営耕地面積に占める65歳以上の農業従事者の割合は依然として大きく、地域の農業を維持する観点からは、これら農業従事者の果たす役割も引き続き大きいと考えられます。
また、農業生産の品目構成においては、米の割合が減少し、畜産や野菜の割合が増加傾向にあり、若年層の農業従事者の割合が畜産や野菜の部門で高くなっていること、さらに1経営体当たりの生産農業所得は米以外の産出額が大きい県の方が大きいことから、需要の変化に応じた生産の取組が今後とも重要であることがうかがえます。
このようなこれまでの変化(シフト)の傾向は、地域ごとに様々な事情もある中での現場の生産者や地方公共団体等の関係者による取組が反映されたものであることから、今後の持続可能な農業構造の実現に向けての大きな方向性を示す道標となると考えられます。
(コラム)食料・農業・農村基本計画における農業経営モデル
令和2(2020)年3月に閣議決定した食料・農業・農村基本計画における「農業経営の展望」では、家族経営を含む多様な担い手が地域の農業を維持・発展できるよう、他産業並の所得を目指し、新技術等を導入した省力的かつ生産性の高い経営モデルを、主な営農類型・地域について例示しています。具体的には、水田作、畑作等営農類型別に、意欲的なモデル、現状を踏まえた標準的なモデル、スマート農機の共同利用や作業の外部委託等を導入したモデル、複合経営モデルの計37モデルを提示しています。あわせて、半農半X等多様なライフスタイルを実現する取組や規模が小さくても安定的な経営を行いながら、農地の維持、地域の活性化等に寄与する取組を事例として取り上げています。また、小規模農家も含めた多様な農業経営の取組事例を参考として提示しています。
各地域で、これらのモデルや事例を参考として、担い手の育成や所得増大に向けた取組が進展することが期待されています。
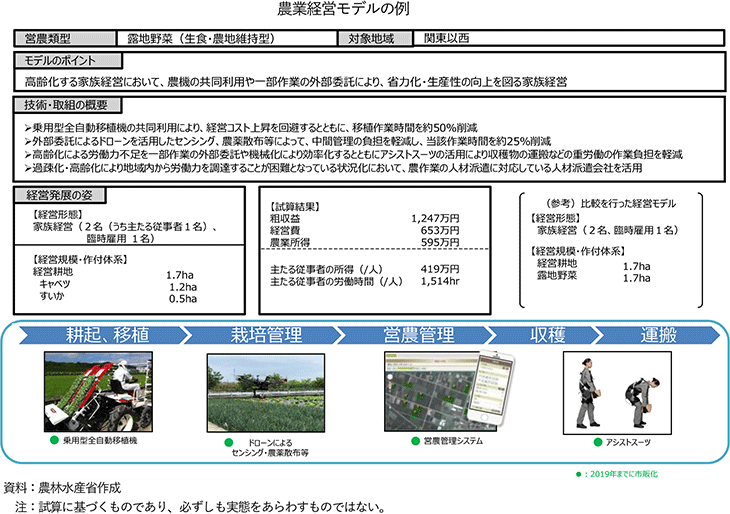
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883




