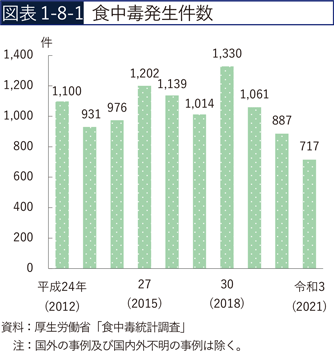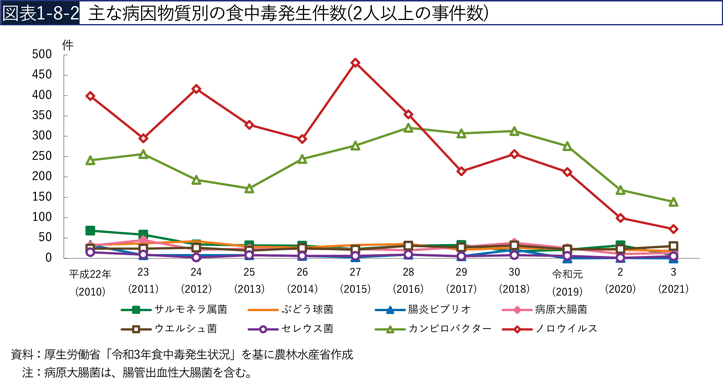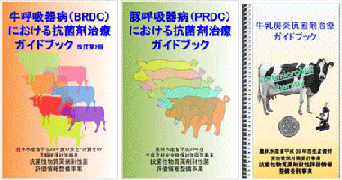第8節 国際的な動向に対応した食品の安全確保と消費者の信頼の確保
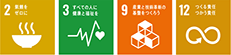
食品の安全性を向上させるためには、食品を通じて人の健康に悪影響を及ぼすおそれのある有害化学物質・微生物について、科学的根拠に基づいたリスク管理等に取り組むとともに、農畜水産物・食品に関する適正な情報提供を通じて消費者の食品に対する信頼確保を図ることが重要です。本節では、国際的な動向等に対応した食品の安全確保と消費者の信頼の確保のための取組を紹介します。
(食中毒発生件数は直近10年間で最少)
食中毒の発生は、消費者に健康被害が出るばかりでなく、原因と疑われる食品の消費の減少にもつながることから、農林水産業や食品産業にも経済的な影響が及ぶおそれがあります。このような中、農林水産省は、食品の安全や、消費者の信頼を確保するため、「後始末より未然防止」の考え方を基本とし、科学的根拠に基づき、生産から消費に至るまでの必要な段階で有害化学物質・微生物の汚染の防止や低減を図る措置の策定・普及に取り組んでいます。
令和3(2021)年の食中毒の発生件数は、全体で717件と令和2(2020)年に引き続き直近10年間で最少となりました(図表1-8-1)。食中毒発生件数が減少した要因としては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の発出、いわゆる3密(密閉、密集、密接)を避ける生活様式の常態化により、飲食店の利用機会が減少したことが考えられます。
一方で、患者数が2人以上の食中毒事件の病因物質別内訳において、カンピロバクター(*1)とノロウイルス(*2)の二つが他の物質より多いという傾向は、依然として変わっていません(図表1-8-2)。
1 食中毒の原因細菌の一つ。加熱不足の鶏肉が主な原因
2 食中毒の原因ウイルスの一つ。加熱不足の二枚貝や、ウイルスに汚染された食品が主な原因
(最新の科学的知見・動向を踏まえリスク管理を実施)
農林水産省は、食中毒の発生件数の増減等の最新の科学的知見や、消費者・食品関連事業者等関係者の関心、国際的な動向を考慮して、令和4(2022)年2月に「農林水産省が優先的にリスク管理を行うべき有害微生物のリスト」を更新しました。
更新した優先リストでは、カンピロバクター、サルモネラ、腸管出血性大腸菌、ノロウイルス、リステリア・モノサイトジェネスを「リスク管理を継続するため、生産段階での保有実態や食品中の汚染実態の調査の実施及びリスク管理措置の策定・検証の必要がある危害要因」としました。また、E型肝炎ウイルス、A型肝炎ウイルスを「リスク管理措置の必要性を検討するための基礎的情報が不足しているため、継続して情報を収集する必要がある危害要因」としました。このほか、この優先リストに基づいて、令和4(2022)年2月に、令和4(2022)年度から令和8(2026)年度までの有害微生物の実態調査の計画(サーベイランス・モニタリング中期計画)を作成しました。
農林水産省では、有害化学物質・微生物について、中期計画に基づいて毎年度の計画(サーベイランス・モニタリング年次計画)を策定し、農畜水産物・食品の実態調査等とともに、汚染低減のための指針等の導入・普及や衛生管理の推進などの安全性向上対策を食品関連事業者と連携して実施しています。令和3(2021)年7月には、野菜の生産段階における衛生上の注意点をまとめた「栽培から出荷までの野菜の衛生管理指針」を、令和4(2022)年2月には、コメに含まれる無機ヒ素を低減する技術等をまとめた「コメ中ヒ素の低減対策の確立に向けた手引き」を改訂しました。
さらに、食品安全に関する国際基準・国内基準や規範の策定、リスク評価に貢献するため、これらの取組により得た科学的知見やデータをコーデックス委員会(*1)や関連の国際機関、関係府省へ提供しています(図表1-8-3)。
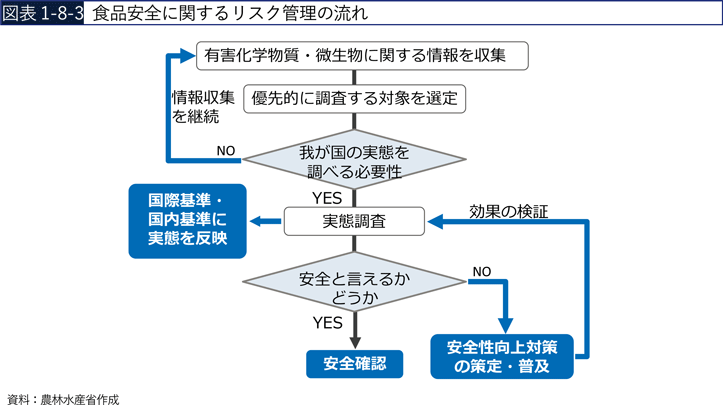
1 用語の解説3(1)を参照
(抗菌剤の適正かつ慎重な使用のため、薬剤耐性の知識・理解に関する普及啓発を推進)
近年、畜水産物の安定供給に必要な抗菌剤は、その不適切な使用を原因とした薬剤耐性菌(*1)の発生により、動物だけでなく人への影響も懸念されることから、国内外で薬剤耐性菌の監視・動向調査、抗菌剤の適正かつ慎重な使用に関する厳しい対応が求められています。こうしたことから、省庁横断的に取り組むべき対策を関係閣僚会議(*2)において、「薬剤耐性(AMR(*3))対策アクションプラン(以下「アクションプラン」という。)」として取りまとめたことを受け、厚生労働省や農林水産省等はアクションプランに基づき、薬剤耐性菌の増加を防ぐ対策に取り組んでいます。
アクションプランに位置付けられた目標に基づいて薬剤耐性菌の発生を防ぐため、農林水産省は、平成28(2016)年からポスターや家畜疾病の抗菌剤治療ガイドブックなどを活用しながら獣医師、家畜の飼養者、獣医系大学生、愛玩(あいがん)動物飼育者等に抗菌剤の適正かつ慎重な使用を促しています。医療分野と連携したシンポジウムの開催や大学における講義に加え、令和3(2021)年3月から、事故率の低減や生産性の向上を実現し、抗菌剤に頼らない養豚生産を実践している飼養者の取組を、優良事例動画としてWebサイトで紹介しています。
このほか、農林水産省は、抗菌剤の飼料添加物としての指定の取消しや薬剤耐性菌の動向調査の強化を進めてきました。家畜に対する使用量が多いテトラサイクリン(*4)と人の健康に大きな影響が及ぶおそれがある第3世代セファロスポリン(*5)、フルオロキノロン(*6)について、薬剤への耐性率を成果指標として定め、毎年モニタリングを行っています。
1 薬剤耐性とは抗菌性物質に対する、細菌の抵抗性のことで、この抵抗性を示した細菌のことを薬剤耐性菌という。
2 平成28(2016)年4月に開催された国際的に脅威となる感染症対策関係閣僚会議
3 Antimicrobial Resistanceの略
4 作用機序はタンパク質の合成阻害。比較的安全な抗生物質だが、歯の着色や投与局所の刺激性が特徴
5 作用機序は細菌の細胞壁の形成阻害。フルオロキノロンとともに医療のみならず獣医療でも重要な抗菌剤
6 作用機序は細菌のDNA複製に不可欠な酵素である、DNAジャイレース及びトポイソメラーゼの活性阻害
(肥料の原料管理制度が開始)
産業副産物等の未利用資源の肥料としての有効活用や、農業者のニーズに応じた肥料生産に向け、令和元(2019)年12月に公布された「肥料取締法の一部を改正する法律」に基づき、令和3(2021)年12月に原料管理制度が施行されました。
これにより、産業副産物等に由来する肥料を農業者がより安心して利用できるよう、肥料に使用できる原料の種類や条件について規格が設定されるとともに、肥料の生産業者・輸入業者に対しては、適切に原料が利用されていることを確認できるよう原料帳簿の備付けが義務付けられたほか、生産業者や輸入業者が掲示物等で使用原料等の虚偽宣伝を行うことが禁止になりました。
また、令和2(2020)年12月に施行された肥料の配合に関する規制の見直しにより、普通肥料(化学肥料等)と特殊肥料(堆肥等)を配合した肥料や、肥料と土壌改良資材を配合した肥料を、届出で生産・輸入できるようになりました。令和3(2021)年度には、こうした肥料の生産・輸入に係る農林水産大臣への届出が176件ありました。また、当該制度の更なる活用に向け、肥料事業者向けオンライン説明会の開催等を通じた制度内容の周知を行いました。
(最新の科学的知見に基づく農薬の再評価を開始)
農林水産省は、農薬の安全性の一層の向上を図るため、平成30(2018)年12月に改正された農薬取締法に基づき、令和3(2021)年度から再評価制度を開始しました。
農薬の再評価は、農薬の安全性に関する最新の科学的知見に基づき、全ての農薬についておおむね15年ごとに実施することとしています。再評価の対象となる農薬は、平成30(2018)年12月時点で4千以上あるため、人の健康や環境に対する影響の大きさを考慮し、国内での使用量が多い農薬から優先して順次再評価を進めていくこととしています。再評価の結果、必要に応じて随時登録内容の見直し等を実施します。
令和3(2021)年度は、国内での使用量が多い農薬として、グリホサートやネオニコチノイド系農薬等、14有効成分(*1)を含む農薬を対象に、最新の科学的知見に基づき再評価を開始しました。
1 アセタミプリド、イソチアニル、イミダクロプリド、グリホサートアンモニウム塩、グリホサートイソプロピルアミン塩、グリホサートカリウム塩、グリホサートナトリウム塩、クロチアニジン、1,3-ジクロロプロペン、ジノテフラン、チアメトキサム、チオベンカルブ、チフルザミド、ブタクロール
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883