第9節 動植物防疫措置の強化
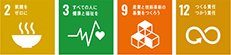
食料の安定供給や農畜産業の振興を図るため、農林水産省は関係省庁や都道府県と連携し、高病原性鳥インフルエンザ(*1)や豚熱(ぶたねつ)(*2)を始めとする家畜伝染病や植物病害虫に対し、侵入・まん延を防ぐための対応を行っています。また、近年、アフリカ豚熱(*3)、口蹄疫(こうていえき)等畜産業に甚大な影響を与える越境性動物疾病が近隣のアジア諸国において継続的に発生しています。これら疾病の海外からの侵入を防ぐためには、関係者が一丸となって取組を強化することが重要です。
本節では、こうした観点から動植物防疫措置の強化等に関わる様々な取組を紹介します。
*1 用語の解説3(1)を参照
*2 用語の解説3(1)を参照
*3 用語の解説3(1)を参照
(高病原性鳥インフルエンザへの備えを徹底)
令和3(2021)年11月に秋田県で高病原性鳥インフルエンザが発生して以降、令和4(2022)年3月末までに11県(*1)17例の発生が確認され、約109万羽が殺処分の対象となっています(図表1-9-1)。農林水産省は関係省庁や都道府県と連携し、迅速な防疫措置が実施されるよう、必要な人的・物的支援を行いました。
また、全国の都道府県に対しては、発生状況等に応じて飼養衛生管理基準の遵守指導の徹底等を通知するとともに、各都道府県を通じて飼養衛生管理の全国一斉点検等の取組を実施しました。
引き続き、消毒や防鳥ネットの管理等、全ての関係者による飼養衛生管理の徹底や早期発見・通報のための監視の強化が求められます。
なお、我が国の現状において、家きんの肉や卵を食べることにより、ヒトが鳥インフルエンザウイルスに感染する可能性はないと考えています。
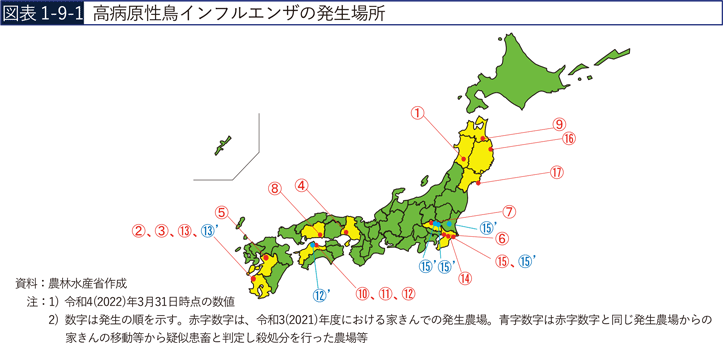
*1 秋田県、鹿児島県、兵庫県、熊本県、千葉県、埼玉県、広島県、青森県、愛媛県、岩手県、宮城県
(豚熱はワクチン接種開始後も引き続き発生)
平成30(2018)年9月に26年ぶりに国内で豚熱が確認されてから、令和4(2022)年3月時点で16県(*1)の豚又はイノシシの飼養農場において77例の発生が確認されています(図表1-9-2)。令和元(2019)年10月の豚熱ワクチン接種開始後も19例の発生が確認され、ワクチン接種推奨地域は39都府県に拡大しています。
令和3(2021)年度は、7県(*2)の飼養農場で、14例が発生しました。
農林水産省は豚熱対策として、農場防護柵の設置や飼養衛生管理の徹底に加え、サーベイランスや捕獲の強化、経口ワクチン散布等の野生イノシシ対策を行うとともに、令和元(2019)年10月から飼養豚への予防的ワクチンの接種を実施しています。
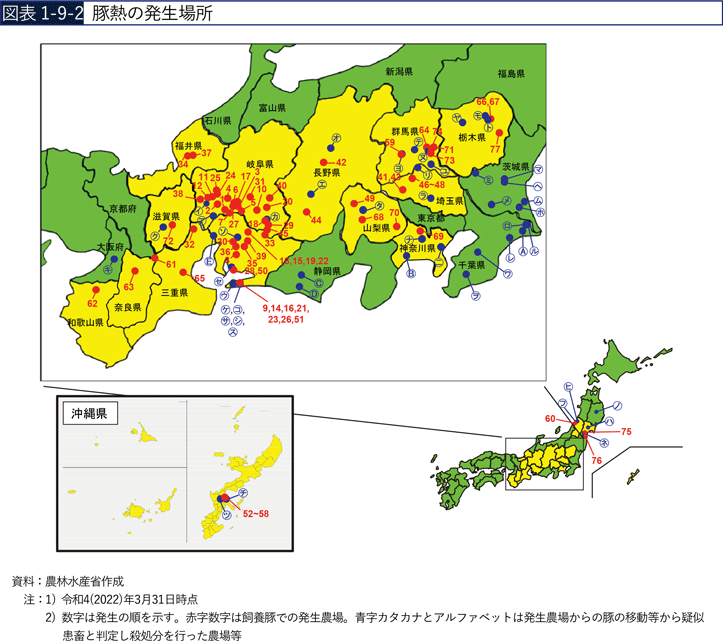
*1 岐阜県、愛知県、三重県、福井県、埼玉県、長野県、山梨県、沖縄県、群馬県、山形県、和歌山県、奈良県、栃木県、神奈川県、滋賀県、宮城県
*2 群馬県、三重県、栃木県、山梨県、神奈川県、滋賀県、宮城県
(家畜衛生対策を強化するため飼養衛生管理基準等を改正)
令和2(2020)年度の高病原性鳥インフルエンザの過去最大の発生と豚熱ワクチン接種農場での豚熱の継続的な発生を踏まえ、農林水産省は家畜衛生対策を強化するため、令和3(2021)年9月に飼養衛生管理基準等を改正し、大規模農場における畜舎ごとの飼養衛生管理者の配置や対応計画の策定、埋却地確保の取組の必要性を明確化しました。

飼養衛生管理基準について
URL:https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_shiyou/
(事例)豚熱対策による一時飼養中断から黒豚飼養に挑戦(愛知県)
愛知県田原市(たはらし)の愛知県立渥美(あつみ)農業高等学校は、市内で大きな被害が出た豚熱からの復興に力を入れています。同校はこれまで、三元交配豚(*1)を飼育し年間約350頭を出荷してきました。くわえて、地域では珍しい黒豚(バークシャー種)の導入も計画していましたが、平成31(2019)年2月以降、市内各地で豚熱の感染確認が相次いだため、同年11月に全頭出荷を完了した後、飼養を一時中断しました。
令和2(2020)年2月、県内の飼養豚へのワクチン接種開始を機に、同校は長野県の農場から英国系統の黒豚(雄2頭、雌6頭)を仕入れ、豚熱対策を徹底した上で飼養を開始し、令和3(2021)年2月、市外の精肉店に初めて出荷しました。黒豚の肉質は繊細で、臭みもなく好評でした。
今後、地元酒造会社の芋焼酎かすや市内の規格外トマトを黒豚に給与して、黒豚の発育調査に取り組み、食品廃棄物の有効活用とともに、黒豚飼養の振興を進めていくこととしています。
*1 2種の品種を交配させて生まれた雌の豚と、もう1種類の雄を交配させて生まれた、3種類の品種を重ね合わせた豚
(家畜伝染病予防法を改正し水際検疫体制を強化)
令和2(2020)年7月に施行された改正家畜伝染病予防法により、家畜防疫官の質問・検査権限の強化や廃棄権限の新設、輸出入検疫に係る罰則の引上げ等の措置が講じられました。また、動植物検疫探知犬については令和2(2020)年度末までに140頭体制へと増頭し、家畜防疫官については令和3(2021)年度末には508人体制とするなど体制の強化も図っています。
近隣のアジア諸国においては、アフリカ豚熱、口蹄疫等畜産業に甚大な影響を与える越境性動物疾病が確認されています。引き続き、海外の越境性動物疾病の国内侵入を阻止するため、入国者に対する家畜防疫官の口頭質問や動植物検疫探知犬を活用し、旅客の携帯品や国際郵便による肉製品の違法持込みを摘発するなど、強化した体制で水際対策を徹底して行っています。

動物検疫所から肉製品の持ち込みについてのお知らせ
(海外から肉や肉製品を持ち込まないで!)
URL:https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg20233.html(外部リンク)
(植物の病害虫の侵入・まん延を防止)
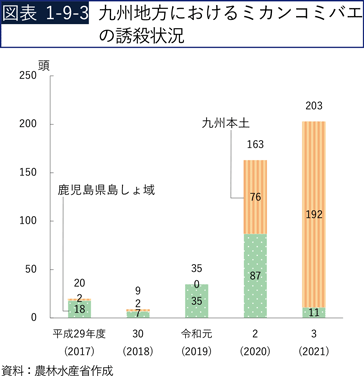
農林水産省では、病害虫の侵入を効果的かつ効率的に防止するため、海外での発生情報等を踏まえた適切な検疫措置を検討する病害虫リスクアナリシスを行うとともに、その結果に基づき、侵入を警戒すべき病害虫の見直し等を実施しています。
病害虫リスクアナリシスの結果等を踏まえ、病害虫の国内侵入を阻止するため、空港・港等において、貨物、携帯品、国際郵便物により輸入される全ての植物やその容器包装を対象に検疫を行っています。また、国内での病害虫のまん延を防ぐため、都道府県と連携し、病害虫の侵入警戒調査を実施しています。病害虫の侵入が連続して見られる場合、防除区域を指定し生果実等の移動を禁止するなど、侵入病害虫に対する緊急防除等の取組を進めています。
令和3(2021)年5月以降、沖縄及び九州の一部の県において、かんきつ類等の重要害虫であるミカンコミバエ種群の発見が相次ぎました。これを受けて農林水産省は県と連携し、初動防除として雄成虫を誘引して殺虫する誘殺板を設置しました。くわえて、本虫に寄生された果実が確認された地域では、寄主植物の除去やヘリコプターによる誘殺板の散布(航空防除)を実施し、本虫の定着防止に取り組んでいます(図表1-9-3)。
(植物防疫法改正案を国会に提出)
近年、温暖化等による気候変動、人やモノの国境を越えた移動の増加等に伴い、植物の病害虫の侵入・まん延リスクが高まっています。
他方、化学農薬の低減等による環境負荷低減が国際的な課題となっていることに加え、国内では化学農薬に依存した防除により薬剤抵抗性が発達した病害虫が発生するなど、発生の予防を含めた防除の普及等を図っていくことが急務となっています。
また、農林水産物・食品の輸出促進に取り組む中で、植物防疫官の輸出検査業務も増加するなど、植物防疫をめぐる状況は複雑化しています。
このため、 輸入検疫等の対象及び植物防疫官の権限の拡充・強化、新たに海外から侵入する病害虫について国内への侵入状況等に関する調査事業の実施及び防除内容等に係る基準の作成等による緊急防除の迅速化、国内に広く存在する病害虫について発生予防を含めた総合防除を推進するための仕組みの構築、農林水産大臣の登録を受けた登録検査機関による輸出検査の一部の実施等を内容とする「植物防疫法の一部を改正する法律案」を令和4(2022)年2月に国会に提出しました。

第208回国会提出法律案(農林水産省)
URL:https://www.maff.go.jp/j/law/bill/208/index.html
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883










