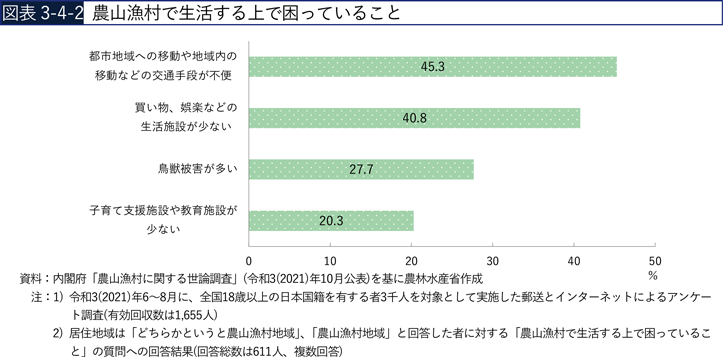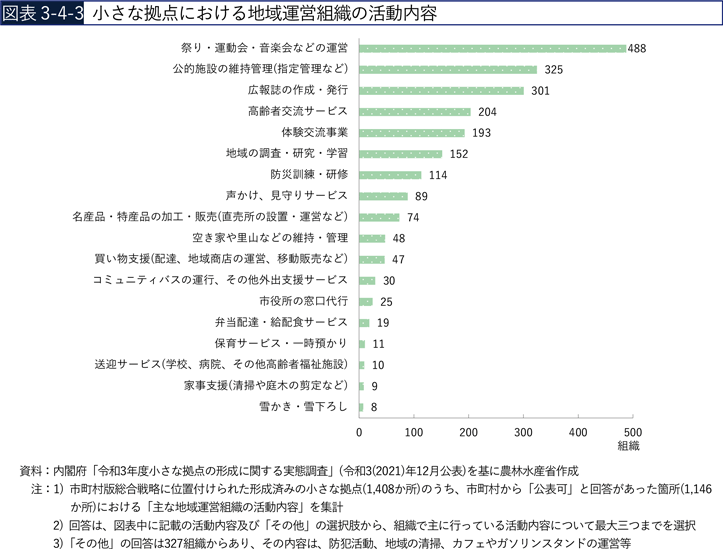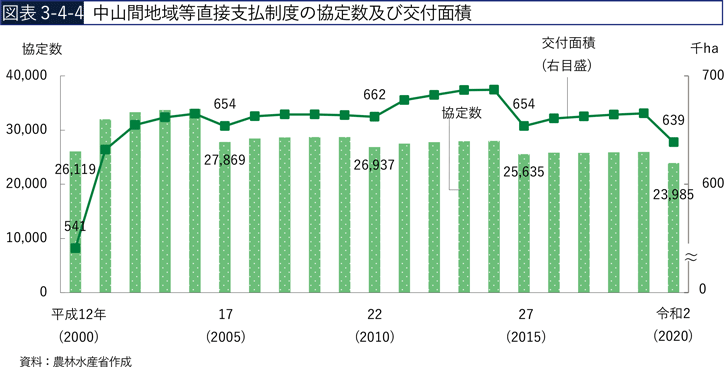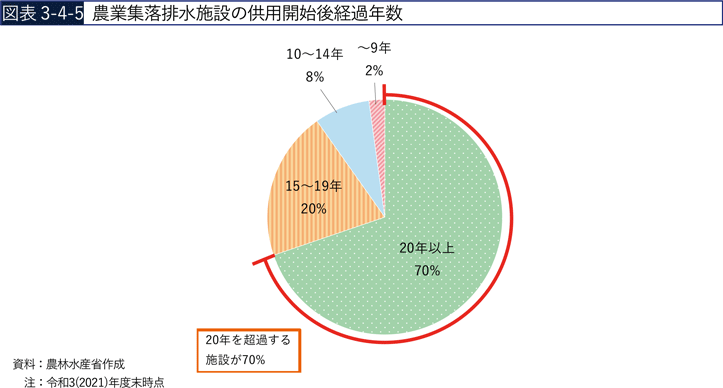第4節 中山間地域をはじめとする農村に人が住み続けるための条件整備

中山間地域(*1)を始めとする農村は、多様な地域住民が生活する場ですが、人口減少や少子高齢化が都市に先駆けて進行しています。このような中で農村を維持し、次の世代に継承していくためには、集落の現状を踏まえた地域コミュニティの維持を目的とする活動を支援するとともに、多面的機能(*2)の発揮を促進するための日本型直接支払制度(*3)の活用等により、農村に人が安心して住み続けるための条件が整備されることが必要です。本節では、これらの取組に係る動向について紹介します。
1 用語の解説2(7)を参照
2 用語の解説4を参照
3 多面的機能支払制度、中山間地域等直接支払制度、環境保全型農業直接支払制度の三つの制度から構成
(1)地域コミュニティ機能の維持や強化
ア 地域コミュニティ機能の形成のための場と世代を超えた人々による地域のビジョンづくり
(集落の現状を踏まえ地域コミュニティを維持)
農村は、地域住民の生活や就業の場になっています。そして農村を支える農業集落(*1)は、地域に密着した水路・農道・ため池等の農業生産基盤や収穫期の共同作業・共同出荷等の農業生産面のほか、集落の寄り合い(地域の諸課題への対応を随時検討する集会、会合等)といった協働の取組や伝統・文化の継承等、生活面にまで密接に結び付いた地域コミュニティとして機能しています。
2020年農林業センサスによると、寄り合いの開催回数が年間5回以下と少ない集落の割合を地域別に見ると、北海道や中国、四国地方で大きい傾向にあります(図表3-4-1)。これらの地域での集落活動が弱体化し、地域コミュニティの維持が難しくなりつつあると考えられます。
また、令和3(2021)年6~8月に内閣府が行った世論調査によると、農山漁村で生活する上で困っていることとして、「都市地域への移動や地域内の移動などの交通手段が不便」や、「買い物、娯楽などの生活施設が少ない」との回答がそれぞれ4割を超えています(図表3-4-2)。このことからも、今後、一層農村の地域コミュニティの維持が難しくなることが考えられます。
こうした中、同年6月に公表した「新しい農村政策の在り方に関する検討会」及び「長期的な土地利用の在り方に関する検討会」の中間取りまとめ(*2)(以下「両検討会中間取りまとめ」という。)においては、中山間地域を中心に、集落そのものは当面維持されるとしつつも、農地の保全や、買物・子育て等の集落の維持に必要不可欠な機能が弱体化する地域が増加していくことが懸念されるとしています。また、こうした集落の機能を補完するためには、地域の有志の協力の下、地域コミュニティの維持に資する取組を支援することが重要だとしています。
農林水産省は、地域住民がいきいきと暮らしていける環境の創出を行うため、地域住民団体等からなる地域協議会に対して、買物支援等の農山漁村で暮らす人々が引き続き住み続けるための取組等の活動計画の策定やそれを実施するための体制構築等を支援しています。令和3(2021)年度は、全国で58地区の活動計画の策定や体制構築等を支援しました。
1 用語の解説3(1)を参照
2 第3章第3節を参照
イ 「小さな拠点」の形成の推進
(「小さな拠点」の形成数が増加)

「小さな拠点」の形成について
URL:https://www.chisou.go.jp/sousei/about/chiisanakyoten/index.html(外部リンク)
地域住民が地方公共団体や事業者、各種団体と協力・役割分担をしながら、行政施設や学校、郵便局等の各種生活支援機能を集約・確保するほか、地域の資源を活用し、仕事・収入を確保する取組等により地域のコミュニティを維持する「小さな拠点」については、令和3(2021)年5月末時点で、全国で前年より約1割増加となる1,408か所(*1)で形成されています。
このうち85%の1,199か所においては住民主体の地域運営組織(*2)(RMO)が設立され、地域の祭りや公的施設の運営、広報誌の作成のほか、高齢者交流サービス、体験交流、特産品の加工・販売、買物支援等、様々な取組が行われています(図表3-4-3)。
関係府省庁が連携し、遊休施設の再編・集約に係る改修や、廃校施設の活用等に取り組む中、農林水産省は、農産物加工・販売施設や地域間交流拠点等、インフラの整備を行っています。
1 市町村版総合戦略に位置付けのある小さな拠点の数
2 地域の暮らしを守るため、地域で暮らす人々が中心となって形成され、地域内の様々な関係主体が参加する協議組織が定めた地域経営の指針に基づき、地域課題の解決に向けた取組を持続的に実践する組織のこと(総務省「暮らしを支える地域運営組織に関する調査研究事業報告書」)
(集落の機能を補完する「農村RMO」の形成を支援)
中山間地域を中心に、集落の維持に必要不可欠な機能が弱体化する地域が増加していくことが懸念されている中で、両検討会中間取りまとめにおいては、複数の集落の機能を補完して、農用地保全活動や農業を核とした経済活動と併せて、生活支援等の地域コミュニティの維持に資する取組を行う「農村型地域運営組織(*1)」(以下「農村RMO」という。)を形成していくことの重要性が示されました。この農村RMOは、中山間地域等直接支払の農用地の保全活動を行う組織等を中心に、地域の多様な主体を巻き込みながら、農山漁村の生活支援に至る取組を手掛ける組織へと発展していくものです。
これを受け、農林水産省は、複数の農村集落の機能を補完する農村RMOの形成を推進するため、農村RMOを目指すむらづくり協議会等が策定する将来のビジョンに基づく農用地保全、地域資源の活用、生活支援に係る計画の作成、実証事業等の取組に対して支援します。また、関係する部局や機関(都道府県、市町村の関連部局や農協、NPO法人(*2)等)から構成される都道府県単位の支援チームや、全国プラットフォームの構築を支援し、農村RMOの形成を促進することとしています。
1 集落の機能を補完して、農地・水路等の地域資源の保全・活用や農業振興と併せて、買物・子育て支援等の地域コミュニティの維持に資する取組を行う事業体を指す。
2 用語の解説3(2)を参照
(2)多面的機能の発揮の促進
(中山間地域等直接支払制度の交付面積が減少、集落の将来像の話合いを促進)
農業・農村の多面的機能の維持・発揮を目的として、平成26(2014)年度から日本型直接支払制度(*1)が実施されています。

日本型直接支払制度について
URL:https://www.maff.go.jp/j/nousin/index.html#5-5
令和2(2020)年度から始まった中山間地域等直接支払制度の第5期対策では、人口減少や高齢化による担い手不足、集落機能の弱体化等に対応するため、制度の見直しを行いました。人材確保や営農以外の組織との連携体制を構築する活動のほか、農地の集積・集約化(*2)や農作業の省力化技術導入等の活動、棚田地域振興法の認定棚田地域振興活動計画に基づく活動を行う場合に、これらの活動を支援する加算措置を新設しました。
同年度の協定数は、交付面積が10ha未満の小規模な協定等において、「高齢化等で5年間続ける自信がない」、「集落のリーダーを確保できない」等を主な理由として協定が廃止されるケースがあったことから、前年度から2千協定減の2万4千協定となり、交付面積は前年度から2万6千ha減の63万9千haとなっています(図表3-4-4)。
令和2(2020)年度の協定数のうち、農業生産活動等を継続するための活動に加え、集落の話合いにより、集落の将来像を明確化する集落戦略の作成を要件としている「体制整備単価」の協定については、前年度から443協定増加し、1万8千協定となりました。中山間地域において農業や集落の維持を図っていくためには、協定参加者が地域の将来や地域の農地をどのように引き継いでいくか話合いを行うことが重要であるため、集落戦略の作成を推進しています。

中山間地域等直接支払制度の概要について
URL:https://www.maff.go.jp/j/nousin/tyusan/siharai_seido/s_about/index.html
1 日本型直接支払制度のうち、環境保全型農業直接支払制度については、第1章第6節を参照
2 用語の解説3(1)を参照
(多面的機能支払制度を着実に推進)
多面的機能支払制度は、農地維持支払と資源向上支払の二つから構成されています。
地域共同で行う農地法面(のりめん)の草刈り、水路の泥上げ等の地域資源の基礎的な保全活動等を対象とする農地維持支払は、令和2(2020)年度の認定農用地面積が、前年度から1万7千ha増加し、農用地面積(*1)の55%に当たる229万haとなっています。活動組織2万6,233のうち991の組織が広域活動組織として活動しており、前年度から44組織増加しています。
また、資源向上支払のうち、水路、農道等の軽微な補修を始めとする地域資源の質的向上を図る共同活動については、令和2(2020)年度の認定農用地面積が前年度から2万8千ha増加し、農用地面積の49%に当たる204万haとなっています。
資源向上支払のうち施設の長寿命化のための活動は、令和2(2020)年度の対象農用地面積が前年度から1万6千ha増加し、農用地面積の18%に当たる76万haとなっています。
このほか、令和3(2021)年度からは、水田の雨水貯留機能の強化(田んぼダム)の取組を行い、一定の取組面積等の要件を満たす場合に、資源向上支払のうち地域資源の質的向上を図る共同活動の単価を加算する措置を新たに講じました。さらに、多面的機能の増進を図る活動として、従来の農地周りの環境改善活動に加えて、鳥獣緩衝帯の整備・保全管理も対象としました。

多面的機能支払交付金の概要について
URL:https://www.maff.go.jp/j/nousin/kanri/tamen_siharai.html
1 農用地区域内の農地面積に農用地区域内の採草放牧地面積(共に令和元(2019)年時点、農林水産省調べ)を加えた面積
(3)生活インフラ等の確保
農村の生活インフラ等については、供用開始後20年(機械類の標準耐用年数)を経過する農業集落排水施設が70%に達するなど、老朽化の進行や災害への脆弱(ぜいじゃく)性が顕在化しています(図表3-4-5)。
このような状況を踏まえ、農林水産省は、老朽化の進行や災害への脆弱性が顕在化している農村のインフラの持続性を確保するとともに、地方移住への関心が高まっている機を捉えて農村の活性化を図るため、農業集落排水施設や農道といった生活インフラ等の再編・強靱(きょうじん)化、高度化等、農村に人が安心して住み続けられる条件整備を計画的・集中的に推進しています。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883