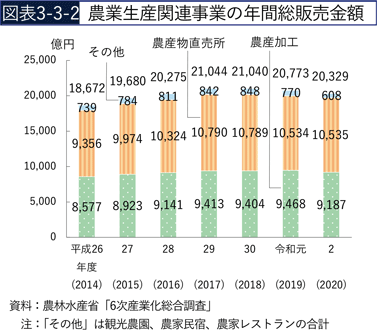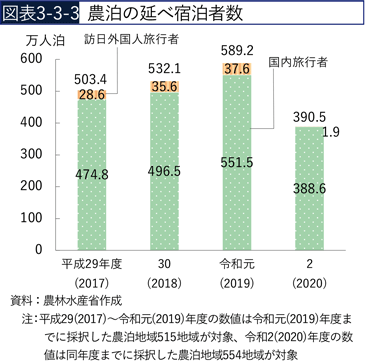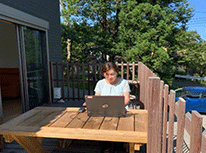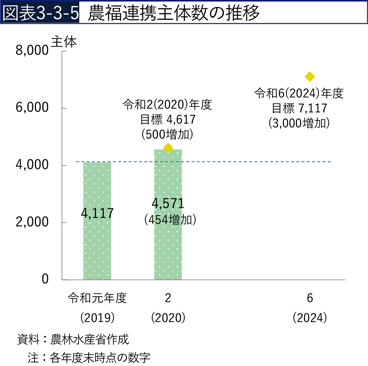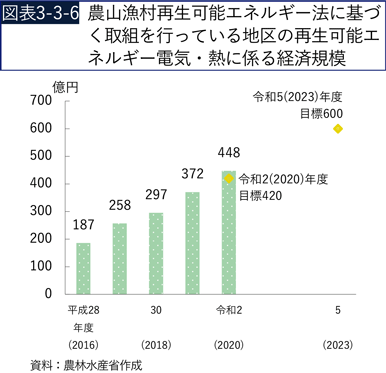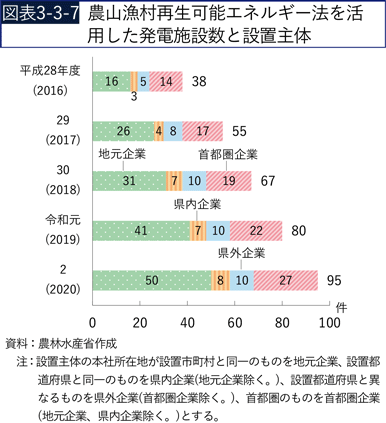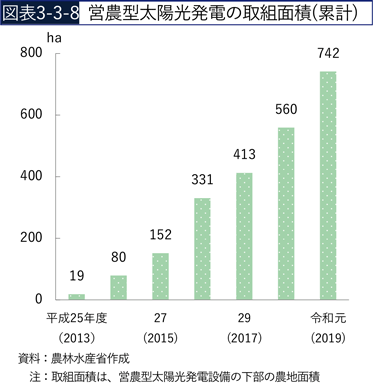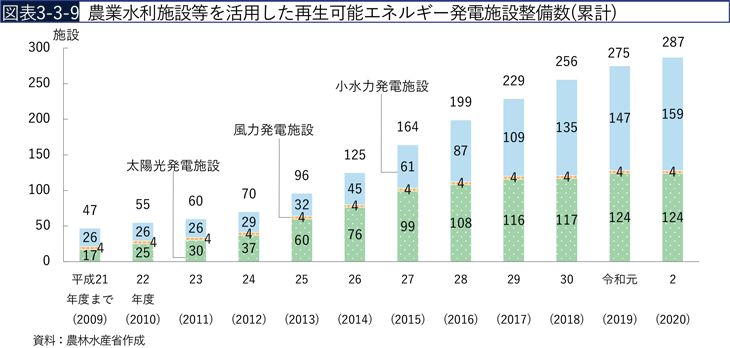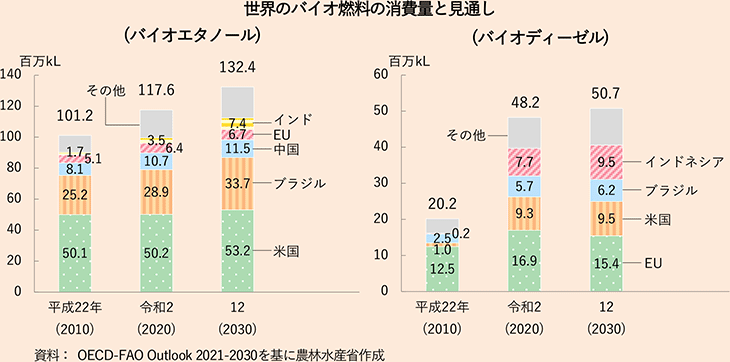第3節 農山漁村発イノベーションの推進
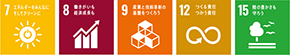
農山漁村を次の世代に継承していくためには、6次産業化(*1)等の取組に加え、農泊、農福連携、再生可能エネルギーの活用等、他分野との組合せにより農山漁村の地域資源をフル活用する「農山漁村発イノベーション」の取組も重要です。本節ではそれらの取組の推進状況について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響にも触れつつ紹介します。
1 用語の解説3(1)を参照
(1)人口減少社会に対応した農村振興
(多様な地域資源を活用した農山漁村発イノベーションを推進)

新しい農村政策の在り方に関する検討会・
長期的な土地利用の在り方に関する検討会
URL:https://www.maff.go.jp/j/study/nouson_kentokai
/farm-village_meetting.html
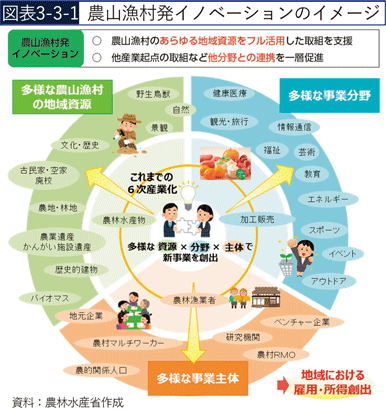
人口減少社会に対応した農村振興に関する施策や土地利用の方策等を検討するため、農林水産省は、令和2(2020)年5月から「新しい農村政策の在り方に関する検討会」及び「長期的な土地利用の在り方に関する検討会」を開催し、令和3(2021)年6月に中間取りまとめ(*1)を行いました。
中間取りまとめでは、農山漁村における所得向上や雇用機会の創出を図るため、従来の6次産業化の取組を発展させ、農林水産物や農林水産業に関わる多様な地域資源を活用し、観光・旅行や福祉等の他分野と組み合わせて新事業や付加価値を創出する農山漁村発イノベーションの取組を推進することとしています(図表3-3-1)。
これを踏まえて、農林水産省は、多様な地域資源を新分野で活用した商品・サービスの開発等への支援を行うとともに、国及び都道府県段階に農山漁村発イノベーションサポートセンターを設けて、取組を行う農林漁業者等に対して、専門家派遣等の伴走支援や都市部の起業家とのマッチング等を行うこととしています。
さらに、農山漁村発イノベーション等に必要な施設整備が円滑に実施できるよう、「農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部を改正する法律案」を令和4(2022)年3月に国会に提出しました。これにより、それらの施設整備に当たっての農地転用等の手続を迅速化することを目指しています。
1 「しごと」、「くらし」、「土地利用」、「活力」の四つの観点から、「農山漁村発イノベーションの推進」、「農村RMOの形成の推進(第3章第4節参照)」、「最適土地利用対策(第2章第4節参照)」、「農的関係人口の拡大・創出(第3章第6節参照)」等の農村政策に関する基本的な考え方や今後の施策の方向性を整理
(2)需要に応じた新たなバリューチェーンの創出
(6次産業化による農業生産関連事業の年間総販売金額は2兆329億円)
6次産業化に取り組む農業者等による加工・直売等の農業生産関連事業の年間総販売金額は、近年横ばいで推移していましたが、令和2(2020)年度の年間総販売金額は、農産加工等の減少により前年度と比べ443億円減少し、2兆329億円となりました(図表3-3-2)。
(6次産業化に取り組む事業者の売上高平均額は増加傾向)
六次産業化・地産地消法(*1)に基づく総合化事業計画(*2)認定件数の累計は、令和3(2021)年度末時点で2,616件となりました。農林水産省が令和2(2020)年度に行った認定事業者を対象としたフォローアップ調査によると、総合化事業に5年間取り組んだ事業者の売上高の平均額は、5年間で約1.5倍に増加しています。
1 正式名称は「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」
2 用語の解説3(1)を参照
(3)農泊の推進
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大が農泊の宿泊者数に大きく影響)
農泊とは、農山漁村において農家民宿や古民家等に滞在し、我が国ならではの伝統的な生活体験や農村の人々との交流を通じて、その土地の魅力を味わってもらう農山漁村滞在型旅行のことです。
令和2(2020)年度までに採択された554の農泊地域(*1)では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受ける中で、令和2(2020)年度の延べ宿泊者数は前年度から約199万人減少して約391万人となりました。そのうち、訪日外国人旅行者の延べ宿泊者数は前年度から約36万人減少し、約2万人となりました(図表3-3-3)。
1 農山漁村振興交付金(農泊推進対策)を活用した地域
(新たなニーズへの対応による宿泊者数回復の取組)
農林水産省は、令和3(2021)年度末までに全国599の農泊地域を採択し、これらの地域において、宿泊、食事、体験に関するコンテンツ開発等、農泊をビジネスとして実施できる体制の構築等に取り組んでいます。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受ける中、ワーケーションや近隣地域への旅行(「マイクロツーリズム」)といった新たな生活様式に対応したニーズが顕在化しており、農泊地域では、そのような新たなニーズに対応した都道府県内での教育旅行や地元企業の研修の受入れといった取組が行われています。農林水産省では、新型コロナウイルス感染症の収束後を見据えたコンテンツの磨き上げの取組等を支援するなど、安全・安心な旅行先としての農泊の需要喚起に向けて取り組んでいます。
(事例)新たなニーズへの対応により宿泊者数が回復(宮城県)

宮城県蔵王町(ざおうまち)の蔵王農泊振興協議会(ざおうのうはくしんこうきょうぎかい)は、株式会社ガイア、生産者組合等が構成員となって、別荘地「蔵王山水苑(ざおうさんすいえん)」を中心に農泊を推進している組織です。空き家を宿泊施設にするとともに、荒廃農地(*)を観光農園や就農する移住者に貸す農地として活用するなど、地域で山積していた問題を地域の資源として転化しながら、農泊の推進を通じた地域活性化とまちづくりを進めています。
同町では、観光客の半数以上が訪日外国人旅行者であったこともあり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により宿泊者数が一時大幅に減少しました。同協議会はワーケーションやマイクロツーリズムといった新たなニーズにターゲットを切り替えたことにより、令和2(2020)年にはワーケーションの宿泊者を350人泊取り込むとともに、マイクロツーリズムの旅行者(宿泊数)を前年より約7割増加させることができました。これにより、令和2(2020)年度は全体として95%以上の宿泊稼働率を確保することができました。
用語の解説3(1)参照
(「SAVOR JAPAN」認定地域に6地域を追加)

農林水産省は、平成28(2016)年度から、農泊を推進している地域の中から、特に食と食文化によりインバウンド誘致を図る重点地域を「農泊 食文化海外発信地域(SAVOR JAPAN(セイバージャパン))」に認定する取組を行っています。インバウンド需要の回復に備え、令和3(2021)年度は新たに6地域を認定し、認定地域は全国で37地域となりました(図表3-3-4)。
(4)農福連携の推進
(農福連携に取り組む主体数は前年度に比べて約1割増加)
障害者等の農業分野での雇用・就労を推進する農福連携は、農業、福祉両分野にとって利点があるものとして各地で取組が進んでいます。
農福連携に取り組む主体数については、令和2(2020)年度は目標の500主体創出に対して、新たに454主体が農福連携に取り組み、前年度に比べて約1割増加の4,571主体となりました(図表3-3-5)。
「農福連携等推進ビジョン」(令和元(2019)年6月)においては、令和元(2019)年度末からの5年間で3,000主体創出することを目標としており、引き続き、認知度の向上や人材の育成、施設整備への支援等に取り組むこととしています。
(優良事例25団体をノウフク・アワード2021として表彰)
令和2(2020)年3月に設立した農福連携等応援コンソーシアムでは、普及啓発のためのイベントの開催、連携・交流の促進、情報提供等を行っています。取組の一環として、令和4(2022)年3月、農福連携に取り組む団体、企業等の優良事例25団体を「ノウフク・アワード2021」として表彰しました。

農福連携等応援コンソーシアム
(ノウフク・アワード2021受賞団体の取組概要)
URL:https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/
kourei.html#consortium
また、農福連携の更なる認知度向上に向けて、令和3(2021)年10月に、テレビ番組等で農福連携を紹介する活動を行っているTOKIOの城島茂(じょうしましげる)さんを「ノウフクアンバサダー」に任命しました。城島さんはノウフク・アワード表彰式への参加や各種メディアを活用した情報配信を行いました。
(事例)ノウフク・アワード2021グランプリ受賞団体
○障害者や福祉がプラスとなるユニバーサルデザインによる農業経営を展開(静岡県)
京丸園(きょうまるえん)株式会社は静岡県浜松市(はままつし)で米等の作付けや芽ねぎ等の施設野菜の栽培を行っている法人です。平成8(1996)年から障害者の雇用と研修受入れを開始し、令和3(2021)年度時点で農業、出荷調製作業に携わる障害者22人を雇用しています。
雇用に当たっては、職場に企業在籍型職場適応援助者等を配置するなど、障害者のスキルアップを支援するとともに、職務の内容に応じて給与を増加させる仕組みを導入しています。また、ユニバーサルデザインの機械開発を通じて作業の標準化を図ることにより、作業の精度・効率が上がり、工賃向上にも寄与しています。
○宇治茶や京都の伝統野菜を活かした農福連携の取組を世界に発信(京都府)
さんさん山城(やましろ)は京都府京田辺市(きょうたなべし)で宇治茶やえびいも、田辺ナス等の京都の伝統野菜の生産、加工、販売を行う就労継続支援B型事業所です。聴覚障害者やひきこもり状態にあった者等が野菜等の生産や加工作業に通年で従事するとともに、生産した野菜等を活用した料理を提供する併設のコミュニティカフェにおいても、メニューづくりから接客・調理までを障害者が中心となって行っています。農作物、加工品、カフェ等の売上げは平成26(2014)年の570万円から令和3(2021)年には1,670万円と増加しており、英語等4言語に対応したWebサイトを通じて取組を世界に発信しています。
(現場で農福連携を支援できる専門人材を育成)
現場で農福連携を支援できる専門人材を育成するため、農林水産省は、障害特性に対応した農作業支援技法を学ぶ農福連携技術支援者育成研修を実施しています。令和3(2021)年度は、令和4(2022)年3月時点で新たに118人の農福連携技術支援者を認定し、累計では177人となりました。
(5)再生可能エネルギーの推進
(再生可能エネルギーによる発電を活用して、地域の農林漁業の発展を図る取組を行っている地区の経済規模は増加)
農林水産省は、みどりの食料システム戦略(*1)で掲げる地産地消(*2)型エネルギーマネジメントシステムの構築に向けて、農山漁村における再生可能エネルギーの取組を推進しています。
再生可能エネルギーを活用して地域の農林漁業の発展を図る取組を行っている地区の再生可能エネルギー電気・熱に係る経済規模については、これまでの増加のベースを勘案して、令和5(2023)年度に600億円にすることを目標(*3)としています。令和2(2020)年度末時点の経済規模は目標420億円に対し、前年度と比べて76億円増の448億円となりました(図表3-3-6)。
2 用語の解説3(1)を参照
3 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進による農山漁村の活性化に関する基本的な方針(平成26(2014)年農林水産省・経済産業省・環境省制定)
(農山漁村再生可能エネルギー法に基づく基本計画を作成した市町村数は74に増加)
農山漁村において再生可能エネルギー導入の取組を進めるに当たり、農山漁村が持つ食料供給機能や国土保全機能の発揮に支障を来さないよう、農林水産省では、農山漁村再生可能エネルギー法(*1)に基づき、市町村、発電事業者、農業者等の地域の関係者から成る協議会を設立し、地域主導で農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー発電を行う取組を促進しています。
令和2(2020)年度末時点で、農山漁村再生可能エネルギー法に基づく基本計画を作成し、再生可能エネルギーの導入に取り組む市町村は、前年度に比べ6市町村増加の74市町村となりました。また、同法を活用した再生可能エネルギー発電施設の設置数も年々増加しており、その設置主体も同一都道府県内の企業が過半数を占めています(図表3-3-7)。
1 正式名称は「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律」
(荒廃農地を活用した再生可能エネルギーの導入を促進)
荒廃農地(*1)については、その解消が急務であり、再生利用及び発生防止の取組を進めることが基本ですが、一方で、これらの取組によってもなお農業的な利用が見込まれないものも存在します。
農林水産省は、2050年カーボンニュートラル社会の実現に向け、農業的利用が見込まれない荒廃農地について、農山漁村再生可能エネルギー法も活用するなど、優良農地の確保に配慮しつつ再生可能エネルギーの導入を促進しています。
1 用語の解説3(1)及び第2章第4節を参照
(営農型太陽光発電の導入が進展)
農地に支柱を立て、上部空間に太陽光発電設備を設置し、営農を継続しながら発電を行う営農型太陽光発電の取組は年々増加し、令和元(2019)年度の営農型太陽光発電の取組面積は前年度と比べて182ha増の742haとなりました(図表3-3-8)。
(バイオマス産業都市を新たに3市町村選定)
地域のバイオマス(*1)を活用したグリーン産業の創出と地域循環型エネルギーシステムの構築を図ることを目的として、経済性が確保された一貫システムを構築し、地域の特色を活かし、バイオマス産業を軸とした環境にやさしく災害に強いまち・むらづくりを目指す地域を、関係府省が共同で「バイオマス産業都市」として選定しています。令和3(2021)年度には、北海道雄武町(おうむちょう)、長野県長野市(ながのし)、宮崎県川南町(かわみなみちょう)の3市町を選定し、これまでに97市町村が選定されました。農林水産省は、これらの地域に対して、地域の構想の実現に向けて各種施策の活用、制度・規制面での相談・助言等を含めた支援を行っています。
1 用語の解説3(1)を参照
(農業水利施設を活用した小水力発電等により農業者の負担軽減を推進)
農業水利施設(*1)等を活用した再生可能エネルギー発電施設については、令和2(2020)年度末までに、農業用ダムや水路を活用した小水力発電施設は159施設、農業水利施設の敷地等を活用した太陽光発電施設、風力発電施設はそれぞれ124施設、4施設の計287施設を農業農村整備事業等により整備してきました(図表3-3-9)。発電した電気を農業水利施設等で利用することにより、施設の運転に要する電気代が節約でき、農業者の負担軽減にもつながっています。
また、土地改良施設の使用電力量に対する農業水利施設を活用した小水力等再生可能エネルギーによる発電電力量の割合については、令和2(2020)年度の約3割から、令和7(2025)年度までに約4割以上に引き上げることを目標(*2)としています。令和3(2021)年度は36の小水力発電施設の整備を行っており、引き続き、小水力等発電施設の整備を進めています。
1 用語の解説3(1)を参照
2 新たな土地改良長期計画(令和3(2021)年3月閣議決定)のKPI
(コラム)世界のバイオ燃料用農産物の需要は増加の見通し
近年、米国、EU等の国・地域において、化石燃料への依存の改善や二酸化炭素排出量の削減、農業・農村開発等の目的から、バイオ燃料の導入・普及が進展しており、とうもろこしやさとうきび、小麦、なたね等のバイオ燃料用農産物の需要が増大しています。
令和3(2021)年7月にOECD(経済協力開発機構)とFAO(国際連合食糧農業機関)が公表した予測によれば、令和2(2020)年から令和12(2030)年までに、バイオエタノールの消費量は約1億1,800万kLから約1億3,200万kLへ、バイオディーゼルの消費量は約4,800万kLから約5,100万kLへとそれぞれ増加し、原料の生産も更に増加する見通しとなっています。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883