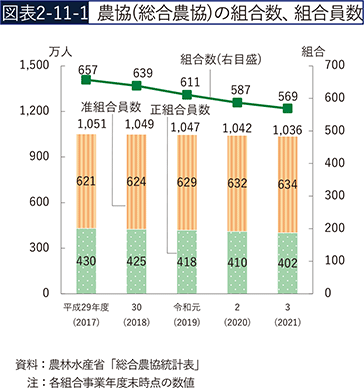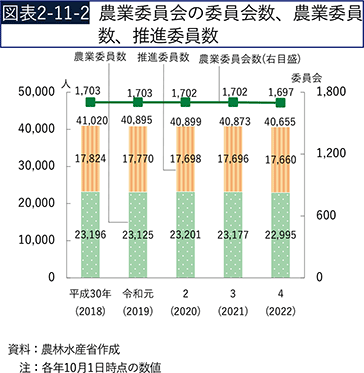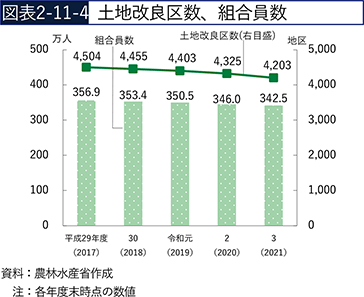第11節 農業を支える農業関連団体

各種農業関連団体については、農業経営の安定や食料の安定供給等において重要な役割を果たしていくことが期待されています。
本節では、我が国の農業を支える各種農業関連団体の取組について紹介します。
(1)農業協同組合系統組織
(農協において自己改革実践サイクルを構築)
農協は協同組合の一つで、農業協同組合法に基づいて設立されています。農業者等の組合員により自主的に設立される相互扶助組織であり、農産物の販売や生産資材の供給、資金の貸付けや貯金の受入れ、共済、医療等の事業を行っています。
農業協同組合系統組織においては、平成28(2016)年に施行された改正農協法(*1)に基づき、農業者の所得向上に向け、農産物の有利販売や生産資材の価格引下げ等に主体的に取り組む自己改革に取り組んできました。農林水産省は、「農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人向けの総合的な監督指針」(以下「監督指針」という。)を改正(令和4(2022)年1月施行)し、農協において、組合員との対話を通じて農業者の所得向上に向けた自己改革を実践していくための自己改革実践サイクルを構築し、これを前提として、行政庁が監督・指導等を行う仕組みを構築しました。また、同改正監督指針において、生産資材価格や輸出、他業種連携、販売網の拡大等の農業者の所得向上のための改革を実施することを通じ、各農協が行う自己改革の取組を支援するよう、行政庁が農業協同組合連合会に対し監督・指導等を行っていくこととしました。
令和3(2021)年度における総合農協の組合数は569組合、組合員数は1,036万人となっています(図表2-11-1)。組合員数の内訳を見ると、農業者である正組合員数は減少傾向となっていますが、非農業者である准組合員数は増加傾向となっています。
1 正式名称は「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律」
(事例)JAグループがかんしょ等の省力的な受託防除を推進(鹿児島県)
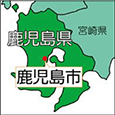
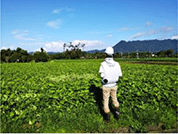
オペレーターによる
かんしょのドローン防除
資料:鹿児島県経済農業協同組合連合会
鹿児島県鹿児島市(かごしまし)の鹿児島県(かごしまけん)経済農業協同組合連合会(以下「JA鹿児島県経済連」という。)では、県内全域を対象に、組合員の要望に対応したかんしょ等の受託防除作業に取り組んでいます。
かんしょに施用できるドローンに適した農薬の登録を契機として、組合員の労力負担軽減のため、令和元(2019)年度からドローンによる省力的な受託防除を開始しました。
かんしょの防除については、従来、組合員が個別に動力噴射器のホースを引き、繁茂した葉やつる等を踏まないよう足場に注意しながら1ha当たり約2時間をかけて防除作業を実施していましたが、ドローンによる防除では作業時間が20分に短縮されました。また、農薬散布計画の作成や薬剤の準備等を農協・JA鹿児島県経済連がまとめて請け負うことで、組合員の負担軽減のほか、圃場(ほじょう)に踏み入らずに防除できるため、作物を傷めないこと等の利点も見られています。
令和4(2022)年度までに、かんしょのほか、水稲、ばれいしょ、さとうきび、さといも等にも受託品目を拡大しており、受託面積を700haとすることを目標として取り組んでいます。今後の受託増加も見据え、JA鹿児島県経済連では、組織体制の整備やオペレーターの育成を進め、組合員負担の更なる軽減に取り組んでいくこととしています。
(2)農業委員会系統組織
(農地利用の最適化に向け、活動の「見える化」の取組を推進)
農業委員会は、農地法等の法令業務及び農地利用の最適化業務を行う行政委員会で、全国の市町村に設置されています。農業委員は農地の権利移動の許可等を審議し、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)は現場で農地の利用集積や遊休農地(*1)の解消、新規参入の促進等の農地利用の最適化活動を担っています。農業委員会系統組織では、農地利用の最適化に向けて、活動の記録・評価等の「見える化」の取組を推進しています。
また、農業委員の任命には、年齢、性別等に著しい偏りが生じないように配慮し、青年・女性の積極的な登用に努めることとしています。
令和4(2022)年の農業委員数は22,995人、推進委員数は17,660人で、合わせて40,655人となっています(図表2-11-2)。
1 用語の解説(1)を参照
(3)農業共済団体
(全国における1県1組合化の実現を推進)
農業共済制度は、農業保険法の下、農業共済組合及び農業共済事業を実施する市町村(以下「農業共済組合等」という。)、都道府県単位の農業共済組合連合会、国の3段階で運営されてきました。
近年、農業共済団体においては、業務効率化のため、農業共済組合の合併により都道府県単位の農業共済組合を設立するとともに、農業共済組合連合会の機能を都道府県単位の農業共済組合が担うことにより、農業共済組合と国との2段階で運営できるよう、1県1組合化を推進しています。令和4(2022)年度においては、北海道で1組合化を果たしたところであり、引き続き業務の効率化を進めていくこととしています。
令和3(2021)年度における農業共済組合等数は56組織、農業共済組合員等数は214万人となっています(図表2-11-3)。
(4)土地改良区
(土地改良事業の円滑な実施を後押しするための改正土地改良法が施行)
土地改良区は、圃場整備等の土地改良事業を実施するとともに、農業用用排水施設等の土地改良施設の維持管理等の業務を行っています。
豪雨災害の頻発化・激甚化、老朽化した土地改良施設の突発事故等による施設の維持管理に係る負担の増大や、土地改良区の技術者不足等の課題によって、土地改良区の運営は厳しさを増しています。小規模な土地改良区では、技術者の雇用や業務の実施が困難な場合もあることから、農林水産省は土地改良事業団体連合会等の関係機関と連携して技術的な助言を行うなど、土地改良区が事業を円滑に実施できるよう取り組んでいます。さらに、令和4(2022)年4月に施行された改正土地改良法(*1)により、土地改良事業団体連合会への工事委託制度が創設されました。
令和3(2021)年度末時点における土地改良区数は4,203地区、組合員数は343万人となっています(図表2-11-4)。
1 正式名称は「土地改良法の一部を改正する法律」
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883