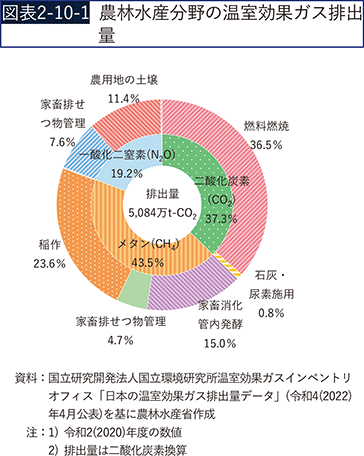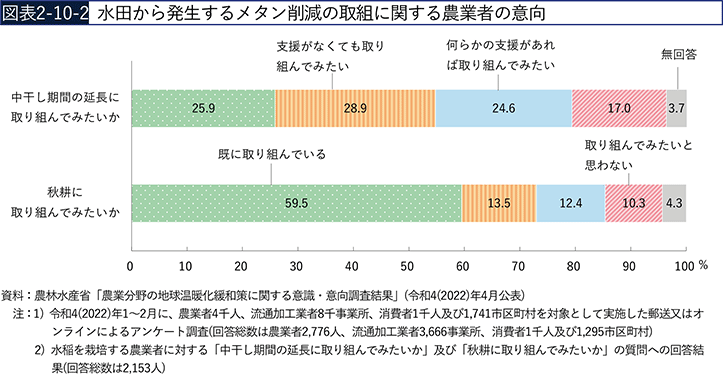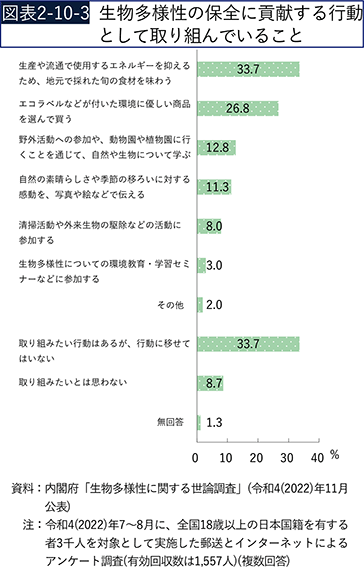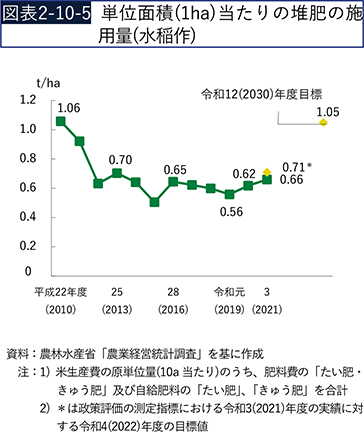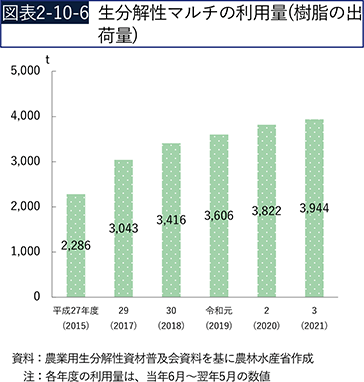第10節 気候変動への対応等の環境政策の推進

我が国では、気候変動対策において、令和32(2050)年までにカーボンニュートラルの実現を目指しており、あらゆる分野ででき得る限りの取組を進めることとしています。また、「生物多様性条約(CBD(*1))第15回締約国会議(COP15)」での議論等を背景に、生物多様性の保全等の環境政策も推進しています。
本節では、食料・農業・農村分野における気候変動に対する緩和・適応策の取組や生物多様性の保全に向けた取組等について紹介します。
1 Convention on Biological Diversityの略
(1)地球温暖化対策の推進
(農林水産分野での気候変動に対する緩和・適応策を推進)
我が国の温室効果ガス(*1)の総排出量は令和2(2020)年度に11億5,000万t-CO2となっているところ、政府は、令和32(2050)年までに温室効果ガスの総排出量を全体としてゼロにするカーボンニュートラルの実現に向け、令和12(2030)年度において温室効果ガス排出量を平成25(2013)年度比で46%削減することを目指し、更に50%の高みに向けて挑戦を続けることとしています。
また、政府は令和3(2021)年10月に、新たな削減目標の裏付けとなる対策・施策を記載して新目標実現への道筋を描く「地球温暖化対策計画」及び農業を始めとする幅広い分野での適応策を示した「気候変動適応計画」を閣議決定しました。
農林水産分野での気候変動に対する緩和・適応策の推進に向け、農林水産省は、みどり戦略(*2)を踏まえ、同年10月に「農林水産省地球温暖化対策計画」と「農林水産省気候変動適応計画」を改定しました。
我が国の農林水産分野における令和2(2020)年度の温室効果ガスの排出量は、前年度から42万t-CO2増加し、5,084万t-CO2となりました(図表2-10-1)。今後、地球温暖化対策計画や、みどり戦略に沿って、更なる温室効果ガスの排出削減に資する新技術の開発・普及を推進していくこととしています。
1 用語の解説(1)を参照
2 第2章第9節を参照
(農業由来の温室効果ガス排出削減に向けた取組を推進)
令和4(2022)年4月に公表した調査によれば、水田から発生するメタンの削減効果がある中干し期間の延長については、水稲を栽培する農業者の25.9%が「既に取り組んでいる」、28.9%が「支援がなくても取り組んでみたい」と回答しました。また、同じく水田から発生するメタンの削減効果がある秋耕(*1)については、59.5%が「既に取り組んでいる」と回答しました(図表2-10-2)。
農林水産省では、農地土壌から排出されるメタン等の温室効果ガスを削減するため、水田作における中干し期間の延長や秋耕といったメタンの発生抑制に資する栽培技術について、その有効性を周知するとともに、それぞれの産地で定着を図る取組を支援しています。
また、畜産分野では、家畜排せつ物の管理や家畜の消化管内発酵に由来するメタン等が排出されることから、排出削減技術の開発・普及を進めることとしています。さらに、家畜排せつ物管理方法の変更について、地域の実情を踏まえながら普及を進めるとともに、アミノ酸バランス改善飼料の給餌について、家畜排せつ物に由来する温室効果ガスの発生抑制や飼料費削減の効果も期待できることを踏まえながら普及を進めていくこととしています。
1 稲わらの秋すき込みのことであり、稲わらのすき込みを代かきの直前ではなく秋に行うことをいう。
(J-クレジット制度の農業分野での活用を推進)
温室効果ガスの排出削減・吸収量をクレジットとして国が認証し、民間資金を呼び込む取引を可能とするJ-クレジット制度は、農林漁業者等が削減・吸収の取組により生じるクレジットを売却することで収入を得ることができるものです。令和4(2022)年8月に「アミノ酸バランス改善飼料の給餌」に係る方法論の対象として従来の豚・ブロイラーに牛が追加されたほか、令和5(2023)年3月には、「水稲栽培における中干し期間の延長」が新たな方法論として承認されました。また、同制度を活用して、令和4(2022)年6月には農業分野の方法論(「バイオ炭(*1)の農地施用」)による取組が初めてクレジット認証されたほか、同年9月に「家畜排せつ物管理方法の変更」、令和5(2023)年3月に「牛・豚・ブロイラーへのアミノ酸バランス改善飼料の給餌」に取り組むプロジェクトが、それぞれ登録されました。今後、農業由来の温室効果ガスの排出削減や吸収に向けた取組の推進に当たって、同制度の一層の活用が期待されています。
1 燃焼しない水準に管理された酸素濃度の下、350℃超の温度でバイオマスを加熱して作られる固形物
(事例)J-クレジットを活用した「バイオ炭の農地施用」の取組が進展(大阪府)

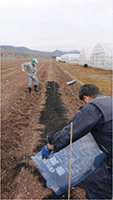
農地に施用されるバイオ炭
資料:一般社団法人日本クルベジ協会
大阪府茨木市(いばらきし)の一般社団法人日本(にほん)クルベジ協会(きょうかい)では、J-クレジット制度を活用した「バイオ炭の農地施用」の取組を推進しています。
同協会では、令和3(2021)年1月に、「炭貯(たんちょ)クラブ」を発足させ、J-クレジット制度を活用したバイオ炭の農地施用によるCO2削減事業に取り組み、令和4(2022)年6月に、「バイオ炭の農地施用」に取り組む案件としては我が国で初めて、クレジット認証を受けました。
バイオ炭は、土壌の透水性を改善する土壌改良資材であるとともに、土壌へ炭素を貯留させる効果を有しています。炭化した木材や竹等は土壌中で分解されにくいため、土壌に施用することで、その炭素を土壌に閉じ込め、大気中への放出を減らすことが可能になります。
同協会では、今後とも、バイオ炭による炭素貯留を通じた環境保全に資する農業の普及を進めるとともに、バイオ炭の農地施用の取組を全国的に推進していくこととしています。
(気候変動の影響に適応するための品種・技術の開発・普及を推進)
農業生産は気候変動の影響を受けやすく、水稲における白未熟粒(しろみじゅくりゅう)や、りんご、ぶどう、トマトの着色・着果不良等、各品目で生育障害や品質低下等の影響が現れていることから、この影響を回避・軽減するための品種や技術の開発、普及が進められています。
果樹では、気温の上昇に適応するため、熊本県におけるうんしゅうみかんから中晩柑(ちゅうばんかん)「しらぬひ」への改植等、より温暖な気候を好む作物への転換や、青森県におけるももの生産等、栽培適地の拡大を活かした新しい作物の導入も進展しています。
(COP27で「シャルム・エル・シェイク実施計画」が決定)
令和4(2022)年11月に、エジプトのシャルム・エル・シェイクにおいて国連気候変動枠組条約第27回締約国会議(COP27)が開催されました。同会議では、全体の成果文書である「シャルム・エル・シェイク実施計画」が決定され、農林水産関連では、気候変動による食料危機の深刻化やパリ協定の温度目標(*1)の達成に向けた森林等の役割の内容が盛り込まれるとともに、「農業及び食料安全保障に係る気候行動の実施に関するシャルム・エル・シェイク共同作業」が決定されました。
また、議長国であるエジプトの主導で各種テーマ別の「議長国プログラム」の一つとして、「適応・農業の日(農業デー)」が開催され、我が国は、「食料・農業の持続可能な変革(FAST)イニシアチブ(*2)」の立上げ閣僚級会合において、農林水産副大臣のビデオメッセージにより、みどり戦略の実施を通じて得られた経験や知見を活用して、各国の持続可能な食料・農業システムへの移行に積極的に貢献していくことを表明しました。
さらに、農林水産省の主催で、持続可能な農業と食料安全保障(*3)をテーマとする国際セミナーを開催し、我が国の研究機関が持つ気候変動対策に資する農業生産技術の紹介等を行いました。
1 パリ協定は、産業革命前からの平均気温の上昇を2℃より十分下方に保持し、1.5℃に抑える努力を追求すること等を目的としている。
2 食料・農業の持続可能な変革に向けた各国の協力を促進することを目的とした新たな国際イニシアチブ。正式名称は「Food and Agriculture for Sustainable Transformation Initiative」
3 用語の解説(1)を参照
(2)生物多様性の保全と利用の推進
(生物多様性保全に貢献する行動では「地元で採れた旬の食材を味わう」が最多)
亜熱帯から亜寒帯までの広い気候帯に属する我が国では、それぞれの地域で、それぞれの気候風土に適応した多様な農林水産業が発展し、地域ごとに独自の豊かな生物多様性が育まれてきました。生物多様性は持続可能な社会の土台であるとともに、食料・農林水産業がよって立つ基盤となっています。
令和4(2022)年7~8月に内閣府が実施した世論調査によると、生物多様性の保全に貢献する行動として、既に取り組んでいるものは、「生産や流通で使用するエネルギーを抑えるため、地元で採れた旬の食材を味わう」と回答した人が33.7%で最も高く、次いで「エコラベルなどが付いた環境に優しい商品を選んで買う」と回答した人が26.8%となっています(図表2-10-3)。
(農林水産業が生態系に与える正の影響を伸ばし、負の影響を低減することが重要)
農林水産業は生物多様性に立脚すると同時に、農林水産業によって維持される生物多様性も多く存在します。
例えば我が国の耕地面積の大半を占める水田は、特有の生態系を維持し、多様な生き物の棲み家(すみか)を提供しています。また、草地の保全管理においては、草刈りや野焼き等、人の手が入ることによって、希少生物を含む多様な動植物の生息・生育環境が安定的に守られている例があります。
このように、農林水産業は、農山漁村において、様々な動植物が生息・生育するための基盤を提供する役割を持つ一方、経済性や効率性を優先した農地や水路の整備、農薬・肥料の過剰使用等、生物多様性に負の影響をもたらす側面もあります。
このため、将来にわたって持続可能な農林水産業を実現し、豊かな生態系サービス(*1)を社会に提供していくためには、農林水産業が生態系に与える正の影響を伸ばしていくとともに負の影響を低減し、環境と経済の好循環を生み出していく視点が重要となっています。
1 用語の解説(1)を参照
(「農林水産省生物多様性戦略」を改定)
令和4(2022)年12月にカナダのモントリオールで「生物多様性条約(CBD)第15回締約国会議(COP15)」第2部及び関連会合が開催され、生物多様性に関する令和12(2030)年までの新たな世界目標である「昆明(こんめい)・モントリオール生物多様性枠組」等が採択されました。
昆明・モントリオール生物多様性枠組には、農林水産関連では、陸と海のそれぞれ30%以上の保護・保全(30by30目標)、環境中に流出する過剰な栄養素や化学物質等(農薬を含む。)による汚染のリスクの削減等の目標が盛り込まれました(図表2-10-4)。
農林水産省では、みどり戦略や昆明・モントリオール生物多様性枠組等を踏まえ、令和5(2023)年3月に、生物多様性保全を重視した農林水産業を強力に推進するため、「農林水産省生物多様性戦略」を改定しました。
同戦略では、生物多様性保全の重要性が認識され、各主体の行動に反映されるようサプライチェーン全体で取り組むことが重要であることから、農林漁業者の理解促進や、消費者の行動変容、自然資本に関連したESG(*1)投融資の拡大等を図ることとしています。
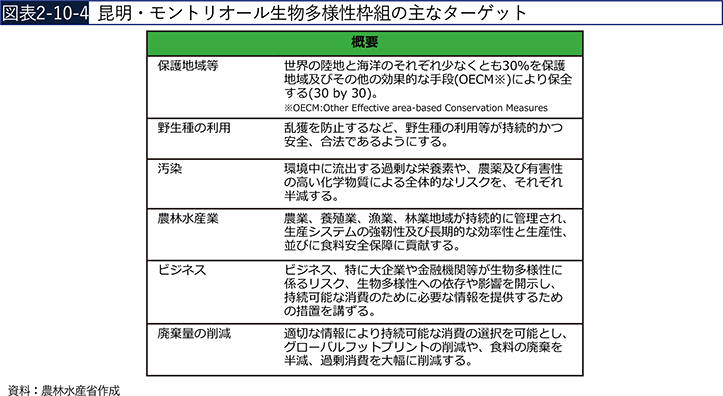
1 用語の解説(2)を参照
(3)土づくり等の推進
(堆肥等の活用による土づくりを推進)
農地土壌は農業生産の基盤であり、農業生産の持続的な維持向上に向けて「土づくり」に取り組むことが必要です。効果的な土づくりのためには、土壌の通気性や排水性、土壌中の養分の含有量や保持力等を分析する土壌診断が有効です。農林水産省では、多くの農業者が科学的なデータに基づく土づくりが行える環境を整備するため、農業生産現場において土壌診断とそれに基づく改善効果の検証を行い、その結果をデータベース化する取組を推進しています。
また、堆肥の施用量は、農業生産現場での高齢化の進展や省力化の流れの中で減少を続けてきましたが、近年横ばい傾向で推移しています。単位面積(1ha)当たりの堆肥の施用量について、農業者による土壌診断や、その結果を踏まえた堆肥の散布による土づくりを着実に推進することが重要となっているところ、農林水産省では令和12(2030)年度までに1.05t/ha(水稲作)とすることを目標としており、令和3(2021)年度は前年度に比べ6.5%増加し0.66t/haとなりました(図表2-10-5)。農林水産省では、土づくりに有効な堆肥の施用を推進するとともに、好気性強制発酵(*1)による畜産業由来の堆肥の高品質化やペレット化による広域流通等の取組を推進しています。
1 攪拌装置等を用いて強制的に酸素を供給し、堆肥を発酵させる方法
(事例)土づくり拠点施設を活用し、露地野菜の生産を推進(大分県)


臼杵市土づくりセンター
資料:大分県臼杵市
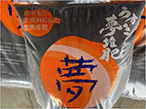
うすき夢堆肥
資料:大分県臼杵市
大分県臼杵市(うすきし)では、土づくり拠点施設で製造した完熟堆肥を用いた土づくりを推進するとともに、「ほんまもん農産物(のうさんぶつ)」を始めとする有機農産物の生産振興やブランド化に取り組んでいます。
同市では、有機農業等の農業生産に取り組みやすい環境を整備するため、平成22(2010)年に土づくりセンターを開設し、完熟堆肥である「うすき夢堆肥(ゆめたいひ)」の製造を行っています。「うすき夢堆肥」は、草木類8割、豚ぷん2割を混ぜ合わせて約6か月間の工程により製造される完熟堆肥であり、年間約1,800t製造されています。
同市では、「うすき夢堆肥」等有機質肥料を使用した土づくりを行い、化学肥料や化学合成農薬の使用を避けた圃場(ほじょう)で生産された農産物を「ほんまもん農産物」として市長が認証しています。「ほんまもん農産物」は、地元農協の直売コーナーや市外の百貨店、一部のスーパー等での流通のほか、ふるさと納税の返礼品としての取扱いを始め、学校給食や飲食店での食材利用、小学生・幼稚園児による収穫体験等で取り上げられ、関心を集める機会が拡大しています。
今後は、行政や農協等の関係者で構成される「ほんまもんの里(さと)・うすき」農業推進協議会が主体となり、土壌診断結果のフィードバックを活用した継続的な土づくり等の取組を推進し、「ほんまもん農産物」を始めとする有機農業の産地づくりを進めていくこととしています。
(生分解性マルチの利用量は増加傾向で推移)
農業用生分解性資材普及会(のうぎょうようせいぶんかいせいしざいふきゅうかい)の調査によると、生分解性マルチの利用量(樹脂の出荷量)は増加傾向で推移しており、令和3(2021)年度は3,944tとなっています(図表2-10-6)。
農林水産省では、生分解性マルチへの転換に向けた取組のほか、農業用ハウスの被覆資材やマルチといった農業由来の廃プラスチックの適正処理対策を推進することしています。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883