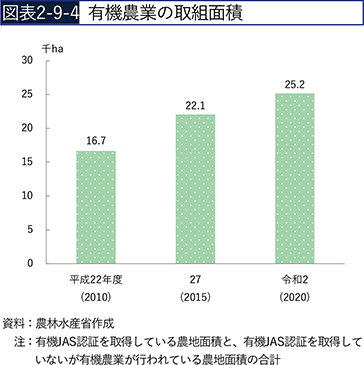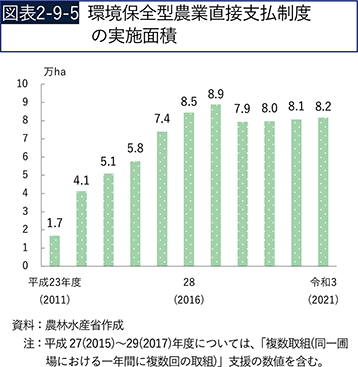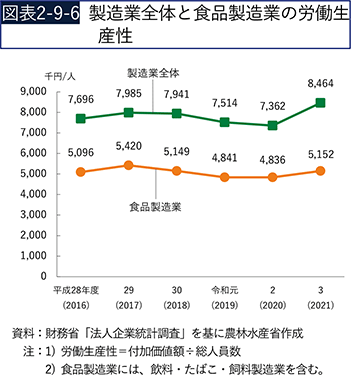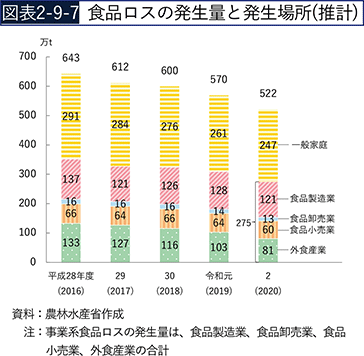第9節 みどりの食料システム戦略の推進

我が国の食料・農林水産業は、大規模自然災害の増加、地球温暖化、農業者の減少等の生産基盤の脆弱(ぜいじゃく)化、地域コミュニティの衰退、生産・消費の変化等の、持続可能性に関する政策課題に直面しています。また、諸外国ではSDGs(*1)や環境を重視する動きが加速し、あらゆる産業に浸透しつつあり、我が国の食料・農林水産業においても的確に対応していく必要があります。
これらを踏まえ、農林水産省は令和3(2021)年5月にみどり戦略を策定しました。本節では、みどり戦略の意義や、調達、生産、加工・流通、消費の各段階での取組の推進状況を紹介します。
1 用語の解説(2)を参照
(1)みどり戦略の実現に向けた施策の展開
(環境負荷低減の取組を後押しする制度を創設)
我が国においては、気候変動への対応等の克服すべき課題に直面しており、将来にわたり食料の安定供給と農林水産業の発展を図るためには、持続的な食料システムを構築することが必要となっています。このため、食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立の実現に向けて、みどり戦略に基づく取組を強力に推進していくことが重要であり、その法的な枠組みとして令和4(2022)年7月に、みどりの食料システム法(*1)が施行されました。
みどりの食料システム法では、生産者だけではなく、食品産業の事業者や消費者等の食料システムの関係者の理解と連携の下で環境と調和のとれた食料システムの確立を図ること等を基本理念として定めるとともに、この基本理念に沿った形で、国、地方公共団体の責務、生産者、事業者及び消費者の努力、国が講ずべき施策について規定しています。また、化学肥料・化学農薬の使用低減や有機農業の取組拡大、温室効果ガス(*2)の排出削減等の環境負荷低減を図る生産者の取組や、環境負荷の低減に役立つ機械や資材の生産・販売、研究開発、食品製造等を行う事業者の取組を、それぞれ都道府県、国が認定し、認定を受けた者に対して支援措置を講ずることとしています。
具体的には、計画の認定を受けた生産者及び事業者は、環境負荷の低減に取り組む際に必要な設備等を導入する際に無利子・低利融資の特例措置を受けることができます。また、化学肥料・化学農薬の使用低減に取り組む生産者や、化学肥料・化学農薬の代替資材の供給を行う事業者の設備投資を後押しするため、みどり投資促進税制を創設し、導入当初の所得税・法人税を軽減する措置を講ずることとしています。これらにより、生産者による環境負荷低減の取組や、その取組を後押しするイノベーション・市場拡大を後押しすることとしています。
また、同年4月に成立した改正植物防疫法(*3)に基づき、同年11月には化学農薬のみに依存しない、発生予防を中心とした総合防除を推進するための基本指針を策定しました。今後は、令和5(2023)年度中に全ての都道府県において、基本指針に即し、地域の実情に応じた総合防除の実施に関する計画の策定が進むよう支援することとしています。
さらに、化学肥料・化学農薬の使用低減、有機農業面積の拡大、農業における温室効果ガスの排出量削減を推進するため、土づくりを始めとした環境にやさしい栽培技術と省力化技術を取り入れたグリーンな栽培体系への転換に向けた取組を後押しするなど、みどりの食料システム戦略推進交付金等により、スマート農業(*4)技術の活用、化学肥料・化学農薬の使用低減、有機農業等の環境負荷低減に取り組む水稲や野菜等の産地を創出することとしています(図表2-9-1)。
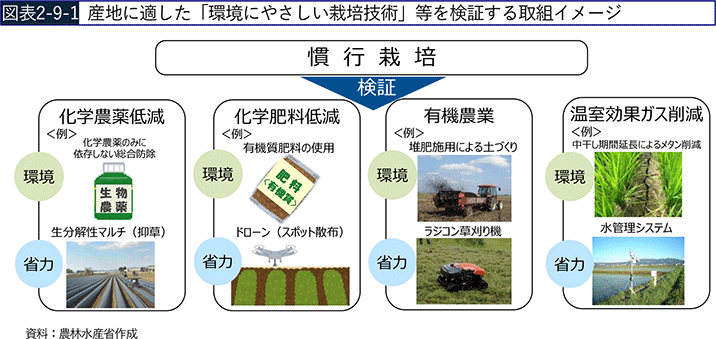
1 正式名称は「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」
2、4 用語の解説(1)を参照
3 正式名称は「植物防疫法の一部を改正する法律」。第1章第8節を参照
(関係者の行動変容と技術の開発・普及を推進)
持続可能な食料システムの構築に向け、食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立を実現するには、調達に始まり、生産、加工・流通、消費に至る食料システムを構成する関係者による行動変容と、それらを後押しする技術の開発・普及を推進することが必要です(図表2-9-2)。みどり戦略では、令和32(2050)年までに目指す姿や中間目標としてのKPI2030年目標を示し、中長期的な観点から取組を進めていくこととしています(図表2-9-3)。
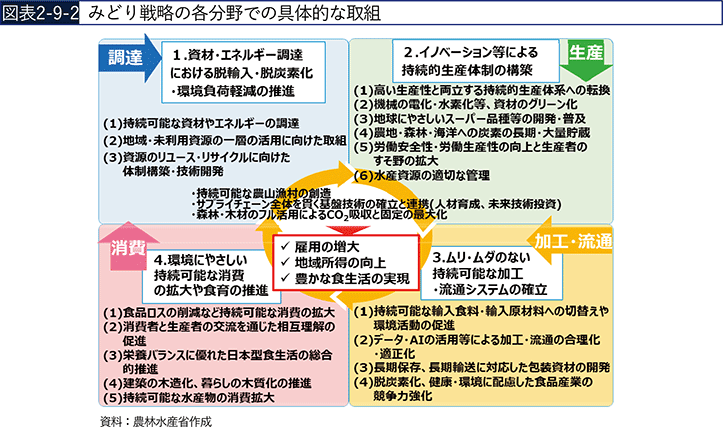
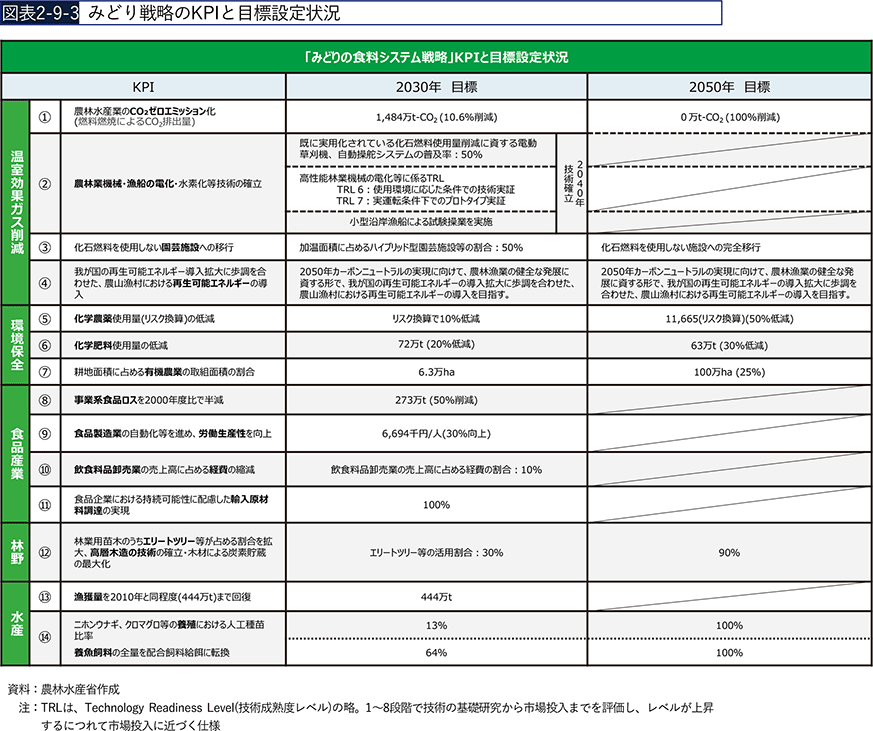
(みどり戦略に対する国民の認知・理解が一層進むよう取組を強化)
みどりの食料システム法では、国が講ずべき施策として、関係者が環境と調和のとれた食料システムに対する理解と関心を深めるよう、環境負荷の低減に関する広報活動の充実等を図ることとしています。
農林水産省は、令和4(2022)年度に、地方公共団体、農協、農林漁業者、食品事業者、小売事業者、機械・資材メーカー、消費者等を対象に、全国9ブロックでみどりの食料システム法の説明会を開催したところであり、引き続き、みどり戦略に対する国民の認知・理解が一層進むよう、取組の強化を図っていくこととしています。
(2)資材・エネルギー調達における脱輸入・脱炭素化・環境負荷低減の推進
(農林水産業の燃料燃焼によるCO2排出量削減に向けた取組を推進)
みどり戦略においては、温室効果ガス削減のため、令和32(2050)年までに目指す姿として、農林水産業のCO2ゼロエミッション化に取り組むこととしています。
その実現に向けて、施設園芸・農業機械等の省エネルギー対策を最大限進めるとともに、中長期的には農林業機械等の電化・水素化等に向けた技術開発・社会実装が必要です。令和12(2030)年までは、ヒートポンプ、農業機械の自動操舵(そうだ)システム等の導入の加速化により、同年における農林水産業の燃料燃焼によるCO2排出量1,484万t-CO2(平成25(2013)年比10.6%削減)の目標達成を目指しています。
令和2(2020)年度における農林水産業の燃料燃焼によるCO2排出量は、1,855万t-CO2となっています。
(化石燃料使用量削減に資する農業機械の担い手への普及を推進)
みどり戦略においては、温室効果ガス削減のため、令和32(2050)年までに目指す姿として、農林業機械・漁船の電化・水素化等の技術の確立に取り組むこととしています。

電動草刈機
資料:株式会社ササキコーポレーション
農業機械については令和12(2030)年までは、既に実用化されている化石燃料使用量削減に資する電動草刈機や自動操舵システムの導入を促進し、同年における担い手への普及率50%の目標達成を目指しています。
令和3(2021)年における化石燃料使用量削減に資する農業機械の担い手への普及率は、電動草刈機で16.1%、自動操舵システムで4.7%となっています。
(省エネルギーなハイブリッド型園芸施設等への転換を推進)
みどり戦略においては、温室効果ガス削減のため、令和32(2050)年までに目指す姿として、化石燃料を使用しない園芸施設への完全移行に取り組むこととしています。
その実現に向けて、令和12(2030)年までは、ヒートポンプと燃油暖房機のハイブリッド運転や環境センサ取得データを利用した適温管理による無駄の削減等、既存技術を活用したハイブリッド型園芸施設や省エネルギー化が図られた園芸施設への転換を支援するとともに、ゼロエミッション型園芸施設の実現に向けた研究開発を進めることで、同年における加温面積に占めるハイブリッド型園芸施設等の割合50%の目標達成を目指しています。
令和2(2020)年における加温面積に占めるハイブリッド型園芸施設等の割合は10%となっています。
(農山漁村における再生可能エネルギー導入を推進)
みどり戦略においては、温室効果ガス削減のため、令和32(2050)年までに目指す姿として、我が国の再生可能エネルギーの導入(*1)拡大に歩調を合わせた、農山漁村における再生可能エネルギーの導入に取り組むこととしています。
カーボンニュートラルの実現に向けて、農山漁村再生可能エネルギー法(*2)の下、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー発電を促進することとしています。
1 第3章第4節参照
2 正式名称は「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律」
(下水汚泥資源の利用を促進)
輸入依存度の高い肥料原料の価格が高騰する中で、持続可能な食料システムの構築に向け、下水汚泥資源を活用することが重要となっています。
国土交通省が実施した調査によると、令和元(2019)年時点で我が国の全汚泥発生量に占める肥料利用の割合は10%となっています。これまで下水汚泥資源の多くが焼却され、焼却灰として埋立てや建設資材等に活用されており、下水汚泥資源中の窒素やりん等を含む有機物の肥料としての利用を更に拡大していくことが必要です。
下水汚泥資源の肥料利用の拡大に向けた推進方策を関係機関と連携して検討するため、農林水産省と国土交通省が共同で「下水汚泥資源の肥料利用の拡大に向けた官民検討会」を開催するなど、下水汚泥資源の利用を推進することとしています。
また、農林水産省では、畜産業由来の堆肥等の有効利用や、食品残さ・廃棄物等を肥料化するリサイクル技術の開発等を進めていくこととしています。
(事例)下水汚泥からりん資源を回収し、肥料として供給する取組を推進(兵庫県)


下水汚泥から回収したりん資源を
配合した肥料を利用する農業者
資料:兵庫県神戸市
兵庫県神戸市(こうべし)では、下水汚泥から肥料成分であるりん資源を回収し、肥料として供給する取組を推進しています。
同市では、平成23(2011)年度から民間企業とりん資源を回収する技術の研究に取り組み、回収手法の実証を行いました。
下水処理の過程で回収されたりんは、「こうべ再生リン」と命名され、肥料の原料になるほか、単体でも肥料として利用することができます。同市では、事業者向けの大口販売のほか、市民向けの小口販売や学術研究、商品開発向けの無償提供を行っています。
また、「こうべ再生リン」を配合した肥料である「こうべハーベスト」は、園芸用や水稲用の肥料として、兵庫六甲(ひょうごろっこう)農業協同組合の協力により市内の農家へ販売されています。同肥料で栽培された米は、令和2(2020)年1月から学校給食で提供されています。
同市では、同肥料の利用促進を通じて、肥料価格高騰の影響を受ける農業者の経営改善を後押しするとともに、環境保全型農業の更なる推進を図ることを目指しています。
(3)イノベーション等による持続的生産体制の構築
(化学農薬の使用量の低減に向けた取組を推進)
みどり戦略においては、環境負荷低減のため、令和32(2050)年までに目指す姿として、化学農薬使用量(リスク換算(*1))の50%低減に取り組むこととしており、令和12(2030)年までは、病害虫が発生しにくい生産条件の整備や、病害虫の発生予測も組み合わせた総合防除の推進、化学農薬を使用しない有機農業の面的拡大の取組等により、同年における化学農薬使用量(リスク換算)の10%低減の目標達成を目指しています。
令和3(2021)農薬年度(*2)においては令和元(2019)農薬年度比で約9%の低減となっていますが、これは、リスクの低い農薬への切替え等による効果のほか、新型コロナウイルス感染症による国際的な農薬原料の物流の停滞で、農薬の製造や出荷が減少したこと等の特殊事情によるものと考えられます。
1 個々の農家段階での単純な使用量ではなく、環境への影響が全国の総量で低減していることを、検証可能な形で示せるように算出した指標。リスク換算は、有効成分ベースの農薬出荷量に、ADI(Acceptable Daily Intake : 許容一日摂取量)を基に設定したリスク換算係数を掛け合わせたものの総和により算出
2 農薬年度は、前年10月から当年9月までの期間
(化学肥料の使用量の低減に向けた取組を推進)
みどり戦略においては、環境負荷低減のため、令和32(2050)年までに目指す姿として、化学肥料使用量の30%低減に取り組むこととしており、令和3(2021)年においては85万t(NPK総量(*1)・生産数量ベース)で、基準年である平成28(2016)年比で約6%の低減となっています。
土壌診断による施肥の適正化等、既に実施可能な施肥の効率化を進めるとともに、国内資源の肥料利用を推進すること等により、令和12(2030)年までに化学肥料使用量の20%低減の目標達成を目指しています。
1 肥料の三大成分である窒素(N)、りん酸(P)、加里(K)の全体での出荷量のこと
(事例)堆肥の完熟化・ペレット化と広域流通を推進(熊本県)


ペレット堆肥
資料:菊池地域農業協同組合
熊本県菊池市(きくちし)の菊池地域(きくちちいき)農業協同組合では、耕畜連携の取組を推進しており、堆肥の高品質化・ペレット化を進めるとともに、生産した堆肥の広域流通に取り組んでいます。
同農協では、畜産農家が一次発酵処理した堆肥を堆肥センターに集約し、期間を要する二次発酵による完熟化を実施しています。また、同センターにペレット化装置を設置し、減容化により広域での輸送に適し専用の散布機械(マニュアスプレッダー)を必要としない「ペレット堆肥」の生産にも取り組んでいます。
生産された堆肥は、県内外の耕種地帯の農協に販売されています。県内の取組では、耕種側がストックヤード等の整備を担い、ストックヤードから各生産者への堆肥の運搬は、耕種側で対応しています。
同農協では、耕種地帯の農協との連携を深化させることにより、安定的な堆肥の販売と稲わらの入手を推進し、管内の畜産農家の経営安定に貢献することとしています。
(耕地面積に占める有機農業の取組面積の割合は前年度に比べ1,400ha増加)
みどり戦略においては、令和32(2050)年までに目指す姿として、耕地面積に占める有機農業の取組面積の割合を25%(100万ha)に拡大することとしています。
有機農業の取組面積の拡大に向けて、有機農業を点の取組から面的な取組に広げていく必要があることから、先進的な農業者や産地の取組の横展開を進めるとともに、有機農産物の生産や流通、販売に関わる関係者による有機市場の拡大を支援し、令和12(2030)年における有機農業の取組面積6万3千haの目標達成を目指しています。
有機農業については、令和2(2020)年度の取組面積は、前年度に比べ1,400ha増加し2万5,200haとなっており、その耕地面積に占める割合は前年度に比べ0.1ポイント増加し0.6%となっています(図表2-9-4)。
農林水産省では、従来現場で使われている有機農業の技術の体系化・横展開を進めるため、令和3(2021)年度末までに全国で366人の有機農業指導員を育成するとともに、有機農業で大きな労力の掛かる除草作業を省力化するため、高能率除草機や自動抑草ロボット等の導入を推進しています。また、有機農産物の消費については、平成30(2018)年1月に実施した調査(*1)では、「週に一度以上有機食品を利用」と回答した人の割合は17.5%となっている一方、「ほとんど利用(購入・外食)していない」と回答した人の割合は54.8%となっており、有機農業の更なる取組拡大に向け、国産有機食品の需要喚起も必要となっています。
1 農林水産省「平成29年度有機食品マーケットに関する調査結果」(平成30(2018)年7月公表)
(事例)新規就農者等と連携し、環境負荷の小さい農業を広げる取組を展開(京都府)


旬のお野菜セット(定期宅配)
資料:株式会社坂ノ途中

提携生産者による有機野菜づくり
資料:株式会社坂ノ途中
京都府京都市(きょうとし)の野菜流通事業者である株式会社坂ノ途中(さかのとちゅう)は、新規就農者を中心とした提携生産者と連携しながら、環境負荷の小さい農業で育てられた有機野菜等の流通・販売を行っています。
新規就農者は、有機農業等の新たな分野に積極的に挑戦する意欲のある人が多い反面、多品目で少量不安定な生産量になることが多く、既存の流通に乗りにくいケースも見られています。新規就農者との取引をスムーズにするため、同社では取引システムを自社開発するとともに、提携生産者の栽培計画づくりに協力し、長期的な信頼関係を構築しています。
また、規格外の農産物等、通常では商品化しづらいものも含めて柔軟な買取りを行うとともに、安定的な出荷先を提供することで、提携生産者の経営の安定・拡大を後押ししています。
消費者に対しては、定期的に届くおまかせの野菜セットを通して、季節の移り変わりや、野菜の個性を楽しむスタイルを消費者に提案しています。取り扱う野菜は年間約500種類に上り、その中から旬の野菜をバランスよくセットにして提供しています。
こうした取組の結果、同社における野菜のサブスクリプションサービスは年々拡大しており、品質の高さと共感獲得により、高い顧客満足度を実現しています。
同社では、「100年先も続く農業」を目指し、今後とも環境負荷の小さい農業と持続可能性を意識したライフスタイルを広げるための取組を展開していくこととしています。
(オーガニックビレッジの創出を促進)
農林水産省では、市町村が主体となり、生産から消費まで一貫した取組により有機農業拡大に取り組むモデル産地であるオーガニックビレッジを令和7(2025)年までに、100市町村創出することとしています。
令和4(2022)年度においては、市町村主導で有機農業の拡大に取り組む市町村やこれから取り組む市町村等が一堂に会する「オーガニックビレッジ全国集会」を「有機農業の日(12月8日)」に開催しました。
(事例)オーガニックビレッジ構想の中核として大規模有機農業を展開(奈良県)


有機小松菜の施設栽培
資料:有限会社山口農園

トラクタでの耕うん作業
資料:有限会社山口農園
奈良県宇陀市(うだし)は、「オーガニックビレッジ」の創出に向けた取組を積極的に進めており、令和4(2022)年11月に全国で初めてオーガニックビレッジ宣言を行いました。
同市の有限会社山口農園(やまぐちのうえん)は、オーガニックビレッジ構想の中核となる農業生産法人であり、四方を山に囲まれた中山間地において有機農産物の生産・加工・販売等の大規模経営を展開しています。
同農園では、化学的に合成された肥料と農薬を使用せず、植付前3年以上の間、堆肥等による土づくりを行った圃場(ほじょう)において、小松菜、ホウレンソウ、ベビーリーフ、水菜、春菊、ハーブ類等の有機野菜の施設栽培を行っており、経営する約10haの圃場で有機JAS認証を取得しています。
また、同農園では、農産物の栽培、収穫、出荷、販売等の作業を完全分業化し、業務の効率化を進めるとともに、回転率の早い作物に絞って周年生産することで収益性の向上を図っています。
さらに、遊休農地(*)の活用等、地域に密着した農業経営を行うとともに、国内外から多数の農業研修生や視察を受け入れ、有機農業を学べる場を提供しています。
将来的には、東南アジアでの現地法人の設立も視野に入れながら、有機農産物の海外市場への展開を目指しています。
用語の解説(1)を参照
(環境保全型農業直接支払制度の実施面積は前年度に比べ1千ha増加)
化学肥料・化学農薬を原則5割以上低減する取組と併せて行う地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い営農活動に対しては、環境保全型農業直接支払制度による支援を行っており、令和3(2021)年度の実施面積は、前年度に比べ1千ha増加し8万2千haとなりました(図表2-9-5)。
令和4(2022)年度からは、有機農業に新たに取り組む農業者の受入れ・定着に向けて、栽培技術の指導等の活動を実施する農業者団体に対し、活動によって増加した新規取組面積に応じて支援する措置を講じています。
(4)ムリ・ムダのない持続可能な加工・流通システムの確立
(食品製造業の労働生産性は前年度に比べ上昇)
みどり戦略においては、食品製造業の労働生産性の向上に取り組むこととしており、令和3(2021)年度における食品製造業の労働生産性は、前年度に比べ316千円/人上昇し5,152千円/人となっています(図表2-9-6)。
食品製造業の労働生産性の向上を図るためには、AI、ロボット等の先端技術を活用したスマート化の推進が重要であることから、研究開発、実証・改良から普及までを体系的に支援することとしています。このため、令和12(2030)年までは、例えば近年発展著しいAI、ロボット等の先端技術を活用した自動化等を進展させることで、同年における食品製造業の労働生産性30%向上(平成30(2018)年度比)の目標達成を目指しています。
(事例)製造工程の自動化による生産性向上を推進(群馬県)


容器位置決め・容器乗せ
を行うアームロボット
資料:相模屋食料株式会社
群馬県前橋市(まえばしし)の豆腐・大豆加工品メーカーである相模屋食料(さがみやしょくりょう)株式会社は、豆腐に対するニーズの多様化や顧客の品質要求が厳しくなる中、最先端の豆腐工場の実現を目指し、品質改善と自動化の取組を推進しています。
同社は、これまで職人技と見なされてきた豆腐の水さらしとカット作業について自動化を実現し、併せて品質を維持しつつ、省人化のための取組として、豆腐の容器詰め工程をロボットによる「容器位置決め・容器乗せ」と、専用設備による「自動容器被(かぶ)せ」の二工程に分割することで容器詰めの自動化に成功しました。
これらの取組により、品質の向上に加えて配置人員を5人から3人に削減するとともに、1時間当たりの生産量を1,800個から8,000個にまで向上させることに成功しました。
今後は、製造段階での更なる省力化を図るため、マテリアルハンドリング(*)の自動化についても検討を進めています。
生産拠点や物流拠点内での原材料や仕掛品、完成品の全ての移動に関わる取扱いのこと
(飲食料品卸売業の売上高に占める経費割合の縮減を推進)
みどり戦略においては、令和12(2030)年度までに飲食料品卸売業における売上高に占める経費の割合を10%に縮減することとしており、令和2(2020)年度の飲食料品卸売業における売上高に占める経費の割合は13.8%となっています。
飲食料品卸売業の経費率削減に向けて、サプライチェーン全体での合理化・効率化を加速することが重要であることから、例えばパレットサイズや外装サイズ等の標準化、サプライチェーン全体でのデータ連携システムの構築等を実施することで、目標達成を目指しています。
(食品企業における持続可能性に配慮した輸入原材料調達の取組の割合拡大を推進)
みどり戦略においては、令和12(2030)年度までに食品企業における持続可能性に配慮した輸入原材料調達の実現に取り組むこととしており、令和3(2021)年度の上場食品企業における持続可能性に配慮した輸入原材料調達の取組の割合は36.5%となっています。
食品企業における持続可能性に配慮した輸入原材料の調達については、売上向上につながりにくく、コスト増加等の企業負担が増えるなどの課題が見られることから、優良な取組を行う食品製造事業者の表彰等の実施や、優良事例の横展開による取組の加速化、消費者への理解の促進を図ることとしています。令和12(2030)年までは、例えば原材料調達に当たって、認証を得た原材料の活用や、川上の環境・人権への配慮を確認するなどの取組を行う食品企業の割合を増やし、同年の上場食品企業における持続可能性に配慮した輸入原材料調達の取組の割合100%の目標達成を目指しています。
(5)環境にやさしい持続可能な消費の拡大や食育の推進
(事業系食品ロスの発生量は推計開始以降で最少)
農林水産省では、事業系食品ロスの削減に向け、納品期限緩和等の商慣習の見直し等を進めており、地方・中小企業を含めて取組事業者数の全国的な拡大を図ることとしています。こうした取組を通じて、事業系食品ロスを令和12(2030)年度までに平成12(2000)年度比で50%削減の目標達成を目指しています。
我が国の食品ロスの発生量は、近年減少傾向にあり、令和2(2020)年度においては前年度に比べ48万t減少し522万tと推計されています(図表2-9-7)。食品ロスの発生量を場所別に見ると、一般家庭における発生(家庭系食品ロス)は247万t、食品産業における発生(事業系食品ロス)は275万tで、いずれも食品ロスの発生量の推計を開始した平成24(2012)年度以降で最少となっています。これは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による需要減が大きく影響しているほか、値引き販売や需要予測の精緻化といった、食品ロス削減に向けた食品関連事業者の取組も減少に寄与しているものと考えられます。
(食と農林水産業のサステナビリティを考える取組を推進)
みどり戦略の実現に向け、消費者庁、農林水産省、環境省の共催により、企業・団体が一体となって持続可能な生産消費を促進する「あふの環(わ)2030プロジェクト~食と農林水産業のサステナビリティを考える~」を推進しており、令和5(2023)年3月末時点で農業者や食品製造事業者等178社・団体が参画しています。
同プロジェクトでは、令和4(2022)年9月に、食と農林水産業のサステナビリティについて知ってもらうため「サステナウィーク」を開催し、温室効果ガス排出削減の取組の「見える化」実証を実施したほか、「見た目重視から持続性重視」をテーマに、環境に配慮した消費行動に資する情報の発信を行いました。また、令和5(2023)年1月に、サステナブルな取組についての動画作品を表彰する「サステナアワード」も実施したほか、令和5(2023)年2月には消費者庁・農林水産省の共催で「日経SDGsフォーラム消費者共創シンポジウム」を開催するなど、持続可能な消費を推進しています。
このほか、農林水産省では、第4次食育推進基本計画(*1)に基づき、持続可能な食を支える食育の推進に向け、環境に配慮した農林水産物・食品への理解向上の取組に対する支援や、食事バランスガイド(*2)に環境の視点を加味する検討等を進めています。
1 第1章第6節を参照
2 健康で豊かな食生活の実現を目的に平成12(2000)年に策定された「食生活指針」を具体的に行動に結び付けるものとして、平成17(2005)年に厚生労働省と農林水産省にて作成。1日に、「何を」、「どれだけ」食べたら良いかを考える際の参考となるよう、食事の望ましい組合せとおおよその量をイラストで分かりやすく示している。
(農産物の温室効果ガス排出削減の取組の「見える化」を推進)

フードサプライチェーンにおける
脱炭素化の実践・見える化
URL:https://www.maff.go.jp/j/kanbo/
kankyo/seisaku/climate/visual.html
持続可能な食料システムを構築するためには、フードサプライチェーン全体で脱炭素化を推進するとともに、その取組を可視化して持続可能な消費活動を促すことが必要です。農林水産省では、生産者の脱炭素の努力・工夫に関する消費者の理解や脱炭素に貢献する製品への購買意欲の向上等、消費行動の変容を促すため、農産物の生産に伴い排出される温室効果ガスの削減の取組を「見える化」する簡易算定ツールの作成を行いました。さらに、これを活用し、温室効果ガスの削減割合に応じて星の数で等級ラベル表示した農産物の実証を行い、消費者の意識や行動の変化への影響を検証しました。今後、「見える化」の対象品目の拡大を図るほか、生物多様性保全の指標を追加することとしています。
(6)みどり戦略に基づく取組を世界に発信
(国際会議において、みどり戦略に基づく我が国の取組を紹介)
みどり戦略の実現に向けた我が国の取組事例について、広く世界に共有する取組を進めています。
令和4(2022)年9月、マニラで開催したアジア開発銀行(ADB)との政策対話において、我が国の優れたイノベーションに関する取組事例を含め、みどり戦略を紹介しました。これに対し、ADBから、我が国との連携を深めたい旨の発言があり、政策対話の成果として、両者間では初めての協力覚書である「アジア・太平洋地域における持続可能かつ強靱(きょうじん)な食料・農業システムの構築に関する協力覚書」への署名を実施しました。
また、令和4(2022)年10月にオンラインで開催されたASEAN+3農林大臣会合では、みどり戦略を踏まえた強靱(きょうじん)で持続可能な農業及び食料システムの構築に向けた我が国の協力イニシアティブである「日ASEANみどり協力プラン」を発信し、参加したASEAN(*1)各国から賛同を得ました。
くわえて、同年11月にパリで開催されたOECD(経済協力開発機構)農業大臣会合では、持続可能で強靱な農業生産や食料安全保障の確保のためにはイノベーションとその普及が重要であることに鑑み、我が国がみどり戦略に基づく取組を推進していることを発信しました。
このほか、我が国を訪問した各国要人との面談の場や、国連気候変動枠組条約第27回締約国会議(COP27)(*2)、G20等の国際会議等、あらゆる機会を捉え、みどり戦略に基づく我が国の取組を紹介しました。

ASEAN+3農林大臣会合で
「日ASEANみどり協力プラン」
を発信する農林水産大臣

OECD農業大臣会合で
みどり戦略について発言する
農林水産副大臣
1 Association of South-East Asian Nationsの略で、東南アジア諸国連合のこと
2 第2章第10節を参照
(農業技術のアジアモンスーン地域での応用を支援)

国際科学諮問委員会(第1回)
農林水産省では、気候変動の緩和や持続的農業の実現に資する技術のアジアモンスーン地域での実装を促進するため、令和4(2022)年に国立研究開発法人国際農林水産業研究(こくさいのうりんすいさんぎょうけんきゅう)センター(JIRCAS)に設置した「みどりの食料(しょくりょう)システム国際情報(こくさいじょうほう)センター」において、我が国の有望な基盤農業技術の収集・分析を行うとともに、アジアモンスーン地域で共有できる技術カタログ等の形による情報発信等を進めています。また、JIRCASが有する国際的なネットワークを活用し、アジアモンスーン地域の各地で、水田からのメタン排出を抑制する水管理技術や、窒素肥料の使用量を減らしても収量が変わらないBNI強化コムギの栽培実証を開始しました。この取組への助言を得るため、同年10月及び令和5(2023)年3月に、持続的農業等に関する著名な科学者や、アジアモンスーン地域の研究機関の長等で構成する国際科学諮問委員会の会合を開催しました。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883