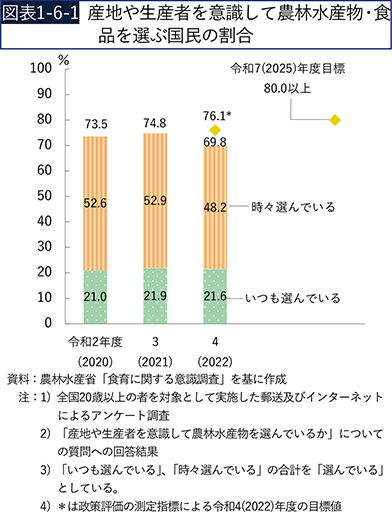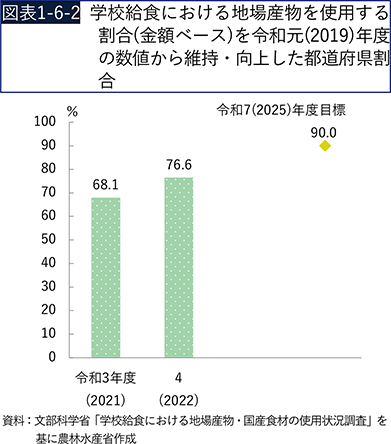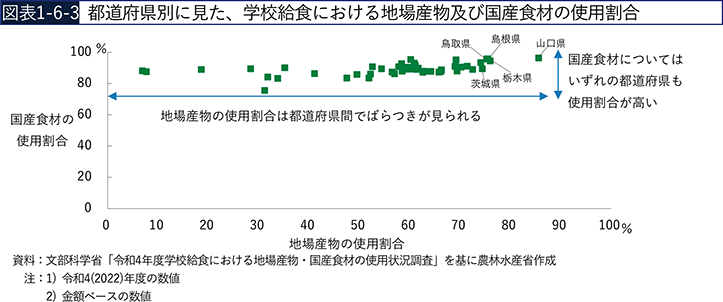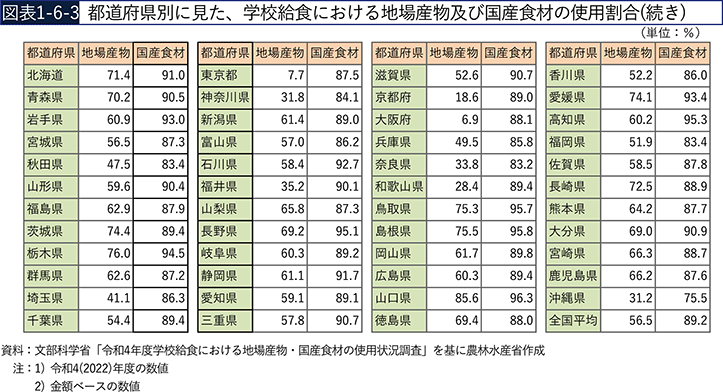第6節 消費者と食・農とのつながりの深化
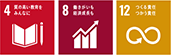
国産農林水産物が消費者や食品関連事業者に積極的に選択されるようにするためには、消費者と農業者・食品関連事業者との交流を進め、消費者が我が国の食や農を知り、触れる機会の拡大を図ることが重要です。また、次世代への和食文化の継承や、海外での和食の評価を更に高めるための取組等も重要です。
本節では、食育や地産地消(*1)の推進等、消費者と食・農とのつながりの深化を図るための様々な取組を紹介します。
1 用語の解説(1)を参照
(1)食育の推進
(「第4次食育推進基本計画」の実現に向けた取組を推進)
食育の推進に当たっては、国民一人一人が自然の恩恵や「食」に関わる人々の様々な活動への感謝の念や理解を深めつつ、「食」に関して信頼できる情報に基づく適切な判断を行う能力を身に付けることによって、心身の健康を増進する健全な食生活を実践することが重要とされています。令和3(2021)年度からおおむね5年間を計画期間とする「第4次食育推進基本計画」では、基本的な方針や目標値を掲げるとともに、食育の総合的な促進に関する事項として取り組むべき施策等が定められています。
目標の達成に向けて、農林水産省は、デジタル化に対応した食育を推進するため、令和4(2022)年4月に、デジタル技術を活用した食育を行う際のヒントを盛り込んだデジタル食育ガイドブックを作成し、普及を進めています。また、農林水産省、愛知県と第17回食育推進全国大会愛知県実行委員会は、同年6月に「第17回食育推進全国大会inあいち」を開催しました。
さらに、農林水産省では、「新たな日常」に対応した食育等、最新の食育活動の方法や知見を食育関係者間で情報共有するとともに、異業種間のマッチングによる新たな食育活動の創出や、食育の推進に向けた研修を実施できる人材の育成等に取り組むため、全国食育推進ネットワークを活用した取組を推進しています。
くわえて、農林水産省では、食育の一環として、栄養バランスに優れた「日本型食生活(*1)」の実践等を推進するため、地域の実情に応じた食育活動に対する支援を行っています。
このほか、農林水産省では、みどり戦略(*2)の実現に向け、環境にやさしい持続可能な食育の推進に取り組むこととしています。

デジタル食育ガイドブック
URL:https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/network/movie/

全国食育推進ネットワーク「みんなの食育」
URL:https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/network/index.html
1 ごはん(主食)を中心に、魚、肉、牛乳・乳製品、野菜、海藻、豆類、果物、お茶等の多様な副食(主菜・副菜)等を組み合わせた、栄養バランスに優れた食生活のこと
2 第2章第9節を参照
(事例)オンラインでの体験型食育活動を展開(沖縄県)


さとうきびの栽培体験キット
資料:株式会社オルタナティブファーム宮古
沖縄県宮古島市(みやこじまし)の農業生産法人である株式会社オルタナティブファーム宮古(みやこ)は、さとうきび等の生産や黒糖製品の製造を行うとともに、体験型の食育プログラムを提供しています。
食育活動においては、さとうきびの収穫や黒糖づくり等の実体験を通じた取組のほか、オンラインでの体験型の食育学習も展開しています。
オンラインによる学習では、距離が離れていても、現地開催と同様に食育プログラムとしての価値を提供できるように、事前送付されるさとうきび苗の栽培体験キットを活用し、五感を使って楽しめる工夫を施しています。
また、一般向けには科学・歴史・生物・地理・経済等、様々な切り口でさとうきび栽培や製糖の話題を提供するとともに、双方向でのコミュニケーションや現地の紀行・文化の紹介等の工夫を行っています。
同社では、距離や参加人数、会場確保等の制約を受けずに、幅広く取組を行うことができるオンラインのメリットを活かしながら、島内の複数事業者が連携したプログラムの提供等も視野に入れ、体験型食育活動を推進していくこととしています。
(こども食堂等の地域における共食の場の提供を推進)
高齢者の一人暮らしや一人親世帯等が増えるなど、家庭環境や生活の多様化により、家族との共食が難しい場合があることから、地域において様々な世代と共食する機会を持つことは、食の楽しさを実感するだけでなく、食や生活に関する基礎を伝え習得する上で重要となっています。
このため、農林水産省では、食育を推進する観点から、こども食堂等地域での様々な共食の場を提供する取組を支援するとともに、政府備蓄米を無償交付するなどの支援を行っています。地域での共食の場によって、食育の推進、孤独・孤立対策、生活困窮者への支援等、様々な効果が期待されています。

資料:株式会社日本海開発

資料:わいわい子ども食堂プロジェクト
共食の場を提供するこども食堂
(2)地産地消の推進
(産地や生産者を意識して農林水産物・食品を選ぶ国民の割合は約7割)
地域で生産された農林水産物をその地域内で消費する地産地消の取組は、国産農林水産物の消費拡大につながるほか、地域活性化や食品の流通経費の削減等にもつながります。
少子・高齢化やライフスタイルの変化等により国内マーケットの構造が変化している中、消費者の視点を重視し、地産地消等を通じた新規需要の掘り起こしを行うことが重要です。消費者や食品関連事業者に積極的に国産農林水産物を選択してもらえるよう取組を進めていくため、農林水産省は令和7(2025)年度までに産地や生産者を意識して農林水産物・食品を選ぶ国民の割合を80%以上とすることを目標としています。令和4(2022)年度の同割合は前年度に比べ5ポイント減少し69.8%となっています(図表1-6-1)。
(約3万校で学校給食が実施)
学校給食は、栄養バランスの取れた食事を提供することにより、子供の健康の保持・増進を図ること等を目的に、学校の設置者により実施されています。文部科学省の調査によると、令和3(2021)年5月時点で、小学校では18,923校(全小学校数の99.0%)、中学校では9,107校(全中学校数の91.5%)、特別支援学校等も含め全体で29,614校において行われており、約930万人の子供を対象に給食が提供されています。また、学校給食費の平均月額は、小学校で4,477円、中学校で5,121円となっており、学校給食法に基づき、給食施設費等は学校の設置者が負担し、食材費は保護者が負担しています。なお、経済状況が厳しい保護者に対しては、生活保護による教育扶助や就学援助を通じて、支援が行われています。
学校給食の現場においては、地方公共団体ごとに献立や年間実施回数が異なるなどの理由により、学校給食費は地域で異なる状況も見られています。
(学校給食における地場産物の使用を推進)
学校等施設給食において地場産農林水産物を使用することは、地産地消を推進するに当たって有効な手段であり、地域の関係者の協力の下、未来を担う子供たちが持続可能な食生活を実践することにつながることから、農林水産省は令和7(2025)年度までに学校給食における地場産物を使用する割合(金額ベース)を令和元(2019)年度の数値から維持・向上した都道府県割合を90%とすることを目標としています。令和4(2022)年度の同割合は76.6%となっています(図表1-6-2)。
また、文部科学省が令和4(2022)年度に実施した調査によると、学校給食における地場産物、国産食材の使用割合を都道府県別に見ると、地場産物の使用割合にばらつきが見られる一方、国産食材の使用割合はほとんどの都道府県で80%以上となっており、全国的に使用割合が高い状況となっています(図表1-6-3)。都道府県ごとに農業生産の条件が異なる中、学校給食における地場産物及び国産食材の活用に向けた取組が全国各地で進められています。
地場産農林水産物の利用については、一定の規格等を満たし、数量面で不足なく納入する必要があるなど多くの課題があるため、農林水産省では、学校等の現場と生産現場の双方のニーズや課題の調整役となる「地産地消コーディネーター(*1)」を全国の学校等施設給食の現場に派遣しています。
このほか、農林水産省では、地産地消の中核的施設である農産物直売所について、観光需要向けの商品開発や農林水産物の加工・販売のための機械・施設等の整備を支援しています。
1 栄養教諭、栄養管理士、栄養士等の給食実務経験者、生産者組織代表、行政担当者等
(3)和食文化の保護・継承
(和食文化の保護・継承に向けた取組を推進)

にっぽん伝統食図鑑
URL:https://traditional-foods.maff.go.jp(外部リンク)
食の多様化や家庭環境の変化等を背景に、和食(*1)や地域の郷土料理、伝統料理に触れる機会が少なくなってきており、和食文化の保護・継承に向けて、郷土料理等を受け継ぎ、次世代に伝えることが課題となっています。このため、輸出促進や食文化を保護・継承することを目的として、地域の食文化の多角的な価値のある情報(*2)を一元的・体系的に整理し、多言語化を含め、国内外に分かりやすく情報発信を行っており、郷土料理の情報を集約した「うちの郷土料理」の海外向けWebサイト「Our Regional Cuisines」、及び伝統的な加工食品の情報を発信するWebサイト「にっぽん伝統食図鑑」を開設しました。
また、身近で手軽に健康的な和食を食べる機会を増やしてもらい、将来にわたって和食文化を受け継いでいくことを目指し、平成30(2018)年度に発足した官民協働の取組である「Letʼs!和ごはんプロジェクト」では、メンバーが令和5(2023)年3月時点で約190企業・団体に達しました。11月24日が「和食の日」とされているところ、令和4(2022)年11月24日・25日の2日間にわたり、同プロジェクトとして初となる消費者向けイベントを大阪で実施し、和ごはん訴求の取組を発信しました。
さらに、子供や子育て世代に対して和食文化の普及活動を行う中核的な人材である「和食文化継承リーダー」を育成するため、栄養士や保育士等向けに研修会で使用する教材の作成や、モデル事業、和食文化に対する理解を深めるための研修会の開催等を行っています。
このほか、文化庁では、我が国の豊かな風土や人びとの精神性、歴史に根差した多様な食文化を次の世代へ継承するために、文化財保護法に基づく保護を進めるとともに、各地の食文化振興の取組に対する支援や、食文化振興の機運醸成に向けた情報発信等を行っています。
1 「和食;日本の伝統的な食文化」が平成25(2013)年12月にユネスコ無形文化遺産に登録。用語の解説(1)を参照
2 歴史、文化、製造方法等の伝統や特徴、健康有用性、持続可能性等
(4)消費者と生産者の関係強化
(消費者と生産者の交流の促進に向けた取組を推進)
消費者と生産者の交流を促進することにより、農村の活性化や、農業・農村に対する消費者の理解増進が図られるなどの効果が期待されています。また、国民の食生活が自然の恩恵の上に成り立っていることや食に関わる人々の様々な活動に支えられていること等に関する理解を深めるために、農業者が生産現場に消費者を招き、教育ファーム等の農業体験の機会を提供する取組等も行われています。
このほか、苗の植付け、収穫体験を通じて食材を身近に感じてもらい、自ら調理し、おいしく食べられることを実感してもらう取組や、生産現場の見学会、産地との交流会等も行われています。
こうした取組を通じ、消費者が自然の恩恵を感じるとともに、食に関わる人々の活動の重要性と地域の農林水産物に対する理解の向上や、健全な食生活への意識の向上が図られるなど、様々な効果が期待されています。
農林水産省は、これらの取組を広く普及するため、教育ファーム等の農林漁業体験活動への支援や、どこでどのような体験ができるか等についての情報発信を行っています。
(事例)米づくりを起点とした食と農を近づけるための取組を展開(栃木県)
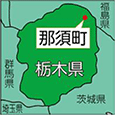

田んぼでカフェの様子
資料:稲作本店

稲作本店を立ち上げた井上夫婦
資料:稲作本店
栃木県那須町(なすまち)の株式会社FARM1739とTINTS株式会社が共同で立ち上げたブランドである「稲作本店(いなさくほんてん)」では、米の生産・販売と共に、米づくりを起点とした食と農を近づけるための取組を展開しています。
同店では、SNSやクラウドファンディングの手法も活用しながら、都市住民や近隣の非農家が田んぼに気軽に立ち寄ってコーヒー等を楽しめる「田んぼでカフェ」の開催や、お米が育った場所で、その地域の薪(まき)を使って釜でご飯を炊く経験をする「田んぼでキャンプ」の開催等に取り組んでいます。
また、近隣のホテルと連携した農業体験プログラムの企画運営のほか、地元小学生の職業体験の受入れや、田んぼに関わる循環型農業について教える出前授業の開催等にも取り組んでいます。
同店は、第9回ディスカバー農山漁村(むら)の宝で優良事例としても選定されており、今後とも、「つくるとたべるがつながるイナサク」をコンセプトに、田んぼを使った様々な取組を通じて、生産者と消費者が互いに交流を深める活動を推進していくこととしています。
(新たな国民運動「ニッポンフードシフト」を通じ、食と農の魅力を発信)
食料の持続的な確保が世界的な共通課題となる中で、食と農の距離が拡大し、農業や農村に対する国民の意識・関心は薄れています。
このような中、農林水産省は、令和3(2021)年度から、食と農のつながりの深化に着目した、官民協働で行う新たな国民運動「食から日本を考える。ニッポンフードシフト」(以下「ニッポンフードシフト」という。)を開始しました。
ニッポンフードシフトは、未来を担う1990年代後半から2000年代生まれの「Z世代」を重点ターゲットとして、食と環境を支える農林水産業・農山漁村への国民の理解と共感・支持を得つつ、国産の農林水産物の積極的な選択に結び付けるために、全国各地の農林漁業者の取組や地域の食、農山漁村の魅力を発信しています。令和4(2022)年度には、宮城県、石川県、東京都、山梨県、兵庫県、福岡県、沖縄県等全国各地で、食について考えるきっかけとなるトークセッションやマルシェ等のイベントを開催しました。また、ニッポンフードシフトの趣旨に賛同した「推進パートナー」等と連携した取組の展開や、テレビ、新聞、雑誌、Webサイト、SNS等のメディアを通じた官民協働による情報発信を実施しました。

食から日本を考える。アニメーション動画
URL:https://nippon-food-shift.maff.go.jp/movie/(外部リンク)

食から日本を考える。NIPPON FOOD
SHIFT FES.東京2022
(消費者と農林水産業関係者等を結ぶ広報を推進)
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、デジタル技術の活用等、生活様式の変化により、消費者はSNS等のインターネット上の情報を基に購買行動を決定し、生産者もこれに合わせて積極的にSNS上で情報発信をするようになりつつあります。これを踏まえ、農林水産省は、職員がYouTuberとなって、我が国の農林水産物や農山漁村の魅力等を伝える省公式YouTubeチャンネル「BUZZ MAFF(ばずまふ)」や、農林水産業関連の情報や施策を消費者目線で発信する省公式Twitter、食卓や消費の現状、暮らしに役立つ情報等を毎週発信するWebマガジン「aff(あふ)」等を通じて、消費者と農林水産業関係者、農林水産省を結ぶための情報発信を強化しています。
特に令和元(2019)年度から開始したBUZZ MAFFは、令和4(2022)年度末時点で動画の総再生回数は3,800万回を超え、チャンネル登録者数は16万9千人を超えています。
また、令和4(2022)年度の「こども霞が関見学デー」の一環として、食や農林水産業について学べる夏の特設Webサイト「マフ塾 ~いのちを支える食の学び舎~」を開設し、小学生から大人まで楽しめる学習ドリル等、全国どこからでも農業・林業・水産業を学べるコンテンツを公開しました。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883