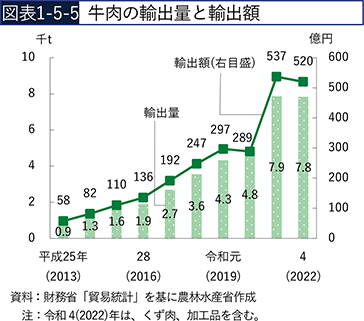第5節 グローバルマーケットの戦略的な開拓
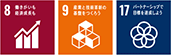
我が国の農林水産物・食品の輸出額は着実に増加しており、令和4(2022)年には過去最高を更新しました。高齢化や人口減少により農林水産物・食品の国内消費の減少が見込まれる中で、農業・農村の持続性を確保し、農業の生産基盤を維持していくためには、今後大きく拡大すると見込まれる世界の食市場を出荷先として取り込んでいくことが重要です。
本節では、政府一体となっての輸出環境の整備、輸出に向けた海外への商流構築やオールジャパンでのプロモーション、食産業の海外展開の促進、知的財産の保護・活用について紹介します。
(1)農林水産物・食品の輸出促進に向けた環境の整備
(輸出促進法の改正等を踏まえた輸出戦略を着実に推進)
政府は、輸出促進法(*1)の改正等を踏まえ、令和4(2022)年5月及び12月に「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」(以下「輸出戦略」という。)を改訂し、先進的な大規模輸出産地の形成、育成者権者に代わり知的財産権を管理する育成者権管理機関の設立、都道府県による海外プロモーションの効果的な実施を図る都道府県・輸出支援プラットフォーム連携フォーラムの設置等、新たな輸出促進施策の方向性を決定しました。
1 正式名称は「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律」
(日本の強みを最大限に発揮するための取組を推進)
輸出戦略に基づき、農林水産省は、海外で評価される日本の強みを有し、輸出拡大の余地が大きく、関係者が一体となった輸出促進活動が効果的な29品目を輸出重点品目に選定しています。
輸出重点品目ごとに、輸出に向けたターゲット国・地域を特定し、ターゲット国・地域ごとの輸出目標を設定するとともに、目標達成に向けた課題と対応を明確化しています。
また、主要な輸出先国・地域に、在外公館や独立行政法人日本貿易振興機構(にほんぼうえきしんこうきこう)(JETRO(ジェトロ))の海外事務所、日本食品海外(にほんしょくひんかいがい)プロモーションセンター(JFOODO(ジェイフードー))等を主な構成員とする「輸出支援プラットフォーム」を設立し、輸出先国・地域において輸出事業者を包括的・専門的・継続的に支援しています。
さらに、改正輸出促進法(*1)に基づき、輸出重点品目について、生産から販売に至る関係者が連携し、オールジャパンによる輸出促進活動を行う体制を備えた団体を農林水産物・食品輸出促進団体(以下「品目団体」という。)として認定する制度を創設しました。令和4(2022)年度においては、コメ等17品目9団体を品目団体として認定しています。
1 正式名称は「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律」
(マーケットインの発想で輸出にチャレンジする事業者を支援)
輸出産地・事業者の育成や支援を行うGFP(*1)(農林水産物・食品輸出プロジェクト)は、令和5(2023)年3月末時点で会員数が7,400を超えていますが、輸出の熟度・規模が多様化しており、輸出事業者のレベルに応じたサポートを行う必要があるほか、新たに輸出に取り組む輸出スタートアップを増やしていく必要があります。このため、地方農政局等や都道府県段階で、現場に密着したサポート体制を強化することとしています。
また、新たな制度資金(農林水産物・食品輸出基盤強化資金)や公庫による債務保証(スタンドバイ・クレジット)の積極的な活用により、輸出にチャレンジする事業者を資金面から強力に後押しすることとしています。
さらに、輸出産地・事業者をリスト化し、輸出促進法に基づく輸出事業計画を策定した者に対し、輸出産地の形成に必要な施設整備等を重点的に支援するとともに、リスト化された輸出産地・事業者をサポートするため、食品事業者や商社OB等の民間人材を「輸出産地サポーター」として地方農政局等に配置し、輸出事業計画の策定と実行を支援しています。
1 Global Farmers/Fishermen/Foresters/Food Manufacturers Projectの略
(事例)GFPの伴走支援を受け、「木桶仕込み醤油」の輸出拡大を推進(香川県)


「FOODEX JAPAN 2022」へ出展
資料:一般社団法人木桶仕込み醬油
輸出促進コンソーシアム

伝統的製法で木桶醤油を醸造
資料:一般社団法人木桶仕込み醬油
輸出促進コンソーシアム
香川県小豆島町(しょうどしまちょう)に拠点を置く一般社団法人木桶仕込(きおけじこ)み醤油輸出促進(しょうゆゆしゅつそくしん)コンソーシアムでは、醸造元ごとに特色のある「木桶仕込み醤油」をプレミアム醤油として海外へ提案し、和食価値の底上げを図る取組を積極的に展開しています。
同コンソーシアムは、令和3(2021)年3月に木桶仕込み醤油のメーカー25社が参画し、GFPの伴走支援を受け、木桶仕込み醤油の輸出拡大を実現するために設立されました。
木桶仕込み醤油は、蔵元ごとに複雑な味や香りに特徴があることに加え、木桶製造の歴史や生産ストーリーを有していることから、和食文化や醤油の魅力発信と合わせて、ブランディングを実施するとともに、その魅力を伝えるための多言語に対応したWebサイトを製作し、醤油の醸造過程を伝えるなど、発酵調味料としての木桶仕込み醤油の認知度向上を図っています。
また、同コンソーシアムは、GFPと連携したオンライン商談会や欧米でのPRイベントの開催等を通じて現地の卸売事業者等のファンを増やし、レストランへの納入や小売店でのプライベートブランドとしての採用等、販路の拡大に努めています。
こうした取組を重ねることで、令和3(2021)年の輸出額は、2年前と比べて、ほぼ倍増となる1億2,470万円に拡大しています。今後は、「世界の醤油市場の1%(金額ベース)の獲得」を目指し、更なる輸出促進を図っていくこととしています。
(政府一体となって輸出の障害の克服を推進)
東京電力福島第一(とうきょうでんりょくふくしまだいいち)原子力発電所の事故に伴い、55か国・地域において、日本産農林水産物・食品の輸入停止や放射性物質の検査証明書等の要求、検査の強化といった輸入規制措置が講じられていました。これらの国・地域に対し、政府一体となってあらゆる機会を捉えて規制の撤廃に向けた粘り強い働き掛けを行ってきた結果、令和4(2022)年度においては、輸入規制措置が英国、インドネシアで撤廃され、規制を維持する国・地域は12にまで減少しました。
動植物検疫協議については、農林水産業・食品産業の持続的な発展に寄与する可能性が高い輸出先国・地域や品目から優先的に協議を進めています。同年度は、メキシコ向け精米の輸出が解禁されました。また、国内では各地で高病原性鳥インフルエンザ(*1)や豚熱(ぶたねつ)(*2)が発生していますが、発生等がない地域から鶏卵・鶏肉や豚肉の輸出が継続できるよう主な輸出先国・地域との間で協議を行い、これが認められました。
さらに、農林水産物・食品の輸出に際して輸出先国・地域から求められる輸出証明書の申請・発給をワンストップで行えるオンラインシステムを整備し、令和4(2022)年4月には、原則全ての種類の輸出証明書のシステム運用を開始しました。
このほか、令和12(2030)年までに5兆円とする目標のうち2兆円を占める加工食品の輸出促進に向け、輸出先国・地域の食品添加物規制等に対応した加工食品の製造を促進するため、地域の中小事業者等が連携して輸出に取り組む加工食品クラスターの形成を支援しています。
1、2 用語の解説(1)を参照
(2)主な輸出重点品目の取組状況
(果実の輸出額はりんご、ぶどうを中心に増加)
果実の輸出額は、我が国の高品質な果実がアジアを始めとする諸外国・地域で評価され、りんご、ぶどうを中心に増加傾向にあります。令和4(2022)年は、台湾においてりんごの贈答用や家庭内需要が増加したこと等から、前年に比べ増加し316億円となりました(図表1-5-1)。
(茶の輸出額は海外の日本食ブームにより増加)
茶の輸出額は、海外の日本食ブームや健康志向の高まりにより近年増加傾向にあります。令和4(2022)年の茶の輸出額は、前年に比べ7.2%増加の219億円となっており、平成25(2013)年と比べると約3倍に増加しています(図表1-5-2)。
また、有機栽培による茶は海外でのニーズも高く、有機同等性(*1)の仕組みを利用した輸出量は増加傾向にあり、令和3(2021)年は前年に比べ28%増加し過去最高の1,312tとなりました(図表1-5-3)。特にEU・英国や米国が大きな割合を占めています。
1 相手国・地域の有機認証を自国・地域の有機認証と同等のものとして取り扱うこと
(コメ・コメ加工品の輸出額は前年に比べ増加)
令和4(2022)年の商業用のコメの輸出額は、前年に比べ24%増加し73億8千万円となり(図表1-5-4)、パックご飯・米粉及び米粉製品を含めた輸出額は、前年に比べ26%増加し82億7千万円となりました。今後とも輸出ターゲット国・地域として設定している香港、シンガポール、米国、中国を中心に、コメ・コメ加工品の海外市場開拓や大ロットでの輸出用米の生産に取り組む産地の育成を進めていくこととしています。
(牛肉の輸出額は前年に比べ減少)
令和4(2022)年の牛肉の輸出額は、カンボジア向け輸出の減少や、米国での物価高騰等による消費減退の影響で、前年に比べ減少し520億円となりました(図表1-5-5)。
(3)海外への商流構築、プロモーションの促進
(JETRO・JFOODOによる海外での販路開拓支援を実施)
JETROでは、輸出セミナーの開催、輸出関連制度・マーケット情報の提供、相談対応等の輸出事業者等へのサポートを行っています。また、海外見本市への出展支援、国内・海外での商談会開催、サンプル展示ショールームの設置等によるリアルとオンライン双方のビジネスマッチング支援等、輸出に取り組む国内事業者への総合的な支援を実施しています。
JFOODOでは、「日本産が欲しい」という現地の需要・市場を作り出すため、品目団体等とも連携の上、新聞・雑誌や屋外、デジタルでの広告展開、PRイベントの開催等、現地での消費者向けプロモーションを戦略的に実施しています。
(海外における日本食レストランの店舗数が拡大)
令和3(2021)年の海外における日本食レストランの店舗数については、約15万9千店と、平成25(2013)年の3倍近くに増加しており、海外での日本食・食文化への関心が高まっていることがうかがわれます。
また、日本産食材を積極的に使用する海外の飲食店や小売店を民間団体等が主体となって認定する「日本産食材サポーター店」については、令和4(2022)年度末時点で約8千店が認定されています。JETROでは、世界各地の日本産食材サポーター店等と連携して、日本産食材等の魅力を訴求するプロモーションを実施しています。
(訪日外国人旅行者の日本滞在時の食に関する体験を推進)
農林水産省が平成30(2018)年から実施している「食かけるプロジェクト」では、食と芸術や歴史等異分野の活動を掛け合わせた体験を通じて、訪日外国人旅行者の日本食への関心を高めるとともに、帰国後も我が国の食を再体験できる環境の整備を推進しています。
同プロジェクトの一環として、食と異分野を掛け合わせた食体験を募集・表彰する「食かけるプライズ」を実施し、令和4(2022)年9月に大賞等10件を決定しました。
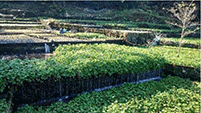
「食かけるプライズ2022」食かける大賞
景観美と世界農業遺産“わさび”を満喫する旅(静岡県)
資料:和とモダンが織りなす里山の古民家 白壁
(インバウンド観光の再開を契機として訪日外国人への日本食の理解・普及を推進)
我が国の食文化は世界に誇る文化遺産であり、農業、食、地域、多様な食産業を支える基盤でもあります。農林水産省を始めとする関係省庁は、海外の消費者への日本の食品の調理方法、食べ方、食体験等を通じた地域の文化とのつながりの発信等を進め、インバウンド観光の再開を契機とした訪日外国人への日本の食や食文化の理解・普及を図ることにより、我が国の農林水産物・食品の輸出市場とインバウンド消費を拡大する取組を支援することとしています。
これを受けて、JETRO・JFOODOと日本政府観光局(にほんせいふかんこうきょく)(*1)(JNTO)は、デジタルマーケティングや海外でのプロモーションイベント等で連携し、日本の農林水産物・食品の輸出市場とインバウンド消費を相乗的に拡大することを目指しています。
1 正式名称は「独立行政法人国際観光振興機構」
(4)食産業の海外展開の促進
(輸出を後押しする事業者の海外展開を支援)
輸出先国・地域において、輸出事業者を包括的・専門的・継続的に支援するため、現地発の情報発信や新たな商流の開拓等を行う輸出支援プラットフォームを整備しています。令和4(2022)年度は、米国(ロサンゼルス、ニューヨーク)、タイ(バンコク)、シンガポール(シンガポール)、EU(パリ)、ベトナム(ホーチミン)、香港(香港)において輸出支援プラットフォームを設立しました(*1)。
また、海外現地法人を設立し、設備投資等を行う場合の資金供給を促進するとともに、投資円滑化法(*2)に基づき、民間の投資主体による輸出に取り組む事業者への資金供給の促進に取り組むこととしています。

輸出支援プラットフォームの立上げ式
(タイ(バンコク))

ごはんフェス×JAPAN Fesでのおにぎり体験
(米国(ニューヨーク))
資料:在ニューヨーク日本国総領事館
1 ()内は事務局設置都市
2 正式名称は「農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法」
(5)知的財産の保護・活用
(輸出拡大や所得・地域の活力向上に向けてGI保護制度を見直し)

GI登録証の授与式
地理的表示(GI(*1))保護制度は、その地域ならではの自然的、人文的、社会的な要因の中で育まれてきた品質、社会的評価等の特性を有する産品の名称を、地域の知的財産として保護する制度です。同制度は、国による登録によりそのGI産品の名称使用の独占が可能となり、模倣品が排除されるほか、産品の持つ品質、製法、評判、ものがたり等の潜在的な魅力や強みを「見える化」し、GIマークとあいまって、効果的・効率的なアピール、取引における説明や証明、需要者の信頼の獲得を容易にするツールとして機能するものです。
令和4(2022)年度は新たに11産品が登録され、これまでに登録された国内産品は、同年度末時点で42都道府県の計128産品となりました(図表1-5-6)。
このほか、日EU・EPA(*2)により、日本側GI 95産品、EU側GI 106産品が相互に保護され、日英EPAにより、日本側GI 47産品、英国側GI 3産品が相互に保護されています。
農林水産省では、農林水産物・食品の輸出拡大に資するよう、令和4(2022)年11月にGI保護制度の運用を見直し、知名度の高い加工品を幅広く登録できるよう審査基準を改正しました。今後、GIの持つ機能を戦略的に活用した取組が全国各地に広がるよう、同制度の活用を推進することとしています。

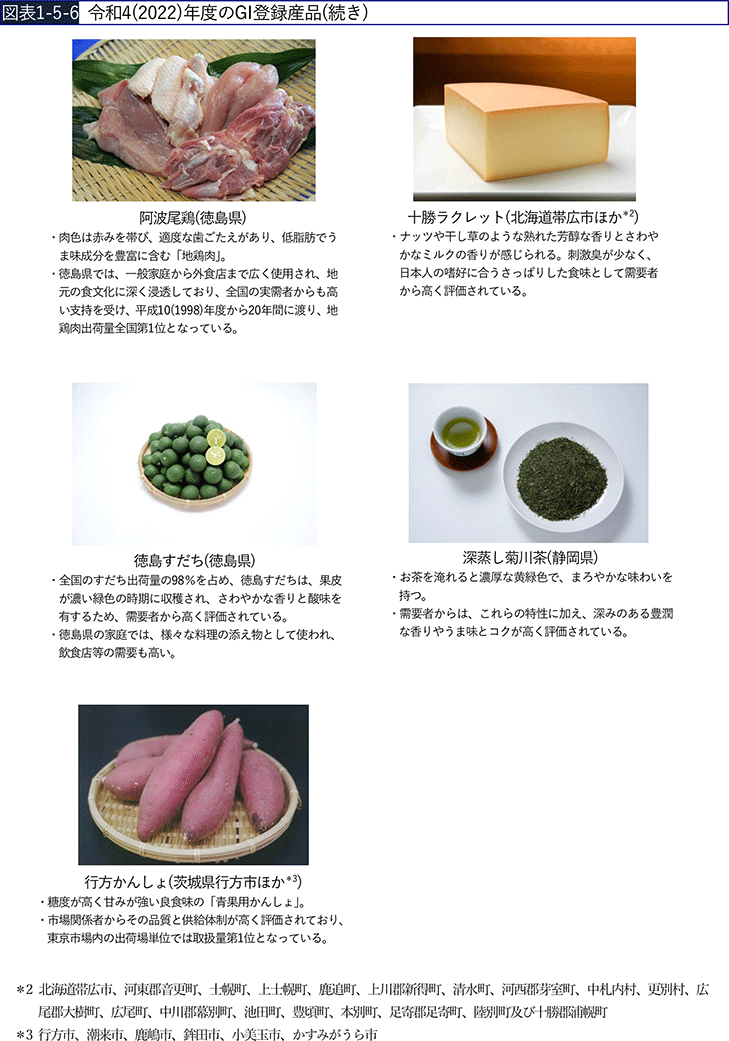
1 Geographical Indicationの略
2 用語の解説(2)を参照
(植物新品種の海外流出防止に向けた取組を推進)
近年、我が国の登録品種(*1)が海外に流出する事例が見られたことも踏まえ、植物品種の育成者権の保護を強化するための改正種苗法(*2)に基づき、令和4(2022)年4月から、登録品種の増殖は農業者による自家増殖も含め育成者権者の許諾が必要となり、無断増殖等が把握しやすくなるとともに、育成者権侵害に対しての立証を容易にする措置が講じられています。
また、登録品種のうち、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(のうぎょう・しょくひんさんぎょうぎじゅつそうごうけんきゅうきこう)(以下「農研機構」という。)や都道府県等の公的機関が開発したほとんどの品種について、海外への持出しが制限されています。
こうした措置を活用することで、育成者権の保護・活用に取り組みやすくなりましたが、公的機関や中小の種苗会社等では、登録品種の国内外での適切な管理や侵害対策の徹底が難しい現状もあります。このため、育成者権者に代わって、海外への品種登録や戦略的なライセンスによる管理された海外生産を通じて品種保護をより実効的に行うとともに、ライセンス収入を品種開発投資に還元するサイクルを実現するため、育成者権管理機関の取組を推進することとしています。植物の新品種は、我が国農業の今後の発展を支える重要な要素となっている中で、育成者権者による登録品種の管理の徹底や海外流出の防止を図り、新品種の開発や、それらを活用した輸出促進を図ることとしています。
1 種苗法に基づき品種登録を受けている品種
2 正式名称は「種苗法の一部を改正する法律」
(和牛遺伝資源の適正な流通管理を推進)
和牛は関係者が長い年月をかけて改良してきた我が国固有の貴重な財産であり、国内の生産基盤を強化するとともに、和牛肉の輸出拡大につなげていくためにも、精液等の遺伝資源の流通管理の徹底や知的財産としての価値の保護が重要です。
このため、家畜改良増殖法に基づき、牛の家畜人工授精用精液等を取り扱う全国の家畜人工授精所4,270か所を対象に法令遵守状況の調査を実施するとともに、令和3(2021)年度末までに615か所の立入検査を行いました。
その結果概要を令和4(2022)年6月に公表するとともに、これを踏まえて、引き続き立入検査等により法令遵守を徹底し、和牛遺伝資源の管理・保護の更なる推進を図っています。
(営業秘密の管理方法等を整理したガイドラインの導入・活用を促進)

農業分野における営業秘密の保護ガイドライン
URL:https://pvp-conso.org/842/(外部リンク)
近年、我が国農業分野の知的財産の重要性への認識が高まり、関連する制度の整備が行われていますが、農業現場における優れた栽培・飼養技術やその他のノウハウ等の知的財産を保護する仕組みについては、その知見が十分に行き渡っておらず、農業分野の知的財産保護における残された課題となっています。このため、農林水産省では、農業分野における技術・ノウハウ等の知的財産について、不正競争防止法の営業秘密を保護する枠組みを活用できるよう、農業分野固有の取引慣行等を踏まえた営業秘密の管理方法等を整理した「農業分野における営業秘密の保護ガイドライン」の現場での導入・活用を促進しています。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883