第4節 新たな価値の創出による需要の開拓
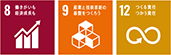
食品産業は、農業と消費者の間に位置し、食料の安定供給を担うとともに、国産農林水産物の主要な仕向先として、消費者ニーズを生産者に伝達する役割を担っています。また、多くの雇用・付加価値を生み出すとともに、食品ロスの削減等にも重要な役割を果たしています。
本節では、食品産業の動向や規格・認証の活用等について紹介します。
(1)食品産業の競争力の強化
(食品産業の国内生産額は92.1兆円)
食品産業の国内生産額は、近年増加傾向で推移していましたが、令和2(2020)年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大により外食産業が大きな影響を受けたことから、前年に比べ9兆2千億円減少し92兆1千億円となりました(図表1-4-1)。食品製造業では清涼飲料や酒類の工場出荷額が減少したこと等から前年に比べ2.8%減少し36兆6千億円となり、関連流通業はほぼ前年並の34兆9千億円となりました。また、全経済活動に占める食品産業の割合は前年と比べ0.3ポイント減少し9.4%となりました。
(食品製造業は地域の雇用において重要な役割)
各都道府県における全製造業の従業員数に占める食料品製造業の従業員数の割合を見ると、多くの都道府県で1割を超えており、特に北海道と沖縄県では40%を超えています(図表1-4-2)。また、同割合の順位については、1位が25道府県、2位が11都県、3位が6府県と、ほとんどの都道府県において1位から3位までに入っています。このことから、食品製造業が地域の雇用において重要な役割を果たしていることがうかがわれます。
(飲食料品製造業分野では外国人材の技能実習から特定技能への移行が拡大)
令和4(2022)年10月末時点での飲食料品製造分野(*1)における外国人材の総数は約14万9千人、外食分野(*2)における外国人材の総数は約18万5千人となっています。
このうち、特定技能(*3)外国人については、令和4(2022)年12月末時点での飲食料品製造業分野の受入数は、全12分野(130,923人)で最多となる42,505人となっています(図表1-4-3)。飲食料品製造業分野における技能実習2号修了者(*4)からの移行は33,042人で、全体の約78%を占めています。
農林水産省では、食品産業の現場で特定技能制度による外国人材を円滑に受け入れるため、試験の実施や外国人が働きやすい環境の整備に取り組むなど、食品産業特定技能協議会等を活用し、地域の労働力不足克服に向けた有用な情報を発信しています。
1 飲食料品製造分野は、「日本標準産業分類(平成25年10月改定)」の「中分類 09 食料品製造業」及び「中分類 10 飲料・たばこ・飼料製造業」に該当する事業所で就労する外国人労働者数を集計
2 外食分野は、「日本標準産業分類(平成25年10月改定)」の「中分類 76 飲食店」及び「中分類 77 持ち帰り・配達飲食サービス業」に該当する事業所で就労する外国人労働者数を集計
3 特定技能制度は、人手不足が続いている中で、外国人材の受入れのために平成31(2019)年に創設された制度で、飲食料品製造業を含む12の特定産業分野が受入対象となり、「特定技能」の在留資格で一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れる制度
4 在留資格「技能実習1号」で最長1年間技能等を要する業務に従事した後、所定の技能検定等に合格し、在留資格「技能実習2号」で最長2年間技能等を要する業務に従事した者
(地域の農産物等を活用した新たなビジネスを継続的に創出する仕組みを構築)
我が国の食品産業は、国内市場の縮小と海外市場の拡大、地球環境の持続性確保への配慮、原材料の安定調達、多様化する消費者ニーズへの対応等、様々な変化に対応した、新たな価値を生み出す取組が求められています。
このため、農林水産省では、令和3(2021)年度から、地域の食品産業を中心とした多様な関係者が参画するプラットフォームを形成し、地域の農林水産物を活用したビジネスを継続的に創出する仕組みである「地域食品産業連携プロジェクト」(LFP(*1))を推進しています。令和4(2022)年度は20道府県において、農業者や食品製造業者、食品流通業者、飲食店、異業種(観光業者等)の各主体が、それぞれの知見や技術、販路等の経営資源を結集したプラットフォームを設置し、地域の社会課題解決と経済性が両立する新たなビジネスとして、地域の農林水産物を活用した新商品等の開発に取り組んでいます。
1 Local Food Projectの略
(「フードテック推進ビジョン」及び「ロードマップ」を策定)
健康志向や環境志向等、消費者の食に関する価値観が多様化していること等を背景に、フードテック(*1)を活用した新たなビジネスの創出への関心が世界的に高まっています。このような中、農林水産省が令和2(2020)年10月に立ち上げた「フードテック官民協議会」において、令和5(2023)年2月に「フードテック推進ビジョン」及び「ロードマップ」が策定されました。
同ビジョンでは、今後のフードテックの推進に当たり、目指す姿や必要な取組等を整理し、ロードマップでは、フードテックの6分野(*2)について、具体的な課題を工程表として整理しています。農林水産省では、これらに沿って、オープンイノベーションとスタートアップの創業を促進するとともに、新たな市場を創り出すための環境整備を進め、フードテックの積極的な推進に取り組んでいくこととしています。
1 生産から流通・加工、外食、消費等へとつながる食分野の新しい技術及びその技術を活用したビジネスモデルのことで、我が国における取組事例としては、大豆ミートや、健康・栄養に配慮した食品、人手不足に対応する調理ロボット、昆虫を活用した環境負荷の低減に資する飼料・肥料の生産等の分野で、スタートアップ等が事業展開、研究開発を実施
2 6分野は、植物由来の代替たんぱく質源、昆虫食・昆虫飼料、スマート育種のうちゲノム編集、細胞性食品、食品産業の自動化・省力化、情報技術による人の健康実現

新事業創出(フードテック等)
URL:https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sosyutu/index.html
(コラム)フードテックの市場規模が拡大
世界の食料需要は、令和32(2050)年に平成22(2010)年比で1.7倍になると想定されており、増大するたんぱく質源の需要に対応するためには、国内の畜産業等の生産基盤を強化することに加え、食に関する先端技術(フードテック)を活用したたんぱく質の供給源の多様化を図ること等により、食料を効率良く持続可能な方式で生産する方法を模索することが重要です。
令和4(2022)年3月に公表したフードテックの市場規模の推計によると、令和32(2050)年に最も市場規模が大きい分野は、プラントベースドフードのうち植物由来乳製品と見込まれています。この中には、豆乳やアーモンドミルク、オーツミルク等が含まれ、これらを使用した加工食品が我が国でも開発されています。植物由来原料を使用した商品としては、豆乳・アーモンドペーストから作られたプリンや、もち米から作られたチーズ代替食品等があります。
こうした製品は、乳糖不耐症や乳製品アレルギーの人でも食べることができます。今後、フードテックの研究開発が進展することで、たんぱく質の供給源の多様化が図られ、持続可能な食料供給に貢献するだけでなく、より多くの人が美味しく、豊かな食事を楽しめるようになることが期待されています。
(2)食品流通の合理化等
(物流の標準化等、食品流通合理化の具体化が進展)
トラックドライバー等の人手不足が深刻化する中で、国民生活や経済活動に必要不可欠な物流の安定を確保するためには、サプライチェーン全体で食品流通の合理化に取り組む必要があります。そのような中、トラックドライバーにも時間外労働の上限規制が適用されることに伴う、いわゆる「物流の2024年問題」により、一層の物流への影響が懸念されています。
このため、農林水産省では、トラックドライバーの拘束時間を縮減できるよう、ドライバーの荷役を前提とした従来のばら積みから、パレットでの輸送に切り替えていくとともに、パレットサイズや段ボール等の標準化による荷積みの効率化を進めるほか、ICTやAIを活用した検品作業等の省力化・自動化等、複数企業でトラック等をシェアする配送システムであるフィジカルインターネットの実現も見据えた効率的な食品流通モデルの構築を推進することとしています。また、共同物流施設の整備を推進するとともに、トラック輸送から鉄道や海運への輸送切替(モーダルシフト)を推進することとしています。
(卸売市場の物流機能を強化)
卸売市場は、野菜、果物、魚、肉、花き等日々の食卓に欠かすことのできない生鮮品等を、国民に円滑かつ安定的に供給するための基幹的なインフラです。多種・大量の物品の効率的かつ継続的な集分荷、公正で透明性の高い価格形成等、重要な機能を担っています。
食料安全保障(*1)の強化が求められる中、持続的に生鮮食料品等の安定供給を確保していくため、単に老朽化に伴う施設の更新のみならず、物流施策全体の方向性と調和し、標準化・デジタル化に対応した卸売市場の物流機能を強化することが必要となっています。
農林水産省では、卸売市場の活性化に向け、卸売市場のハブ機能の強化やコールドチェーンの確保、パレット等の標準化、デジタル化・データ連携による業務の効率化等を推進することとしています。
1 用語の解説(1)を参照
(事例)共同物流拠点施設を整備し、輸送効率化とモーダルシフトを推進(福岡県)


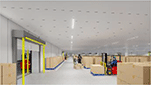
共同物流拠点施設の
完成予定イメージ
資料:北九州青果株式会社
福岡県北九州市(きたきゅうしゅうし)の北九州青果(きたきゅうしゅうせいか)株式会社は、北九州市中央卸売市場(きたきゅうしゅうしちゅうおうおろしうりしじょう)の構内に共同物流拠点施設(荷捌(にさば)き場施設及び冷蔵庫施設)を整備し、出荷車両の積載率向上やフェリーを活用した大規模なモーダルシフトを実現することを目指しています。
九州の各産地で生産されている青果物の関東・関西方面への輸送は、各産地が個別に対応している状況ですが、トラックの積載効率が低くなることや輸送費が高額になること等の問題を抱えています。また、令和6(2024)年度からはトラックドライバーに時間外労働の上限規制が適用されるため、トラックでの長距離輸送が一層困難になることが見込まれています。
これらの問題への対処が求められる中、同社では共同物流拠点施設の整備による輸送効率化を進めていくこととしており、令和5(2023)年8月頃に竣工(しゅんこう)し、準備が整い次第供用を開始する予定です。
同施設が九州の玄関口の物流拠点として重要な役割を果たし、流通合理化が一層進展することが期待されています。
(3)規格・認証の活用
(輸出拡大に向けてJAS法を改正)
近年、輸出の拡大や市場ニーズの多様化が進んでいることから、農林水産省では、日本農林規格等に関する法律(以下「JAS法」という。)に基づき、農林水産物・食品の品質だけでなく、事業者による農林物資の取扱方法、生産方法、試験方法等について認証する新たなJAS(*1)制度を推進しています。令和4(2022)年度には、ベジタリアン又はヴィーガンに適した加工食品、廃食用油のリサイクル工程管理のJAS等、5規格を制定しました(図表1-4-4)。これらのJASによって、事業者や産地の創意工夫により生み出された多様な価値・特色を戦略的に活用でき、我が国の食品・農林水産分野の競争力の強化につながることが期待されています。
また、同年10月に施行された改正JAS法(*2)において、JAS規格の制定の対象に有機酒類が追加されるとともに、登録認証機関の有する事業者の認証に係る情報が他の登録認証機関に提供される仕組みの導入等が行われました。これを受け、有機農産物加工食品について既に同等性を相互承認している米国やEU等と有機酒類の同等性交渉を進めることとしています。
このほか、農林水産省では、輸出促進に向け海外との取引を円滑に進めるための環境整備として、産官学の連携により、ISO(*3)規格等の国際規格の制定・活用を進めています。
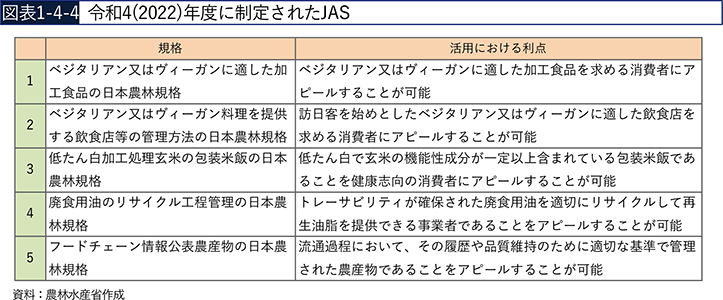
1、3 用語の解説(2)を参照
2 正式名称は「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律」
(日本発の食品安全管理に関する認証規格である「JFS規格」の取得件数は増加)
食品の民間取引において、安全管理の適正化・標準化が求められるようになりつつあり、食品安全マネジメント規格(以下「FSM規格(*1)」という。)への関心が高まっています。FSM規格の認証取得により、食品製造事業者がHACCP(*2)に基づく衛生管理や食品防御(*3)を適切に実施していることを、取引先等に客観的に立証することが容易となるほか、国内外の商談に有効となるなどの利点が挙げられています。
FSM規格は、欧米で先行して作られていたため、国内の食品事業者も海外の規格の認証を受けていましたが、我が国の食品製造の特性にも適していて、日本語で書かれた規格を望む声が高まり、平成28(2016)年に一般財団法人食品安全(しょくひんあんぜん)マネジメント協会(きょうかい)によって日本発のFSM規格であるJFS(*4)規格が設けられました。その特徴として、我が国特有の食文化である生食や発酵食等の食品製造においても導入しやすいということがあります。くわえて、JFS規格の各製造セクターでは、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理を包含するJFS-A規格や、HACCPに基づく衛生管理を包含するJFS-B規格、国際取引にも通用する高水準のJFS-C規格(*5)が設けられており、経営規模等に応じて段階的に取り組みやすい仕組みとなっています。
JFS-A/B/C規格の国内取得件数は、運用開始以降、年々増加してきており、令和5(2023)年3月末時点で2,275件(*6)となりました(図表1-4-5)。
今後、JFS規格の更なる普及により、我が国の食品安全レベルの向上や食品の輸出力強化が期待されます。
農林水産省では、JFS規格の認証取得の前提となるHACCPに沿った衛生管理の円滑な実施を図るための研修や海外における認知度向上のための周知、取得ノウハウ等を情報発信して横展開する取組等を支援しています。
1 FSM規格は、安全な食品を消費者に提供することを目的として、食品製造事業者が、安全レベルを維持・向上する仕組み(システム)を構築し、安全を脅かす危害要因を適切に管理していることを客観的に説明できるようにした認証規格。一般的に、国際的に認められているFSM規格は、適正製造規範(GMP(Good Manufacturing Practice))、HACCP、食品安全マネジメント(FSM(Food Safety Management))の3事項で構成され、これらを統合する食品安全マネジメントシステムとしての運用が要求されている。
2、4 用語の解説(2)を参照
3 意図的な異物混入等から食品を守ること
5 平成30(2018)年10月にGFSI(世界食品安全イニシアティブ)により国際規格として承認
6 製造セクター以外の規格を含めた国内取得総件数は2,363件
(4)食品産業における環境問題等への対応
(厳しい納品期限等の商慣習の見直しを食品業界に要請)
食品ロスの削減に向けて、農林水産省は令和4(2022)年10月30日の「全国一斉商慣習見直しの日(*1)」に、食品小売事業者が賞味期間の3分の1を経過した商品の納品を受け付けない「3分の1ルール」の緩和や、食品製造事業者における賞味期限表示の大括り化(年月表示、日まとめ表示)の取組を呼び掛けました。
また、農林水産省では、食品ロスの削減を図るため、厳しい納品期限等の商慣習の見直しを食品業界に要請するなどの取組を抜本的に強化しています。
1 令和元(2019)年10月に施行された「食品ロスの削減の推進に関する法律」において、10月が「食品ロス削減月間」、10月30日が「食品ロス削減の日」と定められている。
(事業系食品ロス削減の取組を推進)
農林水産省は、みどり戦略(*1)の実現に向け、食品ロスの削減を進めており、商慣習の見直しのほか、食品製造事業者等による出荷量、気象等のデータやAIを活用した需給予測システム等の構築を推進しています。
また、国の災害用備蓄食品について、食品ロス削減や生活困窮者支援等の観点から有効に活用するため、更新により災害用備蓄食品としての役割を終えたものを、原則としてフードバンク(*2)団体等に提供することとしました。農林水産省が「国の災害用備蓄食品の提供ポータルサイト」を設け、各府省庁の情報を取りまとめて公表を行っています。
消費者への啓発については、食品ロス削減推進アンバサダーを起用した啓発ポスターの作成のほか、小売店舗が消費者に対して、商品棚の手前にある商品を選ぶ「てまえどり」を呼び掛ける取組を促進しています。「てまえどり」を行うことで、販売期限が過ぎて廃棄されることによる食品ロスを削減する効果が期待されます。
さらに、令和4(2022)年10月の「食品ロス削減月間」には、農林水産省公式YouTubeチャンネル「BUZZ MAFF(ばずまふ)」において、「てまえどり」を呼び掛ける動画を公開しました。同年12月には、「てまえどり」が「「現代用語の基礎知識」選 2022ユーキャン新語・流行語大賞」のトップ10に選出され、生活協同組合コープこうべ、神戸市(こうべし)、一般社団法人日本(にほん)フランチャイズチェーン協会(きょうかい)、消費者庁・環境省・農林水産省、農林水産省BUZZ MAFF撮影メンバーが受賞者となりました。
このほか、食品の売れ残りや食べ残しのほか、食品の製造過程において発生している食品廃棄物について、発生抑制と減量により最終的に処分される量を減少させるとともに、飼料や肥料等の原材料として再生利用するため、食品リサイクルの取組を促進しています。
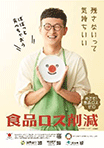
食品ロス削減を呼び掛けるポスター

「てまえどり」を呼び掛ける店頭掲示
資料:生活協同組合コープこうべ

新語・流行語大賞表彰式
資料:現代用語の基礎知識 選
「ユーキャン新語・流行語大賞」事務局
1 第2章第9節を参照
2 用語の解説(1)を参照
(事例)原料野菜の未利用部を飼料化する取組を推進(神奈川県)

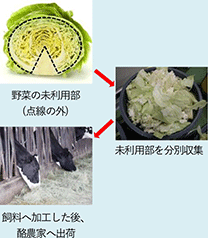
野菜未利用部の有効活用の流れ
資料:株式会社グリーンメッセージ
神奈川県大和市(やまとし)の株式会社グリーンメッセージでは、業務用向けカット野菜を製造する過程で生じる野菜の端材を「産業廃棄物」ではなく「未利用部」と位置付け、乳牛用飼料として再生利用する取組を進めています。
同社では、乳牛の飼料として使用できる野菜の未利用部が1日約1~2t発生しており、これらを分別収集し、粉砕・脱水した後、フレキシブルコンテナバッグの中で乳酸発酵を促し、長期保管可能な状態にして酪農家へ出荷しています。
同社では、主に国産野菜を使用しているため、飼料自給率の向上に寄与するとともに、未利用資源の有効活用や、酪農家への安価での安定供給といった面でも効果が見られています。
(プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律が施行)

バイオマスプラスチックを
原料としたカトラリー
資料:株式会社モスフードサービス
令和4(2022)年4月に施行された「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」に基づき、製品の設計からプラスチック廃棄物の処理までに関わるあらゆる主体におけるプラスチック資源循環等の取組を促進することとしています。製造事業者等においては環境配慮型の製品設計に努めること、フォーク、スプーン等の使い捨てプラスチック製品の提供事業者においては使用の合理化のための取組を行うこと、排出事業者においては可能な限りプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出抑制と再資源化を実施すること等が求められています。
(食品産業の持続的な発展に向けた取組を推進)
食品産業の持続的な発展のため、環境負荷を低減するとともに、人手不足に対応していく必要があり、サプライチェーン全体での持続可能性の確保や効率化・省力化が課題となっています。
また、環境、人権への関心が世界的に高まる中、機関投資家等は既に、ESG(*1)に積極的に取り組む企業に対する投資を優先しており、今後、我が国の食品産業が持続的な発展を図っていくためには、情報開示等を進め、ESG投資による資金を食品企業に円滑に引き込んでいくことが不可欠となっています。
農林水産省では、令和5(2023)年3月に「食品企業のためのサステナブル経営に関するガイダンス」を策定し、地域の中堅食品企業や中小企業も含めたサプライチェーン全体としてのESG課題への取組を推進しています。
1 用語の解説(2)を参照
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883











