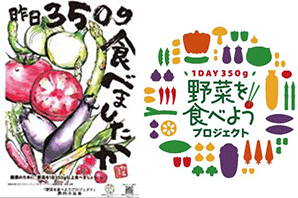第3節 新型コロナウイルス感染症の影響と食料消費の動向

我が国においては、高齢化や人口減少により食市場が縮小すると見込まれる一方、社会構造やライフスタイルの変化に伴い、食の外部化が進展すること等が見込まれています。こうした中、令和2(2020)年3月以降、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、食料消費の動向に大きな変化がもたらされており、令和4(2022)年においてもその影響は継続しています。
本節では、新型コロナウイルス感染症の影響のほか、食料消費や農産物・食品価格の動向、国産農林水産物の消費拡大の取組について紹介します。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響
(外食支出の減少が長期化)
家計における食料支出の状況を見ると、外食への支出は、令和2(2020)年3月以降、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の下で大きく減少しました。その後、感染の状況等に応じて回復と減少を繰り返し、令和4(2022)年においてもその影響が終息していないことがうかがわれます(図表1-3-1)。
(パブレストラン・居酒屋の売上回復に遅れ)
一般社団法人日本(にほん)フードサービス協会(きょうかい)の調査によれば、令和4(2022)年の外食産業全体の売上高は回復傾向にあり、令和元(2019)年同月比で見ると、90%前後で推移しました。一方、一部の業態、特にパブレストラン・居酒屋の売上高は、令和元(2019)年同月比で他の業態の売上高を大きく下回って推移しています(図表1-3-2)。新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、生活様式に変化が見られる中で、夜間に酒類を提供する業態においては、十分な宴会需要が戻っていないことがうかがわれます。
(一部の業務用需要の回復に遅れ)
新型コロナウイルス感染症の影響については社会的に落ち着きを取り戻しつつあるものの、夜の会食を控える傾向が依然として継続していることもあり、一部の農林水産物の需要回復が遅れています。
業務用仕向けの取扱いが多い東京都中央卸売市場(とうきょうとちゅうおうおろしうりしじょう)豊洲市場(とよすしじょう)の取引状況を見ると、令和4(2022)年の青果部門及び水産部門の卸売数量は新型コロナウイルス感染症の感染拡大以前の水準を下回って推移しています(図表1-3-3)。
(新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者への支援を実施)
新型コロナウイルス感染症による影響が継続している中、農林水産省では、これらの影響を受ける農林漁業者や食品事業者に対し、各般の支援措置を実施しました。
令和4(2022)年度においては、外食やインバウンドの需要減少の影響を受け、販路が減少した農林漁業者や加工業者等に対し、国産農林水産物等の新たな販路開拓の取組を支援したほか、学校給食やこども食堂等への食材として提供する際の食材調達費や輸送費等を支援しました。

新型コロナウイルス感染症
について(農林水産省)
URL:https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/index.html
また、新型コロナウイルス感染症の感染状況等を踏まえながら、感染拡大により甚大な影響を受けている飲食店の需要喚起に向けて、都道府県ごとのプレミアム付食事券の発行等を実施しました。
このほか、農林水産省では新型コロナウイルス感染症に関する特設ページにおいて、政府の感染防止対策、関係団体の感染防止に係るガイドライン、各種相談窓口・支援情報等の発信を行っています。
(2)食料消費の動向
(消費者世帯の食料消費支出は名目で増加、実質で減少)
消費者世帯(二人以上の世帯)における1人当たり1か月間の「食料」の支出額(以下「食料消費支出」という。)について、令和4(2022)年の名目での年間平均値は約2万7千円となり、前年に比べ3.0%上昇しました。一方、物価変動の影響を除いた実質(*1)での年間平均値は約2万5千円となり、前年に比べ1.4%減少しました。
また、同年における食料消費支出を前年同月比で見ると、実質ではおおむね前年を下回る状況が続いた一方、名目では前年を上回る状況が続きました(図表1-3-4)。食料価格の上昇により、食料消費支出が増加し、家計の負担感の増加につながっていることがうかがわれます。
1 令和4(2022)年各月の食料消費支出について、消費者物価指数(令和2(2020)年基準)を用いて物価の上昇・下落の影響を取り除き、年間の平均値を算出したもの
(食料品の価格上昇に直面する消費者の購買行動に変化)
生鮮食品を除く食料の消費者物価指数は、令和3(2021)年7月以降上昇傾向で推移し、令和5(2023)年2月には109.4まで上昇しました(*1)。
食料品は、購入頻度の高い品目が多く、消費者が生活の中でその価格変化に直面しやすい商品であることから、食料品の価格高騰が食料消費に大きな影響を及ぼすことが懸念されています。
公庫が令和4(2022)年7月に実施した調査によると、値上げを感じる生鮮・加工食品を購入する際の消費行動の変化について、「今まで通り購入」は、野菜(46.6%)、パン(43.4%)、調味料(42.2%)の順で高くなりました。一方、「購入量を減らす」は、菓子(35.1%)、果物(32.1%)の順で高くなりました(図表1-3-5)。
1 特集第1節を参照
(コラム)エシカル消費の関心が高まり
近年、地域の活性化や雇用等を含む、人、社会、地域、環境に配慮した消費行動である「エシカル消費」への関心が高まっています。
エシカル消費の主な取組としては、フェアトレードや寄附付きの食品、有機食品等の環境に配慮した農林水産物・食品、被災地産品等を購入することや、地産地消(*)を実践するといった消費活動を行うこと等が挙げられます。
消費者庁が令和4(2022)年度に実施した調査によると、エシカル消費について45.5%が「興味がある」(「非常に興味がある」又は「ある程度興味がある」)と回答し、半数近くがエシカル消費に興味を持っていることがうかがわれます。
また、エシカル消費に関連するマークのうち、食に関する認証マークの認知度については、「有機JASマーク」が36.2%、「フェアトレード」が19.8%となっています。今後は、環境に配慮した農林水産物・食品等の判断材料となる認証マークを活用した普及啓発等、エシカル消費を実践する人を増やすための一層の働き掛けが重要となっています。
用語の解説(1)を参照
(3)農産物・食品価格の動向
(国産牛肉・豚肉の小売価格はやや上昇、鶏肉・鶏卵の小売価格は上昇傾向で推移)
令和4(2022)年度における国産牛肉、豚肉の小売価格は、飼料価格やエネルギー価格の高騰等に伴い、やや上昇傾向で推移している一方、生産コストの上昇分が十分に価格転嫁できていない状況も見られています(図表1-3-6)。
また、輸入牛肉の小売価格は、豪州の干ばつや新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等による生産量の減少から国際相場が上昇したことに加え、令和4(2022)年以降の円安の影響もあいまって、上昇傾向で推移しています。
また、鶏肉、鶏卵の小売価格は、飼料価格の高騰等による生産コストの上昇に加え、鶏肉においては、輸入鶏肉の価格上昇に伴う代替需要の増加、鶏卵においては高病原性鳥インフルエンザ(*1)の影響による生産減により、上昇傾向で推移しています(図表1-3-7)。
鶏卵の供給については、消費者向けの鶏卵で、地域によって購入制限を設ける事例や、夕方には品薄になるといった事例があるほか、加工向けの鶏卵に不足が見られ、一部の食品企業では、卵の使用量の削減や卵を使用した商品の販売中止を行うなど、高病原性鳥インフルエンザの高頻度での発生が食料消費の動向にも影響を及ぼしています。
1 トピックス4を参照
(米の相対取引価格は前年産より上昇、野菜の小売価格は品目ごとの供給動向に応じ変動)
令和4(2022)年産米の令和5(2023)年3月までの相対取引価格は、民間在庫が減少したこと等から年産平均で60kg当たり1万3,865円となり、前年産に比べ8.3%上昇しました(図表1-3-8)。
また、野菜は天候によって作柄が変動しやすく、短期的には価格が大幅に変動する傾向があります。令和4(2022)年においては、にんじんは主産地における8月の降雨の影響により出荷量が減少し、9~11月に小売価格は平年と比べて上昇しました(図表1-3-9)。一方、キャベツは主産地における7月以降の適温・適雨により出荷量が増加し、8~9月にかけて小売価格は平年と比べて低下しました。たまねぎについては、令和3(2021)年夏季の北海道における干ばつの影響により出荷量が減少し、同年9月以降小売価格は平年と比べて上昇し、令和4(2022)年5月にピークを迎えましたが、供給が回復するにつれて、徐々に落ち着きを取り戻しました。
(食パン・食用油の小売価格は上昇傾向で推移)
穀物等の国際価格の上昇により、輸入原料を用いた加工食品の小売価格は上昇傾向で推移しています(図表1-3-10)。
食パンの小売価格は、原材料やエネルギーの価格等が上昇したことから、令和4(2022)年1月以降上昇傾向で推移し、同年12月には521円/kgとなり、前年同月比で14.0%上昇しました。また、食用油(サラダ油)の小売価格は、世界的に旺盛な食用油需要や原料主産国の天候不順等による需給逼迫(ひっぱく)に加え、ウクライナ情勢等による油脂原料等の供給不安を背景として令和3(2021)年以降上昇傾向で推移し、令和4(2022)年12月には502円/kgとなり、前年同月比で32.1%上昇しました。このほか、豆腐の小売価格は、原料大豆や包材、燃料等の価格上昇を受け、一部の小売事業者において価格転嫁が進んだことから、令和3(2021)年以降微増傾向で推移し、令和5(2023)年3月には254円/kgとなり、前年同月比で8.1%上昇しました。
(4)国産農林水産物の消費拡大
(食に関して「できるだけ日本産の商品であること」を重視する消費者の割合が高い)
令和5(2023)年3月に公表した調査によれば、食に関して重視していることは、「できるだけ日本産の商品であること」と回答した人が約4割で最も高く、「同じような商品であればできるだけ価格が安いこと」を上回りました。「できるだけ日本産の商品であること」は、男女とも年代差が大きく、高齢層で高く若年層で低くなる傾向が見られました(図表1-3-11)。
(米の消費拡大に向けた取組を推進)
米(*1)の1人当たりの年間消費量は、食生活の変化等により、昭和37(1962)年度の118.3kgをピークとして減少傾向が続いています。令和3(2021)年度は、中食(*2)・外食需要の回復等により、前年度の50.8kgと比べて0.7kg増加し51.5kgとなりました(図表1-3-12)。
米の1人当たりの年間消費量については、平成30(2018)年度以降も毎年度一定程度減少することを見込みつつ、消費拡大の取組を通じて令和12(2030)年度には51.0kgと消費量の減少傾向に歯止めをかけることを目標としています。
農林水産省では、消費拡大のため、Webサイト「やっぱりごはんでしょ!」運動や、農林水産省の職員がYouTuberとして情報発信する「BUZZ MAFF(ばずまふ)」における農林水産大臣や芸能人が出演する動画の投稿等、米消費を喚起する取組を実施しています。さらに、「米と健康」に着目した「ごはんで健康シンポジウム」を令和4(2022)年12月に開催するなどの取組を行っています。
また、米の消費の形態については、パックご飯や米粉等の、これまでと異なる形態での消費が進んでいます。
1 主食用米のほか、菓子用・米粉用の米
2 用語の解説(1)を参照
(野菜の消費拡大に向け「野菜を食べようプロジェクト」を展開)
野菜の1人当たりの年間消費量は、食生活の変化等により減少傾向で推移しており、令和3(2021)年度は85.7kgとなりました(図表1-3-13)。農林水産省では、野菜の消費拡大を推進する「野菜を食べようプロジェクト」を展開しており、1日当たりの摂取目標(350g)を示したポスターとロゴマークを作成・公表するとともに、栄養価の高い旬の時期等の野菜に関する情報発信や、賛同企業・団体等の「野菜サポーター」と共に野菜の消費拡大に取り組んでいます。
(砂糖の需要拡大に向け「ありが糖運動」を展開)
砂糖の消費量は、近年減少傾向で推移していましたが、経済活動の回復等もあり、令和3(2021)砂糖年度は前砂糖年度に比べ3万6千t増加し174万6千tとなりました(図表1-3-14)。農林水産省では、加糖調製品から国内で製造された砂糖への置換えを促すための商品開発等への支援を行うとともに、砂糖関連業界等による取組と連携しながら、砂糖の需要、消費の拡大を図る「ありが糖運動」を展開しており、WebサイトやSNSも活用しながら、情報発信を行っています。
(「牛乳でスマイルプロジェクト」を開始)
牛乳乳製品の1人当たりの年間消費量は、チーズの消費量増加に伴い過去10年で約7%増加していますが、令和3(2021)年度は前年度と同じ94.4kgとなりました(図表1-3-15)。
令和4(2022)年6月、農林水産省は、一般社団法人Jミルクと共に、「牛乳でスマイルプロジェクト」を立ち上げました。同プロジェクトは、酪農・乳業関係者のみならず、企業・団体や地方公共団体等の幅広い参加者と共に、共通ロゴマークにより一体感を持って、更なる牛乳乳製品の消費拡大に取り組むことを目的としています。令和4(2022)年度においては、参加者同士のコラボレーションを促すための交流会の開催等の取組を実施しています。
(花きの利用拡大に向け「花いっぱいプロジェクト」を展開)
切り花の1世帯当たりの年間購入額は減少傾向で推移していましたが、令和4(2022)年は前年より93円上昇し7,992円となりました(図表1-3-16)。農林水産省では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によるイベントの中止・縮小等により、業務用を中心に需要が減少した花きの利用拡大や、令和9(2027)年に神奈川県横浜市(よこはまし)で開催される2027年国際園芸博覧会を契機とした需要拡大を図るため、「花いっぱいプロジェクト」を展開しています。同プロジェクトでは、花きの暮らしへの取り入れ方や同博覧会に関する情報発信等、花や観葉植物をより身近に感じてもらうための広報活動等を進めています。

花いっぱいプロジェクト
URL:https://www.maff.go.jp/j/seisan/kaki/flower/hanaippai2022/
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883