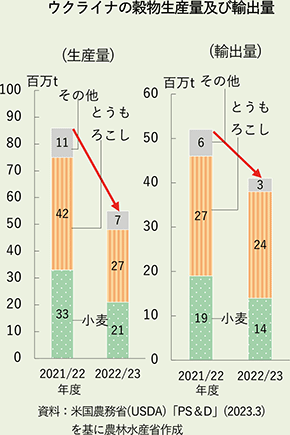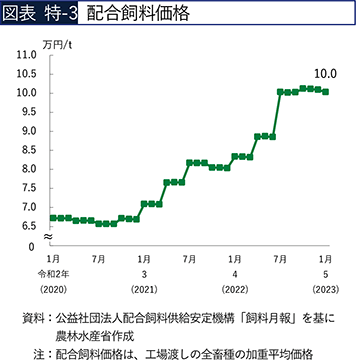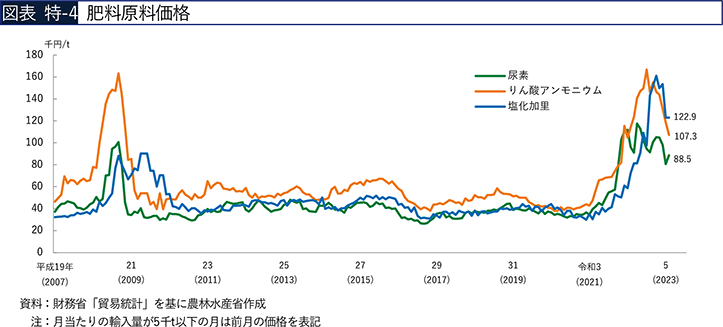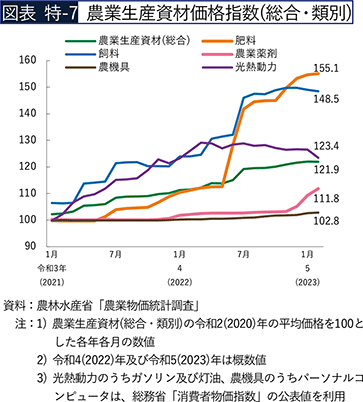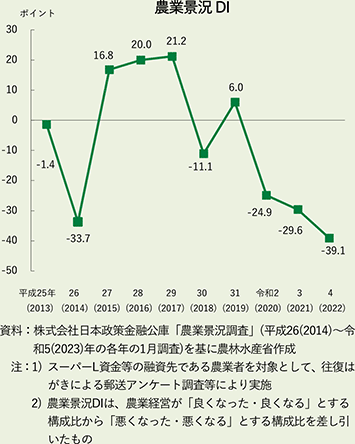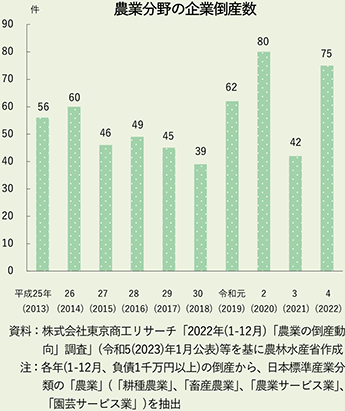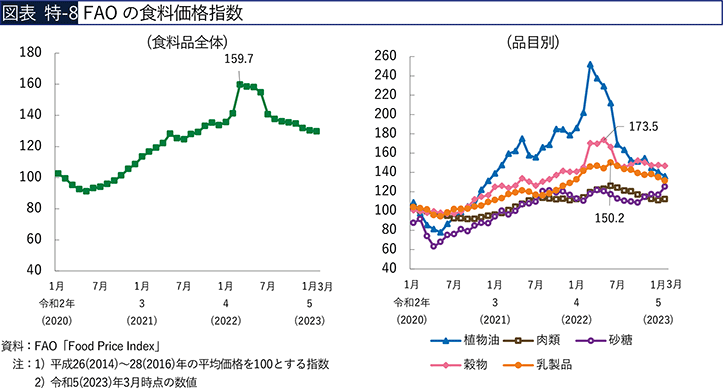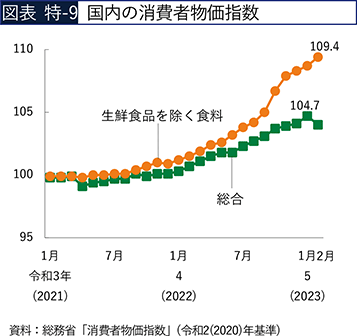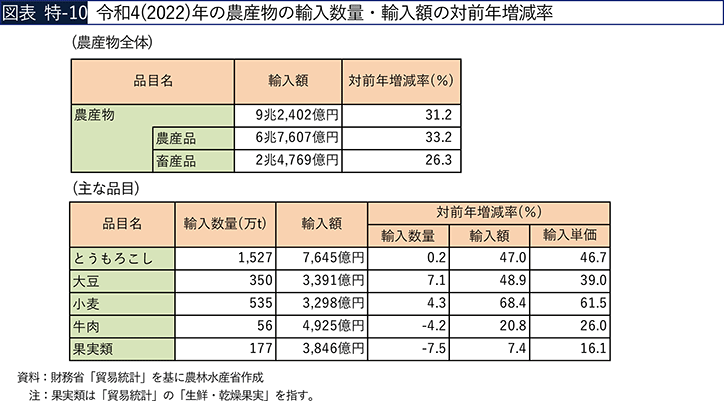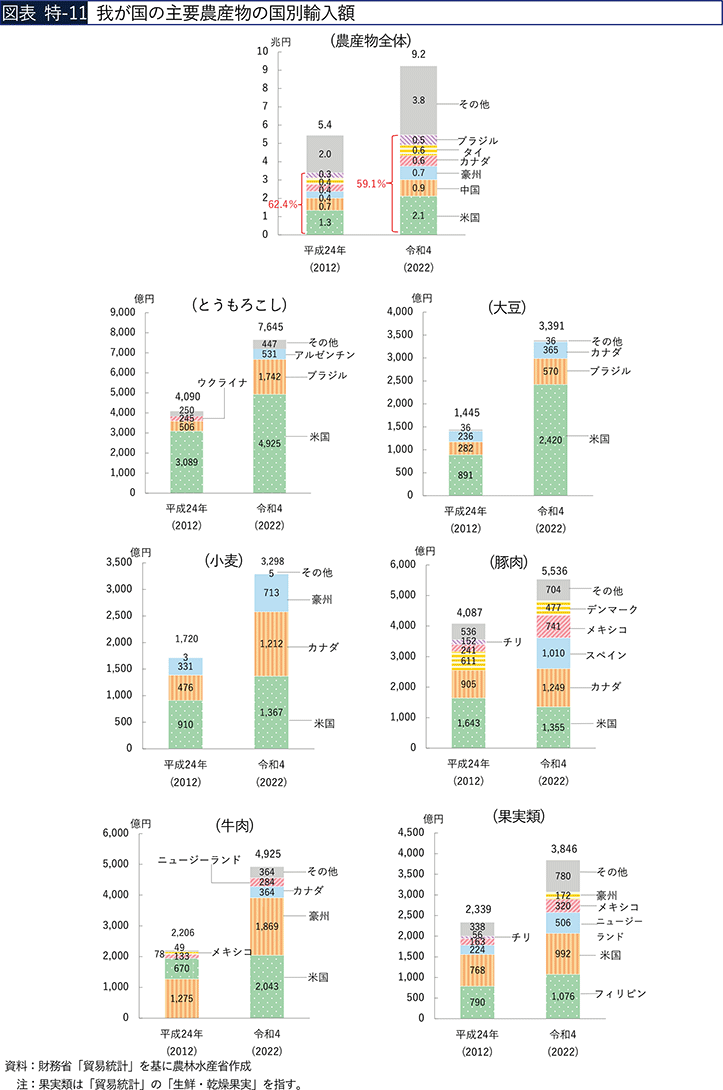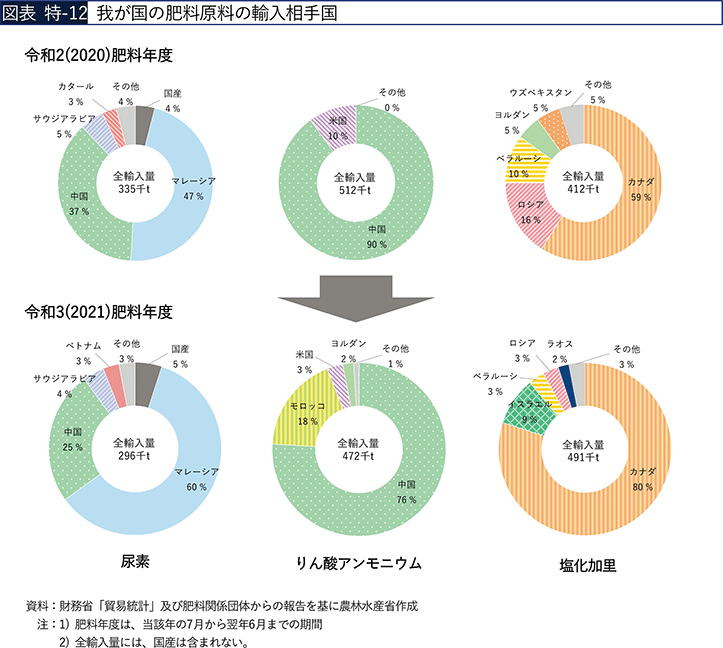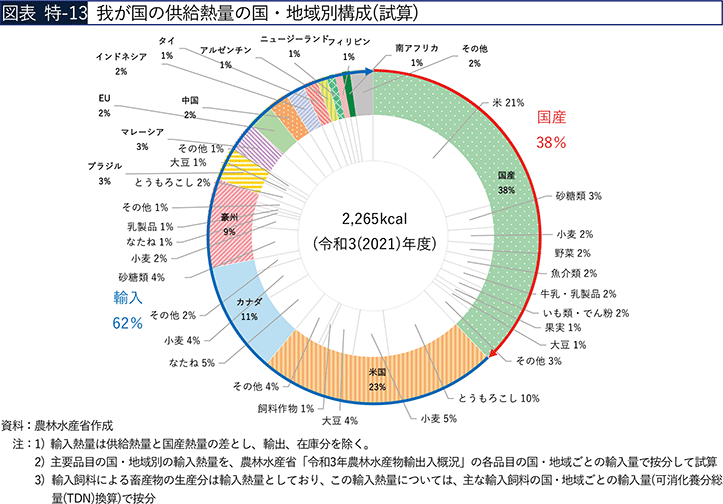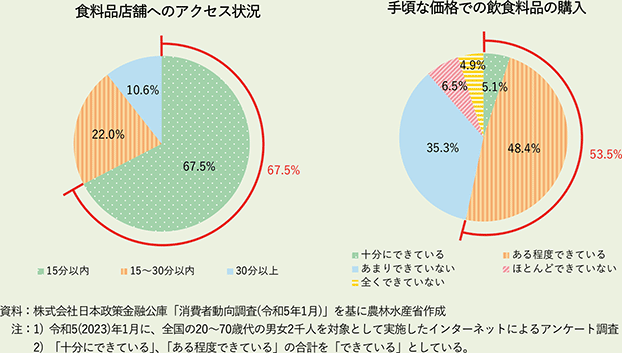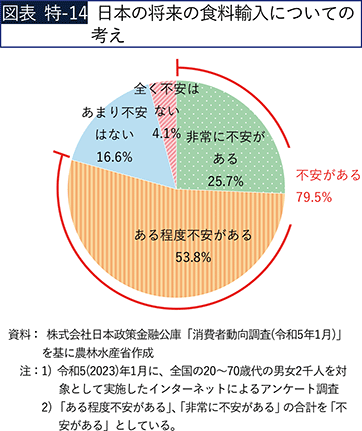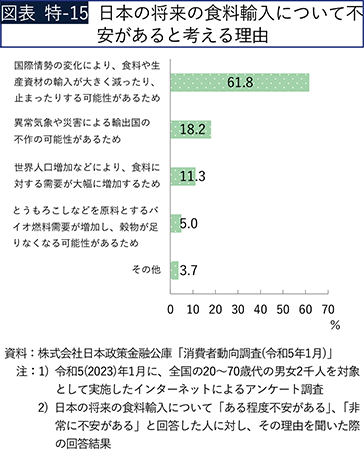第1節 世界的な食料情勢の変化による食料安全保障上のリスクの高まり
(1)食料品や農業生産資材の価格高騰
(世界の食料需給等をめぐるリスクが顕在化)
世界の食料需給については、世界的な人口増加や、新興国の経済成長等により食料需要の増加が見込まれる中、地球温暖化等の気候変動の進行による農産物の生産可能地域の変化や異常気象による大規模な不作等が食料供給に影響を及ぼす可能性があり、中長期的には逼迫(ひっぱく)が懸念されます。
さらに、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴うサプライチェーン(供給網)の混乱に加え、令和4(2022)年2月のロシアによるウクライナ侵略等により、小麦やとうもろこし等の農作物だけでなく、農業生産に必要な原油や肥料等の農業生産資材についても、価格高騰や原料供給国からの輸出の停滞等の安定供給を脅かす事態が生じるなど、我が国の食料をめぐる国内外の状況は刻々と変化しており、食料安全保障上のリスクが増大しています(図表 特-1)。
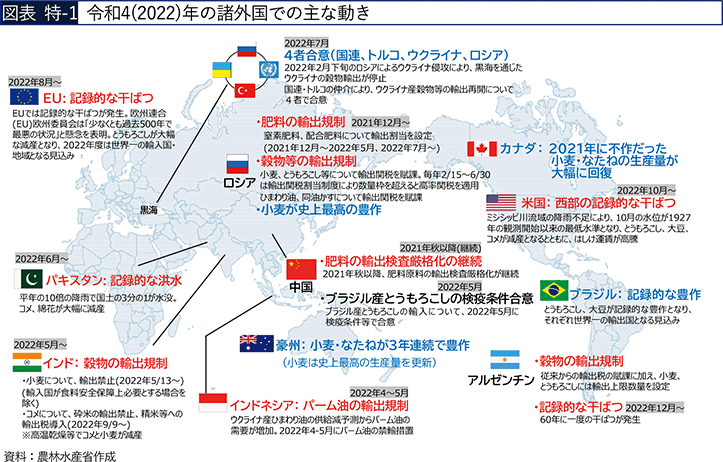
(フォーカス)ウクライナの穀物生産量は、著しく減少する見通し
令和5(2023)年3月に米国農務省(USDA)が公表した資料によれば、ウクライナの2022/23年度における小麦生産量は、ロシアによる侵略の影響を受け、前年度比36%減少の2,100万tの見通しとなっており、輸出量は前年度比28%減少の1,350万tの見通しとなっています。また、2022/23年度におけるとうもろこし生産量は前年度比36%減少の2,700万tの見通しとなっており、輸出量は前年度比13%減少の2,350万tの見通しとなっています。
ウクライナ農業政策食料省による令和5(2023)年3月21日時点の予測によれば、冬小麦の作付けがロシアによるウクライナ侵略前であった2022/23年度と比較して減少したこと等から、2023/24年度の穀物・豆類の作付面積は、141万ha減少の1,024万haの見込みとなっています。
さらに、同省の令和5(2023)年3月21日時点の予測によれば、2023/24年度の穀物・豆類の生産量は、4,430万t(2022/23年度5,310万t)となる見通しとなっています。
我が国ではウクライナから穀物をほとんど輸入していませんが、今後ともウクライナ情勢が国際穀物貿易や価格に与える影響等について注視していく必要があります。
(小麦の国際価格は高水準で推移)
穀物等の国際価格は、新興国の畜産物消費の増加等を背景とした需要やバイオ燃料等のエネルギー向け需要(*1)の増大、地球規模の気候変動の影響等により、近年上昇傾向で推移しています。令和3(2021)年以降、小麦の国際価格は、主要輸出国である米国やカナダでの高温乾燥による不作や中国における飼料需要の拡大に加え、ロシアによるウクライナ侵略が重なったことから、高水準で推移しています。令和4(2022)年3月には、前年同月の240.3ドル/tに比べ2倍以上上昇し過去最高値となる523.7ドル/tに達しました。令和5(2023)年1月以降はおおむねウクライナ侵略前の水準まで低下したものの、引き続き高い水準で推移しています(図表 特-2)。また、とうもろこし、大豆の国際価格については平成24(2012)年の過去最高値に迫る高い水準で推移しています。
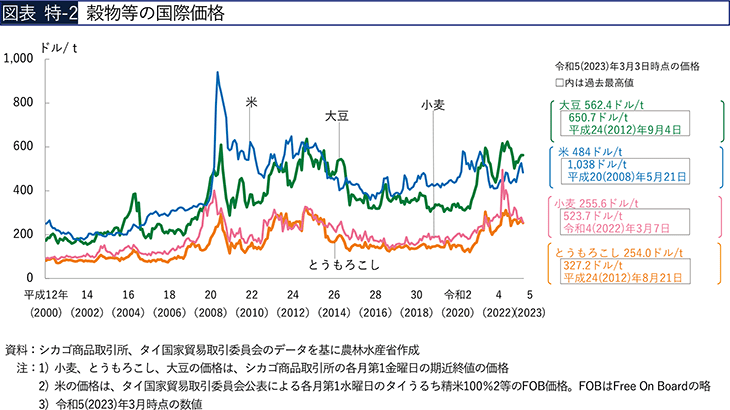
*1 第1章第2節を参照
(配合飼料価格は約2割上昇)
家畜の餌となる配合飼料は、その原料使用量のうち約5割がとうもろこし、約1割が大豆油かすとなっています。我が国は原料の大部分を輸入に頼っていることから、穀物等の国際相場の変動に価格が左右されます。とうもろこしの国際相場は、バイオエタノール向け需要の拡大や主産国における生産動向等を背景に、高い水準で推移しています。令和2(2020)年9月以降、米国産とうもろこしの中国向け輸出成約の増加や、ロシアによるウクライナ侵略等を受け、とうもろこしの国際価格は上昇しており、為替相場の影響等の要因も重なり、配合飼料の工場渡価格は、令和5(2023)年1月には10万円/tと、前年同月の8万3千円/tと比べ20%上昇しています(図表 特-3)。
(肥料原料価格は一時過去最高に達するなど価格が大きく変動)
肥料原料の輸入価格は、令和3(2021)年以降上昇傾向にある中で、ロシアによるウクライナ侵略や為替相場の影響等の要因も重なり、一時は過去最高に達するなど価格が大きく変動しています(図表 特-4)。
こうした中、我が国においては平成20(2008)年の価格高騰時に講じた対策も参考に、化学肥料使用量の低減に向けた取組を行う農業者に対する肥料費を支援する対策を講ずるとともに、肥料原料の備蓄や国内資源の肥料利用の拡大等の肥料の安定供給に向けた対策を講ずるなど、国際情勢の変化に伴う影響への対応を図っていくことが求められています。
(原油価格の上昇や円安の進行が影響)
原油価格は、ロシアによるウクライナ侵略直後に大きく上昇しました。令和4(2022)年3月には123.7ドル/バレルに達し、前年同月の62.4ドル/バレルと比べ98.2%上昇しました。令和4(2022)年度は下落傾向にあるものの、高い水準で不安定に推移しています(図表 特-5)。
また、為替相場は、令和3(2021)年秋以降、円安方向に推移し、令和4(2022)年10月には1ドル150円台まで下落するなど、円安の急速な進行が見られました(図表 特-6)。
原油価格の上昇や円安の進行は、石油関連製品の値上げとともに、海上輸送運賃や包装資材価格の値上げによる食料品価格の値上げといった形で国民生活に様々な影響を及ぼすほか、農業生産資材価格の上昇を招き、農業経営にも影響を与えています。
(国内における農業生産資材価格が上昇)
世界的な穀物需要の増加、エネルギーや肥料原料の価格上昇、為替相場の影響等の要因が重なり、我が国の農業生産資材価格は上昇しています。
農業生産資材価格指数は、令和3(2021)年以降上昇傾向で推移しており、令和5(2023)年2月には、前年同月比で肥料が39.5%上昇、飼料が19.8%上昇しています(図表 特-7)。
農業生産資材価格の上昇は、農業経営にも影響を及ぼしており、ウクライナ情勢等も踏まえ、今後も価格動向を注視していく必要があります。
(フォーカス)令和4(2022)年の農業景況DIは調査開始以来の最低値
株式会社日本政策金融公庫(にっぽんせいさくきんゆうこうこ)(以下「公庫」という。)が令和5(2023)年1月に実施した調査によれば、令和4(2022)年における農業全体の農業景況DIは前年から9.5ポイント低下しマイナス39.1ポイントとなり、平成8(1996)年の調査開始以来の最低値となりました。
また、株式会社東京商工(とうきょうしょうこう)リサーチが令和5(2023)年1月に公表した調査によれば、令和4(2022)年における農業分野の企業倒産は75件となり、過去10年間で2番目に高い水準となりました。
輸入原料や肥料、飼料、燃油等の生産資材の国際価格の高騰に加え、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による外食やインバウンドの需要減少の影響、高病原性鳥インフルエンザ(*1)や豚熱(*2)(ぶたねつ)等の家畜伝染病の発生等が重なり、農業経営が厳しい状況下にあることがうかがわれます。
*1、2 用語の解説(1)を参照
(世界的に食料価格が上昇)
穀物等の国際価格の上昇の影響を受け、FAO(国際連合食糧農業機関)が公表している食料価格指数(*1)は、令和4(2022)年3月に食料品全体で159.7に達し、平成2(1990)年の統計公表以来最高値を記録しました(図表 特-8)。
品目別では、穀物の価格指数については、小麦やとうもろこし等の国際価格の上昇を反映し、令和4(2022)年5月に173.5と平成2(1990)年の統計公表以来最高値を記録しました。また、乳製品の価格指数については、欧州やオセアニアにおける供給減等により、令和4(2022)年6月に150.2と前年同月比で25.2%上昇しました。
その後価格指数は低下傾向にありますが、穀物等の国際相場は、ロシアによるウクライナ侵略等を背景に、高水準で推移しています。
*1 国際市場における五つの主要食料(穀物、肉類、乳製品、植物油及び砂糖)の国際価格から計算される世界の食料価格の指標
(国内における消費者物価も上昇)
世界的な食料価格の上昇に加え、原油価格の上昇や為替相場の影響、さらには、世界的なコンテナ不足、海上運賃の上昇、ロシアによるウクライナ侵略等、グローバル・サプライチェーン(供給網)の各段階における様々な要因が重なり、我が国の穀物等の輸入価格は上昇しています。
こうした中、我が国の消費者物価指数は上昇基調で推移しており、総合の消費者物価指数は令和5(2023)年1月に104.7となっています。また、生鮮食品を除く食料の消費者物価指数は、同年2月に109.4となり、前年同月比で7.8%上昇しました(図表 特-9)。
(2)食料の安定供給に影響を及ぼすリスクの高まり
(農産物の輸入額は前年に比べ3割増加)
令和4(2022)年の我が国の農産物輸入額は、前年に比べ31.2%増加し約9兆2千億円となりました。このうち、農産品は33.2%増加し約6兆8千億円、畜産品は26.3%増加し約2兆5千億円となりました(図表 特-10)。
この要因としては、世界的な価格の上昇に加え、為替相場が円安方向で推移したことにより、円ベースで輸入価格の上昇につながったことが大きいものと考えられます。特にとうもろこし、大豆、小麦の輸入量については、前年と比べ大きな変動が見られない中で、輸入額はそれぞれ47.0%、48.9%、68.4%上昇し、いずれも過去10年間で最大の値となりました。また、牛肉や果実類は、輸入単価が上昇する中で、輸入量は前年と比べ、それぞれ4.2%、7.5%の減少となりました。輸入農産物の単価上昇は国産農産物の需要拡大の好機ともなり得る中、国内産地の生産基盤の強化を図り、国産農産物の供給拡大を図っていくことが重要となっています。
(我が国の主要農産物の輸入構造は少数の特定国に依存)
令和4(2022)年の我が国の農産物輸入額を国別に見ると、米国が2兆1千億円で最も高く、次いで中国、豪州、カナダ、タイ、ブラジルの順で続いており、上位6か国が占める輸入割合は6割程度となっています(図表 特-11)。
品目別に見ると、とうもろこし、大豆、小麦、牛肉の輸入は、特定国への依存傾向が顕著となっており、上位2か国で8~9割を占めています。小麦については、米国、カナダ、豪州の上位3か国に99.8%を依存している状況です。
一方、豚肉、果実類は、令和4(2022)年の上位2か国からの輸入割合が5割程度であり、平成24(2012)年と比べ、豚肉はカナダ、スペイン、メキシコ等からの輸入割合が、果実類はニュージーランド、メキシコ、豪州等からの輸入割合が上昇しています。
このように、一部の品目では輸入先の多角化が進みつつあるものの、我が国の農産物の輸入構造は、依然として米国を始めとした少数の特定国への依存度が高いという特徴があります。
海外からの輸入に依存している主要農産物の安定供給を確保するためには、輸入相手国との良好な関係の維持・強化や関連情報の収集等を通じて、輸入の安定化や多角化を更に図ることが重要です。一方、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化や、ウクライナ情勢等を踏まえると、国内の農業生産の増大に向けた取組がますます重要となっています。
(肥料原料も輸入に大きく依存)
我が国は、化学肥料原料の大部分を輸入に依存しています。主要な肥料原料の資源が世界的に偏在している中で、りん酸アンモニウムや塩化加里はほぼ全量を、尿素は95%を、限られた相手国から輸入しています。輸出国側の輸出制限や国際価格の影響を受けやすいことから、輸入の安定化・多角化や輸入原料から国内資源への代替を進める必要があります(図表 特-12)。
令和3(2021)年秋以降、中国による肥料原料の輸出検査の厳格化や、ロシアによるウクライナ侵略の影響により、我が国の肥料原料の輸入が停滞したことを受け、りん酸アンモニウムではモロッコの割合が上昇するなど、代替国から調達する動きが見られます。
(国産と輸入先上位4か国による食料供給の割合は約8割)

食料の安定供給に関するリスク検証(2022)
URL:https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/anpo/risk_2022.html
農林水産省では、令和4(2022)年2月に「食料安全保障に関する省内検討チーム」を立ち上げ、将来にわたって我が国の食料安全保障を確立するために必要な施策の検討に資するよう、食料の安定供給に影響を及ぼす可能性のある様々な要因(リスク)を洗い出し、包括的な検証を行った上で、同年6月に「食料の安定供給に関するリスク検証(2022)」を公表しました。
我が国の食料供給は、国産と輸入先上位4か国(米国、カナダ、豪州、ブラジル)で、供給熱量(*1)の約8割を占めている中、今後の食料供給の安定性を維持していくためには、これらの輸入品目の国産への置換えを着実に進めるとともに、主要輸入先国との安定的な関係を維持していくことも必要となっています(図表 特-13)。
また、このリスク検証では、対象品目ごとに、分析・評価の対象リスクについて、その「起こりやすさ」と「影響度」の分析を行い、その結果を基に、起こりやすさを5段階、影響度を3段階で評価し、「重要なリスク」、「注意すべきリスク」を特定しました。
その結果、輸入については、価格高騰のリスクは、輸入割合の高い主要な品目のうち、とうもろこし等の飼料穀物等では顕在化しつつあり、「重要なリスク」と評価しました。また、小麦、大豆、なたねでは、その起こりやすさは中程度であるが、その影響度が大きく、「重要なリスク」と評価しました。
国内生産については、労働力・後継者不足のリスクが、特に労働集約的な品目(果実、野菜、畜産物等)を中心にその起こりやすさが高まっているか、顕在化しており、「重要なリスク」と評価しました。また、関係人材・施設の減少リスクは多くの品目で顕在化しつつあり、「注意すべきリスク」と評価しました。
輸入依存度の高い生産資材のうち、燃料の価格高騰等のリスクについては、その起こりやすさが高まっており、燃料費の割合が高い品目(野菜、水産物等)では「重要なリスク」と評価しました。肥料の価格高騰等のリスクについては、肥料は農産物の生産に必須で、その影響度は大きく、ほとんどの品目で「重要なリスク」と評価しました。
温暖化や高温化のリスクは、ほとんどの品目で顕在化しつつあり、「注意すべきリスク」等と評価しました。
家畜伝染病のリスクについては、水際対策の強化を図っているものの、口蹄疫(こうていえき)やアフリカ豚熱(ぶたねつ)(*2)が近隣諸国で継続的に発生しており、その起こりやすさが高まっていることに加え、発生した場合の影響度が大きいため、「重要なリスク」と評価しました。
*1、2 用語の解説(1)を参照
(食品アクセスの確保に向けた課題への対応が必要)
我が国において、消費者が健康な生活を送るために必要な食品を入手できない、いわゆる「食品アクセス(*1)」の問題への対応が重要な課題となっています。
人口減少・高齢化等により、小売業や物流の採算がとれない地域が発生しており、人口減少・高齢化が進行する地域を中心に、食品を簡単に購入できない、いわゆる「買い物困難者」等が発生しています。さらに、トラックを含む自動車運送業に係るいわゆる「物流の2024年問題(*2)」によって物流コストの増加は不可避であり、問題はより深刻化することも考えられます。
また、我が国の経済成長が停滞する中で、個人の所得も伸び悩み、低所得者層が増加しています。家計の経済的事情や家族を取り巻く状況変化が、十分かつ健康的な食生活の実現に負の影響をもたらすといった問題も発生しています。
このため、関係省庁等と連携し、円滑な食品アクセスを確保するため、産地から消費地までの幹線物流の効率化や、消費地における地域内物流の強化等、食品流通上の課題への対応を強化していくほか、地域ごとに、様々な食品アクセスに関する課題や実態を把握するとともに食に関する関係者が連携する体制の構築を支援することが重要となっています。また、国民の健康な食生活を確保する立場から食品関連事業者やフードバンク(*3)等の役割を明確にするとともに、フードバンクやこども食堂(*4)等の活動の支援を強化することも必要となっています。
*1 トピックス6を参照
2 第1章第4節を参照
*3 用語の解説(1)を参照
*4 第1章第6節を参照
(フォーカス)食料店舗へのアクセス等が十分でない者も一定数存在
家庭段階における食料安全保障の確保に向けては、食料店舗へのアクセスや合理的な価格での食料購入が重要となります。
公庫が令和5(2023)年1月に実施した調査によれば、食料店舗へのアクセスについて、「公共交通手段の利用又は徒歩により、15分以内で食料店舗にアクセスすることができる」と回答した人は67.5%となっている一方、「15分以内ではできない」と回答した人は32.6%となっています。
また、同調査によれば、健康的な食事のため、飲食料品を手頃な価格で購入できているかどうかについて、「できている」と回答した人は53.5%となっている一方、「できていない」と回答した人は46.7%となっています。我が国においては、平常時においても家庭レベルでの食品アクセスの確保に課題があることがうかがわれます。
なお、英国が令和3(2021)年に公表した食料安全保障報告書(*)によれば、2019年においては、イングランドの住民の少なくとも84%は公共交通手段の利用又は徒歩により、15分以内に食料店舗にアクセスすることが可能と回答しています。
また、2019/20年度における英国の家庭世帯の92%が、健康で栄養のある食料に、入手可能である合理的な価格で十分にアクセスできると感じ、自らの世帯における食料が保障されていると回答しています。
社会経済システム等諸条件の異なる英国と、我が国の置かれた状況を一概に比較することはできませんが、我が国においても食品アクセスの確保に向けた対応を図っていくことが求められています。
* 正式名称は「UK Food Security Report 2021」
(将来の食料輸入に不安を持つ消費者の割合は約8割)
将来の食料輸入に対する消費者の意識について、公庫が令和5(2023)年1月に実施した調査によると、79.5%の人が日本の将来の食料輸入に「不安がある」と回答しました(図表 特-14)。また、日本の将来の食料輸入について「不安がある」と回答した人にその理由を聞いたところ、「国際情勢の変化により、食料や生産資材の輸入が大きく減ったり、止まったりする可能性があるため」と回答した人が61.8%と最も高くなりました(図表 特-15)。世界的な食料需要の増加や国際情勢の不安定化等に伴う食料安全保障上のリスクが高まる中、将来にわたって食料を安定的に確保していくことが求められています。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883