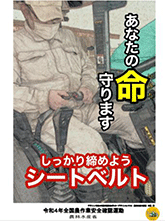第7節 需要構造等の変化に対応した生産基盤の強化と流通・加工構造の合理化

我が国では、各地の気候や土壌等の条件に応じて、様々な農畜産物が生産されています。消費者ニーズや海外市場、加工・業務用等の新たな需要に対応し、国内外の市場を獲得していくためには、需要構造等の変化に対応した生産供給体制の構築を図ることが重要です。
本節では、各品目の生産基盤の強化や労働安全性の向上等の取組について紹介します。
(1)畜産・酪農の生産基盤強化等の競争力強化
(酪農経営に関し、需給両面から需給ギャップの早期解消を推進)
我が国の酪農経営については、ロシアによるウクライナ侵略や為替相場等の影響による飼料費等の高騰等により、深刻な影響が及んでいます。
一般社団法人中央酪農会議(ちゅうおうらくのうかいぎ)が令和5(2023)年3月に公表した調査によれば、指定生乳生産者団体の受託農家戸数は、令和4(2022)年以降、特に都府県において例年と比べて減少率が拡大しており、令和5(2023)年2月には前年同月比で8.6%の減少となるなど、離農が進んでいる状況にあります(図表2-7-1)。
このため、農林水産省では、酪農経営について、配合飼料の高騰対策に加えて、国産粗飼料の利用拡大等に継続して取り組む酪農経営に対し、購入する粗飼料等のコスト上昇分の一部に対する補塡金の交付や、金融支援等、飼料価格の高騰の影響緩和対策を推進しています。
また、生乳の需給状況については、新型コロナウイルス感染症の影響等により牛乳乳製品の需要が低迷し、令和4(2022)年12月時点で脱脂粉乳の在庫量が8万2千tとなっています(図表2-7-2)。40万t以上とも言われる生乳の需給ギャップが生じており、その解消が緊急の課題となっています。このため、生産者団体においては、厳しい生乳需給の状況を踏まえ、苦渋の決断で自主的に抑制的な生産に取り組んでいます。
農林水産省では、需給ギャップを早期に解消し、生産コストの上昇を適正に価格に反映できる環境を整え、酪農経営の改善を図っていくことが重要との認識の下、生産者が早期に乳用経産牛をリタイアさせ、生乳の生産抑制を図る取組を後押しするとともに、生産者や乳業者が協調して行う乳製品在庫の低減に向けた取組を支援しています。
くわえて、酪農乳業界の枠を超えた取組である「牛乳でスマイルプロジェクト」等、消費拡大や販路開拓の取組等を推進しています。さらに、新規需要を開拓するため、訪日外国人観光客やこども食堂等に対し、牛乳を安価に提供する活動等を緊急的に支援することとしました。このほか、幅広い関係者から成る協議会を設置し、国民の理解と協力の下で飼料コストの増加分等を販売価格に反映しやすくするための環境整備を図ることとしています。
なお、令和3(2021)年度の総合乳価(全国)は103.5円/kgとなっており、さらに、生産者団体と乳業メーカーの乳価交渉により、令和4(2022)年11月から牛乳等向け乳価が10円/kg(税抜き)引き上げられ、また、令和5(2023)年4月から乳製品向け乳価が10円/kg(税抜き)引き上げられることとなっています(図表2-7-3)。
(地域における畜産の収益性向上を図る取組を推進)
農林水産省では、国内外の需要に応じた畜産物の生産を進めるため、キャトルブリーディングステーション(CBS)(*1)、キャトルステーション(CS)(*2)の活用による肉用繁殖牛の増頭のほか、ICT等の新技術を活用した発情発見装置や分べん監視装置等の機械装置の導入等による生産基盤強化、衛生管理の改善、家畜改良や飼養管理技術の向上等を推進しています。
また、畜産農家を始め地域の関係者が連携し、地域の畜産の収益性向上を図る畜産クラスターの取組を推進しています。収益性向上のための実証のほか、中心的な経営体の施設整備や機械導入、経営継承の支援等、畜種を問わず、様々な取組が実施されています。
さらに、畜産農家・食肉処理施設・食肉流通事業者がコンソーシアムを形成し、国産食肉の生産・流通体制の高度化や輸出拡大を図る取組のほか、国内外の多様化する消費者ニーズに対応するための精肉加工施設の整備等を支援することにより、産地の生産供給体制や収益力の強化を推進しています。
1 繁殖雌牛の分べん・種付けや子牛の哺育・育成を集約的に行う施設
2 繁殖経営で生産された子牛の哺育・育成を集約的に行う施設
(持続可能な畜産物生産のための取組を推進)
近年、世界的に農林水産分野における環境負荷軽減の取組が加速する中で、我が国の温室効果ガス(*1)排出量の約1%を占める酪農・畜産でも排出削減の取組が求められています。
農林水産省では、家畜生産に係る環境負荷軽減等の展開、資源循環の拡大、国産飼料の生産・利用の拡大、有機畜産の振興、アニマルウェルフェアに配慮した飼養管理の普及、畜産GAP認証の推進、消費者の理解醸成等に取り組み、持続可能な畜産物生産を図ることとしています。
1 用語の解説(1)を参照
(アニマルウェルフェアに配慮した飼養管理の普及を推進)
家畜を快適な環境下で飼養することにより、家畜のストレスや疾病を減らし、生産性の向上や安全な畜産物の生産にもつながるアニマルウェルフェアの推進が求められています。
農林水産省では、アニマルウェルフェアに対する相互の理解を深めるため、幅広い関係者による「アニマルウェルフェアに関する意見交換会」を開催しています。また、アニマルウェルフェアに配慮した生産体制の確立を加速させるため、OIEコード(*1)に基づき畜種ごとの飼養管理方針についての指針に関して新たな策定に向けた取組を進めるなど、我が国のアニマルウェルフェアの水準を国際水準と同程度にするための取組の普及・推進等を図ることとしています。
1 OIE(国際獣疫事務局)の陸生動物衛生規約。OIEについては、用語の解説(2)を参照
(畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律が施行)
畜舎、堆肥舎等の建築に関し建築基準法の特例を定めることを内容とする「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律」(以下「畜舎特例法」という。)が令和4(2022)年4月に施行されました。これにより、都道府県に畜舎建築利用計画を申請し、認定を受ければ、一定の利用基準を遵守することで、緩和された構造等の技術基準で畜舎を建築することができるため、農業者や建築士の創意工夫により建築費を抑え、規模拡大や省力化機械の導入が一層進むことが期待されています。
また、令和5(2023)年4月から、畜舎特例法の「畜舎等」の対象に畜産業の用に供する農業用機械や飼料・敷料の保管庫等を追加することとしています。
(コラム)第12回全国和牛能力共進会が鹿児島県で開催
令和4(2022)年10月に、第12回全国和牛能力共進会が鹿児島県で開催されました。全国和牛能力共進会は、5年に1度、全国の優秀な和牛を一堂に集めて和牛改良の成果を競うとともに今後の和牛改良の方向性を共有する大会であり、今回は、「地域かがやく和牛力」をテーマに、41道府県から選抜された438頭が出品されました。
大会では、雄牛・雌牛の和牛改良の成果を競う「種牛の部」が同県霧島市(きりしまし)で開催され、同県の出品牛が内閣総理大臣賞を獲得しました。また、肉質を競う「肉牛の部」が同県南九州市(みなみきゅうしゅうし)で開催され、宮崎県の出品牛が内閣総理大臣賞を獲得しました。開催地である鹿児島県は、9部門中6部門で優等賞1席を獲得しました。
今回の共進会から、従来のサシ(脂肪交雑)を中心とした肉質評価に加え、新たに、牛肉の食味に関連する脂肪酸の含有量を評価する「脂肪の質評価群」が設けられました。和牛肉の美味しさに着目し、従来と異なる角度から和牛の魅力にスポットを当て、地域の特色ある牛づくりや新たな和牛肉の特性を見直すための取組として、大きな関心を集めました。
さらに、特別区「高校及び農業大学校の部」が新たな出品区として設けられ、将来の和牛生産の中心となる若い担い手が大いに活躍しました。
同大会を契機に、和牛の魅力や生産性が向上し、将来にわたって和牛生産が成長し、次世代に引き継がれていくことが期待されています。

内閣総理大臣賞を受賞

共進会の会場の様子
(競馬法を改正し、競馬の健全な発展等のための措置を強化)
令和4(2022)年11月に、競馬の健全な発展を図るとともに、競馬に対する国民の信頼を確保するため、競馬活性化計画の目的及び記載事項の見直し、地方競馬全国協会(ちほうけいばぜんこくきょうかい)の資金確保措置の恒久化及び延長、競馬の公正かつ円滑な実施を確保するために必要な措置の充実等を図ることを内容とする「競馬法の一部を改正する法律」が公布されました。今後は、地方競馬の経営基盤や馬産地の生産基盤の強化を安定的に推進するとともに、競馬に対する国民の信頼を確保していくこととしています。
(2)新たな需要に応える園芸作物等の生産体制の強化
(加工・業務用野菜の出荷量は前年産に比べ減少)
加工・業務用野菜は、冷凍食品会社等の実需者から国産需要が高く、野菜需要の約6割を占めています。一方、加工・業務用野菜は、国産品が出回らない時期がある品目等を中心に輸入が約3割を占めています。
令和3(2021)年産の指定野菜(*1)(ばれいしょを除く。)の加工・業務用向け出荷量は、外食産業等において新型コロナウイルス感染症の影響で業務用需要が十分に回復しなかったことから、前年産に比べ1.2%減少し100万4千tとなりました(図表2-7-4)。
農林水産省では、加工・業務用野菜等の生産体制の一層の強化、輸入野菜の国産切替えを進めるため、畑地化のほか、水田を活用した新たな園芸産地における機械化一貫体系の導入、新たな生産・流通体系の構築や作柄安定技術の導入等を支援しています。
指定野菜の加工・業務用向け出荷量については、畑地化や、水田を活用した新産地の形成等の克服すべき課題に対応し、令和12(2030)年度までに145万tに拡大することを目標としています。
1 野菜生産出荷安定法において、消費量が相対的に多い又は多くなることが見込まれる14品目(キャベツ、きゅうり、さといも、だいこん、たまねぎ、トマト、なす、にんじん、ねぎ、はくさい、ばれいしょ、ピーマン、ほうれんそう、レタス)をいう。
(高品質果実の生産基盤の強化を推進)
国産果実の生産量が減少する中、「おいしい」、「食べやすい」などの消費者ニーズに対応した新品種が育成され、主要産地に広く普及されています。また、機能性成分の含有を高めた付加価値の高い品種等、高品質な優良品目・品種への転換が行われています(図表2-7-5)。
近年では、皮ごと食べられる手軽さと優れた食味が特長の「シャインマスカット(ぶどう)」や、貯蔵性が高く長期保存できる「シナノゴールド(りんご)」、外観が良くむきやすい「せとか(かんきつ)」等、需要が高い品種の生産が拡大しています。
また、産地では、高品質果実の生産基盤の維持・強化のため、省力的で多収な樹形への転換が進められています。果樹の省力樹形は、小さな木を密植して直線的な植栽様式とするため、作業動線が単純で効率的となり、労働時間を従来の慣行樹形に比べ大幅に削減することができます。また、日当たりが均一になることで品質がそろいやすく、密植することで高収益化が可能になります。
農林水産省は、省力樹形の導入等による労働生産性の向上と共に、気候変動への適応、担い手や労働力の確保に向けた取組等、高品質果実の生産基盤の強化を推進しています。
(サツマイモ基腐病対策を推進)
令和2(2020)年以降、つるが枯れ、いもが腐る「サツマイモ基腐病(もとぐされびょう)」による被害が宮崎県、鹿児島県等で発生しており、令和5(2023)年3月末時点で、31都道府県で発生が確認されています。
このため、農林水産省では、令和4(2022)年産への影響を最小限にするため、薬剤防除等の取組への支援に加え、交換耕作や健全な苗等の供給能力強化のための施設整備、被害軽減対策の実証等の取組に対する支援の拡充を行いました。
また、関係都道府県と連携し、健全種苗の生産・流通・使用の徹底や、圃場(ほじょう)における本病の早期発見・早期防除の徹底等のまん延防止に向けた取組を指導するとともに、産地からの要望を踏まえた農薬の登録拡大を推進しています。
さらに、農研機構では、抵抗性品種の育成や診断技術の開発、薬剤・資材を利用した防除技術の開発等を進めるとともに、研究事業で得られた成果を踏まえつつ、防除技術の確立・普及に向けた取組を推進しています。
(3)米政策改革の着実な推進
(水田作の農業経営体数は減少傾向で推移)
田のある農業経営体数は、減少傾向で推移しており、令和2(2020)年は約84万経営体と、平成17(2005)年の174万1千経営体と比べて約5割減少しています(図表2-7-6)。このうち、個人経営体数は、令和2(2020)年は約82万経営体となっており、主業経営体、準主業経営体、副業的経営体の全ての分類で減少しています。一方、団体経営体数は、令和2(2020)年は約2万経営体と、平成17(2005)年の7千経営体と比べて約3倍となっています。また、田における主業経営体及び法人等の団体経営体が占める経営耕地面積の割合は、平成17(2005)年の41%から令和2(2020)年に55%まで増加しており、水田農業経営体数が減少する中で、集落営農組織を含めた担い手による農地集積が進展していると考えられます。
担い手の確保に向け、農林水産省では、「効率的かつ安定的な経営体」を目指す意欲ある農業者を、経営規模の大小や、法人か家族経営かの別を問わず、幅広く育成・支援することとしています。
(米の需要に応じた生産・販売を推進)
主食用米の需要量が年間10万t程度減少している中、消費者ニーズにきめ細かく対応した米や、国産需要のある麦・大豆、加工・業務用野菜等を生産する産地を形成していくことが必要となっています。
このため、農林水産省では、産地・生産者と実需者が結び付いた事前契約や複数年契約による安定取引、水田活用の直接支払交付金等による作付転換への支援のほか、都道府県別の販売進捗、在庫・価格等の情報提供を実施しています。
(高収益作物の産地を308産地創設)
野菜や果樹等の高収益作物は、必要な労働時間は水稲より長くなるものの、単位面積当たりの農業所得は高くなっています。近年では、排水対策等の基盤整備や機械化一貫体系等の新しい技術を導入し、高収益作物への作付転換を図る動きも見られています。
このため、農林水産省では、高収益作物への作付転換、水田の畑地化・汎用化(*1)のための農業生産基盤整備、栽培技術や機械・施設の導入、販路確保等の取組を計画的かつ一体的に支援し、令和7(2025)年度までに水田農業における高収益作物の産地を500産地とすることを目標としており、令和4(2022)年9月末時点で308産地まで増加しています。
1 用語の解説(1)を参照
(令和4(2022)年産米において5万2千haの作付転換を実現)
令和4(2022)年産米においては、主食用米需要の減少や在庫の増加等により、平年単収ベースで3万9千haの作付転換が必要となる見通しが示されました。
このため、農林水産省では、同年産米の作付転換に向けた支援として、水田リノベーション事業や麦・大豆収益性・生産性向上プロジェクトを措置するとともに、水田活用の直接支払交付金において、新市場開拓用米の新規の複数年契約に対する支援や地力増進作物による土づくりの取組に対する支援を創設しました。さらに、このような関連施策や需給の動向について、全国会議や各産地での説明会、意見交換会を通じて周知し、需要に応じた生産・販売を推進しました。
この結果、5万2千haの作付転換が進められ、主食用米の作付面積は125万1千haとなりました(図表2-7-7)。平成30(2018)年産において国による生産数量目標の配分が廃止されて以降、米の需給の安定に必要な転換面積を超える作付転換が実現されたのは初めてであり、需要に応じた生産が着実に進展しています。
また、農林水産省では、引き続き需要に応じた生産を推進するため、畑作物の生産が定着した水田については畑地化を促すとともに、水田機能を維持しながら畑作物を生産する農地については、水稲とのブロックローテーションを促す観点から、令和8(2026)年度までの5年間に一度も水張りが行われない農地は水田活用の直接支払交付金の交付対象としない方針を令和3(2021)年12月に決定しました。その上で、本方針に係る現場の課題を踏まえ、畑地化の促進等、必要な支援を措置しました。
(事例)ブロックローテーションと深層施肥技術の導入で大豆増産を実現(島根県)


中耕除草機
資料:農事組合法人ふくどみ

大豆の収穫に向けた
圃場での確認作業
資料:農事組合法人ふくどみ
島根県出雲市(いずもし)の農事組合法人ふくどみは、水稲・大麦・大豆の2年3作ブロックローテーションに取り組むとともに、深層施肥技術やドローンによる防除を導入し、大豆の増産に取り組んでいます。
同法人では、近隣の離農者から農地集積を進めて経営面積を拡大しており、令和3(2021)年の大豆の作付面積は13.6haで、10年前の約2倍に増加しています。大豆の品種は、サチユタカA1号、タマホマレを主に栽培しており、そのほとんどが契約栽培で実需者から好評を得ています。
大豆の生産に当たっては、播種(はしゅ)・収穫を約3日で行うなど天候を考慮して適期作業に努めています。また、弾丸暗渠(あんきょ)(*)の施工時に併せて石灰窒素の深層施肥を行う機械を工夫し、開花期以降の養分供給を可能にするとともに、中耕除草機による3回の除草・土寄せを行っています。さらに、ドローンを導入し植物活性剤等の散布を実施することで安定生産を実現しています。
同法人では、今後とも、更なる技術革新に取り組みながら、高収量・高品質の大豆生産の実現を目指していくこととしています。
機械力により土層中に弾丸を通して通水孔を設けるもの
(畑作物の本作化を推進)
需要に応じた生産が行われる中、令和4(2022)年度においては、約3千haの水田の畑地化が進みました。畑作物の本作化をより一層推進するため、畑地化後の畑作物の定着までの一定期間を支援する「畑地化促進事業」や、低コスト生産等の技術導入や畑作物の導入定着に向けた取組を支援する「畑作物産地形成促進事業」を措置しました。
(4)麦・大豆の需要に応じた生産の更なる拡大
(パン・中華麺用小麦の作付比率が拡大)
麦の消費量に占める国内生産量の割合は、小麦で12~17%、大麦・はだか麦で8~12%となっています。我が国においては、年間消費量の8~9割を外国産麦が占めていることから、今後、国産麦の割合を伸ばしていく余地があります。一方、耐病性や加工適性に優れた新品種の導入・普及が進み、実需者が求める品質に見合った麦の生産が進展しています。令和3(2021)年における小麦作付面積に占めるパン・中華麺用小麦の作付比率は、前年に比べ3ポイント増加し26%となっています(図表2-7-8)。
(食用大豆の需要量に占める国産大豆の割合は増加)
食用大豆の需要量は、健康志向の高まりにより増加傾向で推移してきましたが、令和3(2021)年度は、前年度に比べ5.2%減少し99万8千tとなりました(図表2-7-9)。
国産大豆は、実需者から味の良さ等の品質が評価され、ほぼ全量が豆腐、納豆、煮豆等の食品向けに供されており、令和3(2021)年度の食品向け国産大豆は、23万9千tとなりました。
食用大豆の需要見込みについては、豆腐、納豆、味噌(みそ)等の各実需者は、令和9(2027)年度の大豆の使用量を令和3(2021)年度に比べ14%増やす見込みであり、特に国産大豆の使用量を25%増やす見込みとしています(図表2-7-10)。国産大豆を増やす理由については、「消費者ニーズに応えられる」、「付加価値が向上する」などが多く挙げられており、今後、国産大豆の需要が一層高まることが期待されます。

(5)GAP(農業生産工程管理)の推進
(国際水準GAPを推進)
GAP(*1)は、農業生産の各工程の実施、記録、点検及び評価を行うことによる持続的な改善活動であり、食品の安全性向上や環境保全、労働安全の確保等に資するとともに、農業経営の改善や効率化につながる取組です。
我が国の農業の競争力強化と持続的な発展のためには、「食品安全」、「環境保全」、「労働安全」、「人権保護」、「農場経営管理」の5分野を含む国際水準GAPの普及を推進することが有効です。また、SDGs(*2)に対する関心が国内外で高まる中、国際水準GAPは、SDGsが目指す経済・社会・環境が調和した持続可能な世界の実現にも幅広く貢献できるものです。このため、農林水産省では、令和4(2022)年3月に「我が国における国際水準GAPの推進方策」を策定するとともに、国際水準GAPの我が国共通の取組基準として「国際水準GAPガイドライン」を策定し、その普及を推進しています(図表2-7-11)。

また、都道府県では、農業者へのGAPの普及に関して、国際水準GAPガイドラインや独自のGAP基準(都道府県GAP)に基づく指導や、GAP認証取得を目指した指導等を行っています。農林水産省では、国際水準GAPの推進方策を受け、都道府県GAPを存続する都道府県に対し、令和6(2024)年度末を目途として、都道府県GAPを国際水準GAPガイドラインに則したものとするよう求めています。
さらに、ISO(*3)規格に基づき、GAPの取組が正しく実施されていることを第三者機関が審査し証明する仕組みであるGAP認証について、我が国では主にGLOBALG.A.P.(*4)、ASIAGAP(*5)、JGAP(*6)の3種類のGAP認証が普及しています。令和3(2021)年度のGAP認証取得経営体数は、7,977経営体となりました(図表2-7-12)。また、同年度において、国内で国際水準GAPを実施する経営体数は2万4,653経営体となっています。
国際水準GAPの更なる取組拡大に向けて、農林水産省では、GAP認証農産物を取り扱う意向を有している事業者である「GAPパートナー」を募集し、農業者とのマッチングを進めています。これらの事業者とも連携し、農業者による国際水準GAPの取組を消費者へも情報発信することで、国際水準GAPを更に推進していくこととしています。

国際水準GAPとSDGs
URL:https://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/gap_sdgs.html

Goodな農業!GAP-info
URL:https://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/gap-info.html
1~4 用語の解説(2)を参照
5 一般財団法人日本GAP協会が策定した第三者認証のGAP。対象は青果物、穀物、茶
6 一般財団法人日本GAP協会が策定した第三者認証のGAP。対象は青果物、穀物、茶、家畜・畜産物
(事例)高校生が主体となってGLOBALG.A.P.認証を取得(愛知県)

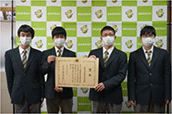
「令和3年度未来につながる持
続可能な農業推進コンクール
(GAP部門)」において
農林水産大臣賞を受賞
愛知県田原市(たはらし)の愛知県立渥美(あつみ)農業高等学校は、生徒自らがGLOBALG.A.P.認証の取得に必要な情報を収集して申請書類を作成し、地域の主力品目である菊やトマトでの認証取得を実現しました。
同校では、毎年度、農業、施設園芸を専攻する2年生、3年生の生徒約80人がGAPを学習するとともに、GAP認証を受けた農場で実習を行っており、生徒の間でもGAPへの関心が高くなっています。
また、田原(たはら)地域は、国内最大の菊の産地であり、今後、農産物輸出でGAP認証が求められること等も考えて、認証の取得に取り組みました。
国内には、花き専門のGAP認証審査員がいませんでしたが、同校の働き掛けによって、国内初の花きのGAP認証審査員が誕生しています。
GLOBALG.A.P.の取得や、農場実習等の経験を基に、卒業後にGAP認証取得企業に就職し、GAPの実践に貢献する者も出てきており、今後、同校を中心にGAPが地域に広まっていくことが期待されています。
(6)効果的な農作業安全対策の展開
(農作業中の事故による死亡者数は、農業機械作業に係る事故が約7割)
農作業中の事故による死亡者数は、令和3(2021)年は前年に比べ28人減少し242人となりました。農作業死亡事故を要因別に見ると、農業機械作業に係る事故が171人(70.7%)となっており、このうち、乗用型トラクターに係るものが58人(24.0%)と最も多くなっています(図表2-7-13)。
これらの事故実態を踏まえ、令和3(2021)年に取りまとめた「農作業安全対策の強化に向けて(中間とりまとめ)」に基づいた対応を進めています。
このうち農作業環境の安全対策については、農研機構が農機メーカーからの依頼に基づいて農業機械の安全性を確認する安全性検査制度の見直しを行う中で、乗用型トラクターにおいてシートベルトを装着せずに運転した際に運転手に警告を行う装置や、果樹園で防除作業を行うスピードスプレーヤーの転落時に運転手の安全域を確保する構造の基準化に向けた検討等が行われています。
また、農業者の安全意識の向上対策については、普及指導センターや農協、農業機械販売店等の協力を得て、約3,700人の農作業安全に関する指導者を育成するとともに、令和4(2022)年度から、農作業事故の発生状況、農業経営への影響、シートベルト装着の徹底等、効果的な事故防止対策等について農業者に直接研修を行っているほか、ポスター等を用いた啓発を行っています。
(農作業中の熱中症による死亡事故は継続的に発生)
令和3(2021)年における農作業中の熱中症による死亡者数は23人となっており、死亡事故要因の上位を占めています。農作業中の熱中症による死亡事故は、日中の最高気温が30℃を超える日が多い7~8月に多い傾向がありますが、春先や5月頃であってもビニールハウス内等においては死亡事故が発生しています(図表2-7-14)。
農林水産省では、環境省と気象庁が連携して運用する「熱中症警戒アラート」が発出された際、MAFF(まふ)アプリにも熱中症に注意するよう通知される機能の活用や、体温を下げる機能を持つタオルや体温上昇を検知して警告する機器等、「熱中症対策アイテム」の活用を促しています。
このほか、スマート農業(*1)実証プロジェクトにおいても、農業者の熱中症等の異変を検知する安全見守りシステムの実証に取り組んでいます。
1 用語の解説(1)を参照
(7)良質かつ低廉な農業資材の供給や農産物の生産・流通・加工の合理化
(農産物の流通・加工の合理化等に向けた取組を推進)
農業が将来にわたって持続的に発展していくためには、農業の構造改革を推進することと併せて、良質で低廉な農業資材の供給や農産物流通等の合理化といった、農業者の努力では解決できない構造的な問題を解決していくことが重要です。
このため、農林水産省では、農業競争力強化支援法に基づき、良質かつ低廉な農業資材の供給や、農産物の流通合理化に資する事業再編や事業参入の支援を行っています。令和4(2022)年度においては、農産物の流通・加工分野において、国産農産物の販売拡大に寄与する食品の製造機能の集約等の取組を支援しました。
(農協による買取販売等の取組が拡大)
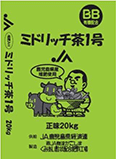
鹿児島県経済農業協同組合連合会が
開発・販売している、堆肥を活用した
低コスト肥料
資料:鹿児島県経済農業協同組合連合会
農業者の所得向上のためには、農協(*1)が農産物の有利販売を行うことが重要ですが、いわゆる「買取販売」を実施する農協については、平成27(2015)年は361農協であったところ、令和2(2020)年は398農協と、全体の約7割に増加しており、農協が販売事業に力を入れる取組が広がっています。
また、JA全農では、青果物の卸売業者や流通業者との業務提携により、共同配送やパレットの共通化等の流通の合理化に向けた取組を進めています。
さらに、一部の農協等では、低コスト肥料の開発・販売やドローンによる受託防除の取組を実施しています。
1 第2章第11節を参照
(担い手の米の生産コスト削減に向けた取組を推進)
稲作経営の農業所得を向上させるには、生産コストの削減が重要となっています。担い手の生産コストについては、令和5(2023)年までに平成23(2011)年産(全国平均1万6,001円/60kg)から4割削減することを目標に掲げています。このため、米の生産については、農地の集積・集約化(*1)、多収品種の導入、スマート農業技術の普及による省力化に加え、生産資材の低減を推進しています。
特に生産コストの約5割を占める生産資材(農機具費、肥料費、農業薬剤費)と労働費については、令和6(2024)年度までに5,470円/60kgとすることを目標としており、令和3(2021)年産米に係る生産資材と労働費の合計は、個別経営で6,160円/60kg、組織法人経営で6,491円/60kgとなっています(図表2-7-15)。
1 用語の解説(1)を参照
(スマート・オコメ・チェーンの構築に向けた取組を推進)
米の生産から消費に至るまでの情報を関係者間で連携し、生産の高度化や流通の最適化、販売における付加価値向上等を図るスマートフードチェーン(スマート・オコメ・チェーン)の構築に向け、米の消費拡大や付加価値向上、輸出拡大に資する情報項目の調査・検証を行い、各種情報の標準化に向けた検討を進めました。
また、「農産物検査規格・米穀の取引に関する検討会」での検討を踏まえ策定された「機械鑑定を前提とした農産物検査規格」については、令和4(2022)年産米の検査から適用されています。

スマート・オコメ・チェーンコンソーシアムについて
URL:https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/okomechain.html
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883