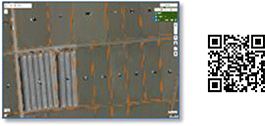第8節 情報通信技術等の活用による農業生産・流通現場のイノベーションの促進

農業生産・流通現場でのイノベーションの進展、農業施策に関する各種手続や情報入手の利便性の向上は、高齢化や労働力不足等に直面している我が国の農業において、経営の最適化や効率化に向けた新たな動きとして期待されています。
本節では、スマート農業(*1)の導入状況や農業・食関連産業におけるデジタル変革に向けた取組、産学官連携による研究開発の動向等について紹介します。
1 用語の解説(1)を参照
(1)スマート農業の推進
(農作業の自動化、作業記録のデジタル化等の取組が進展)
農業の現場では、ロボット・AI・IoT等の先端技術や、データを活用し、農業の生産性向上等を図る取組が各地で広がりを見せています。
具体的には、ロボットトラクタ、スマートフォンで操作する水田の水管理システム等の活用により、農作業を自動化し省力化に資する取組が進められているほか、位置情報と連動した経営管理アプリの活用により、作業の記録をデジタル化・自動化し、熟練者でなくても生産活動の主体になることも容易となっています。令和4(2022)年7月時点では、走行経路を「見える化」するGNSS(*1)ガイダンスシステムが2万8,270台、ハンドルを自動制御する自動操舵(そうだ)システムが1万7,990台出荷されています(*2)。また、ドローンによる農薬等の散布実績は増加傾向で推移する中、令和2(2020)年度末時点で約12万haと推計されています(図表2-8-1)。さらに、ドローン等によるセンシングデータや気象データのAI解析により、農作物の生育や病虫害を予測し、高度な農業経営を行う取組等も展開されています。
1 Global Navigation Satellite Systemの略で、全球測位衛星システムのこと。人工衛星からの信号を受信することにより、世界のどこにいても現在位置を正確に割り出すことができる測位システム
2 北海道庁が調査した出荷台数(全国)の数値。調査を開始した平成20(2008)年度以降の累計台数
(事例)IoT水管理システムを活用し、米生産の省力化を推進(富山県)


IoT水管理システム
資料:有限会社スタファーム
富山県高岡市(たかおかし)の農業生産法人である有限会社スタファームは、IoTを活用した水管理システムを導入し、米生産の省力化と生産性向上に取り組んでいます。
同社では、ふだん管理している圃場(ほじょう)から7km程度離れた地区において約15haの圃場管理を請け負ったことを契機に、令和3(2021)年度にIoTセンサーにより水門を自動的に管理できるシステムを導入しました。
圃場ごとに、スマートフォンで遠隔操作できる水管理システムの設備を合計で60台設置し、タイマー機能や水位センサーを利用することで、水門を見回る労力や水管理の手間が軽減されています。また、水管理システムによる効果的な管理を通じて雑草等が減少し、除草剤の量を削減できることにより、生産性や品質向上の面でも効果が見られています。
今後も、農地中間管理機構を活用した農地賃借による水稲等の生産に取り組むほか、米生産の省力化によって削減した時間を活用し、にんじんを主体とした野菜の生産にも力を入れていくこととしています。
(データを活用した農業を実践している農業の担い手の割合は前年に比べ増加)
データを活用した農業を実践している農業の担い手の割合は、令和3(2021)年が48.6%となっており、前年の36.4%から12.2ポイント増加しています(図表2-8-2)。
農林水産省では、スマート農業実証プロジェクトに参加して技術・ノウハウを培った生産者、民間事業者等から成るスマートサポートチームが新たな産地へ実地指導する取組を推進し、現地でのデータ活用とスマート農業人材の育成を図っています。また、農業支援サービスの活用により、スマート農業に関心はあるが自力では取り組むことが困難な生産者・産地の支援を行っています。さらに、普及指導員による、データに基づく生産者・産地指導への支援を行っています。
こうした取組を進め、令和7(2025)年までに農業の担い手のほぼ全てがデータを活用した農業を実践することを目標としています。
(事例)施設園芸農業のデータを集約し、営農指導を高度化(高知県)


「SAWACHI」の画面
資料:高知県
高知県では、環境制御技術にIoTやAI等の先端技術を融合し、施設園芸農業の発展を図る「IoP(Internet of Plants)プロジェクト」に取り組んでおり、農業データ連携基盤であるIoPクラウド「SAWACHI(さわち)」を活用した、データに基づいた施設園芸農業の普及を推進しています。
令和4(2022)年9月に本格運用を開始したSAWACHIは、ハウス内に設置した環境測定装置で測定した環境情報や、作物の生育状況、出荷情報等のデータを「見える化」し、共有できるクラウドサービスです。クラウド上のデータは農業者だけでなく、県やJAの指導員も利用でき、モデル農家のデータと比較して改善点を分かりやすく指導するなど、営農指導の高度化に役立てられています。
県は、JAグループと連携し、県内各地区にデータ駆動型農業推進の担当者を配置して体制を整備するとともに、指導員向けのデータ分析研修等を実施し、栽培技術・経営指導の最適化を図っています。
今後は、データ駆動型農業を実践していない農業者への環境測定装置の試験的な導入を支援しながらSAWACHIの普及を進め、農業所得の更なる向上を後押ししていくこととしています。
(農業関連データの連携・活用を促進)

WAGRI
URL:https://wagri.naro.go.jp(外部リンク)
様々なデータの連携・共有が可能となるデータプラットフォーム「農業データ連携基盤(WAGRI(わぐり)(*1))」を活用した農業者向けのICTサービスが民間企業等により開発され、農業者への提供が始まっています。運営主体である農研機構ではデータの充実や利用しやすい環境の整備に取り組んでいます。
また、農林水産省は、農業者が利用する農業機械等から得られるデータについて、メーカーの垣根を越えてデータを利用できる仕組み(オープンAPI(*2))の整備を支援しています。
このほか、スマート農業の海外展開に向けて、農林水産省は、農研機構、民間企業と連携し、国際標準の形成に向けた調査・検討を行っています。
1 農業データプラットフォームが、様々なデータやサービスを連環させる「輪」となり、様々なコミュニティの更なる調和を促す「和」となることで、農業分野にイノベーションを引き起こすことへの期待から生まれた言葉(WA+AGRI)
2 Application Programming Interfaceの略。複数のアプリ等を接続(連携)するために必要な仕組みのこと
(小型農業ロボットの公道走行に向けた環境整備を推進)
運搬、農薬散布等の農作業を補助する農業ロボットについては、小型で小回りが利き、圃場、果樹園等、幅広い場面で使用できる多様な走行方式の機種が実用化されています。
令和4(2022)年4月に成立した改正道路交通法(*1)では、遠隔操作により通行する小型の車であって、一定の構造基準を満たすものについては、「遠隔操作型小型車」とし、歩行者と同様の交通ルールを適用することとなりました。農林水産省では、小型農業ロボットが遠隔操作型小型車として道路を走行するために必要となる車体の大きさや構造の基準、道路を通行させようとする場合における届出の方法等について、開発メーカー等に情報提供することとしています。
1 正式名称は「道路交通法の一部を改正する法律」
(全ての農業高校・農業大学校においてスマート農業をカリキュラム化)
農業現場においてスマート農業の活用が進む中、今後の農業の担い手を育成する農業大学校や農業高校等においても、スマート農業を学ぶ機会を充実させることが重要です。このため、令和4(2022)年度から、全ての農業高校・農業大学校においてスマート農業がカリキュラム化(*1)されました。
また、スマート農業に精通する人材の育成を進めるためには、スマート農業に関心を持つ学生や経営を発展させたい農業者等が、いつでも誰でもスマート農業について体系的に学べるようにするとともに、農業教育機関の教員がスマート農業の指導に必要な知識を身に付けることが必要です。農林水産省では、スマート農業の最新技術等を学べるよう、農業者や教員等を対象としたスマート農業研修を推進するとともに、農業高校・農業大学校等への研修用スマート農業機械・設備の導入や動画コンテンツの充実を推進しています。
1 農業大学校については、令和3(2021)年度末までに、全ての学校においてカリキュラム化。農業高校については、スマート農業に関する内容が盛り込まれた新たな高等学校学習指導要領が令和4(2022)年度の1年生から年次進行で実施
(スマート農業を支える農業支援サービスの取組が拡大)
近年、ドローンやIoT等の最新技術を活用して、農薬散布作業を代行するサービスや、データを駆使したコンサルティング等、スマート農業を支える農業支援サービス(*1)の取組が人手不足に悩む生産現場で広がっています。これらの取組には、スマート農業機械等の導入コストの低減や、コンサルティングによる生産性の向上等の効果が期待されています。
農林水産省は、ドローンや自動走行農機等の先端技術を活用した作業代行やシェアリング・リース等の次世代型の農業支援サービスの定着を促進することとしています。
1 第2章第3節を参照
(コラム)スタートアップによる次世代型の農業支援サービスが拡大
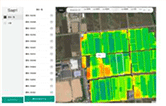
生育状況を色で把握可能な
営農支援アプリ
資料:サグリ株式会社
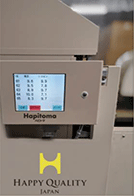
近赤外センサー選果機による
トマトの全量検査
資料:株式会社Happy Quality
近年、次世代型の農業支援サービスの事業化を進めるスタートアップが存在感を高めています。
兵庫県丹波市(たんばし)のサグリ株式会社は、衛星データとAI技術等を組み合わせたデータプラットフォームの開発・提供を行っています。同社の営農支援アプリは、衛星データから分析した作物の生育状況のほか、土壌のpHや窒素成分等を把握できる機能を備えており、アプリを利用する農業者は、適切な施肥管理による肥料費の節減や環境負荷の低減を図ることが可能となっています。さらに、荒廃農地(*)を「見える化」する農地状況把握アプリは、衛星データから未利用農地を高精度に判定できる機能を備えており、アプリを利用する農業委員会は、現地確認や文書事務の労力軽減を図ることが可能となっています。
また、静岡県浜松市(はままつし)の株式会社Happy Quality(ハッピークオリティー)は、センシング技術とAI技術を組み合わせた高糖度トマトの生産や選果機データを活用した栽培ノウハウの改善等に取り組んでいます。同社では、パートナー契約を締結した農業者に栽培技術と栽培指導を一体的に提供し、生産物を全量買取りすることで農業者の収益基盤の確立をサポートしています。農業経営支援サービスを受ける農業者は、相場価格にとらわれずに高品質トマトの生産に取り組んでいます。
このように農業の現場では、データ分析やデータ活用等の技術により農業経営や農作業をサポートするスタートアップの活躍の場が広がっています。今後とも、顧客との距離が近く、小回りが利き、対応のスピードが早いといったスタートアップならではの強みを活かした事業展開が期待されています。
用語の解説(1)を参照
(2)農業施策の展開におけるデジタル化の推進
(eMAFFによる行政手続のオンライン利用を推進)
農林水産省では、所管する法令や補助金・交付金において3千を超える行政手続がありますが、現場の農業者を始め、地方公共団体等の職員からは、申請項目や添付書類が非常に多いとして、改善を求める声が多数寄せられています。このような状況を改善し、農業者が自らの経営に集中でき、地方公共団体等の職員が担い手の経営サポートに注力できる環境とするため、行政手続をオンラインで行えるようにする「農林水産省共通申請サービス(eMAFF(イーマフ))」の開発を進め、令和3(2021)年度から運用を開始しました。
eMAFFは、政府方針にある「デジタル化3原則(*1)」に則していることはもちろん、申請者等の負担を軽減するため、全ての手続について点検を行い、申請に係る書類や申請項目等の抜本的な見直し(BPR(*2))を行った上でオンライン化を進めています。令和5(2023)年3月末時点で、約3,300の手続のオンライン化を完了しています。また、今後のオンライン利用の本格化に向けて、行政手続の審査機関である地方公共団体等向けのeMAFFの利用に関する説明会や農業者等に対するセミナー等を実施しています。セミナーに参加した農業者からは、「一度申請した手続の内容を次回以降に再入力する必要がないのは魅力的である」、「毎年行っている申請について実際にeMAFFを利用してみたい」等の意見が寄せられました。引き続き、eMAFFの利用の推進に取り組みつつ、利用者の声を聴きながら、利便性の向上を図っていくこととしています。
1 デジタルファースト(個々の手続・サービスが一貫してデジタルで完結すること)、ワンスオンリー(一度提出した情報は、二度提出することを不要とすること)、コネクテッド・ワンストップ(民間サービスを含め、複数の手続・サービスを一元化すること)の三つの原則を合わせたもの
2 Business Process Reengineeringの略で、業務改革のこと
(eMAFF地図の開発が進展、eMAFF農地ナビ・現地確認アプリの運用を開始)
農林水産省では、現場の農地情報を統合し、農地の利用状況の現地確認等の抜本的な効率化・省力化を図るため、「農林水産省地理情報共通管理システム(eMAFF地図(イーマフちず))」プロジェクトを進めています。
農地に関する情報については、農業委員会が整備する農地台帳や地域農業再生協議会が整備する水田台帳等、施策の実施機関ごとに個別に収集・管理されています。このため、農業者は、実施機関ごとに繰り返し同じ内容を申請する必要があるとともに、実施機関は、手書きの申請情報をそれぞれのシステムに手入力し、それぞれが作成した手書きの地図により現地調査を行っています。
農林水産省は、こうした農地関係業務を抜本的に改善するためにeMAFF地図の開発を進めています。eMAFF地図により、農業者は申請手続において画面上の地図から農地を選択することで農地情報を入力する手間が省けます。また、農業委員会等の実施機関は、現地調査の際にタブレットを活用することで、手書きの地図の作成が不要になるとともに、確認結果をその場で入力できること等により、行政コストが低減されます。
令和4(2022)年度からは、インターネット上で農地の所在、利用権設定等の情報を公開する「eMAFF農地ナビ」の運用とともに、農地の利用状況等の現地確認業務を効率化できる現地確認アプリの運用を開始しています。現地確認アプリを活用している地域では、「タブレットで現地確認できることで、手書きの地図作成が不要となった」、「GPS機能により圃場を探しやすくなり調査の時間が短縮された」等の意見が寄せられました。引き続き、現地確認アプリの経営所得安定対策等への対応も進めており、利用者の声を聴きながら、農地関連業務の抜本的効率化を図っていくこととしています。

農地の利用状況等の現地確認業務を
効率化できる「現地確認アプリ」
(スマートフードチェーンの構築による生産性向上等を推進)
近年、農業分野においても、ITやロボット技術等の先端技術を活用した、生産性を飛躍的に向上させる技術革新が起きています。このような中、流通の面では、生産から販売・消費までの様々なデータをつなぎ、利活用を促進することにより、農業や食品産業のフードチェーン全体の生産性の向上等を図っていくことが重要です。
農林水産省では、内閣府の研究開発プログラム「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)」の下、平成30(2018)年度から令和4(2022)年度にかけて、農林水産物の生産・加工・流通・販売・消費の各段階を連携させるハブとなる情報共有システムである「スマートフードチェーン」を開発し、トレーサビリティ等の各種機能の実証を進めました。
また、農業DXの実現に向けたプロジェクトを推進し、パレット単位によるデータ連携システムの構築や、二次元コードを活用した生産・流通情報を共有できるプラットフォームの構築等が進展しました。今後、デジタル化・データ連携による流通の合理化・効率化や、トレーサビリティの実現等が期待されています。
(3)イノベーションの創出・技術開発の推進
(農林水産・食品分野においてもスタートアップの取組が拡大)
我が国の経済成長を実現するためには、新しい技術やアイデアを生み出し、成長の牽引(けんいん)役となるスタートアップの活躍が不可欠です。農林水産・食品分野においても政策的・社会的課題の解決や新たな可能性を広げるビジネスの創出に向けて研究開発に取り組むスタートアップの動きが広がりを見せており、機動性を持って新しい分野に挑戦するスタートアップの取組への関心が高まっています。
農林水産省では、令和3(2021)年4月に導入された新たな日本版SBIR制度(*1)を活用し、新たな技術・サービスの事業化を目指すスタートアップの研究開発等を発想段階から事業化段階まで切れ目なく支援しています。
また、農林漁業者等の所得の向上につながる新たな技術やサービスを提供するスタートアップの活躍や参入によって農林水産分野のイノベーションの創出を促すため、平成28(2016)年度から、日本スタートアップ大賞において農林水産大臣賞を創設し、若者等のロールモデルとなるような、インパクトのある新事業を創出した起業家やスタートアップを表彰しています。
1 中小企業技術革新制度(Small Business Innovation Research)の略で、中小企業者による研究技術開発と、その成果の事業化を一貫して支援する制度
(事例)独自の流通規格を導入し、花のサブスクリプションサービスを展開(東京都)


ポストに届けられる花
資料:ユーザーライク株式会社
東京都渋谷区(しぶやく)に本拠を置くスタートアップであるユーザーライク株式会社は、花のサブスクリプションサービスを運営しており、日本スタートアップ大賞2022において農林水産大臣賞を受賞しました。
同社は、平成28(2016)年に、花のサブスクリプションサービス「ブルーミー」を開始し、インターネット購入で自宅のポストに週替わりで多様な花を届ける事業を展開しています。「お花を飾ったことがない」層にアプローチし、新しい需要を生み出すことで、令和5(2023)年1月時点で会員数が10万世帯を上回る規模に拡大しています。また、花の累計出荷数も2,000万本以上となっており、花の普及にも貢献しています。
また、同社では、独自の流通規格である「ブルーミー規格」を導入し、通常では値が付きづらく廃棄される場合もあった規格外の花も含め、市場と連携して適正価格で買い取る取組を進めています。
今後とも、低価格で利用でき、花のある生活を習慣化できるサービスを展開するとともに、業界全体への貢献につながる持続可能な仕組みづくりを積極的に推進することとしています。
(「知」の集積と活用の場によるオープンイノベーションを促進)
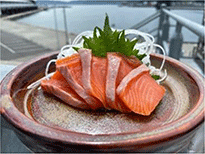
海面養殖のサクラマス
資料:さんりく養殖産業化プラットフォーム
「知」の集積と活用の場は、農林水産・食品産業の成長産業化を図るため、様々な分野の知識・技術・アイデアを導入し、オープンイノベーションを促進する仕組みとして運営・活用されています。
令和5(2023)年3月末時点で、IT、電機、医学等幅広い分野から、4,500以上の法人・個人が会員として参加しており、海面養殖のサクラマスや介護食用米粉等、新たな技術や商品が創出されています。こうした研究の成果は、速やかな社会実装や事業化につながるよう、アグリビジネス創出フェア等を通じて広く情報を発信しています。農林水産省では、イノベーションにつながる革新的な技術の実用化に向けて、基礎から実用化段階までの研究開発を推進することとしています。
(みどり戦略に資する技術開発・普及を推進)
近年、みどり戦略(*1)の実現に資する様々な技術開発が進展しています。令和4(2022)年度においては、飛んでいるヤガ類(害虫)にレーザー光を照射して打ち落とすことに成功し、化学農薬の使用量低減に貢献する新たな害虫の防除技術として期待されています。また、牛のメタン産生抑制と生産性向上に関与する胃の中の微生物機能の解明を進め、メタンの産生を抑制する候補資材の有効性を評価しました。さらに、メタンの産生が少ない牛の育種改良や、堆肥化工程等における温室効果ガス(*2)削減技術の開発等に取り組んでいます。
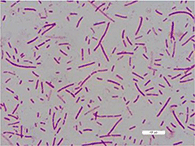
低メタン産生牛から分離された
新規細菌種「Prevotella lacticifex」
(プレボテラ・ラクティシフェクス)
資料:農研機構

「みどりの食料システム戦略」技術カタログ
URL:https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/
midori/catalog.html
農林水産省では、害虫管理や環境保全型農業に関し、ドイツとの共同研究等を進めていますが、同年度からメタンの排出削減に向けて米国との国際共同研究を新たに開始したほか、令和4(2022)年8月にはタイとの間でスマート農業技術等に関する覚書を締結するなど、国際的な連携にも取り組んでいます。
農林水産省では、みどり戦略で掲げた各目標の達成に貢献し、現場への普及が期待される技術について、「「みどりの食料システム戦略」技術カタログ(Ver1.0)」として取りまとめ、令和4(2022)年1月に公開しました。さらに、同年11月には、令和12(2030)年までに利用可能な技術を追加したVer2.0を公開しています。
1 第2章第9節を参照
2 用語の解説(1)を参照
(ムーンショット型研究開発を推進)
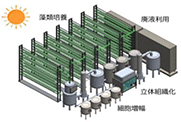
バイオエコノミカルな
培養食料生産システム
資料:東京女子医科大学先端生命医科学研究所
内閣府の総合科学技術・イノベーション会議(CSTI(システィ)(*1))では、困難だが実現すれば大きなインパクトが期待される社会課題等を対象とした目標を設定し、その実現に向けた挑戦的な研究開発(ムーンショット型研究開発)を関係府省と連携して実施しています。このうち、農林水産・食品分野においては、「2050年までに、未利用の生物機能等のフル活用により、地球規模でムリ・ムダのない持続的な食料供給産業を創出」することが目標として掲げられており、「藻類等を用いた循環型細胞培養による食料生産」を始めとする研究開発プロジェクトに取り組んでいます。
1 Council for Science, Technology and Innovationの略
(「スマート育種基盤」の構築を推進)
農林水産省では、みどり戦略の実現に向け、化学肥料・化学農薬等の使用量低減と高い生産性を両立する品種の早期開発や品種開発の活性化の方向性を示した「みどりの品種育成方針」を令和4(2022)年12月に策定しました。サツマイモ基腐病(もとぐされびょう)抵抗性品種の育成や、少量の窒素肥料でも高い生産性を示すBNI(*1)(生物的硝化抑制)強化コムギ・トウモロコシの育成等、各作物の主要な育種目標を整理しています(図表2-8-3)。
また、これらの品種育成の迅速化を図るため、最適な交配組合せを予測するツール等、新品種開発を効率化する「スマート育種基盤」の構築を推進し、国の研究機関、都道府県の試験場、大学、民間企業等による品種開発力の充実・強化に取り組むこととしています。
このほか、近年では天然毒素を低減したジャガイモや無花粉スギの開発等、ゲノム編集(*2)技術を活用した様々な研究が進んでいます。一方、ゲノム編集技術は新しい技術であるため、農林水産省は、同年10月に、ゲノム編集研究施設見学会を農研機構で実施したほか、大学や高校に専門家を派遣して出前授業等を行うなど、消費者に研究内容を分かりやすい言葉で伝えるアウトリーチ活動を実施しています。

1 Biological Nitrification Inhibition の略。植物自身が根から物質を分泌し、硝化を抑制する働きのこと
2 酵素等を用い、ある生物がもともと持っている遺伝子を効率的に変化させる技術
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883