第3節 農業現場を支える多様な人材や主体の活躍
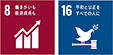
地域農業を維持し、持続可能なものとしていくためには、担い手の育成・確保の取組と併せて、中小・家族経営等多様な人材や主体の活躍を促進することも重要です。
本節では、家族経営協定(*1)の締結や外国人材の受入れ等の農業現場を支える多様な人材や主体の活躍に向けた取組等について紹介します。
1 用語の解説(1)を参照
(農業経営体に占める経営耕地面積1.0ha未満層の割合は約5割)
令和4(2022)年の農業経営体に占める個人経営体の割合は95.9%、経営耕地面積1.0ha未満の農業経営体の割合は52.0%となっており、中小・家族経営等の経営体が農業経営体の大きな割合を占めています(図表2-3-1)。
また、生産現場では中小・家族経営等多様な経営体が産地単位で連携・協働して、農業生産や共同販売を行っており、地域社会の維持に重要な役割を果たしている実態に鑑み、生産基盤の強化に取り組むこととしています。
(家族経営協定締結数は6万戸)
家族経営に携わる世帯員が意欲とやりがいを持って農業経営に参画するとともに、仕事と生活のバランスに配慮した働き方を実現していく環境を整えるため、農林水産省は、経営方針や労働時間・休日、役割分担について、家族間の十分な話合いを通じて家族経営協定を締結することを普及・推進しています。協定の中で役割分担や就業条件等を明確にすることにより、仕事と家事・育児を両立しやすくなるほか、それぞれが研修会等に気兼ねなく参加しやすくなるなどの効果があります。
家族経営協定の締結数は増加傾向で推移しており、令和3(2021)年度末時点で前年度に比べ353戸増加し5万9,515戸となりました(図表2-3-2)。これは、令和4(2022)年の主業経営体数(20万4,700経営体)の約3割に相当する経営体が締結していることになります。令和3(2021)年度に締結した協定において取り決められた内容を見ると、農業経営の方針決定(94.4%)、労働時間・休日(94.0%)、農業面の役割分担(88.4%)、労働報酬(74.1%)が多くなっています。また、締結した主な理由は、親世代からの経営継承(27.9%)、新規就農(18.3%)、定期的な見直し(15.6%)が多くなっています。
農業の現場においても誰もがやりがいを持て、働きやすい環境を整えることが求められているところ、農林水産省は、家族経営協定締結数を令和7(2025)年度までに7万戸とすることを目標としています。
(農業支援サービス事業体の育成・普及を促進)

ガイドラインに沿ってサービスを提供する
農業支援サービス事業者リスト
URL:https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/service.html#gl
農林水産省は、生産現場における人手不足を解決するため、農作業の受託や、機械・機具のシェアリング、人材派遣、データ分析等様々な農業支援サービス事業体の育成・普及を促進するとともに、農業者がそれらのサービスを活用できる環境を整備しています。
農業支援サービスについては、その活用により経営の継続や効率化を図ることが重要であるところ、農林水産省は、令和7(2025)年までに農業支援サービスの利用を希望する農業の担い手のうち8割以上が実際に利用できていることを目標としており、令和4(2022)年度に実施した調査によると、利用を希望する農業の担い手のうち実際に利用している割合は59.6%となりました(図表2-3-3)。
農業者等が各種支援サービスを比較・選択できる環境整備の一環として、令和3(2021)年から、「農業支援サービス提供事業者が提供する情報の表示の共通化に関するガイドライン」に沿って情報表示を行う事業者について、Webサイトにリストを公開しています。
また、近年は、ドローンや収穫ロボット等のスマート農業(*1)技術を活用した次世代型の農業支援サービスを展開する事業体も見られており、そうしたサービスについても育成・普及を図っています。
1 用語の解説(1)を参照
(生産現場における短期労働力の確保に向けた取組を展開)
生産現場では多くの産地で人手不足が生じていることから、特に農繁期における労働力の確保が重要な課題となっています。
このため、農林水産省では、農繁期等における産地の短期労働力の確保に当たり、他産地・他産業との連携や労働力募集アプリの活用によるマッチング等を行う産地の取組を支援しています。
このほか、全国の生産現場では、高齢者、障害者等の多様な人材を確保し、それぞれの持つ能力を活かす取組が広がっているほか、近年、地方公共団体や農協で農業を副業として認める地域や地方公共団体独自の支援策を設けて「半農半X(*1)」を推進する地域も見られます。
1 第3章第7節を参照
(コラム)農業分野で地方公共団体職員の副業・兼業を認める動きが進展

副業としてりんごの生産現場で
農作業を行う弘前市職員
資料:青森県弘前市
果実や野菜等の生産現場では、収穫期等において慢性的な労働力不足が課題となっています。こうした状況に対応するため、近年、農業分野における地方公共団体職員の副業・兼業を認める動きが見られます。
青森県弘前市(ひろさきし)では、令和3(2021)年から、主要作物であるりんごの生産活動(摘果・着色管理・収穫等)に限り、同市職員の副業・兼業を認めています。
また、山形県では、令和4(2022)年から、主要作物であるさくらんぼの収穫作業等について、収穫時期(6~7月)に限り同県職員の副業・兼業を認める「やまがたチェリサポ職員制度」の運用を開始しています。
これらの地方公共団体では、副業・兼業を認めるに当たって、本来の職務遂行に支障を来さないよう、生産活動等に従事可能な時間の上限を設定することで、職員が生産活動等に参加する環境整備を図っています。
職員の副業・兼業を認める制度を導入した地方公共団体においては、産地の短期労働力の確保に加え、生産活動等に従事することにより、職員の能力向上や行政サービスの品質向上等につながることも期待されています。
(農業分野の外国人材の総数は前年に比べ増加)
農村における高齢化・人口減少が進行する中、外国人材を含め生産現場における労働力確保が重要となっています。
令和4(2022)年における農業分野の外国人材の総数は、新型コロナウイルス感染症に関する水際措置の緩和により新規入国が可能となったこと等から、前年に比べ約5千人増加し4万3,562人となっています(図表2-3-4)。
このうち、特定技能制度は、人手不足が続いている中で、外国人材の受入れのために平成31(2019)年に運用が開始された制度で、農業を含む12の特定産業分野が受入対象となり、「特定技能」の在留資格で一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れています。法務省の調査によると、令和4(2022)年12月末時点で、農業分野では16,459人の外国人材が同制度の下で働いており、前年同月末に比べ10,227人増加しました。
農林水産省では、特定技能制度の適切な運用を図るため、受入機関、業界団体、関係省庁で構成する農業特定技能協議会及び運営委員会を設置し、本制度の状況や課題の共有、その解決に向けた意見交換等を行っています。
(外国人技能実習生は前年に比べ1.8%増加)
外国人技能実習制度は、外国人技能実習生への技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的とした制度であり、我が国の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。農業分野においても全国の農業生産現場で多くの外国人技能実習生が受け入れられており、令和4(2022)年は、前年に比べ545人(1.8%)増加し3万575人となっています。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883








