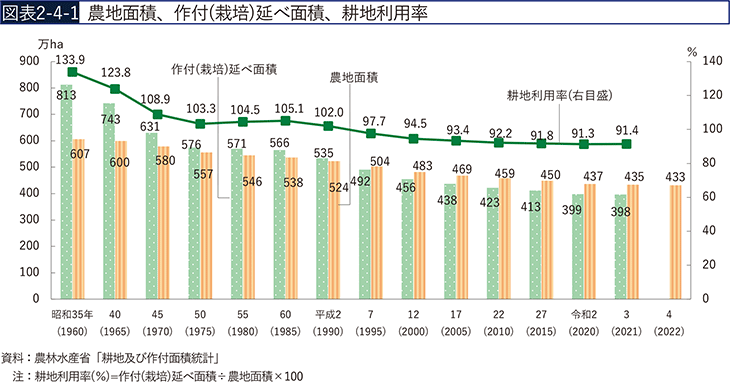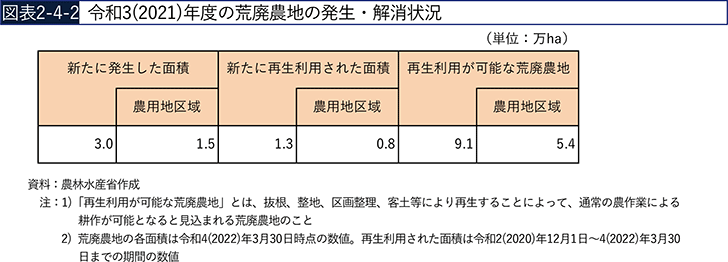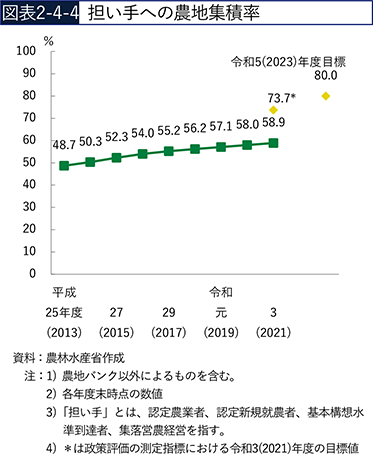第4節 担い手への農地集積・集約化と農地の確保

我が国においては、人口減少が本格化する中で、農業者の減少や荒廃農地(*1)の拡大が更に加速し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されています。このため、農業の成長産業化を進めていく上で、生産基盤である農地が持続性をもって最大限利用されるよう取組を進めていく必要があります。
本節では、担い手への農地の集積・集約化(*2)や農業経営基盤強化促進法に基づく地域計画の取組等の動きについて紹介します。
1、2 用語の解説(1)を参照
(農地面積は減少傾向で推移)
令和4(2022)年の農地面積(*1)は、荒廃農地からの再生等による増加があったものの、耕地の荒廃、転用等による減少を受け、前年に比べ2万4千ha減少し433万haとなりました(図表2-4-1)。作付(栽培)延べ面積も減少傾向が続いており、この結果、令和3(2021)年の耕地利用率は91.4%となっており、耕地利用率の向上が課題となっています。
1 農林水産省「耕地及び作付面積統計」における耕地面積の数値
(荒廃農地の新たな発生面積は3.0万ha)
令和3(2021)年度に新たに発生した荒廃農地面積は3.0万haとなりました(図表2-4-2)。これは、農業者の高齢化・病気・死亡や、担い手・労働力不足が主な理由として挙げられています。
一方、荒廃農地が新たに再生利用された面積は1.3万haとなりました。これは、市町村・農業委員会の働き掛けや、農地所有者・地域住民による保全活動によるものです。なお、再生利用が可能な荒廃農地面積は9.1万haとなっています。
今後とも、地域における積極的な話合いを通じて、多面的機能支払交付金や中山間地域等直接支払交付金の活用、担い手への農地の集積・集約化、農地の粗放的な利用(放牧等)等により荒廃農地の発生を防止するとともに、農業委員会による所有者等への利用の働き掛け等により荒廃農地の再生に取り組むこととしています。
(事例)蜜源作物の作付けによる再生農地の粗放的利用を推進(鹿児島県)

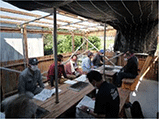
地域での話合いの様子
資料:枕崎市担い手育成総合支援協議会
鹿児島県枕崎市(まくらざきし)の田布川(たぶがわ)地区では、高齢者の割合が高く、地域住民による営農の継続や農地保全が将来的に危惧されるとともに、地区内の農業の担い手も減少しており、急速な農地の荒廃化が懸念されています。
こうした中、同地区では、蜜源を増やしたい養蜂業者と、農地の荒廃化を防ぎたい地域との希望が一致したことが契機となり、農山漁村振興交付金(最適土地利用対策)の支援を受けながら、蜜源作物の作付けによる再生農地の粗放的利用に取り組んでいます。
地域での話合いにより、条件の良い農地は、担い手が甘しょ等の生産を行う一方、条件の悪い農地は、粗放的な利用を行うこととしています。再生農地の粗放的利用では、菜の花やレンゲ草等の蜜源作物の作付けを行い、養蜂業者と連携して収益を得ることで持続性を確保することとしています。
同地区では、再生利用が可能な荒廃農地30aと遊休農地(*)100aの計130aを年間再生目標として掲げており、令和3(2021)年度から令和7(2025)年度までの5年間で658aの農地再生を目指しています。
用語の解説(1)を参照
(所有者不明農地への対応を推進)
相続未登記農地は、令和4(2022)年3月末時点で52.0万ha(うち遊休農地2万9千ha)、相続未登記のおそれのある農地は50万9千ha(うち遊休農地2万9千ha)存在しています。
通常、農地の貸付けには、所有者の同意を得る必要があるため、所有者不明農地があると、法定相続人を探索し、同意を集めなければならず、円滑な貸付けが困難となります。
このため、改正農業経営基盤強化促進法(*1)では、所有者不明農地や遊休農地も含め、将来の農地利用の姿を目標地図として明確化した上で、目標地図に位置付けられた農地の受け手に対し、農地中間管理機構(以下「農地バンク」という。)を通じて農地の集積・集約化を進めていくこととしています。
また、所有者不明農地や遊休農地の利用を促進するため、農業委員会による不明所有者の公示期間を6か月から2か月へ短縮し、農地バンクから農地の受け手に対する農地の貸付期間の上限を20年から40年に引き上げたところです。
1 正式名称は「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律」
(外国法人が議決権を有する日本法人等による農地取得は5.3ha)
令和3(2021)年に外国法人又は居住地が海外にある外国人と思われる者による農地取得はありませんでした(*1)。また、外国法人又は居住地が海外にある外国人と思われる者について、これらが議決権を有する日本法人又は役員となっている日本法人による農地取得は3社、5.3haとなっています(*2)。
我が国において農地を取得する際には、農地法において、取得する農地の全てを効率的に利用して耕作を行うこと、役員の過半数が農業に常時従事する構成員であること等の要件を満たす必要があります。このため、地域とのつながりを持って農業を継続的に営めない者は農地を取得することはできず、外国人や外国法人が農地を取得することは基本的に困難であると考えられます。
1 居住地が海外にある外国人と思われる者について、平成29(2017)年から令和3(2021)年までの累計は1者、0.1ha
2 平成29(2017)年から令和3(2021)年までの累計は6社、67.6ha(売渡面積5.2haを除く。)
(地域計画と活性化計画を一体的に推進)
地域での話合いにより、「人・農地プラン」の作成・実行を進めてきていましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者が減少し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地が利用されやすくなるよう、農地の集積・集約化に向けた取組を加速化することが喫緊の課題となっています。
このため、令和4(2022)年5月に、人・農地プランを法定化し、地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する「地域計画」を策定するとともに、それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集積・集約化を進めるための改正農業経営基盤強化促進法が成立しました。あわせて、農地の保全等により荒廃防止を図りつつ、農山漁村の活性化の取組を計画的に推進する改正農山漁村活性化法(*1)が成立しました。
農地については、農業上の利用が行われることを基本として、まず、改正農業経営基盤強化促進法に基づき、農業上の利用が行われる農用地等の区域について地域計画を策定し、その上で、農業生産利用に向けた様々な政策努力を払ってもなお農業上の利用が困難である農地については、農用地の保全等に関する事業を検討し、粗放的な利用等を行う農地について、必要に応じ改正農山漁村活性化法に基づく活性化計画を策定することが可能となりました。
また、地域の土地利用についての話合いを行い、両法による措置を一体的に推進することにより、地域の農地の利用・保全等を計画的に進め、農地の適切な利用を確保することとしています。
なお、改正農業経営基盤強化促進法においては、「目標地図」を含めた地域計画を市町村が作成することとしていますが、目標地図の素案については、市町村の求めに応じて、農業委員会(*2)が作成することとしており、目指すべき将来の農地利用の姿として、農業者ごとに利用する農用地等を明らかにすることとしています(図表2-4-3)。
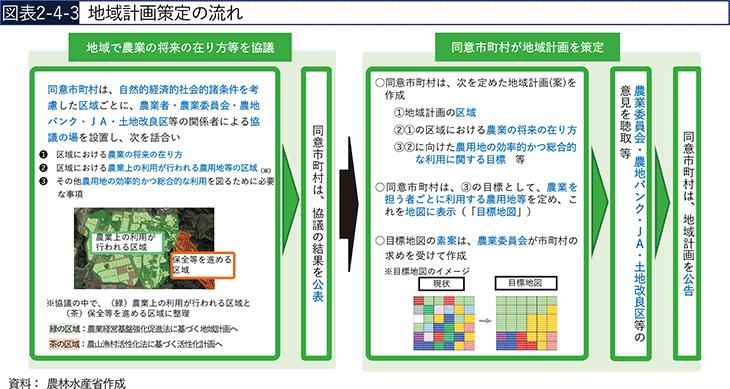
1 正式名称は「農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部を改正する法律」
2 第2章第11節を参照。最適化活動の推進に当たり、農業委員会は、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)及び農業委員の役割分担を定めた上で、両者がその役割に即して密接に連携することとしている。推進委員は、各担当区域内において、農地の出し手及び受け手の意向の把握等の最適化活動を実施し、農業委員は、推進委員の最適化活動の実施状況を把握した上で、推進委員に対して必要な支援を行う。
(事例)将来の農地利用の姿を明確化する「目標地図」の作成が進展(岐阜県)

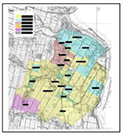
将来の目標地図例
資料:岐阜県養老町
岐阜県養老町(ようろうちょう)の笠郷(かさごう)地区では、全国に先駆けて目標地図を作成し、担い手による農地の集約化に向けた取組を加速させています。
同地区では、平成24(2012)年に、農林水産省が人・農地プランの作成例を示したことを契機として、将来的に目標地図が必要となると考え、関係機関と協力しながら、農地の集積状況等を整理したゾーニング地図を徐々に作りあげてきました。
地図の作成に当たっては、担い手による話合いから始め、ゾーニング地図を含む人・農地プランの素案の作成後、担い手以外の者を含めた地域検討会を開催し、幅広く意見を聴取しました。
同地区では、それまで相対や農地利用集積円滑化事業による利用権設定等を中心に農地の貸借を進めていましたが、目標地図に当たるゾーニング地図の作成により、地域の農地を誰が守っていくのかが明らかになり、地域内で農地の集約化の方針に関する合意形成が図られたことで、農地の集約化が進展しています。
(担い手への農地集積率は前年度に比べ0.9ポイント上昇)
農業者の減少が進行する中、農業の生産基盤を維持する観点から、農地の引受け手となる農業経営体の役割が一層重要となっているところ、農地の集積については、政府として、令和5(2023)年度までに8割を担い手に集積するという目標を設定しています。令和3(2021)年度の担い手への農地集積率は、前年度に比べ0.9ポイント上昇し58.9%となりました(図表2-4-4)。
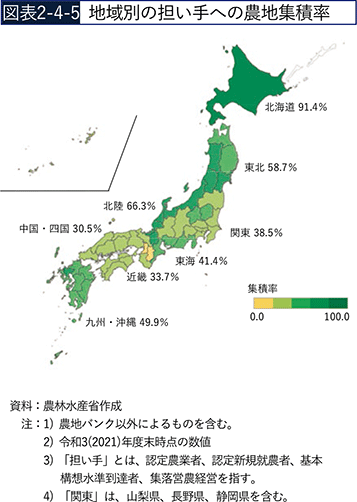
また、令和3(2021)年度の担い手への農地集積率を地域別に見ると、農業経営体の多くが担い手である北海道で9割を超えるほか、水田が多く、農業生産基盤整備や集落営農(*1)の取組が進んでいる東北、北陸でも高くなっています。一方、大都市を抱える地域(関東、東海、近畿)や、中山間地を多く抱える地域(近畿、中国・四国)では低くなっています(図表2-4-5)。
1 用語の解説(1)を参照
(農地バンクの活用が進展)
農地バンクにおいては、地域内に分散・錯綜(さくそう)する農地を借り受け、まとまった形で担い手へ再配分し、農地の集積・集約化を実現する農地中間管理事業を行っています(図表2-4-6)。
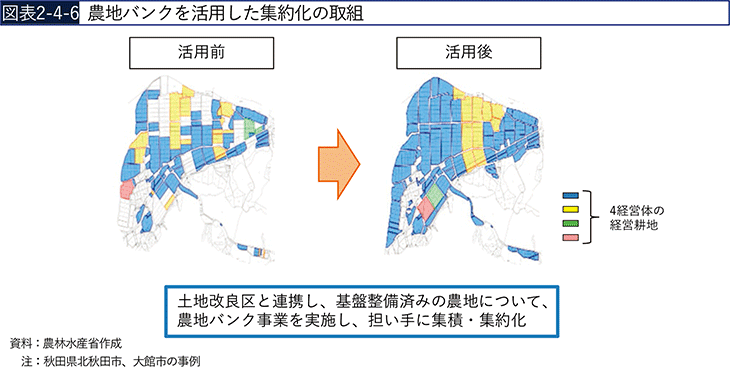
一方、令和5(2023)年度末までに8割の農地を担い手に集積するという目標に向けては、更なる取組の加速化が必要であり、農地が分散している状況を改善し、農地を引き受けやすくしていくことが重要です。そのため、改正農業経営基盤強化促進法に基づき、農地の集積・集約化を進めていくこととしています。
農地の集積・集約化を進めることによって、(1)作業がしやすくなり、生産コストや手間を減らすことができる、(2)スマート農業(*1)等にも取り組みやすくなる、(3)遊休農地の発生防止を図れるなどの効果が期待できます。
1 用語の解説(1)を参照
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883