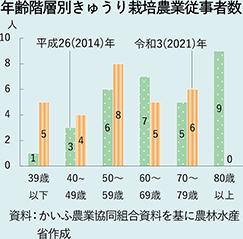第2節 力強く持続可能な農業構造の実現に向けた担い手の育成・確保

農業者の減少・高齢化等の課題に直面している我が国の農業が、成長産業として持続的に発展していくためには、効率的かつ安定的な農業経営を目指す担い手の育成・確保が必要です。
本節では、農業経営体の動向、認定農業者(*1)制度や法人化、経営継承・新規就農、女性が活躍できる環境整備等の取組について紹介します。
1 用語の解説(1)を参照
(1)農業経営体等の動向
(農業経営体数は減少傾向で推移)
農業経営体数は減少傾向で推移しており、令和4(2022)年は前年に比べ5.4%減少し97万5千経営体となりました。
個人経営体と団体経営体との比較では、全体の96%を占める個人経営体が前年に比べ5.7%減少し93万5千経営体となった一方、4%を占める団体経営体は前年に比べ1.5%増加し4万経営体となっています。
なお、個人経営体のうち、主業経営体は20万5千経営体、準主業経営体は12万6千経営体、副業的経営体は60万4千経営体となっています(図表2-2-1)。
(基幹的農業従事者の高齢化が進行)
基幹的農業従事者数は減少傾向で推移しており、令和4(2022)年は50~64歳層、65~74歳層が前年に比べそれぞれ9.3%、7.8%減少するなどにより、全体としては前年に比べ5.9%減少し122万6千人となりました。
このうち、65歳以上の基幹的農業従事者数が86万人と全体の約7割を占めています。また、令和4(2022)年の基幹的農業従事者の平均年齢は68.4歳となっており、高齢化が進行しています(図表2-2-2)。
なお、同年の団体経営体の役員・構成員数(農業従事60日以上)は前年に比べ4.0%増加し12万1千人、個人経営体及び団体経営体が雇用する常雇いは前年に比べ2.8%増加し15万2千人となりました。
また、基幹的農業従事者に占める49歳以下の割合は11.4%(14万人)であるのに対して、常雇いの同割合は52.8%(8万人)となり、雇用就農者に占める若年層の割合が高くなっています。
(2)認定農業者制度や法人化等を通じた経営発展の後押し
(農業経営体に占める認定農業者の割合は22.8%に増加)
認定農業者制度は、農業者が経営発展に向けて作成した農業経営改善計画を市町村等が認定する制度です。農業経営改善計画の認定数(認定農業者数)については、令和3(2021)年度末時点で前年度に比べ2.2%減少し22万2千経営体となりましたが、農業経営体に占める認定農業者の割合は増加傾向で推移しており、令和3(2021)年度末時点で22.8%となっています(図表2-2-3)。
このうち法人経営体の認定数は一貫して増加しており、同年度末時点で前年度に比べ3.2%増加し2万8千経営体となり、法人経営体に占める認定農業者の割合は86.9%となっています。また、農業経営改善計画の認定状況を営農類型別に見ると、年齢が低い階層ほど野菜作や畜産の単一経営の割合が高くなる一方、年齢が高い階層ほど、稲作の単一経営や複合経営の割合が高くなっています(図表2-2-4)。
農林水産省では、農業経営改善計画の実現に向け、認定農業者に対し、農地の集積・集約化(*1)や経営所得安定対策等の支援措置を講じています。
1 用語の解説(1)を参照
(法人経営体は3万2千経営体に増加)
農業経営の法人化には、経営管理の高度化や安定的な雇用、円滑な経営継承、雇用による就農機会の拡大等の利点があります。農林水産省は、効率的かつ安定的な農業経営を育成・確保する観点から、法人経営体数を令和5(2023)年度までに5万法人にする目標を設定しており、令和4(2022)年は前年から1.9%増加し3万2千経営体となりました(図表2-2-5)。
また、法人経営体では農業経営体全体よりも経営耕地面積の大きい層の割合が高いこともあり、農業経営体数に占める法人の割合は3.3%ですが、販売金額3,000万円以上の農業経営体数に占める法人の割合は34.7%、経営耕地面積に占める法人が経営する面積の割合は24.9%と高くなっています(図表2-2-6)。
農林水産省では、農業経営の法人化を進めるため、都道府県が整備している就農・経営サポートを行う拠点による経営相談や、専門家による助言等を通じた支援を行っています。
(法人化した集落営農組織数は5,694組織に増加)
集落営農(*1)組織は、地域農業の担い手として農地の利用、農業生産基盤の維持に貢献しています。令和4(2022)年の集落営農組織数は前年に比べ126組織減少し1万4,364組織となりました(図表2-2-7)。水稲やそば、野菜、農産加工品を生産・販売する組織が増加しています。
一方、法人化した集落営農組織数は、年々増加しており、令和4(2022)年は前年に比べ130組織増加し5,694組織となりました。また、令和4(2022)年の集落営農組織による現況集積面積(*2)は前年に比べ3千ha増加し46万7千haとなり、このうち法人によるものは23万5千ha(50.4%)と初めて非法人によるものを上回りました。
農林水産省では、集落営農組織に対し、法人化のほか、機械の共同利用や人材の確保につながる広域化、高収益作物の導入等、それぞれの状況に応じた取組を促進し、人材の確保や収益力向上、組織体制の強化、効率的な生産体制の確立を支援していくこととしています。
1 用語の解説(1)を参照
2 経営耕地面積と農作業受託面積を合計した面積
(事例)集落営農組織の広域化により効率的な生産体制を確立(福井県)


スマート農機による
効率的な田植え
資料:株式会社若狭の恵
福井県小浜市宮川(おばましみやがわ)地区の「株式会社若狭の恵(わかさのめぐみ)」は、集落営農組織の広域化により効率的な生産体制の確立と人材確保に取り組み、地域の農業を牽引(けんいん)しています。
同地区では平成27(2015)年に四つの集落営農組織を統合し、広域の集落営農法人である同社を設立しました。
同社は、農地の集積・集約化や集落営農組織の広域化により農業機械の所有を減らすなど効率的な生産体制を確立するとともに、柔軟に休暇を取得できる制度の導入等により、地区内外の若年農業者を多数雇用することが可能となりました。
一方、地区内の農業者の減少により、共同活動の継続が懸念されたことから、地区の全住民が構成員となる「一般社団法人宮川(みやがわ)グリーンネットワーク」が設立され、畦畔(けいはん)の草刈りや水路掃除等の共同活動を実施しています。同社は活動に対して対価を支払うなどにより、地区住民全体で同社の営農を支える体制を確立しています。
同社は、特別栽培米「ひまわり米」の作付けや高収益作物の栽培のほか、スマート農業等にも取り組んでおり、今後も積極的な農業経営により、地域農業の発展に注力していくこととしています。
(3)経営継承や新規就農、人材育成・確保等
(49歳以下の新規就農者数は2万人前後で推移)
令和3(2021)年の新規就農者数は前年に比べ2.7%減少し5万2,290人となりました(図表2-2-8)。その内訳を見ると、新規自営農業就農者が全体の約7割となる3万6,890人となっています。新規雇用就農者は、平成27(2015)年以降は1万人前後で推移しており、令和3(2021)年は前年に比べ15.1%増加し1万1,570人となりました。
また、将来の担い手として期待される49歳以下の新規就農者は、近年2万人前後で推移しています。令和3(2021)年は前年と同水準の1万8,420人となっており、調査を開始した平成18(2006)年以降、初めて新規雇用就農者数(8,540人)が新規自営農業就農者数(7,190人)を上回りました。
また、令和3(2021)年の49歳以下の新規雇用者(*1)数は10,720人であり、雇用直前の就業状態別に見ると、農業以外に勤務が51%、学生が21%、農業法人等に勤務が15%を占めています(図表2-2-9)。
1 新たに法人等に常雇いとして雇用され、農作業に従事することとなった「新規雇用就農者」のほか、雇用直前の就業状態が自営農業又は農業法人等に勤務の者も含む。ただし、農作業以外のみに従事した者は除く。
(次世代を担う農業者への経営継承や新規就農を後押し)
農業者等の高齢化と減少が進む中、地域農業を持続的に発展させていくためには、世代間のバランスのとれた農業構造を実現していくことが必要です。このため、農地はもとより、農地以外の施設等の経営資源や、技術・ノウハウ等を次世代の経営者に引き継ぎ、計画的な経営継承を促進するとともに、農業の内外からの若年層の新規就農を促進する必要があります。
農林水産省は、将来にわたって地域の農地利用等を担う経営体を確保するため、農業経営基盤強化促進法に基づく地域計画(*1)に位置付けられた経営体等の経営発展に向けた取組を市町村と一体となって支援するとともに、都道府県が整備している就農・経営サポートを行う拠点において相談対応や専門家による経営継承計画の策定支援、就農希望者と経営移譲希望者とのマッチング等を行うなど、円滑な経営継承を進めています。
一方、新規就農者の就農時の課題としては、農地・資金の確保、営農技術の習得等が挙げられており、就農しても経営不振等の理由から定着できないケースも見られています(図表2-2-10)。このため、農林水産省では、就農準備段階・就農直後の経営確立を支援する資金の交付や、地方と連携した機械・施設等の取得の支援、就農・経営サポートを行う拠点による相談対応や専門家による助言、雇用就農促進のための資金交付、市町村や農協等と連携した研修農場の整備、農業技術の向上や販路確保に対しての支援等を行っています。
また、「農業をはじめる.JP」、「新・農業人ハンドブック」により新規就農に係る支援策等の情報を提供するとともに、複数の民間企業による「農業の魅力発信コンソーシアム」では、ロールモデルとなる農業者の情報発信を通じて、若年層等が職業としての農業の魅力を発見する機会を提供しています。

新規就農の促進
(農業をはじめる.JP、新・農業人ハンドブック)
URL:https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/index.html

農業の魅力発信コンソーシアム
URL:https://yuime.jp/nmhconsortium/(外部リンク)
1 第2章第4節を参照
(事例)きゅうりタウン構想に基づき、地域ぐるみで新規就農者を育成(徳島県)
徳島県の海部次世代園芸産地創生推進協議会(かいふじせだいえんげいさんちそうせいすいしんきょうぎかい)は、移住による新規就農者の募集により産地拡大を図る「きゅうりタウン構想」に基づき、地域ぐるみで新規就農者を育成する取組を推進しています。
きゅうり産地である海部郡(かいふぐん)は、農業者の減少、高齢化により産地の規模が縮小しつつあったことから、美波町(みなみちょう)、牟岐町(むぎちょう)、海陽町(かいようちょう)、かいふ農業協同組合、県が同協議会を設立し、平成27(2015)年に「きゅうりタウン構想」を策定しました。
同協議会は、同構想に基づき、新規就農者を育成するために開講した「海部(かいふ)きゅうり塾(じゅく)」において養液栽培技術や営農計画等の研修を行うほか、研修期間中の収入や住宅の確保、就農に必要なレンタルハウスの整備等について、地域ぐるみで就農を支援する体制を構築しています。
また、海部きゅうり塾の塾生の募集に当たっては、修了生の1年目の農業所得の実績を提示しているほか、きゅうり栽培の魅力の発信にも注力しています。
こうした取組の結果、若年層の農業者が増加し、同地域できゅうり栽培を行う農業者の平均年齢は、平成26(2014)年の66.9歳から、令和3(2021)年には55.2歳と若返りが図られています。
移住就農者は、農業だけではなくサーフィンや釣り等も楽しめる暮らし方を発信しており、海部地域ならではの魅力ある農業の提案によって、定住人口の増加を通じた地域の活性化につながることが期待されています。
(農業高校・農業大学校による意欲的な取組が進展)
農業高校は全ての都道府県、農業大学校は41道府県において設置されています。農林水産省では、若年層に農業の魅力を伝え、将来的に農業を職業として選択する人材を育成するため、スマート農業(*1)や経営管理、環境配慮型農業等の教育カリキュラムの強化のほか、地域の先進的な農業経営者による出前授業等の活動を支援しています。
また、近年、GAP(*2)に取り組む農業高校・農業大学校も増加しており、令和4(2022)年2月末時点で111の農業高校及び31の農業大学校が第三者機関によるGAP認証を取得しています。GAPの学習・実践を通じて、農業生産技術の習得に加えて、経営感覚・国際感覚を兼ね備えた人材の育成に資することが期待されています。
一方、農業経営の担い手を養成する農業大学校の卒業生数は、平成25(2013)年度以降はほぼ横ばいで推移しており、令和3(2021)年度の卒業生数は1,737人、卒業後に就農した者は942人と卒業生全体の54.2%となっています(図表2-2-11)。また、同年度の卒業生全体に占める自営就農の割合は16.5%、雇用就農の割合は33.2%となりました。
1 農業大学校については、令和3(2021)年度末までに全ての学校においてスマート農業がカリキュラム化。農業高校については、スマート農業に関する内容が盛り込まれた新たな高等学校学習指導要領が令和4(2022)年度の1年生から年次進行で実施(第2章第8節参照)
2 用語の解説(2)を参照
(農地リース方式による農業参入は3,867法人に増加)
平成21(2009)年の農地法改正により、リース方式による参入が全面解禁されて以降、農業に参入する法人数は年々増加しており、令和2(2020)年12月末時点で3,867法人、農地リース法人の借入面積の合計は12,260haとなっています(図表2-2-12)。参入した法人格別の割合は、株式会社が64.5%、NPO法人等が23.9%、特例有限会社が11.6%となっています。
(農業者年金の政策支援を実施)
農業者年金は、農業従事者のうち厚生年金に加入していない自営農業に従事する個人が任意で加入できる年金制度です。同制度は平成13(2001)年に抜本的に見直され、農業者の減少・高齢化等に対応した積立方式・確定拠出型を採用しており、青色申告を行っている認定農業者等やその者と家族経営協定を結び経営参画している配偶者・後継者等一定の要件を満たす対象者の保険料負担を軽減するための政策支援を実施し、農業者の老後生活の安定と農業者の確保を図っています。
(4)女性が活躍できる環境整備
(49歳以下の女性の新規就農者数は前年に比べ2%増加し5,540人)
令和4(2022)年における女性の基幹的農業従事者数は、前年に比べ6.3%減少し48万人になりました(図表2-2-13)。女性の基幹的農業従事者は全体の39.2%を占めており、重要な担い手となっています。年齢階層別に女性の割合を見ると、50~64歳層で43.4%を占める一方、49歳以下層では29.6%となりました。
令和3(2021)年における女性の新規就農者数は、前年に比べ14.7%減少し1万2,750人となりました。また、新規就農者に占める女性の割合は3.4ポイント低下し24.4%となった一方、49歳以下の女性の新規就農者数は前年に比べ2.0%増加し5,540人となりました(図表2-2-14)。就農形態別の内訳は、新規自営農業就農者が8,030人、新規雇用就農者が4,020人、新規参入者が700人となりました。新規雇用就農者に占める女性の割合は34.7%と比較的高く、女性の新規雇用就農者の約8割が49歳以下となっています。
(認定農業者に占める女性の割合は前年度と同水準の5.1%)
女性の認定農業者数は、令和3(2021)年度末時点で前年度から164人減少し1万1,440人となりました(図表2-2-15)。一方、全体の認定農業者数に占める女性の割合は、令和3(2021)年度は前年度と同水準の5.1%となりました。
また、認定農業者制度には、家族経営協定(*1)等を締結している夫婦による共同申請が認められており、その認定数は5,764経営体となっています。
農業や地域に人材を呼び込み、また、農業を発展させていく上で、農業経営における女性参画は重要な役割を果たしているところ、農林水産省は、女性の農業経営への主体的な関与をより一層推進するため、認定農業者に占める女性の割合を令和7(2025)年度までに5.5%にする目標を設定しています。
1 第2章第3節を参照
(農業委員、農協役員に占める女性の割合は年々増加)
農業委員会等に関する法律及び農業協同組合法においては、農業委員や農協理事等の年齢や性別に著しい偏りが生じないように配慮しなければならないことが規定されています。農業委員や農協役員に占める女性の割合は増加傾向で推移しており、令和3(2021)年度の農業委員に占める女性の割合は、前年度に比べ0.1ポイント増加し12.4%に、令和4(2022)年度の農協役員に占める女性の割合は前年度に比べ0.4ポイント増加し9.7%になりました (図表2-2-16)。
地域農業に関する方針策定への女性参画を推進するため、農林水産省は、女性の割合について令和7(2025)年度までに農業委員は30%、農協役員は15%にすることを目標としています。この目標の達成に向けて、各組織に対して女性登用に取り組むよう働き掛けており、女性の参画拡大に向けては、令和3(2021)年度末時点で農業委員会では98.7%(*1)、農協では81.5%(*2)が女性登用に関する目標を設定しています。また、農林水産省では、令和4(2022)年3月に、「農業協同組合・農業委員会 女性登用の取組事例と推進のポイント」を公表し、女性登用の更なる推進に取り組んでいます。
また、土地改良区等(土地改良区連合を含む。)の理事に占める女性の割合は、令和7(2025)年度までに10%以上とする目標を定めているところ、令和3(2021)年度末時点で0.6%にとどまっています。このため、農林水産省は、令和4(2022)年度に、土地改良団体における男女共同参画の手引きを活用して全国26府県において土地改良区役職員を対象とした研修を実施するなど、土地改良区関係者の男女共同参画に対する理解の促進や意識改革を進めながら、比較的組織運営体制の整った土地改良区等から女性理事の登用等の取組を進めることとしています。
1 令和3(2021)年度末時点は設定予定で、令和4(2022)年9月16日時点で設定済みの農業委員会を含む。
2 令和3(2021)年度末時点で設定予定の農協を含む。
(女性が働きやすく、暮らしやすい環境を整備する必要)
農村においては、依然として、家事や育児は女性の仕事であると認識され、男性に比べて負担が重い傾向が残っています。総務省の調査によると、令和3(2021)年における女性の農林漁業従事者の1日(週全体平均)の家事と育児の合計時間は2時間57分で、男性の26分に比べて家事・育児の時間は長くなっています(図表2-2-17)。
男性・女性が家事、育児、介護等と農業への従事を分担できるような環境を整備することは、女性がより働きやすく、暮らしやすい農業・農村をつくるために不可欠です。そのためには、家事や育児、介護は女性の仕事であるという意識を改革し、女性の活躍に関する周囲の理解を促進する必要があります。このため、労働に見合った報酬や収益の配分、仕事や家事、育児、介護等の役割分担、休日等について家族で話し合い、明確化する取組である家族経営協定の締結を推進しています。
また、農業経営における女性の地位・責任を明確化するため、農業経営改善計画における共同申請を促進しています。
さらに、農業において女性が働きやすい環境整備に向けて、農業法人等における男女別トイレ、更衣室、託児スペース等の確保に対する支援や、子育て中の女性等が働きやすい仕組みづくりについての優良事例の普及を行っています。
(地域をリードする女性農業者の育成と農村の意識改革が必要)
令和4(2022)年における女性の経営への参画状況を見ると、経営主が女性の個人経営体は、個人経営体全体の6.2%、経営主が男性だが、女性が経営方針の決定に参画している割合は25.9%となっており、女性が経営に関与する個人経営体は全体の32.1%となっています(図表2-2-18)。
今後の農業の発展、地域経済の活性化のためには、女性の農業経営への参画を推進し、地域農業の方針策定にも参画する女性リーダーを育成していくことが必要です。併せて、女性活躍の意義について、男性も含めた地域での意識改革を行うことにより、女性農業者の活躍を後押ししていくことが重要です。
これまで農村を支えてきた女性農業者が直面してきた、生活面や経営面での悩みと解決策等、過去の知見や経験を新しい世代に伝えることや、学びの場となるグループを作り、グループ同士のネットワークをつなげることは女性農業者の更なる育成に有効と言えます。
また、女性農業者が持つ視点を活用し、消費者や教育機関等、農業者の枠を超えたネットワーク形成を進めることも期待されます。
このように活動の幅を更に広げていくことは、農業・農村に新しい視点をもたらすとともに、女性農業者の農業・農村での存在感の向上にもつながると考えられます。

チャレンジする女性農林漁業者
のための支援策
URL:https://www.maff.go.jp/j/keiei/jyosei/gaido.html
このため、農林水産省は、地域のリーダーとなり得る女性農業経営者の育成、女性グループの活動支援、女性が働きやすい環境づくり、女性農業者の活躍事例の普及等に取り組むとともに、家族経営協定の締結、地域における育児と農作業のサポート活動等の取組を支援しています。また、令和4(2022)年度から、女性農業者を始めとする多様な人材の活躍に向けて、農村地域の男性の意識改革を促すこと等をねらいとした研修会の開催等の取組を支援しています。
(コラム)「農業女子プロジェクト」の活動等、女性農業者の取組が更に展開
平成25(2013)年に設立された「農業女子プロジェクト」は、社会全体での女性農業者の存在感を高め、女性農業者自らの意識改革や経営力発展を促すとともに、職業としての農業を選択する若手女性の増加を図ることを目指し、多様な活動を展開しています。
同プロジェクトのメンバーは、令和5(2023)年3月末時点で、農業女子メンバー944人、参画企業35社、教育機関8校にまで拡大しており、農業女子同士のネットワークづくりも進められています。同プロジェクトでは、参画企業と協同し、女性の希望を取り入れた農機具や農作業着の開発等を行う取組や、高校・大学等の教育機関と連携して「チーム“はぐくみ”」を結成し、農業女子による出前授業等を実施する活動が行われています。
また、結婚就農した女性が農産物の加工等6次産業化(*)で活躍する事例や、女性農業者が地域単位でグループを結成し、農産物の販売促進を行う取組も見られます。
令和5(2023)年2月には、女性農業者及び若者のビジネスアイデアや個性を活かした農業経営を行う家族・法人等を「農業女子アワード2022」として表彰しました。
今後とも、女性農業者が日々の生活や仕事、自然との関わりの中で培った知恵を様々な企業の技術・ノウハウ・アイデア等と結び付け、新たな商品やサービス、情報を生み出すとともに、社会に広く発信し、農業で活躍する女性の姿を広く周知していくこととしています。
用語の解説(1)を参照
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883