第1節 農業生産の動向

我が国の農業総産出額は長期的に減少し、近年はおおむね横ばい傾向で推移しています。こうした中、足下では、原油価格・物価高騰等の影響や新型コロナウイルス感染症の影響の長期化により、我が国の農業生産にも変化が見られています。
本節では、このような農業生産の動向について紹介します。
(1)農業総産出額の動向
(農業総産出額は前年に比べ1.1%減少の8.8兆円)
農業総産出額は、近年、米、野菜、肉用牛等における需要に応じた生産の取組が進められてきたこと等により9兆円前後で推移してきましたが、令和3(2021)年は畜産の産出額が3.4兆円を超えて過去最高となった一方、主食用米や野菜等の価格が低下したこと等から、前年に比べ1.1%減少し8兆8,384億円となりました(図表2-1-1)。
部門別の産出額を見ると、米の産出額は、前年に比べ16.6%減少し1兆3,699億円となりました。これは、作付面積の削減により生産量が減少したものの、前年産までの作付転換が十分進まなかったことを受けて、民間在庫量が比較的高い水準で推移したことから、主食用米の取引価格が低下したこと等によるものと考えられます。
野菜の産出額は、前年に比べ4.7%減少し2兆1,467億円となりました。これは、北海道における夏季の干ばつの影響によりたまねぎの出荷量が減少し価格が上昇した一方、秋季から冬季にかけての高温等により多くの品目の出荷量が増加し前年よりも安値となったこと等が影響したものと考えられます。
果実の産出額は、前年に比べ4.8%増加し9,159億円となりました。これは、主としてりんごにおける春先の凍霜害(とうそうがい)による被害や夏の高温乾燥による小玉傾向、みかんにおける隔年結果の影響等により生産量が減少し価格が上昇したこと、ぶどう等において比較的高価格で取引される優良品種への転換が進んだこと等が寄与したものと考えられます。
畜産の産出額は、前年に比べ5.2%増加し3兆4,048億円となり、引き続き全ての部門の中で最も大きい値となりました(図表2-1-2)。このうち肉用牛は、生産基盤の強化に伴い和牛の生産頭数が増加したことや、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を大きく受けた前年から需要が回復し、価格が上昇したこと等により、産出額が増加したものと考えられます。生乳については、生産基盤強化の取組の進展を背景に生産量が増加したこと等により、産出額が増加したものと考えられます。豚については、大規模化の進展により生産頭数は増加したものの、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う巣ごもり需要で価格が高く推移した前年より価格が下回ったこと等が影響し、産出額が減少したものと考えられます。
(都道府県別の農業産出額は、北海道が1.3兆円で1位)
令和3(2021)年の都道府県別の農業産出額を見ると、1位は北海道で1兆3,108億円、2位は鹿児島県で4,997億円、3位は茨城県で4,263億円、4位は宮崎県で3,478億円、5位は熊本県で3,477億円となっています(図表2-1-3)。
農業産出額上位5位の道県で、産出額の1位の部門を見ると、北海道、鹿児島県、宮崎県、熊本県では畜産、茨城県では野菜となっています。
(2)主要畜産物の生産動向
(繁殖雌牛の飼養頭数は前年に比べ増加)
令和4(2022)年の繁殖雌牛の飼養頭数は、前年に比べ0.6%増加し63万7千頭となりました(図表2-1-4)。
また、令和4(2022)年の肥育牛(肉用種)の飼養頭数は、前年に比べ1千頭減少し79万8千頭となりました(図表2-1-5)。
(牛肉の生産量は前年度並)
令和3(2021)年度の牛肉の生産量は、肉専用種や交雑種で増加した一方、ホルスタイン種等で減少したことから、前年度並の33万6千tとなりました(図表2-1-6)。
食料自給率(*1)の向上に向けて、国内生産の維持・増大が求められているところ、農林水産省では、牛肉の生産量については、繁殖雌牛の増頭推進、和牛受精卵の増産・利用推進、公共牧場等のフル活用による増頭等の克服すべき課題に対応し、令和12(2030)年度までに40万tとすることを目標としています。
1 用語の解説(1)を参照
(乳用牛の飼養頭数は前年に比べ増加、生乳の生産量は前年度に比べ増加)
令和4(2022)年の乳用牛の飼養頭数は、前年に比べ1.1%増加し137万1千頭となりました(図表2-1-7)。
また、令和3(2021)年度の生乳の生産量は、都府県では前年度に比べ1.8%増加し333万5千t、北海道では前年度に比べ3.7%増加し431万1千tとなりました。その結果、全国では前年度に比べ2.9%増加し764万7千tとなりました(図表2-1-8)。
(豚肉、鶏肉の生産量は前年度に比べ増加、鶏卵の生産量は減少)
令和3(2021)年度の豚肉の生産量は、畜産クラスター(*1)事業の推進を通じ生産基盤の強化が図られたこと等により、前年度に比べ0.7%増加し令和12(2030)年度目標(92万t)を上回る92万3千tとなりました(図表2-1-9)。
また、令和3(2021)年度の鶏肉の生産量は、巣ごもり需要の継続等により需要が堅調に推移したこと等から、前年度に比べ1.5%増加し167万8千tとなりました。農林水産省では、鶏肉の生産量については、家畜疾病に対する防疫対策の徹底等の克服すべき課題に対応し、令和12(2030)年度までに170万tとすることを目標としています。
このほか、令和3(2021)年度の鶏卵の生産量は、高病原性鳥インフルエンザ(*2)の影響等により、前年度に比べ0.8%減少し258万2千tとなりました(図表2-1-10)。
1 第2章第7節を参照
2 用語の解説(1)を参照
(飼料作物の収穫量は前年産に比べ僅かに増加)
令和3(2021)年産の飼料作物の収穫量(飼料用米を除く。)は、単収の高い青刈りとうもろこし等の飼料作物の作付けが拡大したことから、前年産に比べ7千t(TDN(*1)ベース)増加し332万4千TDNtとなりました(図表2-1-11)。
また、令和4(2022)年産の飼料作物の作付面積は、前年産に比べ2.5%増加し102万6千haとなりました。農林水産省では、飼料作物の生産量については、優良品種の普及による単収向上等の克服すべき課題に対応し、令和12(2030)年度までに519万TDNtとすることを目標としています。
さらに、令和3(2021)年度のエコフィード(*2)の製造数量は、前年度に比べ0.9%増加し110万TDNtとなりました。これは、濃厚飼料全体の約5.4%に当たります(図表2-1-12)。農林水産省では、過度な輸入依存から脱却し、国産飼料生産基盤に立脚した畜産物生産を効率的に推進するため、飼料用とうもろこし等の国産飼料の生産・利用拡大や、コントラクター等の飼料生産組織の運営強化、牧草地の整備、地域の未利用資源を新たに飼料として活用するためのエコフィードの生産・利用を推進しています。
1 Total Digestible Nutrientsの略で、家畜が消化できる養分の総量
2 食品残さ等を有効活用した飼料のこと。環境にやさしい(ecological)や節約する(economical)等を意味するエコ(eco)と飼料を意味するフィード(feed)を併せた造語
(コラム)飼料増産に向け、子実とうもろこしの大規模実証試験を実施

子実とうもろこし収穫作業に係る
現地見学会
資料:JA全農
全国農業協同組合連合会(以下「JA全農」という。)は、古川(ふるかわ)農業協同組合(以下「JA古川」という。)と連携し、水田の転作作物として子実(しじつ)とうもろこしの生産・乾燥調製・飼料原料利用を一貫して実施する大規模実証試験に取り組んでいます。
令和4(2022)年度は、JA古川管内の大豆生産組合を中心とした31経営体が参加して91.5haの作付けを行いました。その後収穫した子実とうもろこしは、宮城県内の飼料工場で配合飼料の原料としたほか、一部は単味飼料として肥育和牛への給与試験を行い、嗜好性(しこうせい)や栄養価の確認を行いました。実証試験は同年度から3年程度継続する計画です。
将来的には、単位面積当たりの労働時間が短い省力転作作物として大豆との輪作体系に組み込み、作付面積を拡大して、主食用米の需給環境改善と米価の安定、食料自給率の向上、耕畜連携による地域資源の循環を目指すこととしています。
(3)園芸作物等の生産動向
(野菜の国内生産量は前年度に比べ減少)
令和3(2021)年度の野菜の国内生産量は、前年度に比べ3.7%減少し1,102万tとなりました(図表2-1-13)。
農林水産省では、産地の収益力強化に必要な基幹施設の整備、実需者ニーズに対応した園芸作物の生産・供給を拡大するための園芸産地の育成、農業者等が行う高性能機械・施設の導入等に対して総合的に支援し、野菜の生産振興に取り組んでいます。
(事例)農業従事者が働きやすい作業環境を整え、高品質の野菜栽培を展開(福井県)


農作業環境の整備に取り組む経営者

トマトの高度環境制御栽培
資料:三つ星株式会社
福井県坂井市(さかいし)の三つ星(みつぼし)株式会社は、「普段使いの上質野菜」を栽培する農業生産法人であり、50aのハウスでトマトの高度環境制御栽培を行うとともに、8haの水田及び砂丘地で白ネギの生産等も行っています。
同社では、トマトの栽培施設において、有機培地を使用し、地下100mからくみ上げる清浄な水で栽培するとともに、気化熱冷房システムを導入し、旨味成分を多く含むトマトを4~12月まで継続して出荷しています。
また、同社では、従業員の誰もが同一の作業を担当することがきるよう、農作業をマニュアル化するとともに、クラウド型の農業支援システムを活用し作業記録の管理を行っています。ハウス内には音楽や時報、作業終了5分前のアナウンスが流れ、作業に集中しやすい環境も整えられています。
夫婦で共同代表取締役を努める冨田美和(とみたみわ)さんは、農業女子プロジェクトのメンバーとしても活動を行っており、今後とも、高品質のトマト栽培に加え、障害者が働きやすい農作業環境の整備等、地域を大切にし、農地や自然環境の保全に最善を尽くすことを目指した農業経営を進めていくこととしています。
(果実の国内生産量は前年度に比べ減少)
令和3(2021)年度の果実の生産量は、りんごが春先の凍霜害、うんしゅうみかんが隔年結果の影響等により生産量が減少したことから、前年度に比べ2.8%減少し259万9千tとなりました(図表2-1-14)。
農林水産省では、果実の生産量については、省力樹形や機械作業体系の導入、担い手や労働力の確保等の克服すべき課題に対応し、令和12(2030)年度までに308万tとすることを目標としています。
(事例)広島県産レモンのブランド化と生産拡大を推進(広島県)


広島県産レモン
資料:広島県果実農業協同組合連合会

広島レモンサイダー
資料:広島県果実農業協同組合連合会
広島県東広島市(ひがしひろしまし)の広島県果実(ひろしまけんかじつ)農業協同組合連合会(以下「JA広島果実連」という。)は、広島県産レモンのブランド価値の向上や生産拡大に取り組んでいます。
国産レモンの約6割を同県産が占めていますが、その認知度が県内外で低かったため、同県による観光キャンペーンと連携して認知度を向上させるとともに、県内の小売店等で年間を通じて売場を確保し、販売の促進を図りました。
また、一年を通じて供給できるよう、ベースとなる露地栽培に加え、冷蔵貯蔵、ハウス栽培、鮮度保持フィルムで個包装した商品の開発により周年供給体制の確立を進めました。
くわえて、更なる生産拡大に向け、改植・新植後の早期成園化と生産者の未収益期間短縮のため、JA広島果実連が育てた2年生大苗を生産者に供給しています。
令和4(2022)年5月に開催された日米首脳会談の夕食会では、同県産レモンの果汁を使った「広島レモンサイダー」が使われ、米国大統領との乾杯の際に、広島の味として脚光を浴びました。
JA広島果実連では、令和5(2023)年5月のG7広島サミットを好機と捉え、同県産レモンの販売促進と生産振興に取り組んでいくこととしています。
(花きの産出額は前年産に比べ減少)
令和2(2020)年産の花きの産出額は、前年産に比べ5.4%減少し3,296億円となりました。また、作付面積は前年産に比べ3.2%減少し2万5千haとなりました(図表2-1-15)。
農林水産省では、需要に応じた花き品目の安定供給、生産性の向上や流通の効率化に資する技術導入、日常生活における花き消費の拡大、国際園芸博覧会を通じた日本産花き・花き文化のPR等を進めることとしています。
(茶の栽培面積は前年産に比べ減少)
令和4(2022)年産の茶の栽培面積は、前年産に比べ2.9%減少し3万7千haとなりました(図表2-1-16)。また、荒茶の生産量は、前年産に比べ1.2%減少し7万7千tとなりました。
農林水産省では、園地の老園化や機械化の遅れ等の課題の克服に向けて、茶樹の改植・新植等の支援を行うとともに、スマート農業(*1)技術の研究・開発や実証・導入の推進を行っています。
1 用語の解説(1)を参照
(薬用作物の栽培面積は前年産に比べ減少)
令和2(2020)年産の漢方製剤等の原料となるミシマサイコやセンキュウ等の薬用作物の栽培面積は、国内需要の約8割を占めている中国産の価格高騰等により、製薬会社において国内産地育成のニーズが高まっているものの、実需者が求める品質を確保するための栽培技術等の確立が遅れていること等から、前年産に比べ5.5%減少し494haとなりました(図表2-1-17)。
一方、漢方製剤の生産金額は直近5年間で30.0%増加するなど、薬用作物の需要は今後も増加することが見込まれています。
農林水産省では、薬用作物の栽培面積については、実需者主導の産地づくり等を進め、令和7(2025)年度までに630haとすることを目標としています。

ミシマサイコの圃場
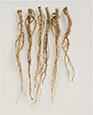
ミシマサイコ
(生薬名:柴胡(さいこ))
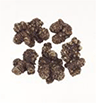
センキュウ
(生薬名:川芎(せんきゅう))
(てんさいの収穫量は前年産に比べ減少)
令和4(2022)年産のてんさいの作付面積は、前年産に比べ4.0%減少し5万5千haとなりました(図表2-1-18)。また、収穫量は、前年産に比べ12.7%減少し354万5千tとなりました。このほか、糖度は前年産と比べ0.1ポイント減少し16.1度となりました。
てんさいは、労働時間が長く省力化が課題となっていることを踏まえ、農林水産省では、労働時間縮減に向け、省力化や作業の共同化、労働力の外部化や直播(ちょくはん)栽培(*1)体系の確立・普及等を推進しています。
1 圃場に直接種をまく方法で、作業の省力化や経費節減のために有効な栽培方法
(さとうきびの収穫量は前年産に比べ減少)
令和3(2021)年産のさとうきびの収穫面積は、前年産に比べ3.6%増加し2万3千haとなりました(図表2-1-19)。また、収穫量は前年産に比べ1.7%増加し135万9千tとなりました。このほか、糖度は前年産に比べ0.8ポイント上昇し15.1度となりました。
令和4(2022)年産の収穫面積は、前年産に比べ0.5%増加し2万3千ha、収穫量は前年産に比べ5.2%減少し128万9千tを見込んでいます。
さとうきびは、規模拡大が進んでいるものの、人手不足等により適期に作業ができないこと等から単収が低迷していることを踏まえ、農林水産省では、通年雇用による作業受託組織の強化等の地域の生産体制強化、機械収穫や株出(かぶだ)し栽培(*1)に適した新品種「はるのおうぎ」の普及等に取り組んでいます。
1 さとうきび収穫後に萌芽する茎を肥培管理し、1年後のさとうきび収穫時期に再度収穫する栽培方法
(かんしょの収穫量は前年産に比べ増加)
令和4(2022)年産のかんしょの作付面積は、前年産並の3万2千haとなりました(図表2-1-20)。一方、収穫量は前年産に比べ5.8%増加し71万1千tとなりました。
農林水産省では、共同利用施設の整備や省力化のための機械化体系確立等の取組を支援しています。特にでん粉原料用かんしょについては、多収新品種への転換や生分解性マルチの導入等の取組を支援しています。
(ばれいしょの収穫量は前年産に比べ減少)
令和3(2021)年産のばれいしょの作付面積は、前年産に比べ1.4%減少し7万1千haとなりました(図表2-1-21)。また、収穫量は前年産に比べ1.4%減少し217万5千tとなりました。
令和4(2022)年産の春植えばれいしょの作付面積は6万9千ha、収穫量は224万5千tとなりました。
ポテトチップス向け等の加工用ばれいしょは、メーカーから国産原料の供給要望が強いことから、国産ばれいしょの増産が課題となっています。さらに、ポテトチップスを含めた全ての加工食品について、原料原産地表示制度が義務化(*1)されたことにより、国産志向が高まっています。
このような中、農林水産省では、増産に向け省力化のための機械導入の取組や、収穫時の機上選別を倉庫前集中選別等に移行する取組を支援しています。
1 第1章第7節を参照
(4)米の生産動向
(主食用米の生産量は前年産に比べ減少)
令和4(2022)年産の主食用米の作付面積は、需要量の減少や他作物への作付転換が進んだこと等から、前年産に比べ4.0%減少し125万1千haとなりました。また、生産量は、前年産に比べ4.4%減少し670万1千tとなりました(図表2-1-22)。
(米粉用米の生産量は前年度に比べ増加)
令和3(2021)年度の米粉用米の生産量は、主食用米からの作付転換が進んだことから前年度に比べ24.6%増加し4万2千tとなりました(図表2-1-23)。
令和3(2021)年度の米粉用米の需要量は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響から業務用需要が減少した前年度に比べ13.9%増加し4万1千tとなりました。
農林水産省では、引き続き米粉用米の需要拡大を推進するとともに、海外のグルテンフリー市場に向けて輸出拡大を図ることとしており、さらに、令和5(2023)年度からは専用品種の栽培や加工適性の実証を支援することとしています。
米粉用米の生産量については、大規模製造ラインに適した技術やアルファ化米粉等新たな加工法を用いた米粉製品の開発による加工コストの低減等の克服すべき課題に対応し、令和12(2030)年度までに13万tとすることを目標としています。

広がる!米粉の世界
URL:https://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/komeko/
(事例)アレルギーの心配が少ない国産米粉パンを開発・販売(新潟県)


国産米粉100%の食パンと丸パン
資料:株式会社タイナイ
新潟県胎内市(たいないし)の米粉パン製造事業者である株式会社タイナイでは、新潟県産米粉を原材料として使用し、グルテンフリーやアレルギーの心配が少ないといった米粉の強みを活かした製品づくりを進めています。
価格が高騰する輸入小麦の代替品として国内で自給できる米粉に注目が集まる中、同社では、アレルゲン特定原材料等28品目不使用の米粉パンを製造・販売しています。
開発された国産米粉100%のパンは、米に含まれる粘り成分であるアミロペクチンの作用により、きめが細かく、もちっとした食感になっています。また、粒子の細かい微細米粉を使用することにより、小麦粉を使用しなくともふんわりさせることが可能となっています。
同社では、米粉パンが主食として定着するよう、地元サッカーチームとも連携して米粉パンの販売促進を積極的に進めており、将来的にはグルテンフリー需要の高い欧米市場も視野に入れながら、事業拡大を図っていくこととしています。
(飼料用米の作付面積は前年産に比べ増加)
令和4(2022)年産の飼料用米の作付面積は、既存の農機具等が活用できるといった取り組みやすさから、主食用米からの作付転換が大幅に進み、前年産に比べ22.7%増加し14万2千haとなりました(図表2-1-24)。また、生産量についても、前年産に比べ14.9%増加し令和12(2030)年度目標(70万t)を上回る76万1千tとなりました。
今後は、より定着性が高く、安定した供給につながる多収品種への切替えを進めていく観点から、令和6(2024)年産以降、一般品種に対する飼料用米の支援単価を段階的に引き下げていくこととしています。
(5)麦・大豆の生産動向
(小麦の作付面積は前年産に比べ増加)
令和4(2022)年産の小麦の収穫量は、北海道における天候不順により、前年産に比べ9.4%減少し99万4千tとなりました(図表2-1-25)。一方、作付面積は、単収の高い品種の開発・普及や、排水対策等の栽培技術の導入が進んだことから、前年産に比べ3.3%増加し22万7千haとなりました。
令和4(2022)年産の大麦・はだか麦の作付面積、収穫量はそれぞれほぼ前年産並みの6万3千ha 、23万3千tとなりました(図表2-1-26)。
農林水産省では、小麦の生産量については、国内産小麦の需要拡大に向けた品質向上と安定供給、畑地化の推進、団地化・ブロックローテーションの推進、排水対策の更なる強化やスマート農業技術の活用による生産性の向上等の克服すべき課題に対応し、令和12(2030)年度までに小麦の生産量を108万tとすることを目標としています。
(大豆の作付面積は前年産に比べ増加)
令和4(2022)年産の大豆の収穫量は、東北や北陸において、開花期以降の大雨や日照不足により、着さや数の減少や粒の肥大抑制があったことから、前年産に比べ1.5%減少し24万3千tとなりました(図表2-1-27)。一方、令和4(2022)年産の作付面積は前年産に比べ3.7%増加し15万2千haとなりました。
農林水産省では、大豆の生産量については、国産原料を使用した大豆製品の需要拡大に向けた生産量・品質・価格の安定供給、畑地化の推進、耐病性・加工適性等に優れた新品種の開発・導入の推進等の克服すべき課題に対応し、令和12(2030)年度までに34万tとすることを目標としています。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883































