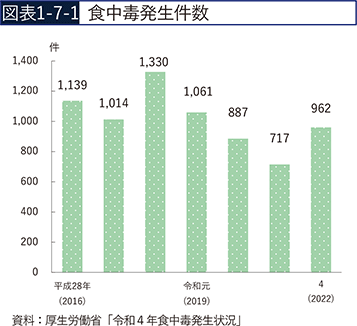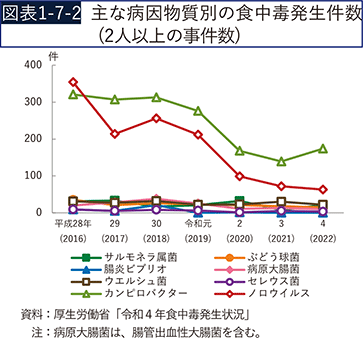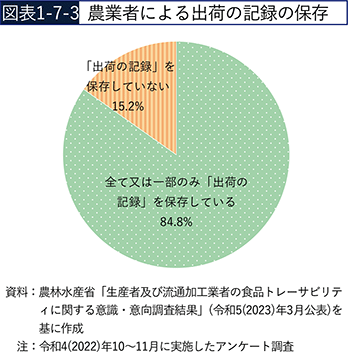第7節 国際的な動向等に対応した食品の安全確保と消費者の信頼の確保
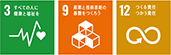
食品の安全性を向上させるためには、食品を通じて人の健康に悪影響を及ぼすおそれのある有害化学物質・有害微生物について、科学的根拠に基づいたリスク管理(*1)等に取り組むとともに、農畜水産物・食品に関する適正な情報提供を通じて消費者の食品に対する信頼確保を図ることが重要です。
本節では、国際的な動向等に対応した食品の安全確保と消費者の信頼の確保のための取組を紹介します。
1 全ての関係者と協議しながら、リスク低減のための政策・措置について技術的な実行可能性、費用対効果等を検討し、適切な政策・措置の決定、実施、検証、見直しを行うこと
(1)科学的知見等を踏まえた食品の安全確保の取組の強化
(食中毒発生件数は新型コロナウイルス感染症の感染拡大前の水準に迫る962件)
食中毒の発生は、消費者に健康被害が出るばかりでなく、原因と疑われる食品の消費の減少にもつながることから、農林水産業や食品産業にも経済的な影響が及ぶおそれがあります。このような中、農林水産省は、食品の安全や、消費者の信頼を確保するため、「後始末より未然防止」の考え方を基本とし、科学的根拠に基づき、生産から消費に至るまでの必要な段階で有害化学物質・有害微生物の汚染の防止や低減を図る措置の策定・普及に取り組んでいます。
令和4(2022)年の食中毒の発生件数は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大前の水準に迫る962件となりました(図表1-7-1)。
一方、患者数が2人以上の食中毒の発生件数を病因物質別に見ると、カンピロバクター(*1)が174件と最も多く、次いでノロウイルス(*2)が63件となっています(図表1-7-2)。
1 食中毒の原因細菌の一つ。加熱不足の鶏肉が主な原因
2 食中毒の原因ウイルスの一つ。加熱不足の二枚貝や、ウイルスに汚染された食品が主な原因
(最新の科学的知見・動向を踏まえリスク管理を実施)
農林水産省は、食中毒の発生件数の増減等の最新の科学的知見や、消費者・食品関連事業者等関係者の関心、国際的な動向を考慮して、食品の安全確保に取り組んでいます。
農林水産省では、優先的にリスク管理の対象とする有害化学物質・有害微生物を選定した上で、5年間の中期計画及び年度ごとの年次計画を策定し、サーベイランス(*1)やモニタリング(*2)を実施しています。また、汚染低減のための指針等の導入・普及や衛生管理の推進等の安全性向上対策を食品関連事業者と連携して実施し、その効果の検証のための調査を実施し、最新の情報に基づいて指針等を更新しています。くわえて、食品安全に関する国際基準・国内基準や規範の策定、リスク評価に貢献するため、これらの取組により得た科学的知見やデータをコーデックス委員会(*3)や関連の国際機関、関係府省へ提供しています。
令和4(2022)年度は、有害化学物質20件、有害微生物10件の調査を実施しました。また、国産麦類のかび毒やアミノ酸液を原材料に含むしょうゆ中のクロロプロパノール類(*4)の実態調査結果を公表するとともに、関係者に低減対策の徹底を要請しました。その他の調査結果についても解析した上で、当省のWebサイトや学術誌、学会等で発表したほか、令和5(2023)年2月には、平成29(2017)年度と平成30(2018)年度に実施した食品中の有害化学物質の含有実態調査の結果等をまとめた「有害化学物質含有実態調査結果データ集(平成29~30年度)」を公表しました。
さらに、これまで実施してきた有害化学物質・有害微生物の汚染の防止、低減のための措置の取組状況や効果について検証・評価し、見直しの必要性等の検討を進めています。

安全で健やかな食生活を送るために
URL:https://www.maff.go.jp/j/fs/index.html
このほか、消費者向けの食品安全に関する情報の発信にも積極的に取り組んでおり、毒キノコ、山菜、ノロウイルス等による食中毒の防止について、Webサイトに掲載するとともに、SNS、動画等を活用して注意喚起を行っています。令和4(2022)年度は、子供にも出演してもらうなど、子育て世代を含む幅広い層に親しみやすいものとなるよう、新たにカレーの調理やお弁当づくりの際に注意したいポイントをまとめた動画を公開しました。
1 問題の程度又は実態を知るための調査のこと
2 矯正的措置をとる必要があるかどうかを決定するために、傾向を知るための調査のこと
3 消費者の健康の保護、食品の公正な貿易の確保等を目的として、昭和38(1963)年にFAO(国際連合食糧農業機関)及びWHO(世界保健機関)により設置された国際的な政府間機関
4 プロパノールに塩素が結合した物質の総称であり、食品の製造工程で原料に含まれる脂質から意図せず生じてしまう物質の一つ
(薬剤耐性菌の増加を防ぐ対策を推進)
近年、抗菌剤の不適切な使用を原因とした薬剤耐性菌の発生により、人や動物の健康への影響が懸念されています。このため、「薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン」に基づき、薬剤耐性対策に取り組んでいます。薬剤耐性対策は、人と動物の健康と環境の保全を担う関係者が緊密な協力関係を構築し、分野横断的な課題の解決のために活動していこうというワンヘルス・アプローチの観点からも重要です。
食用動物に用いる抗菌剤のうち、飼料中の栄養成分の有効利用の促進を目的とした抗菌性飼料添加物については、食用動物への使用により選択される薬剤耐性菌の人の健康への影響評価が令和3(2021)年度で完了し、人の健康に悪影響を及ぼすおそれがあると評価されていた5成分の指定を取り消しました。また、動物用医薬品についても、食品安全委員会と連携して、順次リスク評価を進めています。
このほか、令和4(2022)年度に海外における動物用医薬品の使用規制や畜水産物中の残留基準値について調査を実施し、Webサイトで公表しています。
(肥料制度に基づく取組を推進)
農林水産省では、生産資材の適正使用を推進するとともに、科学的データに基づく生産資材の使用基準の設定・見直し等を行い、安全な農畜水産物の安定供給を確保することとしています。
肥料については、農業者が安心して利用できる有機・副産物肥料の活用拡大が重要となっているところ、令和2(2020)年12月から、肥料の配合に関する規制の見直しによって、化学肥料と堆肥を配合した肥料等が届出で生産・輸入できるようになりました。こうした肥料の生産・輸入に係る農林水産大臣への届出について、令和4(2022)年度は269件となっています。農林水産省は、引き続き肥料制度に基づく取組を推進していくこととしています。
(国内使用量の多い農薬を優先して順次再評価を実施)
農林水産省は、農薬の安全性の一層の向上を図るため、平成30(2018)年に改正された農薬取締法に基づき、令和3(2021)年度から再評価を開始しました。
再評価は、最新の科学的知見に基づき、全ての農薬についておおむね15年ごとに実施することとしており、国内での使用量が多い農薬を優先して順次再評価を進めています。
(2)食品に対する消費者の信頼の確保
(加工食品の原料原産地表示が義務化)
全ての加工食品(*1)を対象に、重量割合1位の原材料の原産地を原則として国別重量順で表示する原料原産地表示制度が、令和4(2022)年4月から義務化されました。これを受け、消費者が加工食品を購入する際に表示を確認し、国産原材料を使用したものを選択することができるようになっています。
1 外食、容器包装に入れずに販売する場合、作ったその場で販売する場合、輸入品等は対象外
(コラム)インターネット販売における食品表示の情報提供方法等を提示
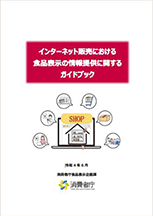
インターネット販売における
食品表示の情報提供に関する
ガイドブック
資料:消費者庁
近年、インターネットを介した電子商取引サイト(以下「ECサイト」という。)における食品購買が増加し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大がその傾向に大きな拍車をかけています。
一方、食品の義務表示事項や表示方法を定めた食品表示基準は食品の容器包装への表示を適用範囲としており、ECサイトにおける食品表示情報の掲載については適用範囲外となっています。そのため、容器包装上の食品表示と、ECサイト上に掲載されている食品表示情報に大きな差が生じています。
こうした状況を踏まえ、消費者庁では、令和4(2022)年6月に「インターネット販売における食品表示の情報提供に関するガイドブック」を公表しました。
本ガイドブックでは、ECサイト上でどのような食品表示情報をどのような方法でどの程度提供すればよいか、その考え方や効用を説明するとともに、具体的な提供例や、それを支えるための情報入手方法・管理方法についても提示しています。ECサイトで食品表示情報を掲載する上での事業者等向けの参考ツールとして活用されることが期待されています。
(食品トレーサビリティの普及啓発を推進)
食品トレーサビリティは、食品の移動を把握できることを意味しています。各事業者が食品を取り扱った際の記録を作成・保存しておくことで、食中毒等の健康に影響を与える事故等が発生した際に、問題のある食品がどこから来たのかを遡及して調べ、どこに行ったかを追跡することができます。
令和5(2023)年3月に公表した調査によれば、農畜産物の「出荷日、出荷先、種別、数量」等が記載された出荷の記録の保存については、「全て又は一部のみ「出荷の記録」を保存している」と回答した農業者の割合が84.8%、「「出荷の記録」を保存していない」と回答した農業者の割合が15.2%となっています(図表1-7-3)。
一方、食品の製造工程における内部トレーサビリティは、記録の整理・保存に手間が掛かることや、取組の必要性や具体的な取組内容が分からないなどの理由から、特に中小零細企業での取組率が低いことが課題となっています。
このため、農林水産省では、令和4(2022)年11月に、食品トレーサビリティに関し、事業者が自主的に取り組む際のポイントを解説するテキスト等を策定し、更なる取組の普及啓発を推進しています。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883