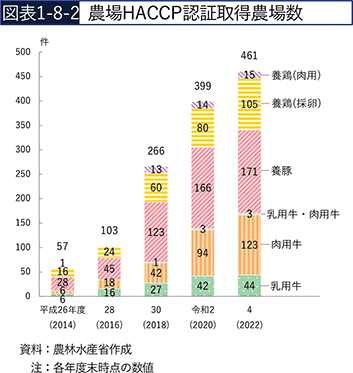第8節 動植物防疫措置の強化
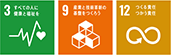
食料の安定供給や農畜産業の振興を図るため、高病原性鳥インフルエンザ(*1)や豚熱(ぶたねつ)(*2)等の家畜伝染病や植物の病害虫に対し、侵入・まん延を防ぐための対応を行っています。また、近年、アフリカ豚熱(*3)や口蹄疫(こうていえき)等の畜産業に甚大な影響を与える越境性動物疾病が近隣のアジア諸国において継続的に発生しています。これら疾病の海外からの侵入を防ぐためには、関係者が一丸となって取組を強化することが重要です。
さらに、国内で継続的に発生が見られるヨーネ病等の慢性疾病や腐蛆病(ふそびょう)等の蜜蜂の疾病への対策のほか、改正植物防疫法(*4)に基づく対策も重要となっています。
本節では、動植物防疫措置の強化に関わる様々な取組について紹介します。
1、2 用語の解説(1)及びトピックス4を参照
3 用語の解説(1)を参照
4 正式名称は「植物防疫法の一部を改正する法律」
(高病原性鳥インフルエンザや豚熱等の家畜伝染病が発生)
令和4(2022)年の主な家畜伝染病の発生状況を見ると、高病原性鳥インフルエンザが66戸、豚熱が9戸、ヨーネ病(牛)が519戸、腐蛆病が26戸となっています(図表1-8-1)。

(越境性動物疾病の侵入・まん延リスク増加に対応した水際対策を強化)
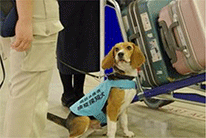
動植物検疫探知犬
海外からアフリカ豚熱や口蹄疫等の越境性動物疾病の国内侵入を防ぐために、空港及び海港において入国者の靴底消毒・車両消毒、旅客への注意喚起、検疫探知犬を活用した手荷物検査等、水際対策を徹底して実施しています。令和2(2020)年7月に改正家畜伝染病予防法(*1)が施行され、輸入禁止品の廃棄等の水際検疫における家畜防疫官の権限を強化したほか、検疫体制も強化し、令和4(2022)年度末時点で、家畜防疫官が526人、検疫探知犬が140頭となっています。
また、越境性動物疾病対策は、国際的な協力が不可欠であるという共通認識の下、国際機関、G7の枠組み、獣医当局間及び研究所間で連携して活動を行っています。さらに、越境性動物疾病が継続的に発生している近隣諸国との連携を強化し、疾病情報の共有、防疫対策等の向上を強力に推進することにより、アジア諸国・地域における疾病の発生拡大を防止し、疾病の侵入リスクを低減しています。
1 正式名称は「家畜伝染病予防法の一部を改正する法律」
(飼養衛生管理向上に向けた取組を推進)
高病原性鳥インフルエンザや豚熱だけでなく、ヨーネ病や牛伝染性リンパ腫等の慢性疾病を含めた伝染性疾病への対策の基本は、病原体を農場に入れないこと及び農場から出さないことであり、農場における適切な飼養管理、消毒等による感染リスクの低減等、日頃からの取組が極めて重要になります。このため、生産農場における飼養衛生管理の向上や家畜の伝染性疾病のまん延防止・清浄化に向け、農場指導、検査、ワクチン接種や淘汰(とうた)等の取組を推進しており、農場、都道府県の家畜保健衛生所、臨床獣医師や関係団体が連携した取組を支援しています。
なお、牛のブルセラ症及び結核については、平成30(2018)年度から3年間にわたる清浄性確認サーベイランスの結果、国内の清浄性が確認されました。我が国の清浄性を維持するための対策を引き続き推進していくこととしています。
また、蜂の幼虫が病原体を含む餌を摂取したときに発症し死亡する家畜伝染病である腐蛆病のまん延防止を推進しています。
(農場段階におけるHACCP方式を活用した衛生管理の取組が進展)
畜産物の安全性を向上させるためには、個々の畜産農場における衛生管理を向上させ、農場から消費までの一貫した衛生管理を行うことが重要です。
農場HACCPは、畜産農場における衛生管理を向上させるため、農場にHACCP(*1)の考え方を取り入れ、危害要因(微生物、化学物質、異物等)を防止するための管理ポイントを設定し、継続的に監視・記録を行うことにより、農場段階で危害要因をコントロールする手法です。農林水産省では、消費者に安全な畜産物を供給するために農場HACCPの取組を推進しており、農場指導員(*2)の養成や、生産から加工・流通、消費まで連携した取組の支援を実施しています。
農場HACCP認証取得農場数は年々増加しており、令和4(2022)年度は461件となりました(図表1-8-2)。
1 用語の解説(2)を参照
2 家畜保健衛生所の職員等の獣医師を始めとした、農場HACCPの導入・実施や認証取得を促す指導員
(事例)養豚経営において農場HACCPを活用した衛生管理の取組を推進(青森県)


衛生的に管理された豚舎
資料:有限会社飯田養豚場
青森県横浜町(よこはままち)の有限会社飯田養豚場(いいだようとんじょう)では、農場HACCPを活用した衛生管理の取組を推進し、消費者の求める安全な畜産物の生産に取り組んでいます。
同農場は、繁殖母豚300頭規模の一貫生産を家族労働で実践する優良経営農場で、衛生管理を重視する観点から、令和2(2020)年に農場を新築し、繁殖母豚を自家生産から多産系母豚の外部導入に切り替えました。
平成31(2019)年には農場HACCP認証の取得により、病原体の持込み防止対策等の飼養衛生管理の強化とともに、作業の文書化により従業員の理解度が向上するなどの効果が見られています。
また、同農場では、地元産の酒かす粉末を添加した飼料給餌によって肥育したブランド豚「あおもりほろよい豚(とん)」を生産し、優れた生産性・収益性を実現しており、将来的には、繁殖母豚500頭規模の一貫養豚生産を目指しています。
(植物の病害虫の侵入・まん延を防止)

アリモドキゾウムシ
令和4(2022)年10月に静岡県で、さつまいもの重要病害虫であるアリモドキゾウムシが本州で初めて確認されました。これを受けて農林水産省は県と連携し、寄主植物の除去等の初動防除を行うとともに、発生範囲を特定するための調査を実施しました。さらに、アリモドキゾウムシの根絶に向け、令和5(2023)年3月に植物防疫法に基づく緊急防除を開始しました。
農林水産省は、このほかにも国内で確認されたジャガイモシロシストセンチュウやテンサイシストセンチュウについても緊急防除を実施し、まん延防止に取り組んでいます。
(植物の病害虫の侵入・まん延リスク増加に対応した改正植物防疫法が公布)
近年、地球温暖化等による気候変動、人やモノの国境を越えた移動の増加等に伴い、植物の病害虫の侵入・まん延リスクが高まっています。
また、化学農薬の使用に伴う環境負荷を低減することが国際的な課題となっていることに加え、国内では化学農薬に依存した防除により薬剤抵抗性が発達した病害虫が発生するなど、化学農薬だけに頼らない防除の普及等を図っていくことが急務となっています。
さらに、農林水産物・食品の輸出促進に取り組む中で、植物防疫官の輸出検査業務も増加するなど、植物防疫をめぐる状況は複雑化しています。

植物防疫法の改正について
URL:https://www.maff.go.jp/j/syouan/shokukaisei.html
こうした状況の中、令和4(2022)年5月に公布された改正植物防疫法においては、法律に基づく病害虫の侵入調査事業の実施、緊急防除の迅速化、発生予防を中心とした総合防除を推進する仕組みの構築、検疫対象への物品の追加、植物防疫官の権限の拡充、農林水産大臣の登録を受けた登録検査機関による輸出検査の一部の実施等の措置を講ずることとしています。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883