第9節 国際交渉への対応
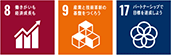
国際交渉においては、我が国の農林水産業が「国の基(もとい)」として発展し、将来にわたってその重要な役割を果たしていけるよう交渉を行うとともに、我が国の農林水産物・食品の輸出拡大につながる交渉結果の獲得を目指しています。
本節では、経済連携交渉等の国際交渉への対応状況等について紹介します。
(複数の国とのEPA/FTAの交渉を実施)
特定の国・地域で貿易ルールを取り決めるEPA/FTA(*1)等の締結が世界的に進み、令和4(2022)年6月時点では380件に達しています。

EPA/FTA等に関する情報
URL:https://www.maff.go.jp/j/kokusai/renkei/fta_kanren/
我が国においても、令和4(2022)年度末時点で、21のEPA/FTA等が発効済・署名済です(図表1-9-1)。これらの協定により、我が国は世界経済の約8割を占める巨大な市場を構築することになります。輸出先国の関税撤廃等の成果を最大限活用し、我が国の強みを活かした品目の輸出を拡大していくため、我が国農林水産業の生産基盤を強化していくとともに、新市場開拓の推進等の取組を進めることとしています。
令和4(2022)年11月にはイスラエル、12月にはバングラデシュとの間で共同研究の立上げを決定しました。
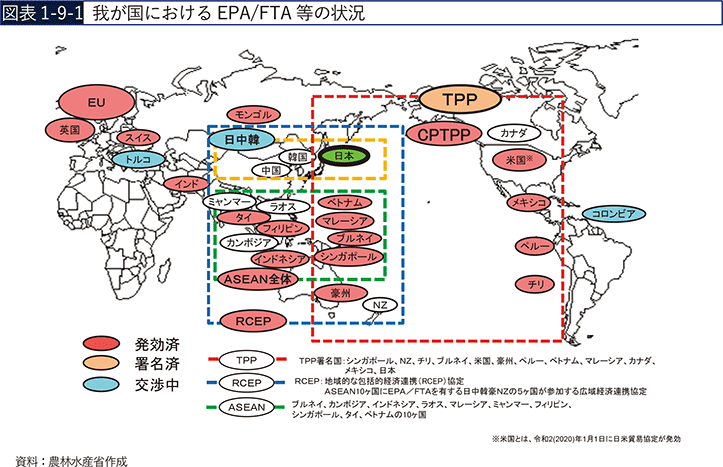
また、世界共通の貿易ルールづくり等が行われるWTO(*2)においても、これまで数次にわたる貿易自由化交渉が行われてきました。平成13(2001)年に開始されたドーハ・ラウンド交渉においては、依然として、開発途上国と先進国の溝が埋まっていないなど、農業分野等の交渉の今後の見通しは不透明ですが、我が国としては、世界有数の食料輸入国としての立場から公平な貿易ルールの確立を目指し交渉に臨んでおり、我が国の主張が最大限反映されるよう取り組んでいます。
1、2 用語の解説(2)を参照
(コラム)IPEFの交渉開始を決定

IPEFの閣僚級会合
資料:外務省
令和4(2022)年9月に、インド太平洋経済枠組み(IPEF(アイペフ)(*1))の閣僚級会合が開催され、貿易、サプライチェーン、クリーン経済及び公正な経済の四つの分野についての閣僚声明が採択されるとともに、米国、日本、豪州等14か国が参加する形で正式に交渉開始が決定されました。
農業分野においては、各国による食料及び農産物の不当な輸出規制措置の回避や、輸入制限措置の改善等に関する文言が閣僚声明に含まれました。今後の議論の進展に応じて、食料安全保障(*2)の確保、農林水産物の輸出拡大、持続可能な農業生産の推進等の課題解決を目指し、我が国の立場を主張していくこととしています。
1 Indo-Pacific Economic Frameworkの略
2 用語の解説(1)を参照
(CPTPPへの英国の加入交渉が実質的に妥結)
平成30(2018)年12月に発効した環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)への英国の加入手続について、CPTPP参加国及び英国の間での協議が進められ、令和5(2023)年3月に交渉が実質的に妥結した旨の閣僚共同声明が発表されました。日本側の関税に関する措置については、現行のCPTPPの範囲内で妥結しました。また、英国側の関税については、英国から短・中粒種の精米等の関税撤廃を獲得しました。今後は、英国の加入の条件等を規定する加入議定書の作成作業等が行われることとなっています。
(日米間の新たな牛肉セーフガードの適用条件を定める日米貿易協定改正議定書が発効)
日米貿易協定に基づく牛肉セーフガードに関する協議については、令和3(2021)年3月に我が国において日米貿易協定に基づき米国産牛肉に対するセーフガード措置がとられたことを受けて、令和元(2019)年10月に日米貿易協定に関連して作成された二国間の交換公文に基づき開始されたものであり、その後の累次にわたる協議を経て、令和4(2022)年3月に、実質合意に至りました。同年11月には、米国産牛肉に対するセーフガード措置の適用条件の修正等を定めた日米貿易協定を改正する議定書が国会で承認され、令和5(2023)年1月に発効しました。
新たなセーフガード措置については、発動水準の大幅な引上げを求める米国に対して、「TPP(*1)の範囲内」との基本方針の下、約1年にわたり交渉を続けた結果、米国とCPTPP締約国からの合計輸入量がCPTPPの発動水準を超えた場合に米国に対して発動する仕組みで合意に至りました。これは、米国とCPTPP締約国からの合計輸入数量を発動水準とする、米国も含めて合意した当初のTPP協定の枠組みに則したものであり、牛肉の国内生産への影響という観点も踏まえた措置です。
1 用語の解説(2)を参照
(G7農業大臣会合においてコミュニケを採択)
令和4(2022)年5月にドイツで開催されたG7農業大臣会合では、ウクライナ情勢が及ぼす世界の食料安全保障への影響や持続可能な農業・食料システムの構築について議論が行われました。我が国は、ウクライナの食料生産・流通の復興、肥料の世界的な需給の安定確保等に向け取り組む必要があること、また、持続可能な食料システムの推進には、万能の解決策はなく、各国・地域の農業形態や気候条件を考慮しながら取り組む必要があること等を訴え、G7農業大臣コミュニケ(「危機時における持続可能な食料システムに向けた道筋」)の採択に積極的に関与しました。
また、同年9月にインドネシアで開催されたG20農業大臣会合では、持続可能な農業・食料システム等の農業政策について議論が行われました。会合では、多くの国が、ロシアによるウクライナ侵略を、世界の食料安全保障を脅かすものとして非難するとともに、持続可能な食料システムに向けた中・長期的な取組を強化すべきと主張しました。我が国からは、これに加え、食料・農業のサプライチェーンを強靱(きょうじん)化し、環境負荷を低減させつつ必要な食料を増産するために、各国がそれぞれの農業資源を持続可能な形で活用していくことの重要性について主張しました。

G7農業大臣会合で議論する農林水産副大臣
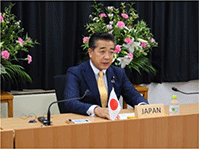
G20農業大臣会合で発言する農林水産大臣政務官
(第12回WTO閣僚会議において閣僚宣言を採択)
令和4(2022)年6月にスイスで開催された第12回WTO閣僚会議では、全加盟国のコンセンサスにより、前回のWTO閣僚会議では発出できなかった閣僚宣言が採択されました。また、漁業補助金協定が採択され、食料安全保障に関する閣僚宣言、WFP(国連世界食糧計画)に関する閣僚決定が作成されるとともに、衛生植物検疫措置の適用に関する協定(SPS協定(*1))の閣僚宣言が発出されました。食料安全保障に関する閣僚宣言では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によるサプライチェーンの混乱やロシアによるウクライナ侵略を背景に、食料安全保障が脅かされる中、国内生産と並んで貿易が世界の食料安全保障のために非常に重要であること、WTO協定の規定に整合的ではない輸出禁止・規制を行わないこと等が盛り込まれました。一方、農業交渉の「今後の作業計画」については、各国の隔たりが埋まらなかったため合意に至らず、議論を継続することとなりました。
1 WTO協定に含まれる協定(附属書)の一つであり、「Sanitary and Phytosanitary Measures(衛生と植物防疫のための措置)」の頭文字をとって、一般的にSPS協定と呼ばれている。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883




