トピックス4 高病原性鳥インフルエンザ及び豚熱への対応
高病原性鳥インフルエンザ(*1)や豚熱(ぶたねつ)(*2)等の家畜伝染病については、家畜伝染病予防法に基づき、発生の予防やまん延の防止に関する措置を講じています。
以下では、令和4(2022)年シーズンに高頻度で発生している高病原性鳥インフルエンザや、継続的に発生している豚熱の防疫措置の強化を図る取組等について紹介します。
*1、2 用語の解説(1)を参照
(高病原性鳥インフルエンザが高頻度で発生)
高病原性鳥インフルエンザウイルスは、その伝播力(でんぱりょく)の強さや高致死性から、一旦発生すれば、地域の養鶏産業に及ぼす影響が甚大であるほか、国民への鶏肉及び鶏卵の安定供給を脅かしかねず、また、鶏肉・鶏卵の輸出が一時的に停止することから、今後も引き続き、清浄性を維持していく必要があります。
令和4(2022)年シーズンにおいては、欧米を始め、世界各地で高病原性鳥インフルエンザが流行しています(図表トピ4-1)。
こうした中、我が国においても、高病原性鳥インフルエンザの発生が史上初めて10月に確認されて以降、過去に一度も発生がなかった地域を含めて令和5(2023)年3月末時点で26道県82事例が確認されており、これまでに過去最大となるおよそ1,701万羽が殺処分の対象となっています(図表トピ4-2)。
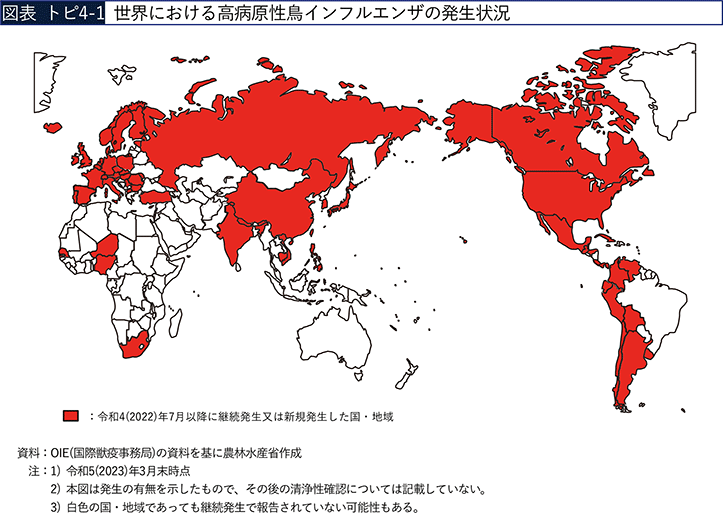

(高病原性鳥インフルエンザの対策を強化)

消石灰による緊急消毒が
行われた家きん農場
高病原性鳥インフルエンザの発生を受け、農林水産省では、都道府県に対し、高病原性鳥インフルエンザの早期発見や早期通報、飼養衛生管理の徹底を改めて通知し、家きん農場における監視体制の強化を実施したほか、経営支援対策の周知を実施しました。また、令和4(2022)年12月の鳥インフルエンザ関係閣僚会議を踏まえ、鶏舎周辺の敷地等、家きん農場における緊急消毒を支援しました。
さらに、農林水産大臣等による都道府県知事との意見交換を実施するとともに、疫学や野鳥等の専門家から成る疫学調査チームを派遣しました。
くわえて、発生農場等の飼養家きんの殺処分や焼埋却、移動制限区域(*1)・搬出制限区域(*2)の設定、消毒ポイントの設置等、都道府県が実施する防疫措置について、関係省庁と連携し、職員の派遣等、必要に応じた支援を実施するとともに、高病原性鳥インフルエンザが発生した養鶏農家の経営再開や、移動制限区域・搬出制限区域内の養鶏農家の経営継続に対する支援等を実施しました。
このほか、消費者、流通業者、製造業者等に対し、鶏肉・鶏卵の安全性の周知、発生道県産の鶏肉・鶏卵の適切な取扱いの呼び掛け等、高病原性鳥インフルエンザに関する正しい知識の普及等を実施しました。
なお、我が国の現状において、家きんの肉や卵を食べることにより、ヒトが鳥インフルエンザウイルスに感染する可能性はないと考えています。
*1 発生農場から半径3km以内の区域
*2 発生農場から半径3~10km以内の区域
(事例)鳥インフルエンザの発生防止のため、ため池周辺の消毒を徹底(香川県)


ため池周辺の消毒作業
資料:香川県
農場の周囲にため池や水場等の野鳥が多数存在するところでは、特に環境中に鳥インフルエンザウイルスが存在するリスクが高いことから、発生農場周囲のため池周辺等の消毒、ため池の水抜き等の野鳥対策等について地域の関係者が一体となった取組を徹底して行うことが重要です。
このため、香川県では、令和4(2022)年11月に、高病原性鳥インフルエンザが発生した養鶏場から半径3km以内で、養鶏場が近くにあるため池を対象として、2週間程度の期間で13か所の消毒作業を各2回ずつ実施しました。消毒に当たっては、水生生物への影響等を考慮し、ため池の外側の法面(のりめん)に消毒液を散布しています。
これらの措置により、ため池に飛来した野鳥によって持ち込まれた鳥インフルエンザウイルスを、圏内に生息する小動物・野鳥が他の場所に持っていく可能性が少しでも低減することが期待されています。
(鶏卵の価格高騰や欠品に対し、供給拡大の取組を実施)
高病原性鳥インフルエンザによる採卵鶏の殺処分羽数が過去最多となり、国内全体の飼養羽数の約1割まで拡大しました。また、飼料価格の高騰等による生産コストの増加もあり、鶏卵の卸売価格は、令和5(2023)年3月に343円/kg(平年比175%)となっています(図表トピ4-3)。長期安定契約の比率が比較的高い家庭消費向け鶏卵については、地域によっては購入制限を設ける事例や、夕方に品薄になるといった事例も生じていますが、加工向けと比較すれば不足感は小さく、小売価格は同年3月に288円/1パック(平年比135%)となっています(図表トピ4-4)。一方、加工向け鶏卵においては不足が見られ、一部の食品企業では、卵の使用量の削減や卵を使用した商品の販売中止を行うなど、食品産業への影響が見られています。
こうした状況を踏まえ、生産者団体は生産者に鶏卵の安定供給を緊急に呼び掛け、生産者は採卵鶏の飼養期間延長等の供給拡大の取組を実施しました。
(豚熱に対して飼養衛生管理の徹底や野生イノシシ対策等を推進)
平成30(2018)年に26年ぶりに国内で豚熱が確認されてから、令和5(2023)年3月末時点で18都県の豚又はイノシシの飼養農場等において86例の発生が確認されています。令和4(2022)年度は、4都県の豚又はイノシシの飼養農場等で9例が発生しました(図表トピ4-5)。
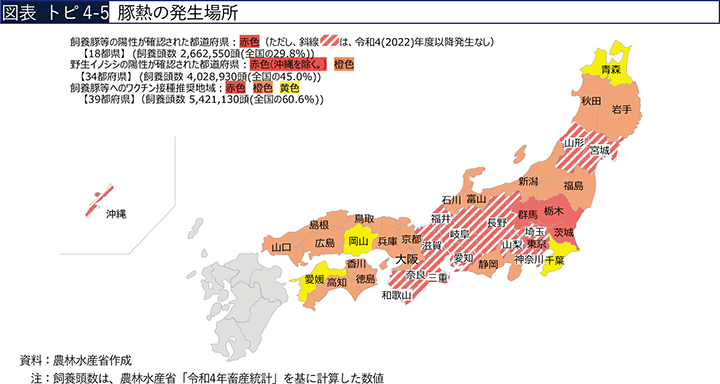
豚熱対策として、野生動物の侵入防止柵の設置や飼養衛生管理の徹底に加え、ワクチン接種推奨地域では予防的なワクチン接種を実施しています。
令和4(2022)年12月には、豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針を改正し、適時・適切な接種及びワクチンの厳格な管理を担保した上で、認定された農場において、研修を修了するなどして都道府県知事が登録した飼養衛生管理者が豚熱ワクチンを接種できるようにしました。これにより、ワクチン接種体制の強化とともに、家畜防疫員による飼養衛生管理の指導等の取組が強化されることが期待されます。

感染拡大防止のための
周知ポスター
資料:公益社団法人中央畜産会
また、野生イノシシの対策として、経口ワクチンの散布を行うとともに、同年4月にWebサイト上で生産者自ら農場周辺の検査状況を確認可能な新たな地図情報システムを提供するなど、サーベイランスの強化を図っています。
豚熱の流行は、野生イノシシによる感染拡大が大きな要因の一つと考えられていることから、野生イノシシの捕獲の強化による密度低下により感染拡大を抑制し、感染イノシシの絶対数を抑制することで、農場への感染拡大リスクを低下させることが期待されています。
このほか、豚熱の感染拡大防止のための取組として、登山者等や狩猟関係者向けのポスターの作成・周知を行っています。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883






