トピックス3 スマート農業・農業DXによる成長産業化を推進
農業者の高齢化や労働力不足が続いている中、我が国の農業を成長産業としていくためには、デジタル技術を活用して、効率的な生産を行いつつ、消費者から評価される価値を生み出していくことが不可欠です。
以下では、スマート農業や農業のデジタルトランスフォーメーション(DX(*1))の実現に向けた取組について紹介します。
*1 Digital Transformationの略で、データやデジタル技術を駆使して、顧客や社会のニーズを基に、経営や事業・業務、政策の在り方、生活や働き方、さらには、組織風土や発想の仕方を変革すること。DXのXは、Transformation(変革)のTrans(X)に当たり、「超えて」等を意味する。
(スマート農業の現場実装を加速するための更なる技術開発と横展開を推進)
農業の現場では、ロボットやAI(*1)、IoT(*2)等の先端技術や農業データを活用し、農業の生産性向上等を図るスマート農業の取組が広がりを見せています。スマート農業は、担い手の減少・高齢化や労働力不足に対応するとともに、化学肥料や化学農薬の削減等環境負荷低減に役立ち、みどり戦略(*3)実現の鍵となるものです。また、令和4(2022)年12月に閣議決定した「デジタル田園都市国家構想総合戦略」においても、その柱の一つである「地方に仕事をつくる」の中に、スマート農業の取組を位置付けています。
このような中、農林水産省は、スマート農業技術を実際の生産現場に導入して、その経営改善の効果を明らかにするため、令和元(2019)年度から全国205地区でスマート農業実証プロジェクト(以下「実証プロジェクト」という。)を展開しています。
実証プロジェクトでは、農作業の自動化、情報共有の簡易化、データの活用等に取り組んでおり、令和4(2022)年度は、スマート農業の社会実装を加速するため、産地ぐるみでの先端技術の導入について現場実証等を実施しました。これまでの実証の成果として、生産者間でデータを共有することで、産地全体で収量が向上し経営の改善につながった事例が見られるほか、労働時間の削減効果等も確認されています。
一方、生産現場では省力化技術へのニーズが高まっているものの、手間の掛かる野菜・果実の収穫作業においてはスマート農業技術の開発が不十分であることや、スマート農業機械の導入コストを回収するためには一定規模の稼働面積を確保する必要があること等の課題も明らかになっています。
このため、令和4(2022)年6月に改訂した「スマート農業推進総合パッケージ」では、実証プロジェクトで明らかになった様々な課題を踏まえ、更なる技術の開発、導入コスト低減に向けた農業支援サービス事業体の育成・普及、実証プロジェクト参加者や産学官の有識者等から成るスマートサポートチームによる実地指導を始めとした技術対応力・人材創出の強化等に取り組んでいます。この実証においては、多数のスタートアップが参画し、収穫物の運搬ロボット、園芸施設の環境制御装置、経営管理ソフト等、様々な新技術の実証に取り組み、実証を通して把握した課題を踏まえて技術を改良し、市販化に結び付けています。
スマート農業技術の更なる開発については、例えばみどり戦略に基づく有機農業を推進するものとして、作物と雑草を識別し機械除草を行う自律型除草AIロボットや碁盤の目のように移植することで縦横二方向の機械除草を可能にする両正条(りょうせいじょう)田植機を開発しています。一方、開発を要する技術については、品目や技術要素等で多岐にわたることがあるため、戦略的に開発を支援していく必要があります。令和4(2022)年11~12月に実施したアンケート調査(*4)では、省力化に直結する機械開発のニーズが高いことを踏まえ、ニーズの高い技術の開発を重点化して支援するなど、生産現場で必要とされる技術がより速やかに開発・改良されるよう取り組むこととしています。
また、導入コスト低減に向けた農業支援サービス事業体の育成・普及については、ドローンやIoT等の最新技術を活用し、農薬散布作業を代行するサービスや、データを駆使したコンサルティング等、次世代型の農業支援サービスの定着を促進することとしています。
さらに、技術対応力・人材創出の強化については、スマート農業技術を積極的に取り入れる産地に対して、令和4(2022)年度に11地区でスマートサポートチームが実地指導を開始し、そこで得られた知見を基に、技術を横展開するための手引書の作成を進めています。実地指導の中では、実証プロジェクトに参画した民間企業、農協、県が連携し、他産地の生産者や農協等に、データを活用した追肥方法や営農支援アプリの活用方法を指導するなどの取組が行われています。
これらの取組を総合的に行うことにより、スマート農業の現場実装を加速化していくこととしています。
*1 Artificial Intelligenceの略で、人工知能のこと。学習・推論・判断といった人間の知能の持つ機能を備えたコンピュータシステム
*2 Internet of Thingsの略で、モノのインターネットのこと。世の中に存在する様々なモノがインターネットに接続され、相互に情報をやり取りして、自動認識や自動制御、遠隔操作等を行うこと
*3 第2章第9節を参照
*4 令和4(2022)年11~12月に、現場で必要とされるスマート農業技術を把握するため、広く農業関係者(農業者、研究者、企業等)を対象に農林水産省Webサイト上で実施したアンケート調査(回答総数は1,095件)
(事例)ドローンのシェアリング体系の実証を推進(三重県)


地域内で共有されて
いるドローンの飛行
資料:株式会社つじ農園
三重県津市(つし)大里(おおざと)地区の農業生産法人である株式会社つじ農園(のうえん)では、令和3(2021)年度スマート農業実証プロジェクトに採択された農業者として、ドローンのシェアリング体系の実証に取り組んでいます。
同地区では、中小規模の農業者が多いため、高額なドローンを購入しても稼働面積が小さく、費用対効果の低さが技術導入の妨げとなっていました。
このため、同社では、約150haの実証面積において、地域の農業者とドローンを共有する「ドローンシェアリング」の体制を構築し、1生産者当たりの導入負担の軽減等を図りました。技術実証では、ドローンで得た生育データの解析と普及センター等の技術知見を組み合わせることにより、肥料の要否判断や適切な時期の防除等の作業をきめ細かく行えるなどの効果も見られています。
今後は、ドローンとオペレーターのシェアリングシステムを普及できる形で提供することで、他の地域でもドローン購入コストや労働時間の削減を可能とする体制の構築が進むことを目指しています。
(消費者ニーズに的確に対応した価値を創造・提供する「FaaS」への変革を推進)
農業従事者の高齢化や労働力不足等の課題に対応しながら、農業の成長産業化を進めるためには、発展著しいデジタル技術等の活用を強力に進め、データ駆動型の農業経営により消費者ニーズに的確に対応した価値を創造・提供する農業である「FaaS(ファース)(Farming as a Service)」への変革を進めていくことが不可欠となっています。その際、従来の営農体系に単にデジタル技術を導入するのではなく、デジタル技術を前提とした新たな農業への変革(デジタルトランスフォーメーション(DX))を実現することが重要となっています。
(事例)AI技術を活用し、ブロッコリー栽培の生産性向上を推進(静岡県)


収穫量予測システム
に基づく収穫作業
資料:株式会社アイファーム
静岡県浜松市(はままつし)の農業生産法人である株式会社アイファームでは、AI技術を活用し、ブロッコリー栽培の生産性を向上させる取組を展開しています。
同社では、年間延べ140ha(秋冬ブロッコリー80ha、春ブロッコリー60ha)の栽培面積でブロッコリーを生産していますが、カメラを搭載したドローンを導入することで、画像処理解析による収穫適期の判断や植物重量の推定が可能となり、圃場(ほじょう)へ収穫に行く回数や圃場間の移動コストを削減しました。
また、ドローンで撮影した画像を利用し、全ての圃場における収穫日の予測を可能とする収穫量予測システムを開発し、30日先までの収穫量を予測することで、業務契約上の欠品リスクを軽減しています。
今後とも、デジタル技術の活用等によって削減した作業時間や人件費を作業員に還元する取組を進め、農業収入の増加や農作業の負担軽減、休日の充実等を図ることを目指しています。
(事例)データ利活用型スマート栽培による持続可能な産地づくりを推進(京都府)


万願寺甘とう栽培の
モニタリングシステム
京都府舞鶴市(まいづるし)では、舞鶴市、京都丹の国(きょうとにのくに)農業協同組合万願寺甘とう(まんがんじあまとう)部会協議会(以下「甘とう部会」という。)、KDDI株式会社、普及センター等が連携し、IoT機器を用いたデータ利活用型のスマート栽培を実装することにより、ブランド京野菜でありGIにも登録されている「万願寺甘とう」の生産量の安定化・収量向上を実現するとともに、伝統野菜を核とした産地づくりを推進しています。
万願寺甘とうの高収益化に向け、甘とう部会では、令和2(2020)年度からデータ取得を開始し、高収量、高品質化に必要な適正栽培環境の「見える化」を進めています。
各生産者が用いるセンサーを統一することで、同一規格でのデータ収集が可能となり、温度、湿度、土壌水分量等が異なる環境下での生育状況が容易に比較できるほか、高収量生産者の栽培環境データや圃場の生育状況を常時確認することが可能となっています。
同市では、将来的に、産地全体の収穫量予測を実現し、予測を活かした流通量の適正管理により価格の安定化につなげるとともに、デジタル技術とアナログの知見を活用した「栽培モデル」を確立し、持続可能な産地づくりを目指すこととしています。
(農業DX構想に基づく多様なプロジェクトを推進)
農業や食関連産業の分野におけるDXの方向性や取り組むべき課題を示し、食や農に携わる人々の参考となるよう取りまとめた「農業DX構想」では、農業・食関連産業におけるDXの実現に向けて、農業・食関連産業の「現場」、農林水産省の「行政実務」、そして現場と農林水産省をつなぐ「基盤」の整備を併せて進めていくこととしています。同構想の下で、データを活用したスマート農業の現場実装、「農林水産省共通申請サービス(eMAFF(イーマフ))」による行政手続のオンライン化等、多様なプロジェクトを推進しています。
(eMAFF・eMAFF地図の取組を推進)
農林水産省では、行政手続の申請に係る書類や申請項目等の抜本的な見直しを進めながら、農林漁業者等が自身のパソコンやスマートフォン、タブレットから補助金等の申請を行えるeMAFFの機能を拡充し、令和5(2023)年3月末時点で、約3,300の手続についてオンラインで申請できるようにしました。
eMAFFの活用により、農林漁業者等は時間にとらわれることなく、遠隔地からでも自身のパソコンやスマートフォン、タブレットを使って非対面で申請することが可能となっています。また、書類の受付・印刷・押印・郵送といった紙申請特有の手間が解消されるほか、申請・審査されたデータはeMAFFに保存されるため、一度申請した内容を再度申請する必要がなくなること、書類の保存や管理の手間が解消されること等の利点もあることから、今後、幅広く活用されることが期待されています。
また、eMAFFの取組を進めながら、デジタル地図を活用して、農地関連業務の抜本的な効率化・省力化等を図るため「農林水産省地理情報共通管理システム(eMAFF地図(イーマフちず))」の開発・運用を進めています。令和4(2022)年4月からは、農地台帳、水田台帳等の現場の農地情報の紐付(ひもづ)け作業を進めるとともに、農地の利用状況等の現地確認業務を効率化できる現地確認アプリ等の運用を開始しています。
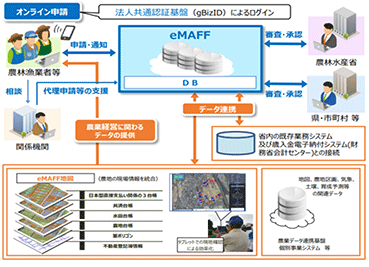
農林水産省共通申請サービス(eMAFF)と
農林水産省地理情報共通管理システム(eMAFF地図)
資料:農林水産省作成

農林水産省共通申請サービス(eMAFF)
URL:https://www.maff.go.jp/j/kanbo/dx/emaff.html
→第2章第8節を参照
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883




