トピックス5 デジタル田園都市国家構想に基づく取組を推進
政府は、地方からデジタルの実装を進め、新たな変革の波を起こし、地方と都市の差を縮めていくことで、世界とつながる「デジタル田園都市国家構想」の実現に向けた取組を推進しています。
以下では、デジタル田園都市国家構想に基づく取組について紹介します。
(地方が抱える課題についてデジタル実装を通じて解決)
デジタル田園都市国家構想は、人口減少、過疎化等の様々な社会課題に直面する地方において、デジタル技術の活用によって地域の個性を活かしながら地方の社会課題の解決や、魅力あふれる地域づくりを進め、地方活性化を加速することを目的としています。
同構想の実現により、地方における仕事や暮らしの向上に資する新たなサービスの創出、持続可能性の向上、Well-being(満足度)の増大等を通じて、デジタル化の恩恵を国民や事業者が享受できる社会を目指しています。これにより、東京圏への一極集中の是正を図り、地方から全国へとボトムアップの成長を推進することとしています。
特に農林水産業が基幹産業である中山間地域等においては、「しごと」、「くらし」、「活力」面での課題をデジタル活用により解決するため、関係府省庁が連携して、地域の実情に合った施策を一体的に展開することとしています。
(事例)テレワーク研修交流施設を整備し、ワーケーションの取組を推進(新潟県)

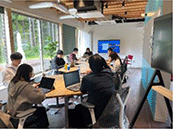
テレワークや研修等に活用
されるコワーキングスペース
資料:新潟県妙高市
新潟県妙高市(みょうこうし)は、コワーキングスペース、シェアオフィス、コミュニティスペース等を備えたテレワーク研修交流施設を整備し、企業等をターゲットとしたワーケーションの取組を推進しています。
妙高(みょうこう)山麓に位置し、温泉、リゾート、アクティビティが豊富な同市は、テレワーク環境の整備や、森林ツーリズム等の各種プログラムを推進しており、ワーケーション体験ができる先進地として注目を集めています。
こうした取組の一環として、同市は、令和4(2022)年7月に、妙高戸隠連山(みょうこうとがくしれんざん)国立公園地内に、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方を提供する施設として、妙高市テレワーク研修交流施設「MYOKO BASE CAMP(ミョウコウベースキャンプ)」を開設しました。
同施設は、「働く、観光する、遊ぶ、交流する」など多様な役割を担う施設であり、企業やフリーランス、起業を考えている人等が快適に働ける環境として、オンライン会議システムを運営しているZVC(ゼットブイシー) JAPAN(ジャパン)株式会社と国内で初めて連携してデザインされたコワーキングスペース等を備えるとともに、ワーケーションや、都市部企業と市内企業のビジネスマッチング等の各種事業を行っています。
今後とも、同施設の活用により、首都圏等から新たな人の流れを加速させ、関係人口を創出しながら、地域課題の解決やローカルイノベーションの創出等、新たな価値の創造を目指すこととしています。
政府は、令和4(2022)年12月に、令和5(2023)年度を初年度とする5か年の「デジタル田園都市国家構想総合戦略」(以下「総合戦略」という。)を策定しました。総合戦略は、デジタル田園都市国家構想が目指すべき中長期的な方向について示すとともに、構想の実現に必要な施策の内容等を示すものです。総合戦略に基づき、国・地方公共団体・企業・大学等、多様な主体が、地域外の主体も巻き込みながら、連携して取組を推進していくことが期待されています。
農林水産省では、農的関係人口(*1)の創出・拡大等により、将来的な農村への移住者や潜在的な農業・農村の担い手を拡大するとともに、デジタルを活用した農林水産業・食品産業の成長産業化と地域の活性化等を推進することとしています。
*1 第3章第7節を参照
(コラム)農山漁村で、デジタル技術を活用し地域課題の解決を図る取組が進展
デジタル田園都市国家構想の実現に向けて、地方公共団体や民間企業等、様々な主体の意欲や国民の関心を高めるため、内閣官房では「Digi田甲子園(デジデンこうしえん)」を実施しています。企業や団体等を対象にした「冬のDigi田甲子園」に応募された取組においても、デジタルの力を活用して地方の社会課題の解決を図る事例が数多く見られます。
例えば京都府福知山市(ふくちやまし)毛原(けはら)地区では、過疎化・高齢化が進む山間集落において、移住促進だけに頼らずに美しい棚田での暮らしを持続可能にするため、住民と関係人口を交えたコミュニティを構築し、デジタルツールを用いて交流・共助・協働活動を容易に行う取組が進められています。

スマートスピーカーを活用した
集落住民間の交流
資料:毛原の棚田ワンダービレッジプロジェクト
また、和歌山県すさみ町(ちょう)では、すさみスマートシティ推進コンソーシアムの実証実験として、ベル・データ株式会社、ソフトバンク株式会社、株式会社ウフルが主体となり、災害時に備えて食品等の備蓄品の個数、賞味期限、アレルギー対応の有無、在庫充当率をデジタル化により管理するとともに、スマートフォンによる発注システムとも連動し運用する取組が進められています。
今後とも全国各地で、デジタル技術の活用により地域の様々な課題を解決する取組が進展し、住民の暮らしの利便性や豊かさの向上等につながっていくことが期待されています。
(「デジ活」中山間地域の取組を支援)
中山間地域等では、少子高齢化や人口減少が進行しており、AI、ICT(*1)等のデジタル技術を活用し、農林水産業や生活サービス等の省力化・効率化を図ることが急務となっています。このため、中山間地域等においては、基幹産業である農林水産業の「仕事づくり」を軸として、教育・文化、医療・福祉、物流等、様々な分野と連携しながら、地域資源やデジタル技術を活用しつつ、社会課題解決・地域活性化に取り組むことが重要となっています。また、集落生活圏においては、複数集落を対象に農用地の保全管理や地域資源の活用、生活支援を担う農村型地域運営組織(農村RMO(*2))が、デジタル技術の活用を通じて「小さな拠点」の持つ機能を効率的・効果的に利用することも期待されています。
こうした取組に意欲的な地域を「デジ活」中山間地域として登録し、令和5(2023)年度から登録地域を公表するとともに、「デジ活」中山間地域に対する優遇措置や現地派遣等を通じて関係府省が連携して支援を実施することとしています。令和9(2027)年度までに150地域以上の「デジ活」中山間地域を登録することを目指しています。
*1 nformation and Communication Technologyの略。情報や通信に関する技術の総称
*2 第3章第5節を参照
→第3章第2節を参照
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883




