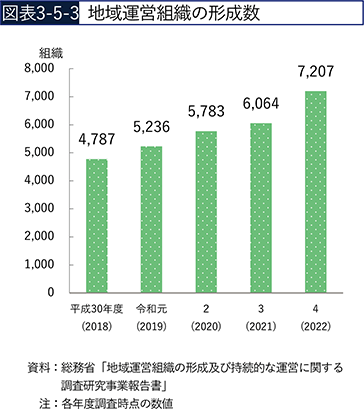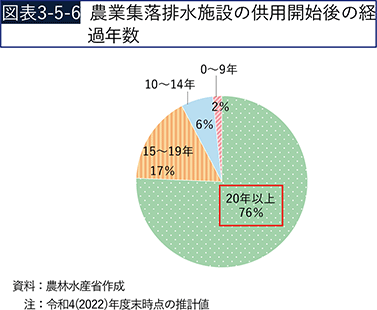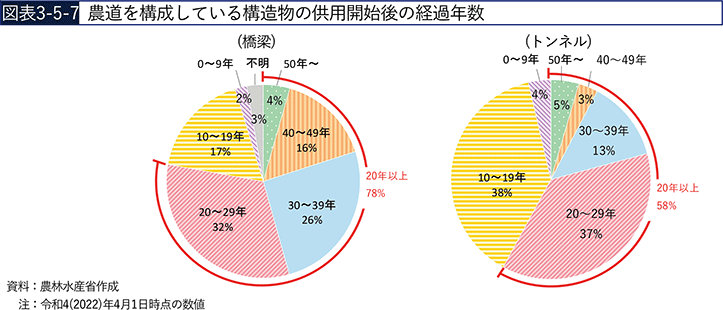第5節 農村に人が住み続けるための条件整備
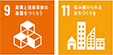
農村は地域住民の生活や就業の場になっていますが、高齢化や人口減少により集落機能が低下し、農地の保全や買い物・子育て等の集落の維持に必要不可欠な機能が弱体化する地域が増加していくことが懸念されています。
本節では、農村に人が住み続けるための条件整備として、地域コミュニティ機能の維持・強化や生活インフラ等の確保を図る取組について紹介します。
(1)地域コミュニティ機能の維持や強化
(農業集落の小規模化が進行)
我が国の「地域の基礎的な社会集団」である農業集落(*1)は、地域に密着した水路・農道・ため池等の農業生産基盤や収穫期の共同作業・共同出荷等の農業生産面のほか、集落の寄り合い(*2)といった協働の取組や伝統・文化の継承等、生活面にまで密接に結びついた地域コミュニティとして機能しています。
しかしながら、農業集落は小規模化が進行するなど高齢化と人口減少の影響が強く表れており、総戸数が9戸以下の小規模な農業集落の割合については、令和2(2020)年は、平成22(2010)年の6.6%から1.2ポイント増加し7.8%となりました(図表3-5-1)。
小規模な集落では、農地の保全等を含む集落活動の停滞のほか、買い物がしづらくなるといった生活環境の悪化により、単独で農業生産や生活支援に係る集落機能の維持が困難となるとともに、集落機能の低下が更なる集落の人口減少につながり、集落の存続が困難になることが懸念されています。このため、広域的な範囲で支え合う組織づくりを進めるとともに、農業生産の継続と併せて、生活環境の改善を図ることが重要です。
また、集落の存続はその地域での農業生産活動の維持にも影響することから、農村人口の維持・増加やコミュニティ機能の維持は重要な課題となっています。
1 用語の解説(1)を参照
2 地域の諸課題への対応を随時検討する集会、会合等のこと
(広域連携により集落機能の維持を支える動きが広がり)
農業用用排水路やため池等の地域資源を有している農業集落のうち、これらの保全活動を行っている集落の割合は、平成27(2015)年から令和2(2020)年までの期間で見ると、いずれも上昇しています。その要因としては、他の農業集落との共同での保全や都市住民の支援を受けた取組が増加していることが挙げられます。農業集落の縮小により集落機能が低下しつつある保全活動を、広域的に連携した取組によって支援する動きが全国的に拡大していることがうかがわれます (図表3-5-2)。
(地域運営組織や小さな拠点の形成数はそれぞれ前年度に比べ増加)
地域の暮らしを守るため、地域で暮らす人々が中心となって形成され、地域内の様々な関係主体が参加する協議組織が定めた地域経営の指針に基づき、地域課題の解決に向けた取組を持続的に実践する組織である「地域運営組織(RMO(*1))」について、令和4(2022)年度の形成数は、前年度に比べ1,143組織増加し7,207組織となっています(図表3-5-3)。
また、地域住民が地方公共団体や事業者、各種団体と協力・役割分担をしながら、行政施設や学校、郵便局等の分散する生活支援機能を集約・確保し、周辺集落との間をネットワークで結ぶ「小さな拠点」では、地域の祭りや公的施設の運営等の様々な活動(*2)に取り組んでいます。令和4(2022)年度の形成数は、前年度に比べ102か所増加し1,510か所となっています(図表3-5-4)。このうち84%の1,262か所で地域運営組織が設立されています。

小さな拠点情報サイト
URL:https://www.chisou.go.jp/sousei/about/
chiisanakyoten/index.html(外部リンク)
小さな拠点の形成に向けて、関係府省が連携し、遊休施設の再編・集約に係る改修や、廃校施設の活用等に取り組む中、農林水産省は、農産物加工・販売施設や地域間交流拠点の整備等の支援を行っています。
1 Region Management Organizationの略
2 内閣府「令和3年度小さな拠点の形成に関する実態調査」(令和3(2021)年12月公表)を参照
(集落の機能を補完する「農村RMO」の形成を促進)
中山間地域を始めとした農村地域では高齢化・人口減少の進行により、農業生産活動のみならず、農地・水路等の保全や買い物・子育て等の生活支援等の取組を行うコミュニティ機能の弱体化が懸念されています。このため、複数の集落の機能を補完して、農用地保全活動や農業を核とした経済活動と併せて、生活支援等の地域コミュニティの維持に資する取組を行う「農村型地域運営組織」(以下「農村RMO」という。)を形成していくことが重要となっています(図表3-5-5)。

また、農村RMOは、中山間地域等直接支払交付金や多面的機能支払交付金の交付を受けて農用地の保全活動を行う組織と、地域の多様な主体が連携し、地域資源を活用した農業振興等による経済活動を展開し、農業集落の生活支援を手掛ける組織へと発展させていくことが重要です。
農林水産省は、令和8(2026)年度までに農村RMOを100地区で形成する目標に向けて、農村RMOを目指す団体等が行う農用地保全、地域資源の活用、生活支援に係る調査、計画作成、実証事業等の取組に対して支援することとしています。また、地方公共団体や農協、NPO法人等から構成される都道府県単位の支援チームや、全国プラットフォームの構築を支援し、農村RMOの形成を後押ししています。
(事例)地域活性化を支える農村RMOを設立し、多岐にわたる事業を展開(島根県)

島根県安来市(やすぎし)のえーひだカンパニー株式会社は、同市比田(ひだ)地区の農村RMOとして、地域農業に貢献する取組を始め、産業振興や生活環境改善、福祉の充実、定住促進等の多岐にわたる事業を展開しています。
同地区では、少子高齢化等による地区存続の危機感から、地域住民が中心となり、行政や農協のサポートを受けて、地区機能維持の仕組みを創るため88個の戦略プランから成る「比田地域ビジョン」を策定しました。このビジョンの確実な実施に向けて、平成29(2017)年に、地域住民を構成員として同社が設立されました。
同社は、農業分野では、産業用ドローンを使った水稲の防除作業や地元農産物を活用した商品開発等の取組を進めています。また、農業以外の分野においても、公共交通の空白地域での輸送事業のほか、高齢者の居場所づくりや買い物支援、地域外住民との交流イベントの開催等の取組を進めています。
今後とも、住民による住民のための株式会社として、生活環境、福祉、産業、観光等、多岐にわたる分野で同地区の活性化に向けて貢献していくこととしています。
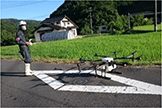
ドローンによる防除作業
(農業生産に係る機能)
資料:えーひだカンパニー株式会社

移動販売車による買い物支援
(生活支援に係る機能)
資料:えーひだカンパニー株式会社
(2)生活インフラ等の確保
(農業・農村における情報通信環境の整備を推進)
データを活用した農業の推進や農業水利施設(*1)等の管理の省力化・高度化、地域の活性化を図るため、農業・農村におけるICT等の活用に向けた情報通信環境を整備することが課題となっています。
農林水産省は、令和3(2021)年に農業農村情報通信環境整備推進体制準備会を設置し、先進地域、民間事業者等と連携して地方公共団体等への技術的なサポートを行っています。また、令和4(2022)年度は、全国21地区において、農山漁村振興交付金(情報通信環境整備対策)により、光ファイバ、無線基地局等の情報通信環境整備に係る調査、計画策定及び施設整備が進められました。
1 用語の解説(1)を参照
(標準耐用年数を超過した農業集落排水施設は全体の約8割)
農業集落排水施設は、農業用水の水質保全等を図るため、農業集落におけるし尿、生活雑排水の汚水等を処理するものであり、農村の重要な生活インフラとして稼働しています。
一方、供用開始後20年(機械類の標準耐用年数)を経過する農業集落排水施設が76%に達するなど、老朽化の進行や災害への脆弱(ぜいじゃく)性が顕在化するとともに、施設管理者である市町村の維持管理に係る負担が増加しています(図表3-5-6)。
このような状況を踏まえ、農林水産省は農業集落排水施設について、未整備地域に関しては引き続き整備を進めるとともに、既存施設に関しては広域化・共同化対策や維持管理の効率化、長寿命化・老朽化対策を進めるため、地方公共団体による機能診断等の取組や更新整備等を支援しています。
また、国内資源である農業集落排水汚泥のうち、肥料等として農地還元されているものは、令和3(2021)年度末時点で約5割となっています。みどり戦略(*1)の推進に向け、農業集落排水汚泥資源の再生利用を更に推進することとしています。
1 第2章第9節を参照
(農道の適切な保全対策を推進)
農道は、圃場(ほじょう)への通作や営農資機材の搬入、産地から市場までの農産物の輸送等に利用され、農業の生産性向上等に資するほか、地域住民により日常の移動に利用されるなど、農村の生活環境の改善を図る重要なインフラです。令和4(2022)年8月時点で、農道の総延長距離は17万719kmとなっています。一方、農道を構成している構造物について、供用開始後20年を経過するものは、橋梁(きょうりょう)で78%、トンネルで58%に達しています。経年的な劣化の進行も見られる中、構造物の保全対策を計画的・効率的に実施し、その機能を適切に維持していくためには、予防保全を図ることが重要となっています(図表3-5-7)。
このため、農林水産省では、農道の適切な保全対策の実務に必要となる基本的事項を取りまとめた「農道保全対策の手引き」を改定し、保全対策の推進に取り組むとともに、農道の再編・強靱(きょうじん)化や拡幅による高度化等、農業の生産性向上や農村生活を支えるインフラを確保するための取組を支援しています。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883