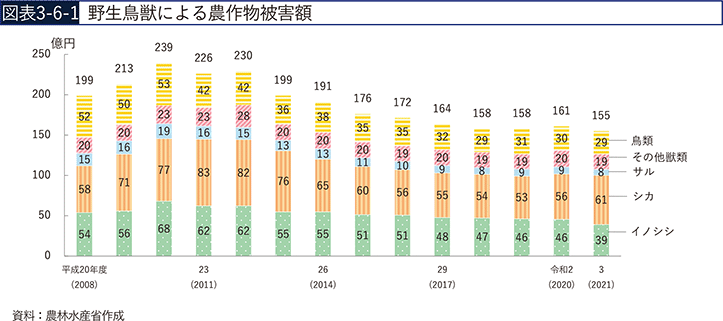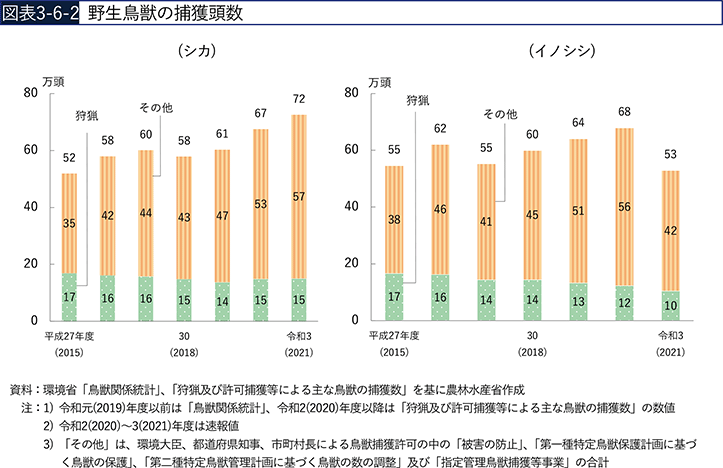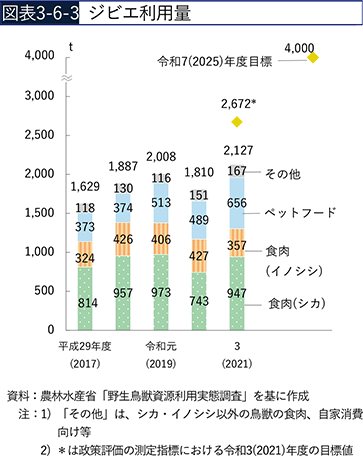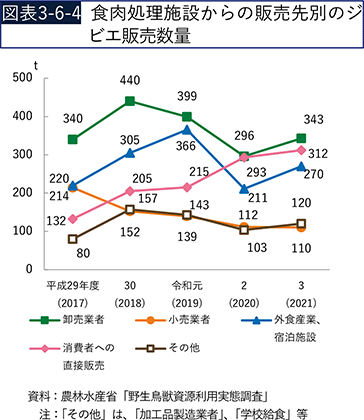第6節 鳥獣被害対策とジビエ利活用の推進
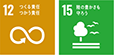
野生鳥獣による農作物被害は、営農意欲の減退をもたらし耕作放棄や離農の要因になるなど、農山村に深刻な影響を及ぼしています。このため、地域の状況に応じた鳥獣被害対策を全国で進めるとともに、マイナスの存在であった有害鳥獣をプラスの存在に変えていくジビエ利活用の取組を拡大していくことが重要です。
本節では、鳥獣被害対策やジビエ利活用の取組について紹介します。
(1)鳥獣被害対策等の推進
(野生鳥獣による農作物被害額は前年度に比べ減少)
野生鳥獣による農作物被害額は、平成22(2010)年度の239億円をピークに減少し、令和3(2021)年度は捕獲等の対策の効果が現れてきたイノシシによる被害の減少等により、前年度に比べ6億円減少し155億円となっています(図表3-6-1)。鳥獣種類別に見ると、シカによる被害額が61億円で最も多く、次いでイノシシが39億円、鳥類が29億円となっています。
野生鳥獣の捕獲頭数については、令和3(2021)年度はシカが前年度に比べ5万頭増加し72万頭となっています(図表3-6-2)。集中捕獲キャンペーンを含む捕獲強化の取組により捕獲頭数が増加している一方、生息頭数の減少ペースは鈍く、引き続き捕獲の強化が必要です。また、イノシシの捕獲頭数は15万頭減少し53万頭となっています。捕獲強化の効果や豚熱(ぶたねつ)(*1)の影響等から生息頭数が減少していることによるものと見られます。
全国各地で鳥獣被害対策が進められている一方、被害が継続して発生している状況にあり、その背景としては野生鳥獣の生息域が拡大したことや過疎化・高齢化による荒廃農地(*2)の増加等がうかがわれます。さらに、鳥獣被害は離農動機としても挙げられていることから、鳥獣被害対策を継続的に推進していくことが重要です。
1、2 用語の解説(1)を参照
(改正鳥獣被害防止特措法に基づき、更なる捕獲強化等に向けた取組を推進)
鳥獣被害の防止に向けては、鳥獣の捕獲による個体数管理、柵の設置等の侵入防止対策、藪(やぶ)の刈払い等による生息環境管理を地域ぐるみで実施することが重要です。
令和3(2021)年に施行した改正鳥獣被害防止特措法(*1)に基づき、令和4(2022)年4月末時点で、1,513市町村が被害防止計画を策定し、そのうち1,234市町村が鳥獣捕獲や柵の設置等、様々な被害防止施策を実施する鳥獣被害対策実施隊を設置しているほか、その隊員数は前年に比べ657人増加し4万2,053人となっています。
農林水産省は、鳥獣被害対策実施隊の活動経費に対する支援を行っており、実施隊員は銃刀法(*2)の技能講習の免除や狩猟税の免除措置等の対象となっています。
更なる捕獲強化等に向け、改正鳥獣被害防止特措法では、行政界をまたいだ広域捕獲を推進するため、都道府県が行う捕獲活動等と国による必要な財政上の措置について規定されました。これを受け、令和4(2022)年度から開始した都道府県広域捕獲活動支援事業では、複数の市町村や都府県にまたがる広域的な範囲において、市町村からの要請を受けた都道府県が生息状況調査や捕獲活動、広域捕獲を担う人材の育成を行っています。あわせて、こうした取組に専門家が参画し、効果的な広域捕獲を目指す取組も推進しています。
また、ICTを用いたわなやセンサーカメラ等の新技術をフル活用した、データに基づく効果的・効率的な鳥獣被害対策を推進するモデル地区の整備を行っています。
1 正式名称は「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律」
2 正式名称は「銃砲刀剣類所持等取締法」
(事例)専門家と地域住民によるICTを活用した鳥獣被害対策を推進(長崎県)

長崎県対馬市(つしまし)では、ICTを活用し被害状況と対策の効果を可視化することで、専門家と地域住民が関連情報を共有するとともに、データに基づく地域に適した防護・捕獲対策の提案を通じ、地域住民主体の対策を実施しています。
同市では、イノシシやシカによる農林業被害を防止するため、防護柵の設置や有害鳥獣捕獲を積極的に進めています。
また、地理情報システム(GIS)やGPS付きカメラ等を活用し、鳥獣被害の状況や柵の設置状況、捕獲の状況を可視化する取組を進めています。地域住民と鳥獣被害対策の現状を共有し、地域に適した対策の検討を行うことで、地域住民主導による対策の強化を図っています。
さらに、被害に悩む地域住民を対象とした被害相談会の開催や、島内の小中学校での鳥獣被害対策授業の実施、狩猟免許を保有していない地域住民も参画した地区捕獲隊の設置等、地域一体となった捕獲対策を進めています。
このほか、地域住民の協力体制を構築するため、「獣害から獣財へ」をキーワードに、捕獲したイノシシやシカをジビエや皮革製品等として有効利用する取組にも力を入れており、特にジビエはふるさと納税の返礼品としても活用されています。
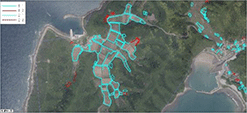
GISを活用し、防護柵の設置状況を可視化
資料:長崎県対馬市
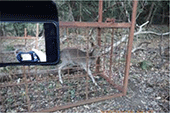
GPS付きカメラ等により捕獲位置を記録
資料:長崎県対馬市
(2)ジビエ利活用の拡大
(ジビエ利用量は前年度に比べ増加)
食材となる野生鳥獣肉のことをフランス語でジビエ(gibier)といいます。我が国では、シカやイノシシによる農作物被害が大きな問題となっており、捕獲が進められるとともに、ジビエとしての利用も全国的に広まっています。害獣とされてきた野生動物も、ジビエとして有効利用されることで食文化をより豊かにしてくれる味わい深い食材、あるいは農山村地域を活性化させ、農村の所得を生み出す地域資源となります。捕獲個体を無駄なくフル活用することにより、外食や小売、学校給食、ペットフード等、様々な分野においてジビエ利用が拡大しており、農林水産省は、この流れを更に進めるため、ジビエ利用量を令和7(2025)年度までに4千tとすることを目標としています。令和3(2021)年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により低迷していた外食需要が一定程度回復し、特にシカの食肉利用が拡大したこと等から、前年度に比べ18%増加し2,127tとなりました(図表3-6-3)。
食肉処理施設からの販売先別の販売数量を見ると、卸売業者や外食産業・宿泊施設向けの販売数量が回復傾向にあるほか、消費者への直接販売は引き続き増加傾向で推移しています(図表3-6-4)。
農林水産省は、改正鳥獣被害防止特措法において、捕獲等を行った野生鳥獣の有効利用の更なる推進が規定されたことを踏まえ、引き続きジビエ需要の開拓・創出や良質なジビエの安定供給等に取り組むこととしています。
また、更なる需要拡大に向けて、食肉利用のほか、皮、骨、角等の多用途利用を推進しています。令和3(2021)年度は、特にペットフード向けがジビエ利用量の約3割を占めるまで増加したほか、動物園では肉食獣の餌に利用されるなど、新たな試みも見られています。
(国産ジビエ認証施設は前年度に比べ4施設増加)
ジビエの利用拡大に当たっては、より安全なジビエの提供と消費者のジビエに対する安心の確保を図ることが必要です。このため、農林水産省では、平成30(2018)年に国産ジビエ認証制度を制定し、厚生労働省のガイドラインに基づく衛生管理の遵守やトレーサビリティの確保に取り組むジビエの食肉処理施設を認証しており、令和4(2022)年度末の認証施設数は新たに認証を取得した4施設を加えて30施設となりました。こうした認証施設で処理されたジビエが大手外食事業者等によって加工・販売され、ジビエ利用量の拡大につながる事例も見られています。
また、農林水産省は、捕獲個体の食肉処理施設への搬入促進や需要喚起のためのプロモーション等に取り組んでおり、ポータルサイト「ジビエト」では、令和5(2023)年3月時点で、ジビエを提供している飲食店等、約420店舗の情報を掲載しています。

国産ジビエ認証制度
URL:https://www.maff.go.jp/j/nousin/gibier/ninsyou.html

ジビエト
URL:https://gibierto.jp/about/(外部リンク)
(事例)食肉に加え、皮、骨、角等の多用途利用を推進(山梨県)

山梨県丹波山村(たばやまむら)の丹波山村(たばやまむら)ジビエ肉処理加工施設は、令和3(2021)年2月に、国産ジビエ認証制度の認証を取得し、高品質で安全なジビエを提供しています。
同施設は、指定管理者である株式会社アットホームサポーターズによって管理運営されており、同村に受け継がれている「狩猟文化」の継承に寄与する拠点施設として位置付けられています。
同社は、野生鳥獣の捕獲から解体、精肉、製造、販売の全ての工程を自社で行うことで徹底した品質管理を行っており、山梨県独自の認証制度である「やまなしジビエ」認証も取得しています。
また、シカの肉だけでなく、皮、骨、角といった部位も余すところなく加工販売することで、廃棄やロスのない生産を進めています。
同社では、猟師の基本行動を学習できる「狩猟学校」を開設し、狩猟や解体のノウハウを教授するとともに、近隣自治体や関係機関とも連携をしながら、ジビエ利用の拡大に向けた取組を進めています。

丹波山村ジビエ肉処理加工施設
資料:株式会社アットホームサポーターズ
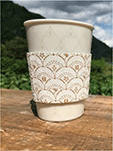
シカの皮を使ったカップスリーブ
資料:株式会社アットホームサポーターズ
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883