第2節 足下での原油・物価高騰の影響と対応
(1)飼料価格高騰への対応
(飼料価格の高騰に対応し、緊急対策を実施)
我が国の畜産経営において、令和3(2021)年の経営費に占める飼料費の割合を営農類型別に見ると、約3~6割となっています。
飼料価格高騰による畜産経営への影響については、公庫が令和4(2022)年7月に実施した調査によると、62.4%が「飼料費が前年比30%以上増加した」と回答しました(図表 特-16)。
農林水産省では、とうもろこし等の飼料原料価格の上昇等により、配合飼料価格が高騰している状況を踏まえ、令和4(2022)年4月に決定した「コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」」(以下「総合緊急対策」という。)や、同年9月に閣議決定した予備費使用、同年10月に閣議決定した「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」(以下「総合経済対策」という。)の一環として、各般の緊急対策を迅速に実施しました。
配合飼料に対しては、価格の上昇が畜産経営に及ぼす影響を緩和するため、生産者に補塡金が交付される配合飼料価格安定制度により、生産者、配合飼料メーカー等が拠出する通常補塡基金と、国と配合飼料メーカー等が拠出する異常補塡基金から、生産者に補塡金を交付し、生産者の負担軽減を図っています(図表 特-17)。
また、総合緊急対策において、異常補塡基金への435億円の積み増しを措置した上で、令和4(2022)年度第1四半期(令和4(2022)年4~6月)及び第2四半期(同年7~9月)の異常補塡の発動基準を特例的に引き下げました。さらに、総合経済対策において、異常補塡基金への103億円の積み増しを措置しました。
くわえて、予備費を活用し、生産コスト削減や飼料自給率の向上に取り組む生産者に対し、令和4(2022)年度第3四半期(令和4(2022)年10~12月)の実質的な飼料コストを第2四半期と同程度の水準まで抑制する緊急対策を実施したほか、酪農経営については、購入粗飼料等の高騰の影響を受け生産コストが上昇していることから、国産飼料の利用拡大や生産コスト削減に取り組む生産者に対し、コスト上昇分の一部を補塡する対策を講じました。
このほか、令和5(2023)年3月に閣議決定した「物価高克服に向けた追加策」としての予備費使用においては、令和4(2022)年度第4四半期(令和5(2023)年1~3月)については、配合飼料価格が前期とほぼ同水準で推移すると見込まれること等を踏まえ、第3四半期の緊急対策を拡大することで、酪農や養鶏等、様々な畜種の飼料コストを抑制することとしました。また、配合飼料に加え購入粗飼料の高騰や需要の減少等により特に収益性が悪化している酪農経営について、引き続き消費・輸出拡大等に取り組みつつ、購入粗飼料等のコスト上昇に対する補塡等を行うこととしました。さらに、令和5(2023)年度第1四半期(令和5(2023)年4~6月)以降については、配合飼料価格が高止まりする中、畜産経営への影響を緩和するため、配合飼料価格安定制度に新たな特例を創設することとしました。
これらの緊急対策により飼料価格高騰の影響を受ける畜産経営への影響緩和が進められている一方、過度に輸入に依存する構造の転換を着実に進めていくことが課題となっています。
(耕畜連携への支援を強化)
水田では、米の収穫に伴い、稲わらやもみ殻といった利用価値の高い副産物が産出されており、家畜の飼料や敷料等の有用な資源として活用されています。また、家畜の飼養に伴い排出される家畜排せつ物は堆肥にすることにより、肥料や土壌改良剤等の有用な資源として活用されています。
生産資材価格が高騰し、耕種農家・畜産農家双方の経営に影響が見られる中、耕種農家と畜産農家が連携し、飼料作物と堆肥を循環させる「耕畜連携」の取組について、その重要性が一層高まっています。
農林水産省では、国産稲わらの収集に必要な機械の導入等を支援しているほか、畜産サイドと耕種サイドが長期の利用・供給契約に基づき、国産飼料を供給するなど、国産飼料の利用拡大のための新たな枠組みの構築等を支援しています。
(コラム)稲わらと堆肥ペレットの広域流通実証試験を開始

稲わら
資料:全国農業協同組合連合会宮城県本部

堆肥ペレット
資料:鹿児島県経済農業協同組合連合会
全国農業協同組合連合会宮城県(みやぎけん)本部(以下「JA全農みやぎ」という。)と鹿児島県(かごしまけん)経済農業協同組合連合会(以下「JA鹿児島県経済連」という。)は、稲わらと堆肥ペレットを相互に流通させる広域流通実証試験に取り組んでいます。
JA全農みやぎの管内では、収穫後の稲わらを乾燥させやすい気候条件にあり、良質な稲わらの一大産地となっており、稲わらの供給先の拡大が可能となっています。一方、JA鹿児島県経済連の管内では、畜産が盛んであり、良質な堆肥が豊富に生産されているものの、需要期にばらつきが見られるなどの課題を抱えています。
このため、両者は、直線距離で約1,500km離れた地理的な制約の克服に向けて連携して取り組み、広域での需給調整を図ることにより、粗飼料の自給率向上や稲作生産者の新たな収入源確保につなげることを目指しています。
令和5(2023)年2月以降、宮城県内の農業協同組合(以下「農協」という。)が生産した稲わら140tがJA鹿児島県経済連に販売されており、鹿児島県内の牧場で使用される予定となっています。また、JA鹿児島県経済連が開発した、堆肥を粒状に成形加工した「堆肥ペレット」60tが宮城県内の3農協に出荷され、主にWCS(*)用稲の肥料として使用される予定となっています。
今後は、トラックやフェリー、鉄道を使用した場合の輸送経費の検証や堆肥ペレット利用の栽培暦の作成、直播等による生産コスト低減対策を進めていくこととしています。
* 用語の解説(2)を参照
(2)肥料価格高騰への対応
(肥料原料の調達不安定化や価格高騰に対応し、緊急対策を実施)
我が国の農業経営において、令和3(2021)年の経営費に占める肥料費の割合は営農類型により異なるものの、約4~18%となっています。我が国は化学肥料原料の大部分を海外に依存しているため、供給量や肥料価格が国際情勢の影響を受けやすい構造となっています。
こうした中、令和3(2021)年秋以降、肥料原料の国際価格が上昇するとともに既存の輸入先国からの原料調達が困難となり、我が国の農業経営への影響が懸念される事態となったこと等を受けて、農林水産省では、令和4(2022)年4月の総合緊急対策や、同年7月の予備費を使用した対策、同年10月の総合経済対策等により、肥料供給の安定化や価格高騰の影響緩和を図るための様々な対策を講じました。
このうち、総合緊急対策においては、中国やロシア等これまで輸入してきた国からの原料調達が停滞したことから、モロッコ等の代替国からの調達に要する掛かり増しのコスト(海上輸送費等)に対し支援措置を講ずるとともに、国内の農業者に対しては、慣行の施肥体系から肥料コスト低減体系への転換を進める取組に対する支援を拡大しました。
また、予備費を使用した対策では、肥料価格高騰による農業経営への影響を緩和するため、化学肥料使用量の低減に向けた取組を行う農業者に対し、肥料費上昇分の7割を支援する新たな対策を講じました。
さらに、肥料原料の大部分を海外に依存している中で、調達先国からの供給途絶等により肥料原料の需給が逼迫(ひっぱく)した場合にも生産現場への肥料の供給を安定的に行うことができるよう、経済安全保障推進法(*1)における特定重要物資として肥料を指定し、主要な肥料原料の備蓄を行う仕組みを創設しました。総合経済対策では、肥料原料の備蓄に要する保管経費と保管施設の整備費を支援するための基金を創設するとともに、肥料の国産化に向けて、畜産業由来の堆肥や下水汚泥資源の肥料利用を推進することとし、畜産農家や下水道事業者、肥料製造業者、耕種農家等が連携した取組や施設整備等を支援しています。
くわえて、国内資源の肥料利用の推進については、関係事業者間の連携が重要となることから、農林水産省では、令和4(2022)年12月に、これら関連事業者に関する情報を一元的に収集し、互いに閲覧できるマッチングサイトを開設しました。また、令和5(2023)年2月には国内肥料資源の利用拡大に向けた全国推進協議会を設立し、各地域において関係事業者の連携を創出していくためのマッチング会合の開催等を進めることとしています。
これらの対策により、現下の肥料価格高騰による影響を緩和しつつ、肥料の安定供給に向けた対応が進められています。一方、輸入の安定化・多角化や過度に輸入に依存する構造の転換を着実に進めていくことが課題となっています。
*1 正式名称は「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律」
(事例)低コスト堆肥入り粒状複合肥料を開発・供給(宮崎県)

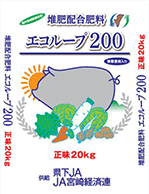
低コスト堆肥入り粒状複合肥料
資料:宮崎県経済農業協同組合連合会
宮崎県宮崎市(みやざきし)に本拠を置く宮崎県(みやざきけん)経済農業協同組合連合会(以下「JA宮崎経済連」という。)は、低コスト堆肥入り粒状(りゅうじょう)複合肥料を供給し、地域資源の活用と農業者の生産コスト削減を推進しています。
JA宮崎経済連では、豚ぷんや鶏ふん等の地域資源を活用した環境に配慮した粒状複合肥料の開発を令和2(2020)年から進めてきましたが、肥料価格の高騰に対応するため早期の開発に努め、令和4(2022)年9月から供給を開始しました。その供給価格は、同年の秋肥(あきごえ)(既存銘柄)の価格と比べて約75~85%の水準に抑制されています。
肥料の製造については、JA宮崎経済連の養豚実証農場から発生する豚ぷん堆肥や、県内の養鶏農協から供給される鶏ふん堆肥を原料として活用し、肥料メーカーでペレット化・粒状化した後、肥料供給センターで配合が行われています。
肥料の種類としては、鶏ふん堆肥を約30%配合した園芸全般向けの製品のほか、豚ぷん堆肥入りペレットを約30%配合した露地野菜等に適した製品等が供給されており、化学肥料使用量の低減にも寄与するものとなっています。
JA宮崎経済連では、今後も作物別の配合設計を進めるなど低コスト堆肥入り粒状複合肥料の更なる活用拡大を図ることとしています。
(肥料原料の安定供給を働き掛け)
政府は、肥料原料の代替国からの調達のため、外交面での取組を推進しています。令和4(2022)年5月には、モロッコに対しりん酸アンモニウムの安定供給に向けた働き掛けを行いました。また、令和4(2022)年6月及び令和5(2023)年1月に、カナダに対し塩化加里の安定供給に向けた働き掛けを行ったほか、令和4(2022)年7月に、マレーシアに対し尿素の安定供給について働き掛けを行いました。

モロッコにりん酸アンモニウムの
安定供給を要請する
農林水産副大臣

カナダに塩化加里の
安定供給を要請する
農林水産大臣

マレーシアに尿素の
安定供給を要請する
農林水産大臣政務官
(3)燃料価格高騰への対応
(燃料価格の高騰に対し、施設園芸農家等向けの支援策を実施)
我が国の施設園芸経営において、令和3(2021)年の経営費に占める燃料費の割合は約2~3割となっています。
重油等の燃油は、その価格が為替相場や国際的な市況等の影響で大きく変動することから、今後の価格の見通しを立てることが困難な生産資材です。また、重油価格指数は、令和3(2021)年3月以降、おおむね前年を上回って推移しています(図表 特-18)。
燃油価格高騰による農業経営への影響については、公庫が令和4(2022)年7月に実施した調査によると、34.4%が「燃料動力費が前年比30%以上増加した」と回答しました(図表 特-19)。
農林水産省では、燃料価格の高騰を踏まえ、令和4(2022)年3月に取りまとめた「原油価格高騰に対する緊急対策」や同年10月の総合経済対策において、燃料高騰の影響を受ける施設園芸農家等に対する支援策を講じました。
原油価格高騰に対する緊急対策においては、計画的に省エネルギー化等に取り組む産地を対象に、農業者と国で基金を設け、A重油・灯油の価格が一定の基準を超えた場合に補塡金を交付する施設園芸等燃油価格高騰対策について、農業者が行う積立ての上限を引き上げることにより、セーフティネット機能を強化するほか、省エネ機器等の導入を支援する産地生産基盤パワーアップ事業(施設園芸エネルギー転換枠)について支援枠の拡充等を行いました。
また、総合経済対策においては、施設園芸等燃料価格高騰対策について、LPガスやLNG(液化天然ガス)も対象に追加する拡充を行ったほか、省エネ機器等の導入支援についても引き続き行いました。
(事例)省エネルギー技術を活用し、化石燃料の使用量を削減(千葉県)


電力で加温するヒートポンプ
資料:千葉県千葉市
千葉県千葉市(ちばし)は、温暖な気候を背景に施設園芸が盛んに行われている一方、その生産体系の多くは冬季に加温を要し、A重油を燃料とする従来式の暖房機を活用した施設が主となっています。
こうした中、千葉市や千葉県等を構成員とする千葉市SDGs対応型施設園芸推進協議会では、施設園芸において暖房を中心とした燃料消費によるCO2排出量削減に資するため、電力を主体とした加温技術の体系化を目指し、技術実証を進めています。
同協議会では、ヒートポンプによる加温エネルギー消費を電力のみとし、加温における燃油消費をゼロにする技術体系の構築に取り組んでいます。また、ヒートポンプと燃油暖房機とのハイブリッド型に、高保温性カーテンを用いた加温栽培技術を組み合わせ、省エネ型CO2発生装置を活用することにより単収を向上させる技術体系の構築等の取組を実施しています。
これらの取組を通じ、令和6(2024)年度までにハイブリッド型において、化石燃料使用量の40%低減、単収当たりの化石燃料使用量を52%削減することを目指しています。
(電気料金の高騰に対し、農業水利施設への支援を実施)
食料の安定供給に不可欠な公共・公益性の高いインフラである農業水利施設(*1)は、維持管理費に占める電気料金の割合が大きく、エネルギー価格高騰による影響を受けやすくなっています。
このため、農林水産省では、昨今の電気料金の急激な高騰を踏まえ、農業水利施設の省エネルギー化を進めるとともに、エネルギー価格高騰の影響の緩和に向け、農業水利施設の省エネルギー化に取り組む土地改良区等の施設管理者に対し、令和4(2022)年度全体の電気料金高騰分の7割を支援する対策を講じました。
また、電気料金が引き続き高騰している状況を踏まえ、令和5(2023)年3月の「物価高克服に向けた追加策」としての予備費使用において、同様の支援策を同年9月まで実施することとしています。
*1 用語の解説(1)を参照
(4)食品原材料価格高騰への対応
(食品企業では、原材料価格の高騰等が大きく影響)
食品企業における原材料価格高騰等に伴うコストの増加について、公庫が令和5(2023)年1月に実施した調査によると、コストが前年同期と比較して2割以上増加したと回答した食品関係企業の割合は、製造業が37.7%と最も高く、次いで飲食業が31.0%となっており、食品企業の経営に大きな影響を及ぼしていることがうかがわれます(図表 特-20)。
(輸入小麦の価格を抑制)
輸入小麦の政府売渡価格は、国際相場の変動の影響を緩和するため、4月期と10月期の年2回、価格改定を行っていますが、ロシアによるウクライナ侵略等を受け、令和4(2022)年10月期と令和5(2023)年4月期に価格高騰対策を実施しました。
令和4(2022)年10月期には、輸入小麦の買付価格が、同年3月以降、ウクライナ侵略を受けて急騰した後、同年6月以降には下落し急激に変動したことから、通常6か月間の算定期間を1年間に延長してその影響を平準化することとし、同年10月期の政府売渡価格は同年4月期の価格(5銘柄加重平均で7万2,530円/t)を適用し、実質的に据え置く緊急措置を実施しました(図表 特-21)。
また、令和5(2023)年4月期には、物価上昇全体に占める食料品価格上昇の影響が高まっていたことを受け、価格の予見可能性、小麦の国産化の方針、消費者の負担等を総合的に判断した結果、ウクライナ侵略直後の急騰による影響を受けた期間を除く直近6か月間の買付価格を反映した水準まで上昇幅を抑制し、令和4(2022)年10月期と比べて5.8%上昇となる7万6,750円/tとする激変緩和措置を実施しました。
(輸入小麦の国産小麦・米粉への原材料切替えを促進)
ロシアによるウクライナ侵略等を背景として、食品製造業者等が使用している輸入食品原材料の価格が高騰しています。このため、総合緊急対策の一環として、国産小麦・米粉等への原材料の切替え、価格転嫁に見合う付加価値の高い商品への転換や生産方法の高度化による原材料コストの抑制等の取組を緊急的に支援しました。
(国産小麦の供給体制を整備)
国際的に小麦等の供給懸念が生じ価格が高騰する中、輸入依存度が高い小麦の安定供給体制を緊急的に強化するため、総合緊急対策の一環として、生産面において作付けの団地化、営農技術・機械の導入等を支援するとともに、流通面において一時保管等の安定供給体制の構築を支援しました。
(小麦・大豆・飼料作物の国産化を推進)
小麦・大豆・飼料作物や加工・業務用野菜の国産化を推進するため、令和4(2022)年11月に取りまとめた「食料品等の物価高騰対応のための緊急パッケージ」に基づき、小麦・大豆等の国内生産の拡大や安定供給のための施設整備、国産原料への切替えに取り組む食品製造事業者等の新商品開発に対する支援、水田の畑地化を強力に推進するとともに、耕畜連携の取組等による国産飼料の生産・利用拡大等を支援しました。
(事例)転作田の団地化等により効率的に小麦を増産(北海道)


大型機械による収穫作業
資料:株式会社ファーム白倉
北海道南幌町(なんぽろちょう)の株式会社ファーム白倉(しらくら)は、農業機械の大型化により生産性を高めつつ、機械の共同利用により投資コストを抑え、作業効率向上と経営所得の安定を図りながら、小麦の増産に取り組んでいます。
同社では、農地を借り受けて経営規模を拡大しながら、水稲から小麦への作付転換を行っています。令和2(2020)年に35haであった小麦の作付面積は、令和4(2022)年には50haに増加しています。
また、転作田の団地化のほか、南幌町(なんぽろちょう)農業協同組合の営農支援サービスを活用した画像診断により収穫適期を把握し、作業効率を高めるとともに、先進技術を導入した排水対策や茎数、葉色値等の測定結果に基づき生育後期に重点的に施肥を行うことで、高水準の単収を確保しています。
同社では、従前から土づくりに力を入れていますが、今後とも緑肥や有機資材の施用による地力増進に取り組み、適切な輪作体系を維持しながら、水稲から小麦への作付転換を行い、小麦の作付面積の拡大を更に進めていくこととしています。
(5)食品アクセスの確保に向けた対応
(食品アクセスの確保に向けた対応を推進)
食品アクセスの確保に向けた対応を推進するため、農林水産省は、食品ロス削減の取組を強化するとともに、こども食堂等へ食品の提供を行うフードバンクやこども宅食に対する支援、共食の場の提供支援等を実施し、農林水産省を中心に関係省庁が連携して生活困窮者への食品支援の取組を行っています。また、フードバンクを通じてこども食堂等に政府備蓄米を無償交付し、支援を強化しています。
(6)コスト上昇分の適切な価格転嫁に向けた対応
(農業生産資材価格の上昇と比べて農産物価格の上昇は緩やか)
農業経営体が購入する農業生産資材価格に関する指数である農業生産資材価格指数については、令和4(2022)年1月以降、飼料や肥料等が上昇したことにより上昇傾向で推移しており、令和5(2023)年2月時点では121.9となっています(図表 特-22)。
一方、農業経営体が販売する農産物の生産者価格に関する指数である農産物価格指数については、令和4(2022)年1月以降、鶏卵や雑穀等が上昇したことによりやや上昇傾向で推移しており、令和5(2023)年2月時点では108.3となっています(図表 特-23)。
両者の推移を比較すると、農産物価格指数の上昇率は、農業生産資材価格指数の上昇率と比べて緩やかな動きとなっています。飼料や肥料原料の高騰等により生産資材価格の高騰が続く一方、農産物価格への転嫁は円滑に進んでいないことがうかがわれます。
農業経営の安定化を図り、農産物が将来にわたり安定的に供給されるようにするためには、生産コストの上昇等を適切な価格に反映し、経営を継続できる環境を整備することが重要となっています。
(コスト高騰に伴う農産物・食品への価格転嫁が課題)
農産物の価格については、品目ごとにそれぞれの需給事情や品質に応じて形成されることが基本となっていますが、流通段階で価格競争が厳しいこと等、様々な要因で、農業生産資材等のコスト上昇分を適切に取引価格に転嫁することが難しい状況にあります。
公益社団法人日本農業法人協会(にほんのうぎょうほうじんきょうかい)が令和4(2022)年11~12月に実施した調査によると、農業生産資材等のコスト高騰を受け「値上げ(価格転嫁)した」と回答した農業者の割合は13.5%、「改定していない(値上げできなかった)」又は「値下げした」と回答した農業者の割合は55.0%となっています(図表 特-24)。また、値上げ(適正な価格形成)の実現に向けた取組・努力については、「日頃から交渉相手と情報を密に共有している」の回答が最も多く、次いで「値上げ交渉において、客観的な経営上の数値やその資料を用いて具体的に交渉している」となっています(図表 特-25)。
また、中小企業庁が令和4(2022)年9~11月に実施した調査(*1)によると、食品製造業(中小企業)におけるコスト増に対する価格転嫁の割合は45.0%となっています。
生産資材や原材料の価格高騰は、生産者・食品企業の経営コストの増加に直結し、最終商品の販売価格まで適切に転嫁できなければ、食料安定供給の基盤自体を弱体化させかねません。
このため、飼料、肥料、燃油等の生産資材や原材料価格の高騰等による農産物・食品の生産コストの上昇等について、消費者の理解を得つつ、事業者を始めフードチェーン全体で、適切な価格転嫁のための環境整備を進めていくことが必要です。
*1 中小企業庁「価格交渉促進月間(2022年9月)フォローアップ調査」(令和4(2022)年12月公表)
(農業経費の動向等を適時に開示していくことも重要)
取引先との値上げ交渉においては、飼料費や肥料費等、客観的な経営上の数値を示すなど、合理的な根拠を持って協議を行うことが重要です。
令和2(2020)年の農業経営体数107万6千経営体のうち、青色申告を実施(*1)している農業経営体数は、38万2千経営体(35.5%)となっており、適切な経営管理や価格交渉力の前提となる農業経費の正確な把握等に課題があることがうかがわれます。
農業者が農産物の適切な価格転嫁を図っていくためには、生産原価を始めとした経営内容の把握を的確に行い、取引先に対して農業経費の動向等を適時に開示していくことも重要となっています。
*1 現金主義を含む。
(適切な価格転嫁のための取組を推進)
政府は、令和3(2021)年に決定した「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」に基づき、中小企業等が賃上げの原資を確保できるよう、取引事業者全体のパートナーシップにより、労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇分を価格に適切に転嫁できる環境整備に取り組んでいます。具体的には、公正取引委員会において、労務費、原材料費、エネルギーコスト等のコスト上昇分を取引価格に反映せず、従来どおりに取引価格を据え置く行為が疑われる事案が発生していると見込まれる業種として、食料品製造業や飲食料品卸売業、飲食料品小売業を含む調査対象業種を選定し、独占禁止法(*1)上の「優越的地位の濫用」に関する緊急調査を行い、具体的な懸念事項を明示した注意喚起文書を送付するなど、コスト上昇分を適正に転嫁できる環境の整備を進めています。
農林水産省では、食品製造業者と小売業者との取引関係において、問題となり得る事例等を示した「食品製造業者・小売業者間における適正取引推進ガイドライン」を策定し、これを普及することで、取引上の法令違反の未然防止、食品製造業者や小売業者の経営努力が報われる健全な取引の推進を図っています。
また、令和4(2022)年4月には、食品製造業者や食品小売業者に対して、コスト上昇の取引価格への適正な反映について、農林水産大臣名で「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」に基づく協力要請を行っています。
さらに、食品の値上げには、消費者の理解が不可欠であるため、食料供給コストの上昇の背景等を理解してもらうための広報活動等を進めており、コストが上昇している品目(牛乳等)に着目した動画を作成し、Webサイトでの情報発信を行うとともに、店舗等で活用できるポスターを作成・公表しています。

消費者に理解を求めるための政府広報動画
資料:内閣府

消費者に理解を求めるための
小売店向けポスター・チラシ
このほか、農業生産資材等の価格が高騰する中で、国産農畜産物の生産コスト上昇分の転嫁が課題となっていることを踏まえ、フランスの「農業及び食料分野における商業関係の均衡並びに健康で持続可能で誰もがアクセスできる食料のための法律」(以下「Egalim法(*2)」という。)や、農業生産者と取引相手との適正な取引関係を強化する法律(以下「Egalim2法」という。)の内容や執行状況等の調査を行っています。
*1 正式名称は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」
*2 食料全体会議「États généraux de l’alimentation」での議論を基に制定されたことから、Egalim法と称されている。
(フォーカス)フランスでは農業生産者と取引相手との適正な取引関係を推進
我が国では、農業生産資材等の価格が高騰する中で、国産農畜産物の生産コスト上昇分の転嫁が課題となっており、農業生産者と取引相手との適正な取引関係の推進を図るフランスでの取組への関心が高まっています。
フランスのEgalim法は、平成30(2018)年11月に、農業生産者と取引相手との関係を見直し、持続可能性に配慮すること等を目的として公布されました。
また、Egalim法の施行後、農業生産者と取引相手との適正な取引関係を更に推進する観点から見直しが行われ、Egalim法を強化するEgalim2法が令和3(2021)年10月に公布されました。
Egalim2法では、(1)農業者と最初の購入者の間での書面契約の義務化、(2)書面契約への価格及び生産費指標を考慮した価格の自動改定方式、契約期間等の記載義務、(3)認定生産者組織が農業者の契約交渉を代行し、契約の枠組み協定を締結する場合の記載義務((2)と同様)、(4)品目ごとに生産から小売の各段階の代表組織が加盟する専門職業間組織による生産費に関する指標の公表、(5)最初の購入者以降の流通における農産物原材料価格を交渉の対象外とすること等が規定されています。
なお、農業生産者と最初の取引者との書面契約義務の対象品目は、牛肉、豚肉、鶏肉、卵、乳・乳製品等(団体等の意見を踏まえて対象を限定)となっており、消費者への直接販売、卸売市場での取引等は適用除外となっています。
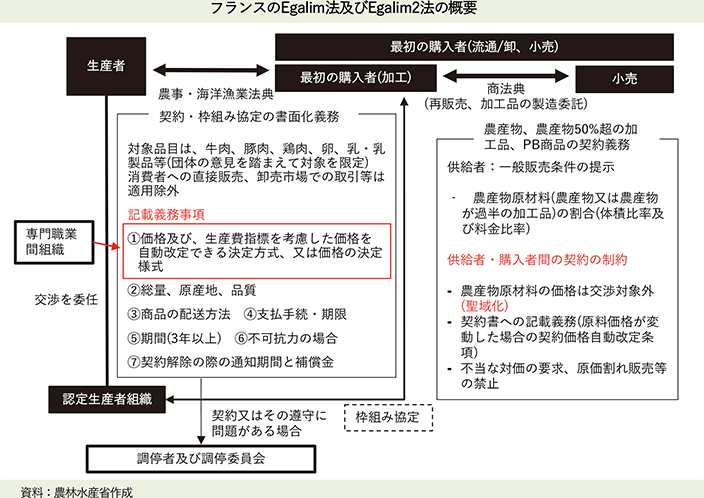
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883














