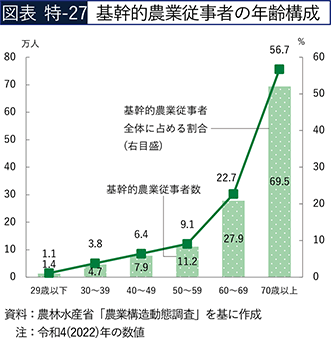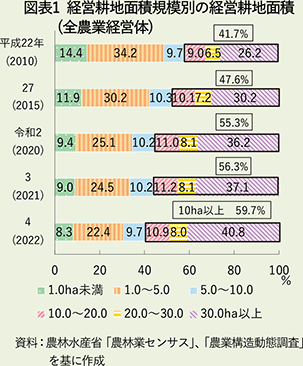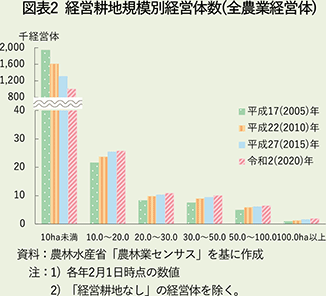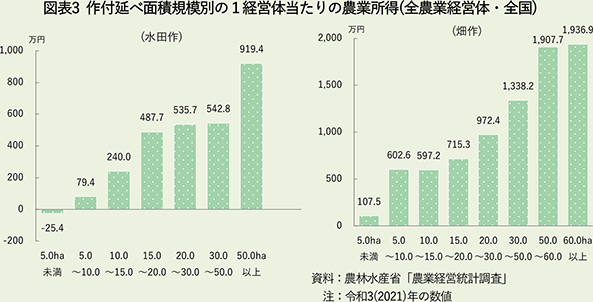第3節 将来を見据えた食料安全保障の強化
(食料安定供給・農林水産業基盤強化本部への改組により体制を強化)

食料安定供給・農林水産業基盤強化本部
第1回会合のまとめを行う内閣総理大臣
資料:首相官邸ホームページ
URL:https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/
actions/202212/27nourin.html(外部リンク)
農林水産業・地域が将来にわたって国の活力の源となり、持続的に発展するための方策を幅広く検討するために、平成25(2013)年5月に設置された「農林水産業・地域の活力創造本部」(本部長は内閣総理大臣)については、令和4(2022)年6月に「食料安定供給・農林水産業基盤強化本部」に改組されました。
同本部では、我が国の食料の安定供給・農林水産業の基盤強化を図ることにより、スマート農林水産業の推進、農林水産物・食品の輸出促進、農林水産業のグリーン化等による農林水産業の成長産業化及び食料安全保障の強化を推進するための方策を総合的に検討することとしています。
(食料安全保障強化政策大綱を決定)
昨今、気候変動等による世界的な食料生産の不安定化や、世界的な食料需要の拡大に伴う調達競争の激化等に、ウクライナ情勢の緊迫化等も加わり、輸入する食品原材料や生産資材の価格高騰を招くとともに、産出国が偏り、食料以上に調達切替えが難しい化学肥料の輸出規制や、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う国際物流の混乱等による供給の不安定化も経験するなど、食料安全保障の強化が国家の喫緊かつ最重要課題となっています。
これを受けて、政府は令和4(2022)年度に各般の対策を講じていますが、特に近年の急激な食料安定供給リスクの高まりを鑑みれば、食料安全保障の強化に向けた施策を継続的に講ずることにより、早期に食料安全保障の強化を実現していく必要があります。
このため、食料安定供給・農林水産業基盤強化本部では、令和4(2022)年12月に「食料安全保障強化政策大綱」(以下「大綱」という。)を決定し、継続的に講ずべき食料安全保障の強化のために必要な対策とその目標を明らかにしました(図表 特-26)。
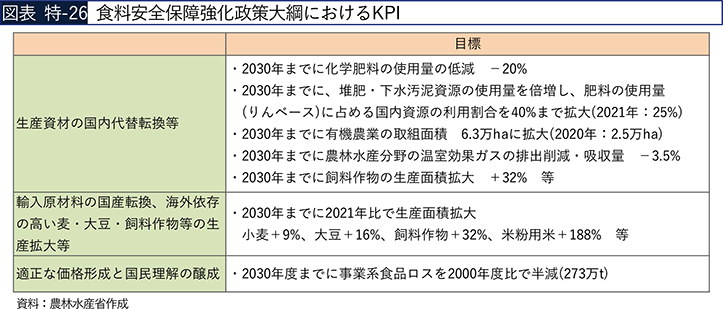
また、食料安全保障の強化に向け、過度な輸入依存からの脱却に向けた構造転換とそれを支える国内の供給力の強化を実現するためには、農林水産業・食品産業の生産基盤が強固であることが前提となることから、大綱では、食料安全保障の強化のための対策に加え、スマート農林水産業等による成長産業化、農林水産物・食品の輸出促進、農林水産業のグリーン化についても、改めてその目標等を整理し、その実現に向けた主要施策を取りまとめました。
(食料・農業・農村基本法の検証・見直しに向けた検討)
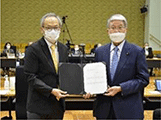
諮問文を食料・農業・農村政策審議会
会長に手交する農林水産大臣
我が国農政の基本方向を示す食料・農業・農村基本法(以下「基本法」という。)は、平成11(1999)年の制定から約20年が経過し、生産者の減少・高齢化等、国内の農業・流通構造の変化に加え、世界的な食料情勢の変化や気候変動に伴い、食料安全保障上のリスクが、基本法制定時には想定されなかったレベルに達しています。
このため、令和4(2022)年9月に農林水産大臣から食料・農業・農村政策審議会に諮問し、新たに設置された「基本法検証部会」において、有識者からのヒアリングや施策の検証等、消費者、生産者、経済界、メディア、農業団体等の代表から成る委員による活発な議論が行われています。
(食料安全保障の強化に向けた構造転換対策を推進)
食料安全保障については、国内の農業生産の振興を図りながら、安定的な輸入と適切な備蓄を組み合わせて強化していくこととしています。そうした中、農林水産物・食品の過度な輸入依存は、原産国の不作等による穀物価格の急騰や、化学肥料原料産出国の輸出規制による調達量の減少等が生じた場合に、思うような条件での輸入ができなくなるなど、平時でも食料の安定供給を脅かすリスクを高めることとなります。
一方、小麦や大豆、米粉等の国産の農林水産物については、品質の向上が進む中で、海外調達の不安定化とあいまって、活用の拡大が期待されるものがあります。飼料については、牧草、稲わら等の粗飼料を中心に国内の生産や供給の余力があり、畜産農家による粗飼料生産に伴う労働負担軽減、生産する耕種農家と利用者である畜産農家との連携や広域流通の仕組み、利用者の利便を考慮した提供の在り方等を実現することにより、活用の更なる拡大が期待されています。そのほか、子実用とうもろこし等の穀物等、輸入に代わる国産飼料の開発・普及等が期待されています。
また、肥料についても、国内には、畜産業由来の堆肥や下水汚泥資源があり、これらの有効活用が期待されるほか、化学肥料の使用量の低減や、国内で調達できない肥料原料の備蓄等の取組の重要性が高まっています。
このため、農林水産物・生産資材ともに、過度に輸入に依存する構造を改め、生産資材の国内代替転換や備蓄、輸入食品原材料の国産転換等を進め、耕地利用率や農地集積率等も向上させつつ、更なる食料安全保障の強化を図ることとしています。
(農業生産資材の国産化を推進)
農業生産資材について、例えば化学肥料原料は、大部分を輸入に依存しており、その安定供給に向けて肥料原料の備蓄等の重要性が増しています。一方、国内には、畜産業由来の堆肥や下水汚泥資源が存在しており、これらの国内資源の有効活用による化学肥料の使用低減は、環境への負荷低減にも資するなど、将来にわたって持続可能な生産への転換を実現するものとなります。そのほかにも、施設園芸等で使用する燃料や、電気等のエネルギーの使用でも同様のことが言えます。
また、飼料、特に牧草、稲わら等の粗飼料は、国内でもまだ生産余力がある中で、海外への依存を減らすことで、家畜の生産基盤を強靱(きょうじん)なものにするとともに、耕畜連携により、粗飼料の生産時に、家畜排せつ物を堆肥として土壌還元することで、環境にやさしい持続的な生産システムの確立を図ることができます。
こうしたことを踏まえ、肥料については、国内資源の肥料利用拡大への支援、土壌診断・堆肥の活用等による化学肥料の使用低減、肥料原料の備蓄に取り組むこととしています。
飼料については、耕種農家と畜産農家の連携への支援等、国産飼料の供給・利用拡大等を促進することとしています。
このほか、施設園芸や畜産・酪農によるヒートポンプの省エネルギー技術等の導入を支援することとしています。
(事例)下水汚泥資源から製造した肥料の活用を推進(佐賀県)


下水汚泥資源を高温発酵し肥料化
資料:佐賀市下水浄化センター

下水汚泥資源から製造した
肥料で育てられた農作物
資料:佐賀市下水浄化センター
佐賀県佐賀市(さがし)の佐賀市下水浄化センターでは、循環型社会を目指すため、バイオガス発電、CO2による藻類培養等、下水浄化の過程で生じる様々なものを資源やエネルギーとして最大限活用する取組を進めており、その一環として、下水汚泥資源から製造した肥料を平成23(2011)年から販売しています。
肥料の製造工程で特殊な微生物を混ぜ、90℃以上の高温発酵を45日間繰り返すことにより、雑草種子や病原菌が死滅するとされています。さらに30日間熟成させると、完熟した良質の肥料になります。
同センターは、NPO*法人等と連携して農業勉強会を定期的に開催して地域の農業者等とコミュニケーションを図っており、そこでの意見を取り入れて食品会社のアミノ酸を多く含む発酵副産物を添加するなど、様々な改良によって肥料の品質を向上させてきました。この肥料で育てた作物を「じゅんかん育ち」と命名して販売し、農産物の差別化や汚泥肥料の普及促進を行っています。
化学肥料の価格が上昇する中、低価格で提供される同センターの汚泥肥料は、循環型社会実現への貢献に加えて農業経営の一助となることも期待されています。
* Non Profit Organizationの略で、非営利団体のこと
(輸入原材料の国産転換や海外依存の高い農作物の生産拡大を推進)
これまでは、価格やロット等の面で利用しやすい輸入原材料が多く使用されていましたが、近年、世界的な食料需要の増加に伴う国際的な調達競争の激化等により、平時でも思うような条件で調達できない場合が出てきています。
一方、国内には、例えばパンや麺類等の米粉・小麦製品や、豆腐等の大豆加工品等、国産の活用・消費が見込まれるものがあります。
こうしたことを踏まえ、持続可能な食料供給の仕組みを構築するため、小麦・大豆等の国内生産の拡大や安定供給のための施設整備支援、水田の畑地化等を強力に推進するとともに、米粉の普及に向けた設備投資等を支援することとしています。また、食品製造事業者に対して、国産原材料への切替えを促すための対策を講ずることとしています。
(事例)国産小麦100%への切替えとともに、県産小麦の地域内流通を推進(埼玉県)


県産小麦をテーマとしたイベント
資料:前田食品株式会社

生産者と連携した麦づくり
資料:前田食品株式会社
埼玉県幸手市(さってし)の製粉企業である前田食品(まえだしょくひん)株式会社は、県産小麦を中心とした国産小麦による小麦粉等の生産・販売を展開しています。
同社では、小麦粉等の生産に当たり、従前は原料の約8割を国産小麦、残りの約2割を輸入小麦としていましたが、国産小麦の価値向上と自給率向上に貢献するため、平成30(2018)年から取り扱う小麦の全量を国産小麦に切り替えました。
また、同社が中心となって、「埼玉産小麦(さいたまさんこむぎ)ネットワーク」を設立し、小麦粉を利用する加工業者や生産者等、約160の会員と共に、農場見学や研修会等を通じて交流を深める取組や消費者向けイベント等を実施し、県産小麦のブランド価値の向上等に取り組んでいます。
同社は、今後も県産小麦の地域内流通を推進していくこととしており、県の農業試験場と協力して加工業者のニーズに即した新たな品種の共同研究に取り組むほか、社内に農産部門を設立し、生産者との連携を一層強化して、有機小麦も含め、安全でおいしい粉づくりを推進していくこととしています。
(農業生産資材等の価格高騰等の影響を緩和する対策を実施)
輸入原材料や農業生産資材の国際価格が高騰し、予断を許さない状況が続く中、すぐには最終商品の販売価格への転嫁ができるわけではないこと等から、価格高騰の影響を受ける農林漁業者に対し、その経営への影響を緩和するため、施設園芸等燃料価格高騰対策、肥料価格高騰対策、配合飼料価格高騰対策、公庫による資金繰り支援等の措置を講じています。
また、農業生産資材の価格高騰は生産者等の経営コストの増加に直結し、最終商品の販売価格に適切に転嫁できなければ、食料安定供給の基盤自体を弱体化させかねません。このため、国民各層の理解と支持の下、生産・流通経費等を価格に反映しやすくするための環境の整備を図ることとしています。さらに、全ての消費者が、いかなる時にも食料を物理的・社会的・経済的に入手できる環境が維持されることが重要ですが、食品価格の高騰は、これに支障を与えるおそれがあります。
こうしたことを踏まえ、食料・農林水産業に対する国民理解の醸成を図るとともに、食品ロス削減の取組の強化、こども食堂等へ食品の提供を行うフードバンクや、こども宅食による食育の取組に対する支援や共食の場の提供支援等を実施し、農林水産省を中心に関係省庁が連携して価格高騰下で日常的に食品へのアクセスがしづらくなっている者への対策を実施することとしています。
(地域農業を支え、雇用の受け皿となる担い手の経営発展を後押し)
少子高齢化、人口減少により、農業従事者の高齢化が進行し、今後一層の担い手の減少が見込まれる中、労働力不足等の生産基盤の脆弱(ぜいじゃく)化が深刻な課題となっています。令和4(2022)年の基幹的農業従事者数の年齢構成を見ると、50代以下は全体の約21%(25万2千人)となっており、今後10年から20年先を見据えると、基幹的農業従事者数が大幅に減少することが見込まれ、少ない経営体で農業生産を支えていかなければならない状況となっています(図表 特-27)。
こうした中、農業の生産現場では、農業経営体が、地域の信頼を得て、農地を引き受けながら徐々に経営拡大・高度化を図り、雇用の受け皿となるなど地域農業・農村社会の維持・発展に欠かせない存在となっているモデル的な事例が全国各地で出てきています。
人口減少・高齢化が更に進展する中、より少ない担い手が、農村社会を支える多様な経営体と連携して生産基盤を維持・強化していくためには、モデル的な農業経営体の創出を促進するとともに、こうした経営体をサポートしていく体制の構築が必要となっています。
(「地域計画」の策定や農地の集積・集約化を推進)
食料の安定的な供給については、安定的な輸入と適切な備蓄を組み合わせつつ、国内の農業生産の増大を図ることを基本とすることとしており、国内農業が様々な課題を抱えている中で、その力が衰退することなく将来にわたって発揮され、また、その力が増進していくように効率的に取り組んでいく必要があります。
そのためには、国内で農業を営むための基盤が確保されていることが不可欠であり、特に農地は、食料生産の基盤であり食料安全保障の根幹を成すものとして、将来にわたって持続的に確保する必要があります。
令和4(2022)年5月に成立した改正農業経営基盤強化促進法(*1)では、市街化区域を除き、基本構想を策定している市町村において、これまでの人・農地プランを土台とし、農業者等による話合いを踏まえて、農業の将来の在り方や目指すべき将来の農地利用の姿を明確化した目標地図を含めた「地域計画」を策定することとしています。
策定された地域計画を実現していくため、農地中間管理機構(農地バンク)を活用した農地の集積・集約化(*2)を推進していくこととしています。
食料安全保障上、国内での増産が求められる小麦、大豆、野菜、飼料等の生産に転換することが重要となっているところ、地域計画の策定に当たっては、地域でどのような農作物を生産するのかを含めて検討の上、需要に応じた生産を推進していくことが重要となっています。
*1 正式名称は「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律」
*2 用語の解説(1)を参照
(フォーカス)農地の集積・集約化等の進展に合わせて、農業構造面でも変化
担い手への農地集積は毎年着実に進んでおり、担い手の利用面積は農地全体の約6割となっていますが、農地の集積・集約化等の進展に合わせて、経営規模の拡大や大規模層における農業所得の向上といった農業構造面での変化も見られています。
農業経営体の経営耕地面積の規模を見ると、10ha未満の農業経営体が経営する面積が減少する一方で、10ha以上の経営体が経営する面積は令和4(2022)年に59.7%と増加傾向となっており、経営耕地面積の規模が拡大しています(図表1)。
また、経営耕地面積規模別の経営体数を見ると、10ha未満の層の経営体数は減少傾向で推移していますが、10ha以上の層の経営体数は増加傾向となっています(図表2)。
さらに、作付延べ面積規模別の1経営体当たりの農業所得を見ると、令和3(2021)年は、水田作、畑作いずれも作付延べ面積が大きくなるほど1経営体当たりの農業所得が増加傾向となっています(図表3)。
今後、農業の競争力強化を図っていくためには、担い手への農地の集積・集約化を加速化するとともに、IT、デジタル技術等を活用したスマート農業(*)の取組を促進するなどにより、生産性を一層向上させることが重要となっています。
* 用語の解説(1)を参照
(今後の食料安全保障の強化に向けて)
国際的な情勢の変化や食料供給の不安定化等により、我が国における食料安全保障上のリスクは高まっています。一方、我が国の人口減少は、農村部で先行して進展しており、農業従事者についても高齢化が著しく進展し、生産基盤が弱体化しています。また、人口減少と高齢化により、需要の減少が見込まれ、国内の食市場が急速に縮小しています。
世界的な食料情勢の変化に伴う食料安全保障上のリスクの高まり等により、我が国の食料・農業・農村を取り巻く情勢は大きく変化しており、国内の生産基盤を維持・強化し、将来にわたって食料を安定的に供給していく上で、ターニングポイントを迎えています。
こうした中、近年では、食料や農業生産資材の安定的な輸入に課題が生じており、食料の安定供給を実現するため、麦や大豆、飼料作物、加工・業務用野菜等の海外依存の高い品目や農業生産資材の国内生産の拡大等を効率的に進めるとともに、輸入の安定化や備蓄の有効活用等に取り組むことも必要となっています。
また、国民一人一人の食料安全保障の確立を図ることも重要です。食料を届ける力の減退が見られる中、全ての国民が健康的な食生活を送るための食品アクセスの改善に向けた取組を進めるとともに、適切な価格形成に向けたフードシステムの構築に向け、農業者等による適切なコスト把握等の経営管理と併せ、フードチェーンの各段階での事業者による取組や、消費者の理解を得ることも重要です。
さらに、農業従事者が大幅に減少することが予想される中で、今日よりも相当程度少ない農業経営体で国内の食料供給を担う必要が生じてきます。このため、農地の集積・集約化や農業経営の基盤強化、スマート農業、新品種の導入等によって、国民に対する食料供給の役割を担うとともに、経営的にも安定した農業経営体を育成し生産性の向上を図ることが必要です。
くわえて、気候変動や持続可能性に関する国際的な議論の高まりに対応しつつ、将来にわたって食料を安定的・持続的に供給できるよう、より環境負荷の低減に貢献する農業・食品産業への転換を目指す必要があります。
その上で、今後の食料安全保障の強化に向けては、不測の事態が発生した場合の対応の検討と、平時から食料安定供給に関するリスクの把握・対応を的確に行うとともに、我が国の農業・食品産業をリスクに強い構造へと転換し、食料安全保障の強化に向けた施策を着実に推進し、食料の安定供給の確保に万全を期していくことが求められています。
→第1章第2節、第2章第2節、第2章第4節、第2章第6節、第2章第7節、第2章第8節及び第2章第9節を参照
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883