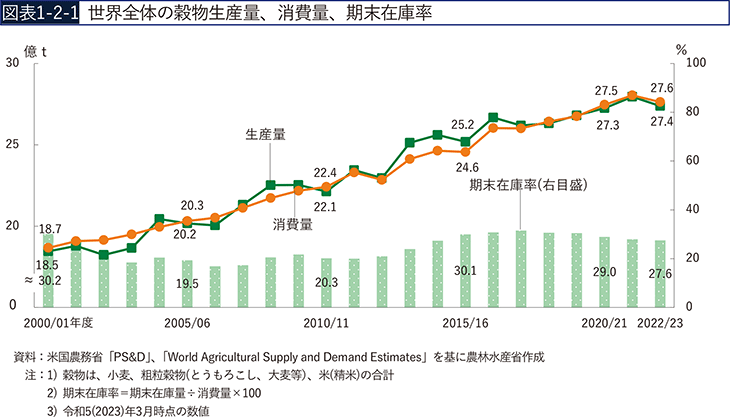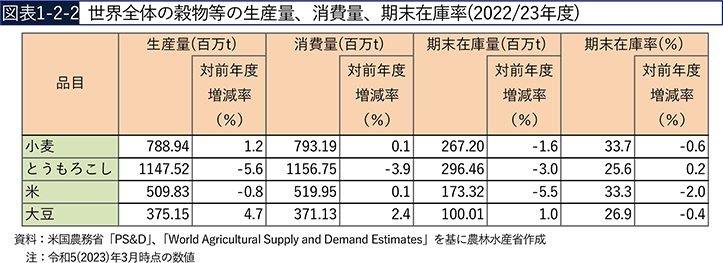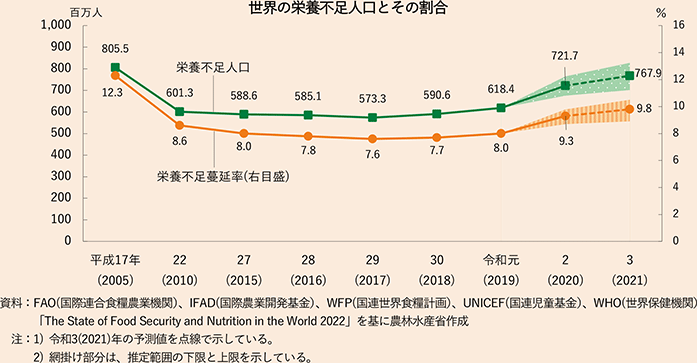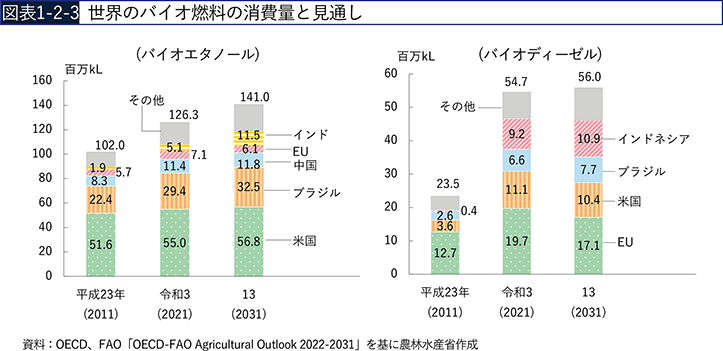第2節 食料供給のリスクを見据えた総合的な食料安全保障の確立
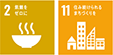
食料は人間の生活に不可欠であり、食料安全保障(*1)は、国民一人一人に関わる国全体の問題です。しかしながら、近年の世界的な人口増加等に伴う食料需要の拡大に加え、ロシアによるウクライナ侵略により、食料品や農業生産資材の価格が高騰するなど、我が国の食料をめぐる国内外の状況は刻々と変化しており、食料安全保障の強化への関心が一層高まっています。
本節では、国際的な食料需給の動向や不測時に備えた食料安全保障の取組等について紹介します。
1 用語の解説(1)を参照
(1)国際的な食料需給の動向
(2022/23年度における穀物の生産量、消費量は前年度に比べて減少)
令和5(2023)年3月に米国農務省(USDA)が発表した穀物等需給報告によると、2022/23年度における世界の穀物全体の生産量は、前年度に比べて0.6億t(2.0%)減少の27.4億tとなる見込みです(図表1-2-1)。
また、消費量は、開発途上国の人口増加、所得水準の向上等に伴い、増加していましたが、2022/23年度は前年度に比べて0.4億t(1.5%)減少の27.6億tとなる見込みです。
この結果、期末在庫量は前年度に比べて3.2%の減少となり、期末在庫率は27.6%と前年度(28.1%)を下回る見込みです。
2022/23年度における世界の穀物等の生産量を品目別に見ると、小麦は、ウクライナ、アルゼンチン等で減少するものの、ロシア、カナダ等で増加することから、前年度に比べて1.2%増加し7.9億tとなる見込みです(図表1-2-2)。
とうもろこしは、ブラジル、中国等で増加するものの、米国、EU、ウクライナ等で減少することから、前年度に比べて5.6%減少し11.5億tとなる見込みです。
米は、インド等で増加するものの、中国、パキスタン等で減少することから、前年度に比べて0.8%減少し5.1億tとなる見込みです。
大豆は、アルゼンチン、米国等で減少するものの、ブラジル、パラグアイ等で増加することから、前年度に比べて4.7%増加し3.8億tとなる見込みです。
期末在庫率については、小麦、米、大豆は前年度に比べて低下する一方、とうもろこしは前年度に比べて上昇する見込みです。
(中長期的には感染症の世界的流行等により世界の穀物等の需要の伸びは鈍化の見込み)
世界の人口は、令和4(2022)年においては80億人と推計されていますが、今後も開発途上国を中心に増加し、令和32(2050)年には97億人になると見通されています(*1)。
このような中、令和13(2031)年における世界の穀物等の需給について、需要面においては、アジア・アフリカ等の総人口が継続的に増加するものの、新型コロナウイルス感染症の世界的流行等の影響も受けて、中期的に多くの国で経済成長が鈍化し、所得水準の向上等に伴う途上国を中心とした食用・飼料用需要の増加がより緩やかになることから、需要の伸びはこれまでに比べて鈍化する見込みです。供給面においては、多くの穀物で収穫面積の伸びがやや低下する一方、単収の上昇によって需要の増加分を補う見込み(*2)です。
世界の食料需給は、農業生産が地域や年ごとに異なる自然条件の影響を強く受け、生産量が変動しやすいことや、世界全体の生産量に比べて貿易量が少なく、輸出国の動向に影響を受けやすいこと等から、不安定な要素を有しています。
また、気候変動や大規模自然災害、豚熱(ぶたねつ)(*3)等の動物疾病、新型コロナウイルス感染症等の流行、ロシアによるウクライナ侵略等、多様化するリスクを踏まえると、平素から食料の安定供給の確保に万全を期する必要があります。
1 国際連合「World Population Prospects 2022」
2 農林水産政策研究所「2031年における世界の食料需給見通し」(令和4(2022)年3月公表)
3 用語の解説(1)を参照
(コラム)世界的な食料安全保障の危機への懸念が高まり
私たちが毎日食べている食料は、生命を維持するために欠かすことができないものであり、健康で充実した生活を送るための基礎として重要なものです。
新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大の影響が長期化する中、令和3(2021)年から続く穀物や燃料、肥料等の価格の上昇に加え、令和4(2022)年2月に始まったロシアによるウクライナ侵略の影響を受け、これらの価格が更に高騰するなど、国際社会においても食料安全保障上の懸念が高まっています。
FAO(国際連合食糧農業機関)等の五つの国連機関が同年7月に公表した報告書によると、令和3(2021)年には、7億200万~8億2,800万人が飢餓の影響下にあると推計されており、前年から4,600万人増加しています。また、飢餓に直面する人々のうち、4億2,450万人がアジア、2億7,800万人がアフリカ、5,650万人がラテンアメリカ・カリブ地域となっています。
SDGs(持続可能な開発目標)(*)の目標として掲げられた「飢餓の終焉(しゅうえん)、食料安全保障と栄養改善の実現、持続可能な農業の促進」を令和12(2030)年までに達成するためには、更なる努力が不可欠な状況です。
用語の解説(2)を参照
(世界のバイオ燃料用農産物の需要は増加の見通し)
近年、米国、EU等の国・地域において、化石燃料への依存の改善や温室効果ガス(*1)排出量の削減、農業・農村開発等の目的から、バイオ燃料の導入・普及が進展しており、とうもろこしやさとうきび、なたね等のバイオ燃料用に供される農産物の需要が増大しています。
令和4(2022)年6月にOECD(経済協力開発機構)とFAOが公表した予測によれば、令和3(2021)年から令和13(2031)年までに、バイオエタノールの消費量は約1億2,600万kLから約1億4,100万kLへ、バイオディーゼルの消費量は約5,500万kLから約5,600万kLへとそれぞれ増加する見通しとなっています(図表1-2-3)。
1 用語の解説(1)を参照
(2)不測時に備えた平素からの取組
(緊急事態食料安全保障指針に基づくシミュレーション演習を実施)
農林水産省では、不測の要因により食料供給に影響が及ぶ可能性のある事態に的確に対処するため、緊急事態食料安全保障指針(*1)を定めています。また、平素から、不測の事態を具体的に想定した上で、同指針に基づく対応やその実施手順の実効性の検証を行うため、シミュレーション演習を行っています。令和4(2022)年度は、ウクライナ情勢等を踏まえた新たなリスクに対応するため、これまで実施してきた食料の供給減少を想定したシナリオに加え、農業生産資材(肥料、農薬、種子・種苗)の供給減少を想定したシナリオに基づいて実施しました。
また、輸入食料の安定的確保に向け、国際協調を通じた輸出規制措置の透明性向上と規律の明確化を推進するとともに、諸外国等との情報交換や国際機関との協力を通じた国際的な食料需給状況、資材の流通状況の分析の強化を推進しました。
さらに、政府は国内の米の生産量の減少によりその供給が不足する事態に備え、政府米を100万t程度(*2)備蓄しています。あわせて、海外における不測の事態の発生による供給途絶等に備えるため、食糧用小麦については国全体として外国産食糧用小麦の需要量の2.3か月分を、飼料穀物についてはとうもろこし等100万t程度をそれぞれ民間で備蓄しています。

食料安全保障について
URL:https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/anpo/index.html
1 平成24(2012)年に策定した、不測の要因により食料供給に影響が及ぶおそれのある事態に的確に対処するため、政府として講ずべき対策の内容等を示した指針
2 10年に1度の不作や、通常程度の不作が2年連続した事態にも国産米をもって対処し得る水準
(3)国際協力の推進
(ウクライナへの食料・農業分野での支援を実施)

ポーランド日本大使公邸にて行われ
たウクライナへの支援物資の引渡式
農林水産省を始めとする関係省庁では、ウクライナ政府からの要請及びG7臨時農業大臣会合でのウクライナ支援に係る各国間の合意も踏まえ、食料品等の支援物資をウクライナ政府に提供しました。支援物資としては、パックご飯、魚の缶詰、全粉乳、缶詰パンの合計15tに加え、在日ウクライナ大使館に寄贈された医薬品等が併せて輸送されました。
また、ウクライナ国内の農業生産の回復のための種子の配布や、同国の穀物輸出を促進する観点からの穀物貯蔵能力の拡大やルーマニア国境に面した検疫所の能力構築支援等を、FAO等の国際機関を通じて実施しました。また、WFPとの連携により、ウクライナ政府から無償で提供された同国産小麦をソマリアに供与する事業を実施しました。
さらに、令和4(2022)年6月に開催された第12回WTO(*1)(世界貿易機関)閣僚会議(*2)では、農業、食料安全保障等について議論され、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によるサプライチェーンの混乱やロシアによるウクライナ侵略を背景に、食料安全保障が脅かされる中、食料安全保障宣言及びWFP決定が合意されました。
1 用語の解説(2)を参照
2 第1章第9節を参照
(アフリカへの農業協力を推進)
農業は、アフリカにおいて最大の雇用を擁する産業である一方、人口の急激な増加等に起因して食料の輸入依存度が高い国が多くなっており、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化やウクライナ情勢等により、その脆弱(ぜいじゃく)性が露呈しました。アフリカ各国が食料安全保障を強化し、経済発展を達成するためには、各国の農業生産の増加や所得の向上が不可欠となっています。このため、我が国は、アフリカに対して農業生産性の向上や持続可能な食料システム構築等の様々な支援を通じ、アフリカ農業の発展への貢献を行っています。
これに加え、近年、気候変動の議論において、農業に起因する森林伐採や過放牧等の環境負荷が課題となっており、環境に調和した農業の確立が求められています。
令和4(2022)年8月にチュニジアで開催された第8回アフリカ開発会議(TICAD8)において採択された「チュニス宣言」においても食料安全保障の確保が重視され、我が国は、アフリカ開発銀行との協調融資で3億ドルの食料生産支援や20万人の農業人材育成を行うことを発表しました。
今後ともアフリカ各国や関連する国際機関等との連携を図りつつ、農業分野の課題解決に取り組むこととしています。また、各国の投資環境や消費者のニーズを捉え、我が国の食産業の海外展開や農林水産物・食品輸出に取り組む企業を支援していくこととしています。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883