第1節 食料・農業・農村基本法見直しの経緯
(1)食料・農業・農村基本法見直しの経緯
(現行基本法制定後、食料・農業・農村を取り巻く情勢が変化)
現行基本法の制定から四半世紀が経過する中、途上国を中心として世界人口は急増し、食料需要も増加する一方、気候変動による異常気象の頻発化や、地政学的リスクの高まり等により、世界の食料生産・供給は不安定化しています(図表 特1-1)。
また、我が国では、長期にわたるデフレ経済下で経済成長が鈍化したのに対して、中国やインド等の新興国の経済は急成長した結果、世界における我が国の相対的な経済的地位は低下し、必要な食料や農業生産資材を容易に輸入できる状況ではなくなりつつあります。
国内農業に目を向けると、農業者の減少・高齢化や農村におけるコミュニティの衰退が懸念される状況が続く中、平成21(2009)年には、総人口も減少傾向に転じ、国内市場の縮小は避け難い課題となっています。
くわえて、SDGs(*1)(持続可能な開発目標)の取組・意識が世界的に広く浸透し、自然資本や環境に立脚した農業・食品産業に対しても、環境や生物多様性等への配慮・対応が社会的に求められ、持続可能性は農業・食品産業の発展や新たな成長のための重要課題として認識されるに至っています。

*1 Sustainable Development Goalsの略
(食料・農業・農村政策審議会において答申を取りまとめ)
我が国の食料安全保障にも関わる大きな情勢の変化や課題が顕在化したことを踏まえ、令和4(2022)年9月に農林水産大臣から食料・農業・農村政策審議会に諮問が行われました。これを受けて同審議会の下に学識経験者や生産者、食関連事業者、関係団体等の様々な分野の委員から成る基本法検証部会が設置され、計17回(*1)にわたって有識者へのヒアリングや施策の検証等の活発な議論が行われました。
令和5(2023)年5月には、中間とりまとめが公表され、全国11ブロックで地方意見交換会を実施するとともに、Webサイト等を通じた国民からの意見募集を行い、広く国民の声を聴きながら検討が進められ、同年9月に答申が取りまとめられました。
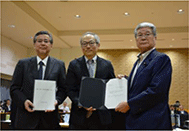
食料・農業・農村政策審議会会長、
基本法検証部会長から答申を
受け取る農林水産大臣
*1 令和6(2024)年3月に、第18回基本法検証部会が開催され、食料・農業・農村基本法改正法案等についての報告が行われた。
(コラム)地方意見交換会を実施するとともに、国民から意見・要望を募集
食料・農業・農村基本法の検証・見直しに関して、全国11ブロックにおいて地方意見交換会を実施するとともに、Webサイトを通じた国民からの意見・要望の募集が実施されました。
地方意見交換会においては、主に、(1)適正な価格形成に向けた食料システム全体での仕組みの構築、食育等を通じた国民の理解醸成、(2)物流の効率化等による食品アクセスの改善、(3)人口減少下における農地・農業インフラの維持等が必要ではないかといった意見が出されました。
また、Webサイトを通じた国民からの意見・要望の募集においては、提出された意見・要望の総計は1,179件でした。その内訳を見ると、「全般」が306件で最も多く、「農業分野」(295件)、「食料・農業・農村基本計画等」(171件)の順となりました。また、寄せられた意見・要望のキーワードを見ると、「種子関係」が540件で最も多く、次いで「肥料関係」(107件)、「食料自給率関係」(107件)、「生物多様性関係」(106件)、「価格関係」(105件)、「有機農業関係」(99件)の順となりました。
このような結果を踏まえ、食料・農業・農村政策審議会の答申が取りまとめられました。

北海道帯広市での地方意見交換会

石川県金沢市での地方意見交換会
(2)食料・農業・農村基本法の制定の経緯
(平成11(1999)年に現行基本法を制定)
現行基本法は、農業基本法(以下「旧基本法」という。)が制定された昭和36(1961)年から30年以上が経過する中で、旧基本法の掲げる政策目標と実勢の乖離(かいり)、国際的な農産物貿易の自由化の進展、農業・農村に対する国民の期待の高まり等を背景として、農業の発展と農業者の地位向上を目的とした旧基本法に代わり、国民から求められる農業・農村の役割を明確化し、その役割を果たすための農政の方向性を示すものとして平成11(1999)年に制定されました。
(フォーカス)農業基本法制下の農政の大きな流れ
農業基本法は、農業の近代化・合理化により、農業と他産業の間の生産性や従事者の所得の格差を縮小させることを目的としていました。その後、我が国の経済が想像を超える成長を見せる中、農業と他産業の生産性には依然として大きな格差が残りました。農村では、農業から他産業への労働力の流出が急増しましたが、機械化の進展や農地の資産的価値の高まり等を背景に、農村に残る農業者の多くが兼業化し、農業構造の改善や自立経営の育成は進みませんでした。
一方で、兼業収入の増加により農業者と他産業従事者との所得格差が解消する方向にあったものの、農村から都市へ、特に若年層の労働力が流出したことにより、社会減による農村人口の減少や高齢化等の問題が顕在化し、農業生産活動の停滞や農村活力の低下等の懸念が高まりました。
また、農業基本法は、価格政策により農業者の所得確保を図ることとしていましたが、輸入農産物との関係においては、価格政策だけでは競争力をカバーできない場合には、関税や輸入割当等の措置を講じることとし、バランスを保つこととしていました。その後、国際的な農産物貿易の自由化が進展する中で、価格支持等の貿易歪曲(わいきょく)的な国内助成の見直しを行いつつ、輸入農産物との直接的な競争にも耐え得る農業経営や農業構造の確立が求められることとなりました。
このような当時の経済情勢において、非効率な農業から国際的な競争力のある産業へ転換していくべきとの意見もあった一方で、国民がゆとり、安らぎ、心の豊かさを従来以上に意識するように変わっていく中で、食料の安定的な供給や多面的機能の発揮を担うものとして農業・農村に対する国民の期待が高まっていました。
これらを踏まえ、「農業」に加え、「食料」、「農村」という視点から施策を構築するとともに、効率的・安定的な経営体の育成や市場原理の一層の導入を基本的課題とする「新しい食料・農業・農村政策の方向」を平成4(1992)年に取りまとめ、平成11(1999)年には食料・農業・農村基本法に基づく農政を展開することとしました。

(3)食料・農業・農村基本法の基本理念
(四つの基本理念を位置付け)
現行基本法はその制定に際し、食料・農業・農村に関する施策について、基本理念及びその実現を図る上で基本となる事項を定めるとともに、国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、食料・農業・農村に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図ることを目的としました。
また、現行基本法は、国民全体の視点から農業・農村に期待される役割として「食料の安定供給の確保」と「多面的機能の十分な発揮」があることを明確化しつつ、その役割を果たすために「農業の持続的な発展」と「農村の振興」が必要であることを基本理念として位置付けました(図表 特1-2)。

(国の政策の第一の理念として「食料の安定供給の確保」を位置付け)
平成10(1998)年には世界の人口は60億人に達し、将来的には、急増する世界人口に応じた食料を確保していくことについて不安視されていました。世界の食料需給と貿易に不安があることから、国の政策の第一の理念として、将来にわたって良質な食料を合理的な価格で供給することを掲げました。また、食料の供給については、国内の農業生産の増大を図ることを基本としつつも、全ての食料供給を国内の農業生産で賄うことは現実に困難であることから、輸入及び備蓄を適切に組み合わせて行わなければならないと明記しました。
さらに、「消費のないところに生産はない」との考えの下、食料の価格を市場メカニズムに委ねることとしました。これにより、需給や品質評価を適切に反映して価格が形成され、価格がシグナルとなってそれらが生産現場に伝達されることを通じて需要に即した農業生産が行われ、国内農業生産の増大とこれを基本とした食料安定供給が可能となることが期待されていました。
また、当時の経済状況では、総量として必要な食料を確保できれば、それを国民に供給していくことについては、民間の事業者が自立的に行うことができ、国民も経済的に豊かで、必要な食料を入手できる購買力があるとの前提の下で、平時においては、食料の安定供給さえ確保されれば食料の安全保障は確保できるとの考えに立脚していました。一方、国際貿易が極度に制限されるような不測の事態が発生した場合には、食料供給にも支障が生じ、国内でどう分配するのか、不足分をどう調達するのかについて、生産、流通、販売全体にわたる取組が必要になることから、不測時における食料安全保障との限定的な意味合いで食料安全保障という用語が用いられました。
(外部経済効果として「多面的機能の十分な発揮」を位置付け)
農村において継続的に農業が営まれることにより、その外部経済効果として、国土の保全、水源の涵養(かんよう)、自然環境の保全等の機能があることを明確にし、このような食料等の供給機能以外の多面にわたる機能である「多面的機能」の十分な発揮を位置付けました。これにより、国内農業生産やそれを支える農村の重要性を位置付け、国内で農業生産を維持することの必要性を説明することが狙いとされていました。
(国民の視点に立ち、「農業の持続的な発展」を位置付け)
旧基本法においては、農業・農業者に関して、他産業との間の生産性や所得水準の格差を縮小させるという、農業・農業者の視点に立った政策目標を掲げていましたが、現行基本法では、食料の安定供給の確保と多面的機能の十分な発揮という基本理念を実現するためには、農業の持続的な発展が必要という「国民の視点」に立った農業の意義付けに変更しました。
農業の持続的な発展を図るためには、効率的な生産により高い生産性と収益性を確保し、所得を長期にわたって継続的に確保できる経営体が、農業生産の相当部分を担う「望ましい農業構造」を実現することが重要であるとの考えの下、このような経営体を「効率的かつ安定的な経営」と定義し、育成すべき対象と位置付けました。また、そのような望ましい農業構造の実現に向けて、生産基盤整備の推進や農業経営の規模拡大等を進めていくこととしました。
(基盤たる役割を踏まえ、「農村の振興」を位置付け)
農村は、農業が持続的に発展し、食料を安定的に供給する機能や多面的機能が適切に発揮されるための基盤たる役割を果たしていることを踏まえ、その振興が図られなければならないとしました。
当時、我が国の経済発展に伴い、農村から都市への人口流出が進むとともに、高齢化が進行し、将来的に農村が農業生産や農業者の生活の場としての機能を果たすことができなくなることが懸念されていたことから、農業の生産条件の整備や生活環境の整備によって、その振興を図ることが謳(うた)われました。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883





