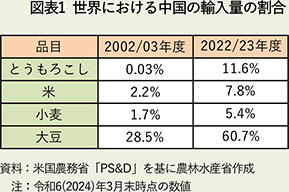第2節 食料・農業・農村基本法制定後の情勢の変化と今後20年を見据えた課題
(1)食料・農業・農村基本法が前提としていた状況の変化と新たな課題
(現行基本法制定以降、食料・農業・農村をめぐる内外の情勢は大きく変化)
現行基本法制定以降、食料・農業・農村をめぐる内外の情勢は大きく変化しました。その中には、政策の前提となる情勢が大きく変化したものや、政策の目的は変わらないものの目的の遂行についての考え方や実現手法が変化したもの等が見られ、その態様は多岐にわたっています。
特に令和4(2022)年2月に始まったロシアによるウクライナ侵略等により、世界の食料生産・供給は不安定化しており、食料安全保障をめぐる情勢は大きく変化しています。
また、現行基本法制定後、環境保全や持続可能性をめぐる国際的な議論は大きく進展し、農業や食品産業と持続可能性との考え方も大きく変化しています。
現行基本法の基本理念が前提としていた状況が大きく変わりつつあり、新たな課題も生じています。
(2)平時における食料安全保障リスク
(世界情勢の変化により食料安全保障に係る地政学的リスクが高まり)

ウクライナ情勢をめぐり開催された
G7首脳会合(令和4(2022)年3月)
資料:首相官邸ホームページ
URL:https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/actions/
202203/24g7.html(外部リンク)
近年、新型コロナウイルス感染症のまん延、エネルギー価格の高騰、気候変動、紛争等による複合的リスクが顕在化しています。そのような中、ロシアによるウクライナ侵略等により、黒海(こっかい)経由の穀物輸出の停滞、国際的な小麦相場や肥料原料価格の高騰といった世界の食料供給を一層不安定化させる事態が発生し、これを契機として、地政学的リスクの高まりが世界の食料供給や国内外の物流に大きな影響を及ぼすことが改めて認識されました。
地政学的な情勢の不安定化は、輸入依存度の高い我が国の食料供給に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
(食料安全保障に関する国際的な議論が進展)
FAO(*1)(国際連合食糧農業機関)は、世界規模で食料問題に関する議論が行われた平成8(1996)年の世界食料サミットにおいて、食料安全保障について「全ての人が、いかなる時にも、活動的で健康的な生活に必要な食生活上のニーズと嗜好(しこう)を満たすために、十分で安全かつ栄養ある食料を、物理的にも社会的にも経済的にも入手可能である」ことと定義しました(図表 特2-1)。
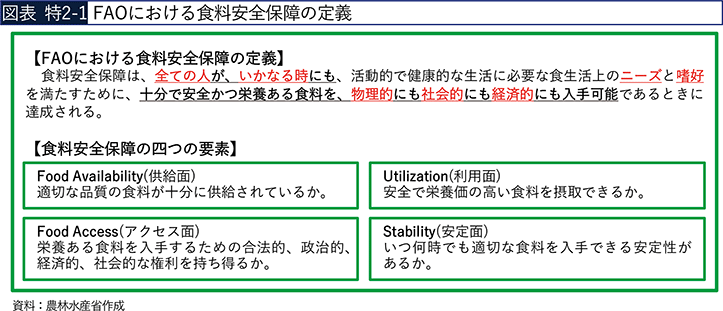
*1 Food and Agriculture Organization of the United Nationsの略
(経済的理由により十分な食料を入手できない人が増加)

厚生労働省の調査によると、所得金額階級別世帯数の相対度数分布について、平成9(1997)年と令和3(2021)年を比較すると、高所得世帯の減少のほか、200万円未満の世帯割合の増加が見られています(図表 特2-2)。このような状況の下、経済的理由により十分な食料を入手できない人が増加していることがうかがわれます。
(食料を届ける力が減退)
農林水産物・食品の流通は約97%をトラック輸送に依存していますが、トラックドライバー不足が深刻化しています。このまま推移すると、令和12(2030)年には、トラックを含む自動車運転者の時間外労働の上限規制が適用される、いわゆる「物流の2024年問題(*1)」の影響と併せて輸送能力の約3割が不足する可能性もあるとの推計があり、食品流通に支障が生じる懸念が高まっています。
また、国内市場の縮小の影響は、特に過疎地で顕在化・深刻化しています。都市部と比べて生活環境の整備等が立ち遅れている中山間地等で人口減少・高齢化が先行して進むことから、小売業や物流等の採算が合わなくなり、スーパーマーケット等の閉店が進むこととなりました。この結果、高齢者等を中心に食品の購入や飲食に不便や苦労を感じる人、いわゆる「買い物困難者(*2)」が増加しています。令和6(2024)年2月に農林水産政策研究所が公表した調査によると、令和2(2020)年の食料品アクセス困難人口は全国で904万3千人と推計され、平成27(2015)年と比べ9.7%増加しました(図表 特2-3)。食品アクセス(*3)の問題は、当初は中山間地等の問題として認識されていましたが、今日では都市部でも発生し、全国的な問題となっています。
*1 トピックス2を参照
*2、3 第1章第4節を参照
(平時における食料安全保障リスクに対応する必要)
我が国では、1990年代以降、非正規雇用の増加等により、低所得者層が増加しつつあり、経済的理由により十分かつ健康的な食事がとれない人等に食品を提供するフードバンクの取組が広がりを見せています。一方、我が国のフードバンクは、米国等と比べても歴史が浅く、食品の提供機能の拡大に向けた組織基盤の強化が課題となっています。
また、産地から消費地まで農産物・食品を輸送する幹線物流の持続性確保が課題となっているほか、買い物困難者の増加等が課題となっています。
このように、平時において食品アクセスに困難を抱える国民が増加傾向にある中、平時から食料を確保し、全ての国民が入手できるようにするため、関係省庁・地方公共団体等が連携して対応する必要があります。
(3)食料安定供給に係る輸入リスク
(新興国や途上国を中心に世界人口が増加)
平成11(1999)年当時に約60億人であった世界人口は、平成22(2010)年には約69億人、令和5(2023)年には80億1千万人、令和32(2050)年には約97億人になると推計されています(図表 特2-4)。
一方、平成22(2010)年に21億3千万tであった穀物生産量は、令和32(2050)年には36億4千万tになると推計されています。人口増加に対応し、世界の穀物生産量も増加していますが、自然条件に左右される農業の特性上、豊凶による生産量の変動によって、豊作時には膨大な在庫を抱え、不作時には価格が急騰する状況が繰り返されています。
また、令和4(2022)年2月に始まったロシアによるウクライナ侵略は、小麦等の主要生産国であるウクライナの輸出量の減少を招き、小麦の国際価格は同年3月に過去最高値となりました。これらの不安定さは、経済的に豊かな先進国・新興国、貧しい途上国の配分の問題を背景に、途上国の飢餓を始め、世界的な食料安全保障に大きな影響を及ぼしています。
(気候変動による異常気象の頻発に起因し、食料生産が不安定化)
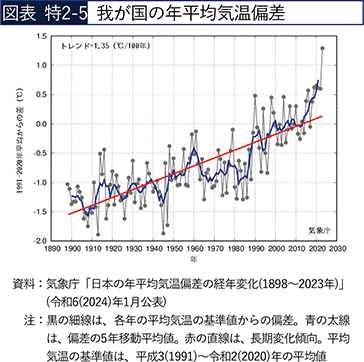
地球温暖化の影響により、高温、干ばつ、大規模な洪水等の異常気象が頻発し、2000年代に入ってからは、毎年のように世界各地で局所的な不作が発生しています。
このような要因もあいまって、世界的な食料生産の不安定化が助長されており、穀物価格の高騰と暴落が繰り返されるようになっています。
食料や農業生産資材を輸入に依存している我が国では、中長期的に見て安定的な調達が困難になるリスクが高まるといった影響が顕在化しています。
例えば我が国の年平均気温は、過去100年当たりで1.35℃の割合で上昇しています(図表 特2-5)。農林水産業は気候変動の影響を受けやすく、高温による品質低下等が既に発生しています。
(輸入国としての影響力が低下)
我が国では約30年にわたるデフレ経済下で経済成長が著しく鈍化したのに対し、世界的には中国やインド等の新興国の経済が急成長しました。その結果、令和2(2020)年時点で、我が国のGDP(国内総生産)は世界第3位を維持していますが、1人当たりGDPでは世界第13位(*1)まで低下しており、今後我が国の経済的地位は更に低下することが予想されています。また、新興国等においては、食料のほか、肥料等の農業生産資材の需要が増加しているため、それらの輸入量も急増しています。
*1 人口1千万人以上でGDP上位60か国・地域を対象とした場合の順位
(フォーカス)世界の穀物在庫量における中国の割合は突出して高い水準
令和6(2024)年3月末時点での米国農務省の推計によると、2023/24年度における中国の穀物等の輸入量の見通しは、とうもろこしが2,300万t、米が210万t、小麦が1,100万t、大豆が1億500万tとなっており、いずれの品目においても世界有数の輸入国となっています。
世界における中国の輸入量の割合(前後3か年平均)の変化を見ると、とうもろこし、米、小麦、大豆については、2002/03年度と比べて2022/23年度はいずれの品目においても上昇しています(図表1)。
また、2022/23年度末時点における世界の穀物在庫に占める中国の割合を見ると、とうもろこし68.3%、米60.2%、小麦51.2%、大豆31.7%となっており、突出して高い水準となっています(図表2)。
一方、我が国では長期にわたるデフレ経済下で経済成長が鈍化し、世界における輸入国としての地位は低下しています。近年では、中国が最大の純輸入国となっており、このような情勢の中で調達競争が激化し、いわゆる「買い負け」の懸念も生じています。
世界の穀物消費量が増加傾向で推移する中、今後とも中国の穀物需給の動向を注視していく必要があります。
このような状況の中、世界最大の農林水産物純輸入国は、平成10(1998)年には日本(シェア40%)でしたが、令和3(2021)年には中国(シェア29%)となっており、中国が食料貿易のプライスメーカーとなっています(図表 特2-6)。
我が国が輸入に大きく依存している穀物、油糧種子、肥料や飼料等の農業生産資材の調達競争が激化しており、世界中から必要な食料や農業生産資材を思うような条件で調達できない状況となってきています。
(食料安定供給に係る輸入リスクに対応する必要)
世界的な食料需要が高まる一方、異常気象等による不作が頻発し、中国のような経済力のある食料の輸入大国が新たに現れる状況において、輸入価格は上昇し、安定的な輸入にも懸念が生じています。
このため、輸入に依存する食料や農業生産資材においては、国内生産の拡大に一層取り組むとともに、輸入の安定化や備蓄の有効活用等にも取り組む必要があります。
(4)合理的な価格の形成と需要に応じた生産
(価格形成機能の問題が顕在化)
GDPデフレータは、平成10(1998)年以降、各国で上昇していますが、我が国では2000年代に低下し続けるなど、平成10(1998)年を下回る水準で推移しており、デフレ下に置かれています(図表 特2-7)。
約30年にわたるデフレ経済下で、国内の農産物・食品価格はほとんど上昇しないまま推移してきました。消費者も低価格の食料を求めるようになる中で、安売り競争が常態化し、サプライチェーン(*1)全体を通じて食品価格を上げることを敬遠する意識が醸成・固定化されました。生産コストが増加しても価格を上げることができない問題が深刻化し、農産物や生産資材の価格が急騰した際にも製品価格に速やかに反映できず、事業継続にも関わる事態が生じています。
*1 第1章第3節を参照
(合理的な価格の形成に向けた取組や需要に応じた生産を推進する必要)
主要な農畜産物の需要量(国内消費仕向量)は、平成14(2002)年度以降の約20年間で、高齢化による総カロリー摂取の減少はあるものの、増加している肉類を除いておおむね横ばい又は減少傾向で推移しています(図表 特2-8)。
我が国では、他品目に比べ農外収入が大きく兼業主体の生産構造や他作物への転換が進まなかった稲作を始め、生産サイドにおいては、その需要に合わせた対応が必ずしもできていません。このため、農産物市場の動向だけでは農業者の経営が変更される状況に至っていないことがうかがわれます。
また、長期にわたるデフレ経済下で、価格の安さによって競争する食品販売が普遍化し、その結果、価格形成において生産コストが十分考慮されず、また、生産コストが上昇しても販売価格に速やかに反映することが難しい状況を生み出しています。
このため、合理的な価格の形成が行われるような仕組みの構築を検討するとともに、需要に応じた生産を政策として推進することが求められています。
(5)農業・食品産業における国際的な持続可能性の議論
(環境に配慮した持続可能な農業を主流化する政策の導入が進展)
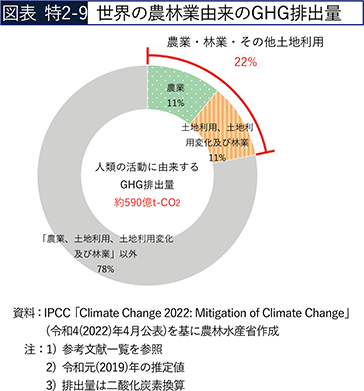
地球環境の保全や貧困問題の解消といった持続的な社会・経済の形成に向けた国際的な議論が進み、そのような議論の動向が農業や食品産業の在り方にも大きな影響を及ぼすようになっています。特に世界の農業・林業・その他土地利用由来の温室効果ガス(GHG(*1))排出量については、令和元(2019)年は排出量全体の22%を占めることから、温室効果ガスの排出削減や土壌・水資源の保全等が求められています(図表 特2-9)。
また、農業が環境に負の影響を与え、持続可能性を損なう側面があることへの関心が高まる中で、食料供給が地力の維持や自然景観の保全等の生態系サービスに与える悪影響を最小化していくことが重要という考え方が国際的に浸透しています(図表 特2-10)。
このような中、農業生産活動においても、環境への負荷を最小限にする取組が求められるようになり、各国・地域において持続可能な農業を主流化する政策の導入が進みました。
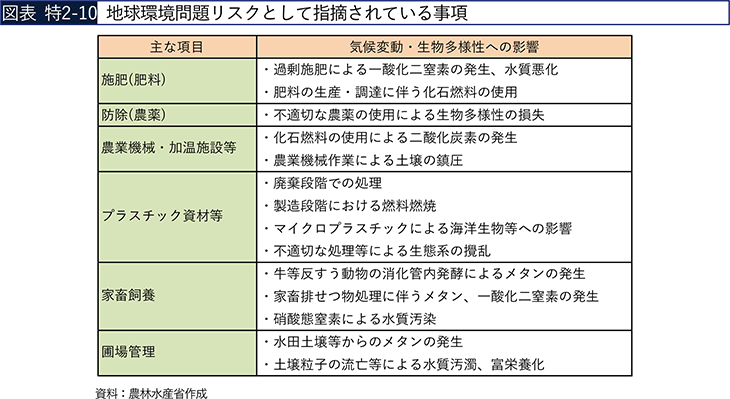
農林水産省では、食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現させるため、令和3(2021)年5月に「みどりの食料システム戦略」(以下「みどり戦略」という。)を策定し、中長期的な観点から、調達、生産、加工・流通、消費の各段階での取組を推進しています(図表 特2-11)。さらに、令和4(2022)年には、みどりの食料システム法(*2)が制定され、農業の環境負荷低減を図る取組が進められています。
くわえて、食品産業も、環境や人権に配慮して生産された原材料の使用や食品ロスの削減といった持続性の確保に向けた取組が求められるようになりました。ビジネスにおいても持続可能性を確保する取組が企業評価やESG(*3)投資等を行う上での重要な判断基準となりつつあります。
今後、国内外の市場において環境や人権等の持続性に配慮していない農産物・食品は消費者・事業者に選ばれにくくなる可能性があること、持続性に配慮していない食品産業等は資金調達がしにくくなる可能性があること、諸外国・地域の規制・政策が持続可能性により重点を置くものに移行することが想定されることを踏まえ、我が国としても、慣行的な農業・食品産業で十分とせず、環境等に配慮した持続可能な農業・食品産業を主流化していく必要があります。

みどりの食料システム戦略
URL:https://www.maff.go.jp/j/kanbo/
kankyo/seisaku/midori/index.html
あわせて、温室効果ガスの吸収や生物多様性の保全といった農業分野が有する効果についても評価をしながら、民間投資の呼び込みにつなげる必要があります。
これらの持続可能な農業・食品産業に向けた取組を進めていく上では、消費者・事業者の理解と行動変容が不可欠となっています。
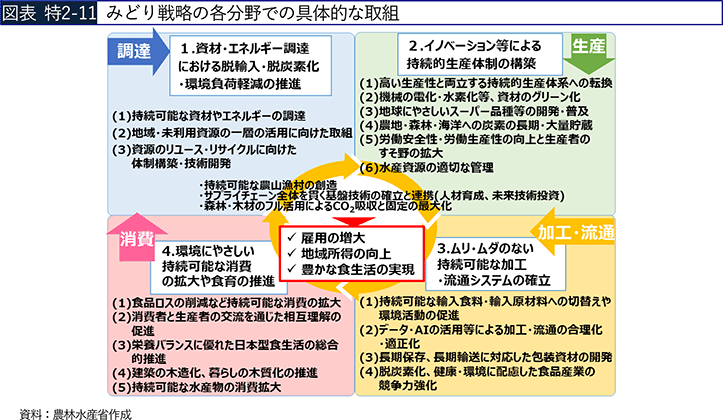
*1 Greenhouse Gasの略
*2 正式名称は「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」
*3 Environment(環境)、Social(社会)、Governance(ガバナンス(企業統治))を考慮した投資活動や経営・事業活動のこと
(6)海外も視野に入れた市場開拓・生産
(人口減少・高齢化に伴い国内市場が縮小)
我が国の人口は平成20(2008)年をピークに減少に転じており、今後とも人口減少や高齢化により、食料の総需要と1人当たり需要の両方が減少することが見込まれ、国内の食市場が急速に縮小していくことが避けられない状況となっています。また、少子化や高齢化の進展により単身世帯が増えることも見込まれており、家庭で直接又は調理を経て消費される生鮮食品から調理済み等の加工食品に需要がシフトすることが予想されています(図表 特2-12)。総世帯の1人当たり食料消費支出における生鮮食品の割合は、平成27(2015)年の27.4%から令和22(2040)年には21.0%にまで縮小することが見込まれています。
我が国の農業は、これまで主として国内市場への供給を想定し、また、生鮮品を生産・販売する志向が強い傾向にありました。このため、これまでの国内需要を想定した農業・食品生産を続けていく場合、農業の経済規模も急速に縮小していくおそれがあります。
(国際的な食市場が拡大)
世界人口の増加に伴い、国際的な食市場は拡大傾向にあり、主要国・地域の飲食料マーケット規模は平成27(2015)年から令和12(2030)年にかけて1.5倍になると予測されています(図表 特2-13)。特にアジア地域は、世界の経済発展の中心地であり、高所得者層の増加等により、日本食が受け入れられ、我が国の農産物や加工食品の需要も高まりつつあります。令和3(2021)年には我が国の農林水産物・食品の輸出額が初めて1兆円を超え、更なる拡大の余地が見込まれています。
(海外も視野に入れた市場開拓・生産を推進する必要)
人口減少とともに国内市場の縮小が避けられない状況において、国内市場のみを指向し続けることは、農業・食品産業の成長の阻害要因となるおそれがあります。
一方、輸出は堅調に増加していることから、今後、国内需要に応じた生産に加え、輸出向けの生産を増加させていくことは、農業・食品産業の持続的な成長を確保し、農業の生産基盤を維持していく上で極めて重要です。
持続的な成長とリスク分散、農業の生産基盤の維持の観点から、国内市場だけでなく海外市場も視野に入れた農業・食品産業への転換を推進していく必要があります。
(7)人口減少下においても食料の安定供給を担う農業経営体の育成・確保
(農業者の急減と経営規模の拡大が進行)
我が国の人口減少は、農村で先行し、農業者の減少・高齢化が著しく進展しています。基幹的農業従事者(*1)数は、平成12(2000)年の約240万人から令和5(2023)年には約116万人と半減し、その年齢構成のピークは70歳以上層となっています。20年後の基幹的農業従事者の中心となることが想定される60歳未満層は、全体の約2割の24万人程度にとどまっています(図表 特2-14)。
このような急激な農業者の減少の中で、農地等を引き受けてきたのは比較的規模の大きい農業経営体であり、その結果、平成17(2005)年から令和2(2020)年にかけて、経営耕地面積20ha以上の農業経営体は約37%、農産物販売金額5千万円以上の農業経営体は約42%増加しています。1経営体当たりの経営耕地面積・農産物販売金額の拡大傾向は、今後とも継続することが見込まれています。
*1 15歳以上の世帯員のうち、ふだん仕事として主に自営農業に従事している者
(スマート農業技術等の生産性向上等に資する技術革新が進展)

ドローンを活用した農薬散布
資料:ヤマハ発動機株式会社
情報通信技術の進展やこれを支える通信インフラの整備等が進んだことを背景に、ロボット、AI(*1)(人工知能)、IoT(*2)等の先端技術やデータを活用したスマート農業技術といった農業の生産性向上等に資する技術革新が見られています。
今後、農業者の減少が見込まれる中、食料の供給基盤の維持を図っていくとともに、生産性の高い農業を確立するためには、デジタル変革の進展を踏まえ、スマート農業を一層推進していくことが重要です。
令和元(2019)年度からスマート農業実証プロジェクトを全国217地区で推進し、作業時間の大幅な削減効果が明らかになったほか、草刈り等の危険な作業や重労働からの解放、水田の水管理や家畜の体調管理等の現場のはり付きからの解放といった効果、環境負荷低減によるみどり戦略の実現への貢献を確認しています。一方で、スマート農業機械等の導入コストの高さやそれを扱える人材の不足、従来の栽培方式にスマート農業技術をそのまま導入してもその効果が十分に発揮されないこと、スマート農業技術の開発が不十分な領域があり開発の促進を図る必要があること等の課題が判明しました。
*1 Artificial Intelligenceの略
*2 Internet of Thingsの略で、モノのインターネットのこと
(人口減少下においても食料の安定供給を担う農業経営体の育成・確保が重要)
農業者が大幅に減少することが予想される中で、今日よりも相当程度少ない農業経営体で国内の食料供給を担う必要が生じています。
今後、離農者の農地の受け皿となる経営体や付加価値の向上を目指す経営体が食料供給の大宗を担うことが想定されることから、これらの経営体への農地の集積・集約化に加え、安定的な経営を行うための経営基盤の強化や限られた資本と労働力で最大限の生産を行うための生産性の向上が求められています。
また、昨今普及しつつあるスマート農業技術や新品種を活用し、生産性を重視する農業経営が必要となっています。
(8)農村における地域コミュニティの維持や農業インフラの機能確保
(農村人口の減少、集落の縮小により農業を支える力が減退)
我が国の農村では都市に先駆けて人口減少・過疎化が進んできました。
その結果、集落機能の維持に支障を来す事態も生じており、集落内の戸数が9戸以下になると用排水路の管理や農地の保全等の集落が担ってきた共同活動が著しく減退するといった状況も見られています(図表 特2-15)。
農村人口の減少や集落機能の低下は食料安全保障上のリスクとして認識されるべき課題となっています。
(農村における地域コミュニティの維持や農業インフラの機能確保が重要)
農村の人口減少は、これまで、農村から都市への人口流出による社会減を主として想定していたため、このような社会減が原因の人口減少に対しては、都市との生活環境の格差の是正により、農村からの人口流出を押しとどめる対策が有効と考えられてきました。しかしながら、過疎地域では、特に中山間地域(*1)での高齢化が顕著であること等を背景として、平成21(2009)年度以降、社会減より自然減が大きくなっています(図表 特2-16)。このため、今後、農村への移住等により社会減が一定程度緩和されたとしても、それを上回る規模で自然減が進行することが予想されています。農村でも人口減少が特に著しい地域では、集落の存続が危惧されており、これまで集落の共同活動により支えられてきた農業生産活動の継続が懸念される状況となっています。
このため、農業以外の産業との連携の強化、農村における生活利便性の向上等により、都市から農村への移住、都市と農村の二地域居住の増加促進のほか、都市農業や農泊等を通じ、都市住民等と農業・農村との関わりを創出し、農村地域の関係人口である「農村関係人口」の拡大・深化により、農村コミュニティの集約的な維持を図っていくことが重要となっています。
一方、都市からの移住等は、農村の人口減少を完全に充足できるわけではなく、農村の人口減少は避けられない状況にあります。各地域では、それぞれが置かれている状況等を踏まえ、地域農業を維持する方策を考える必要があります。その際、特に農村に一定の住民がいることを前提にこれまで地域で支えてきた用排水路や農道といった末端の農業インフラの保全管理等への対応を考える必要があります(図表 特2-17)。
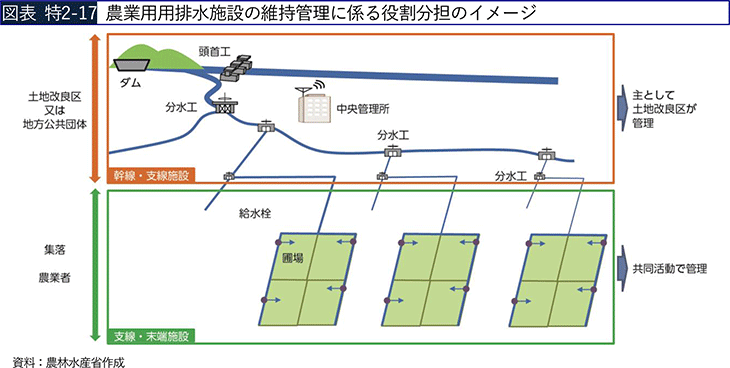
*1 第4章第6節を参照
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883