第3節 食料・農業・農村基本法の見直しに向けて
(1)食料・農業・農村政策の新たな展開方向
(「食料・農業・農村政策の新たな展開方向」を決定)
食料安定供給・農林水産業基盤強化本部では、令和5(2023)年6月に、現行基本法の見直しに当たり、特に基本的施策の追加又は見直しが必要となっている事項について、政策の方向性を整理した「食料・農業・農村政策の新たな展開方向」を決定し、(1)平時からの国民一人一人の食料安全保障の確立、(2)環境等に配慮した持続可能な農業・食品産業への転換、(3)人口減少下でも持続可能で強固な食料供給基盤の確立という新たな三つの柱に基づく政策の方向性を明らかにしました(図表 特3-1)。
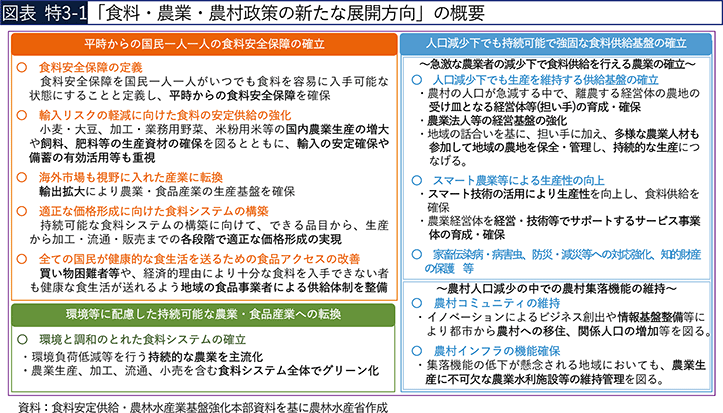
(食料・農業・農村基本法の改正の方向性を取りまとめ)
食料安定供給・農林水産業基盤強化本部は、令和5(2023)年12月に「食料・農業・農村基本法の改正の方向性について」を策定するとともに、「食料・農業・農村政策の新たな展開方向」に基づく施策の工程表を策定し、食料・農業・農村基本法の改正内容を実現するために必要な関連法案やその他の具体的な施策について取りまとめました。今後、令和7(2025)年には次期食料・農業・農村基本計画を策定し、工程表に基づいて施策の進捗管理を行うこととしています。
(ア) 食料安全保障の在り方
(国民一人一人の食料安全保障を確立)
食料安全保障について、基本理念において柱として位置付け、全体としての食料の確保に加えて、国民一人一人が食料にアクセスでき、健康な食生活を享受できるようにすることを含むものへと再整理することとしています。
その際、農地・水等の農業資源、担い手、技術等の生産基盤が強固なものであることは食料安全保障の前提である旨を位置付けるとともに、食料システムを持続可能なものとするため、国・地方公共団体・農業者・事業者・消費者が一体となって取組の強化を進めることとしています。
(食料安全保障の状況を平時から評価する仕組みを検討)
食料安全保障の確立の観点から、現状の把握、分析を行うには、英国の食料安全保障報告書が参考になります。同報告書はテーマとして、(1)世界の食料供給能力、(2)英国の食料供給源、(3)フードサプライチェーンの強靱性(きょうじんせい)、(4)家庭レベルの食料安全保障、(5)食品の安全性と消費者の信頼の五つが設定され、テーマごとの指標、ケーススタディで構成されています。また、指標ごとに現状を分析するレポートの作成が義務付けられています。
(フォーカス)英国では、食料安全保障に係る報告書を作成し、議会に報告
英国では、EU離脱後の同国の農業政策の法的な基礎を規定するものとして、令和2(2020)年11月に「農業法2020」が法制化されており、同法に基づき、食料安全保障の報告書の作成や、農産物の購入者への公正取引義務等が位置付けられています。
同法第19条では、国務大臣は、少なくとも3年に1度、英国の食料安全保障に係る統計データの分析を含む報告書を作成し、議会に提出しなければならない旨が規定されています。また、同条に基づき報告書で分析されるデータは、(1)世界の食料供給能力、(2)英国の食料供給源、(3)フードサプライチェーンの強靱性、(4)家庭レベルの食料安全保障、(5)食品の安全性と消費者の信頼に関するものを含むことができるとされています。
Defra(*)(環境・食料・農村地域省)の責任の下、令和3(2021)年に公表された「英国食料安全保障報告書2021」においては、人口増加と対比させた世界の農業・食料生産に関するトレンド、気候変動やその他の要因による食料生産への影響、労働・水・肥料等の農業生産上の鍵となる投入要素の状態についての検証、英国が世界の食料市場にアクセスする上で重要となる世界の食料貿易のトレンド等について分析しています。その上で、国内生産だけでなく世界市場から食料を調達することは、英国の食料の強靱性に貢献していると評価する一方、世界貿易への過度な依存は、食料供給を世界的なリスクにさらす可能性があるとも指摘しています。
* Department for Environment, Food and Rural Affairs の略
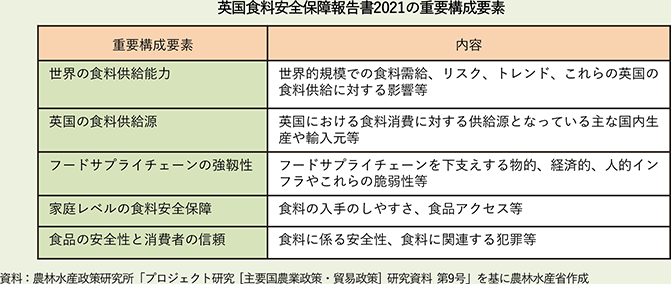
農林水産省では、英国等の先進的な事例も参考とし、様々な指標を活用・分析することにより、我が国の食料安全保障の状況を定期的に評価する仕組みを検討することとしています。
また、食料自給率やその他の食料安全保障の確保に関する事項の目標を定め、目標の達成状況を少なくとも毎年一回調査し、その結果を公表するなど、目標の達成状況を踏まえてPDCAを回す新たな仕組みの導入を検討することとしています。
(不測時における食料安全保障の対応を強化)
世界的な食料需給の変化や生産の不安定化等により、我が国の食料安全保障上のリスクが高まっている中、食料供給が大幅に減少する不測の事態への対応が必要となっています。このため、政府は、令和5(2023)年8月に、生産・流通・消費や法律・リスク管理等の幅広い分野の有識者や関係省庁から成る「不測時における食料安全保障に関する検討会」を立ち上げ、不測の事態への対応について法的な根拠の整理や必要な対策の検討等を行いました。
同検討会では、その基本的な考え方として、(1)農業者を始めとする事業者の自主的な取組を基本とすること、(2)食料の供給不足が予想される段階から対策を講じ、食料供給不足が国民生活や国民経済に与える影響を早期に防止すること、(3)食料の供給確保対策は、事態の進行に合わせて段階的に追加していくこと等を整理し、同年12月に取りまとめました。
これを受け、政府は、米穀、小麦、大豆その他の国民の食生活上又は国民経済上重要な食料の供給が大幅に不足し、又は不足するおそれが高い事態に対応するため、食料供給困難事態対策本部の設置、当該食料等の安定供給の確保のための出荷若しくは販売の調整又は輸入若しくは生産の促進の要請等の措置を定める「食料供給困難事態対策法案」を第213回通常国会に提出したところです(図表 特3-2)。
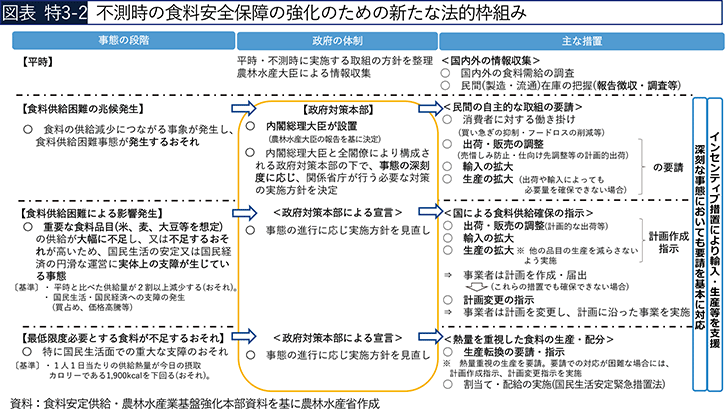
(イ) 食料の安定供給の確保
(食料の安定供給の確保に向けた構造転換を推進)
国内の農業生産の増大を図ることを基本に、輸入・備蓄を行うという食料安定供給の基本的考え方は堅持することとしています。そのため、小麦や大豆、飼料作物といった海外依存度の高い品目の生産拡大を推進するなどの構造転換を進めていくこととしています。
また、食料安定供給を図る上での生産基盤等の重要性、国内供給に加えて輸出を通じた食料供給能力の維持、安定的な輸入・備蓄の確保といった新たな視点も追加し、輸入相手国の多角化や輸入相手国への投資の促進等についても位置付けることとしています。
さらに、農業生産に不可欠な資材である肥料について、主要な原料の大部分を海外に依存する化学肥料の使用量の低減に向けて、堆肥・下水汚泥資源等の国内資源の利用拡大や適正施肥等の構造転換を進めていくこととしています。飼料については、飼料作物を含めた地域計画の策定を促進するとともに、耕畜連携や飼料生産組織の強化等の取組を進め、国産飼料の生産・利用拡大を図っていくこととしています。
くわえて、農業生産資材について、その安定確保の視点を加えるとともに、農業生産資材の価格高騰に対する農業経営への影響緩和の対応も明確化することとしています。
(輸出促進を国内の農業生産基盤の維持に不可欠なものと位置付け)
人口減少に伴い国内市場が縮小する中で、輸出の促進については、国内の農業生産基盤の維持を図るために不可欠なものとして政策上位置付けることとしています。
その際、農業者等へ真に裨益(ひえき)するよう、地域ぐるみで海外の規制・ニーズに対応した生産・流通へ転換することにより、高い付加価値を創出する輸出産地の形成を進めるとともに、マーケットインの発想の下、輸出促進法(*1)に基づく認定農林水産物・食品輸出促進団体の取組や輸出支援プラットフォームによる支援の強化等により、生産から加工、物流、販売までのサプライチェーン関係者が一体となった戦略的な輸出の体制の整備・強化を行うこととしています。あわせて、育成者権管理機関の取組を推進すること等により、海外への流出防止や競争力強化等に資する知的財産等の保護・活用の強化等の施策を講じることとしています。
*1 正式名称は「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律」
(合理的な価格の形成に向けた対応を推進)
食料の合理的な価格の形成に当たっては、農業者、食品事業者、消費者といった関係者の相互理解と連携の下に、農業生産等に係る合理的な費用や環境負荷低減のコストといった食料の持続的な供給に要する合理的な費用が考慮されるようにしなければならないことを明確化することとしています。
その上で、食料の持続的な供給の必要性に対する国民理解の増進や、関係者による食料の持続的な供給に要する合理的な費用の明確化の促進、消費者の役割として持続的な食料供給に寄与すること等を明確化することとしています。
また、農林水産省では、令和5(2023)年8月に、生産者、製造事業者、流通事業者、小売事業者、消費者等から成る食料システムの各段階の関係者の協議の場として「適正な価格形成に関する協議会(*1)」を設立しました。本協議会では、生産から消費に至る食料システム全体で適正取引が推進される仕組みの構築を検討しており、合理的な価格の形成について、生産から消費までの関係者の理解醸成を図ることとしています。
*1 第1章第4節を参照
(全ての国民が健康的な食生活を送るため、円滑な食品アクセスの確保を推進)
全ての国民が健康的な食生活を送ることができるよう、円滑な食品アクセスの確保を図るため、産地から消費地までの幹線物流について、関係省庁と連携し、パレット化や検品作業の省力化、トラック予約システムの導入、鉄道や船舶へのモーダルシフト、中継共同物流拠点の整備等を促進することとしています。さらに、関係省庁と連携し、物流の生産性向上に向けた商慣行の見直しや物流標準化・効率化の推進、荷主企業等の行動変容を促す仕組みの導入等を進めることとしています。
また、消費地内での地域内物流、特に中山間地域でのラストワンマイル物流について、関係省庁と連携しながら、地方公共団体、スーパーマーケット、宅配事業者等と協力し、食品アクセスを確保するための仕組みを検討することとしています。
くわえて、福祉政策、孤独・孤立対策等を所管する関係省庁と連携し、物流体制の構築、寄附を促進する仕組みといった生産者・食品事業者からフードバンク、こども食堂等への多様な食料の提供を進めやすくするための仕組みを検討することとしています。
(事例)移動販売による買い物支援と併せ、高齢者の見守り活動を実施(島根県)


移動販売車「ともに号」
資料:NPO法人ともに

ともにマーケット
資料:NPO法人ともに
島根県奥出雲町(おくいずもちょう)の「NPO法人ともに」では、買い物支援の取組として、食料品や日用品を購入できるスーパーマーケットを運営するほか、移動販売事業を実施しています。販売品目は、利用者からの要望を基に生鮮食品を始め食料品全般を取り扱っています。
同町の三沢(みざわ)地区では、地域内の商店が閉店したことに伴い、平成31(2019)年4月から地域住民が食料品や日用品を販売する「買い物サロン」を開始しました。その後、利用者から多様な品揃えを求められたことを受けて、令和3(2021)年7月に販売品目を見直し、「ともにマーケット」をオープンしました。
また、同年10月に開始した移動販売事業については、冷蔵・冷凍庫を完備した移動販売車「ともに号」に、ドライバーと見守り活動を行うスタッフが同乗し、食料品の販売を行っています。販売は地域の約80軒を対象とし、週に1回ずつ5地区を巡回しています。移動販売訪問時には、ゴミ捨てや電球の付替え等の生活上の小さな困り事の解決も請け負っています。
同地区では、当該事業の運営に地域住民が参画することで雇用の創出につながっているほか、移動販売事業と併せて見守り活動を実施することで、高齢者の様子や健康面等について定期的に確認することが可能になっています。
同法人では、今後とも買い物困難者が増加することを見据え、行政の支援も受けながら、事業の継続・強化を図っていくこととしています。
(ウ) 環境負荷低減に向けた取組の強化
(環境と調和のとれた食料システムの確立を位置付け)
農業者、食品事業者、消費者等の関係者の連携の下、生産から加工、流通・販売まで食料システムの各段階で環境負荷の低減を図ることが重要であることを踏まえ、環境と調和のとれた食料システムの確立を図っていく旨を柱として政策上位置付けることとしています。
その際、農業・食品産業における環境への負荷の低減に向けて、令和4(2022)年7月に施行された「みどりの食料システム法(*1)」に基づいた取組の促進を基本としつつ、最低限行うべき環境負荷低減の取組を明らかにし、各種支援の実施に当たっても、そのことが環境に負荷を与えることにならないよう、補助金の支給要件として最低限行うべき環境負荷低減の取組を義務化するクロスコンプライアンスの導入とともに、先進的な環境負荷低減の取組の支援について検討することとしています(図表 特3-3)。
また、食料システム全体で環境負荷低減の取組を進めやすくなるよう、環境負荷低減の取組の「見える化」の推進、脱炭素化の促進に向けたJ-クレジット制度等の活用、食品事業者等の実需者との連携や消費者の理解の醸成に係る施策を講ずることとしています。
このほか、食品産業についても、食料供給等に向けて重要な役割があり、より主体的な取組が期待される中で、その持続的な発展に向けた施策について明確化することとしています。
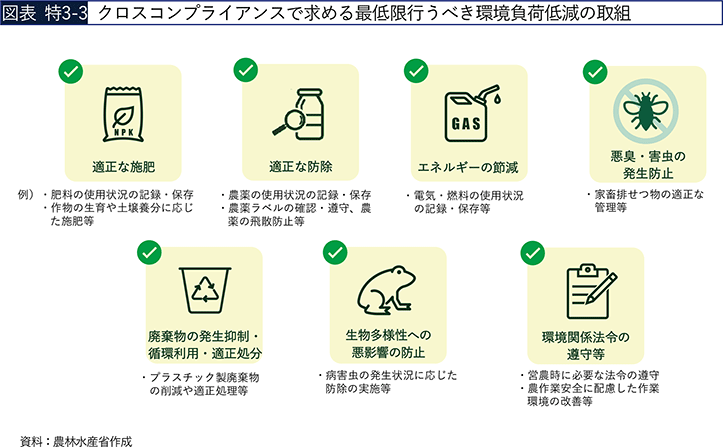
*1 特集第2節を参照
(事例)直販事業者との契約栽培により安定的な有機農業を実現(群馬県)


地域資源を活用した土づくり
資料:くらぶち草の会

有機農業の指導を
受ける新規就農者
資料:くらぶち草の会
群馬県高崎市(たかさきし)の農業者グループである「くらぶち草(くさ)の会(かい)」では、同市倉渕(くらぶち)地区で環境負荷低減に資する取組を推進するとともに、人材の確保・育成等の取組に注力し、安定的な有機農業を実現しています。
同グループは、令和5(2023)年9月時点で41人の会員で構成され、約71haの農地で、レタス、キャベツ等の50品目以上の野菜を、農薬や化学肥料に頼らずに栽培し、販売事業者との契約に基づく計画生産により、安定した所得を確保しています。
有機栽培は「土づくり」を基礎とし、家畜ふん尿やコーヒーかす等の地域資源を活用した堆肥を利用しています。また、研修会を実施し、地域全体での技術を底上げすることで、ベテランの有機農業者は慣行と同程度の収量を、地域全体でも慣行比約8割の安定した生産を実現しています。収穫後は、会員の共同出資により設置した予冷・集出荷施設で、野菜の鮮度維持を図りつつ、ロットの確保による効率的な出荷を実現しています。
さらに、同市では、同地区に滞在型の研修施設を整備し、安心して生産から出荷調整まで学べる環境を整備しているほか、就農相談会等を開催し、関心を示した就農希望者に対して農業体験を実施することにより、人材の確保に積極的に取り組んでいます。研修中は、生産から出荷に係る技術に加え、農地や空き家の確保、地域住民との交流等も積極的に支援しています。くわえて、研修後も、新規就農者を頻繁に訪問し、孤立させないよう手助けするとともに、販路開拓は同グループが担うことで、新規就農者が生産に集中できる環境を整備しています。
同グループでは、令和6(2024)年4月を目途に2人の農業者がみどりの食料システム法に基づく計画の認定を受ける予定となっており、今後とも技術の向上に努めながら、直販事業者との契約栽培や新規就農支援等の取組を推進していくこととしています。
(エ) 農業の持続的な発展
(農業の持続的発展に向けた取組を推進)
農業について、人口減少等の諸情勢が変化する中においても、農産物の供給機能や多面的機能が発揮されるよう、効率的かつ安定的な農業経営の育成・確保を引き続き図ることとしています。
また、スマート農業技術や新品種の開発等を通じた生産性向上、知的財産の保護・活用等を通じた付加価値向上といった農業を持続的に発展させるための政策の方向性を位置付けることとしています。
さらに、人材の育成・確保に加えて、農業法人の経営基盤の強化や農業支援サービス事業体の育成・確保も位置付けることとしています。
(多様な農業者を育成・確保)
今後、人口減少が避けられない中で、食料の生産基盤を維持していくためには、中長期的に農地の維持を図ろうとする者を地域の大切な農業人材として位置付けていくことが必要です。その上で、生産水準を維持するためには、「受け皿となる経営体と付加価値向上を目指す経営体(効率的かつ安定的な経営体)」が円滑に生産基盤を継承できる環境の整備が不可欠です。このため、受け皿となる経営体と付加価値向上を目指す経営体を育成・確保しながら、多様な農業者とともに生産基盤の維持・強化が図られるよう、新規就農の推進を始めとして、将来の農業人材の育成・確保を図ることとしています。
(農地の確保と適正・有効利用を推進)
目標地図を含む「地域計画(*1)」に基づき、目標地図上の受け手に対する農地の集約化等を着実に進めるほか、世界の食料事情が不安定化する中で、我が国の食料安全保障を強化するため、国が責任を持って食料生産基盤である農地を確保するとともに、その適正かつ効率的な利用を図る必要があります。
政府は、我が国の食料及び農業をめぐる諸情勢の変化に鑑み、国民に対する食料の安定供給を確保するため、国及び都道府県において確保すべき農用地の面積の目標の達成に向けた措置の強化、農地の違反転用に対する措置の強化、農地所有適格法人の食品事業者等との連携による経営の発展に関する計画認定制度の創設等の措置を講ずることを内容とする「食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律案」を第213回通常国会に提出したところです(図表 特3-4)。
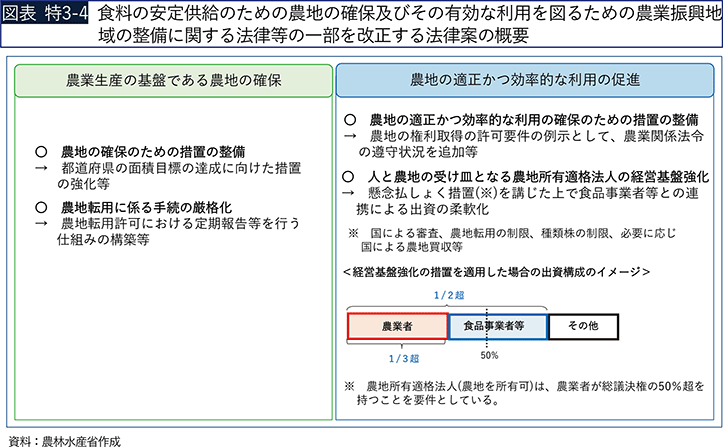
*1 トピックス1を参照
(農業生産基盤の整備や適切な保全に向けた取組を推進)
農業者が減少する中で、スマート農業技術等を活用した営農が進めやすくなるよう、圃場(ほじょう)の一層の大区画化やデジタル基盤の整備を推進すること等により、農地の受け皿となる者への農地の集積・集約化を促進することとしています。このほか、需要に応じた生産を促進するため、水田の汎用化に加えて、水田の畑地化を推進することとしています。
また、農業生産基盤の整備については、災害の頻発化・激甚化が顕著となる中、災害の防止・軽減を図るためにも行う旨や、施設の老朽化等が進む中、人口減少により施設の点検・操作や集落の共同活動が困難となる地域でも生産活動が維持されるよう、農業水利施設等の農業生産基盤の保全管理も適切に図っていく必要がある旨を、それぞれ位置付けるとともに、必要な事業や仕組みの見直し等も行うこととしています。
さらに、農業生産基盤の保全管理に当たって、頭首工(とうしゅこう)等の基幹施設については省エネルギー化や再生可能エネルギーの利用、集約・再編、ICT(*1)(情報通信技術)等の新技術活用等を、用水路等の末端施設については開水路の管路化、畦畔(けいはん)拡幅、法面(のりめん)被覆等を、それぞれ推進することとしています。
*1 Information and Communication Technologyの略
(スマート農業技術の導入による生産性の高い農業への転換を推進)
政府は、農業の生産性の向上を図るため、スマート農業技術の活用及びこれと併せて行う農産物の新たな生産の方式の導入に関する計画並びにスマート農業技術等の開発及びその成果の普及に関する計画の認定制度を設け、これらの認定を受けた者に対する株式会社日本政策金融公庫(にっぽんせいさくきんゆうこうこ)(以下「公庫」という。)による貸付けの特例等の措置を講ずることを内容とする「農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律案」を第213回通常国会に提出したところです(図表 特3-5)。
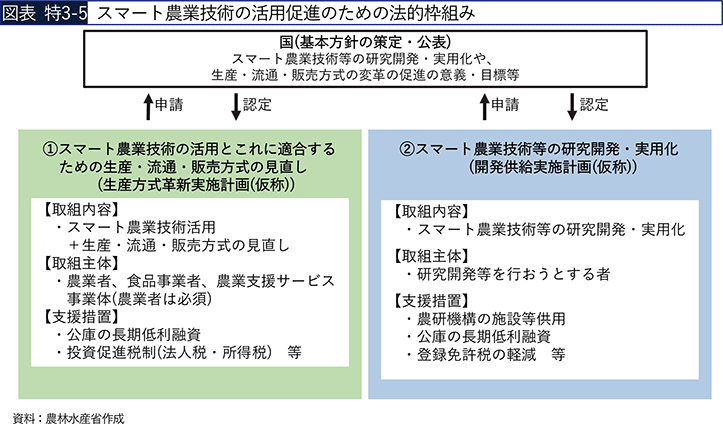
また、スマート農業技術の導入効果を十分に発揮するため、生産現場において、スマート農業技術の活用を支援する農業支援サービス事業体等と連携しながら、スマート農業技術に適合した栽培体系の見直し等の生産・流通・販売方式への転換を促進することとしています(図表 特3-6)。
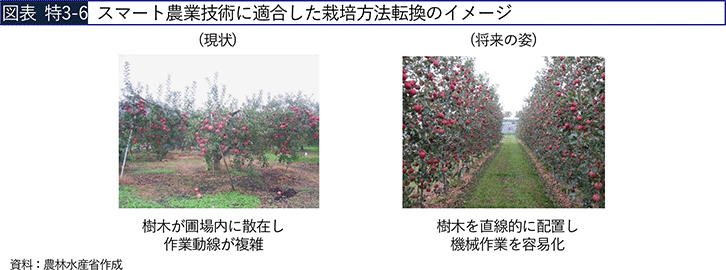
(事例)圃場規格の整備と高畝栽培での自動収穫ロボットの開発を推進(神奈川県)


通路幅の広い高畝栽培の圃場
資料:inaho株式会社

アスパラガスの
自動収穫ロボット
資料:inaho株式会社
神奈川県鎌倉市(かまくらし)のinaho(イナホ)株式会社では、人手による作業を前提とした栽培方式の変革に向け、高畝栽培の改良・普及とアスパラガスを自動収穫するロボットを開発しており、少人数でより大きな面積に対応できる栽培方式の実現を目指しています。
アスパラガス栽培においては、従来の平畝栽培では、圃場内の茎葉の密度が高く、機械導入による栽培管理が困難であるほか、一本一本目視で確認しながらの人手による収穫作業となり、生産性の向上に結び付かないことが課題となっています。
このため、同社では、通路幅が広く、機械導入・栽培管理が容易になる圃場規格の整備とアスパラガス自動収穫ロボットの開発を一体的に進めています。高畝栽培で自動収穫ロボットを用いると、平畝栽培と比較して、作業時間が約5分の1に短縮することが確認されています。また、推奨圃場規格においては、春芽で80%、夏芽で65%の収穫を達成しています。
同社では、令和2(2020)年度からは、アスパラガス生産における働き方改革の実現を目指し、枠板式高畝栽培を基盤とした省力安定栽培システムの開発を産学連携で進めています。また、令和3(2021)年からは、自動収穫機の効率的な稼働を目指し、香川県や北海道にて実証導入を行っています。実証圃場では、株当たり3.3本程度の親茎を立てるところ、株当たり2本と疎植栽培にすることにより、自動収穫ロボットがアスパラガスを認識・アクセスすることが容易になることが確認されています。
同社では、今後とも関係機関と連携しながら、収量性と親茎密度の適切な関係性の確認を進め、枠板式高畝栽培の普及に向けた取組を推進し、若手農業者の参入促進を図っていくこととしています。
さらに、スマート農業技術には、開発が不十分な領域があること等の課題を踏まえ、国が主導で実装まで想定した重点開発目標を明確にした上で、これに沿って研究開発等に取り組むスタートアップ等の事業者に対する国立研究開発法人農業(のうぎょう)・食品産業技術総合研究機構(しょくひんさんぎょうぎじゅつそうごうけんきゅうきこう)(以下「農研機構」という。)の施設供用等を通じた産学官連携の強化により研究開発を促進することとしています。
(家畜伝染病、病害虫等への対応を強化)
家畜伝染病や病害虫の侵入・まん延リスクが高まる中で、これらの発生予防・まん延防止等について新たに位置付けるとともに、効果的に動植物検疫を実施する体制や予防を重視した生産現場での防疫体制を構築することとしています。具体的には、(1)家畜防疫官・植物防疫官の体制の充実、ICT技術等の活用による効果的な検疫体制の構築と厳格な水際措置の実施、(2)家畜診療所等における産業動物獣医師の確保、遠隔診療等による適時適切な獣医療の提供、データに基づく農場指導等による飼養衛生管理水準の向上、(3)病害虫発生予測の迅速化・精緻化や防除対策の高度化等による総合防除体系の構築等の施策を講じることとしています。
(オ) 農村の振興
(農村の活性化に向けた取組を推進)
農村に関わりを持つ人材を増やすため、地産地消・6次産業化(*1)や農泊といった地域資源を活用した農山漁村発イノベーションを推進するとともに、関係人口も交えて地域に根ざした経済活動が安定的に営まれるよう、地方公共団体と民間企業の連携による取組の支援を行うこととしています。農村の活性化や地域課題の解決に向けた取組も広がっており、有機農業のブランド化・販路拡大、地域農業の条件に合ったスマート農業技術の導入による農作業の効率化といった事例も見られています。このような取組の拡大に向け、これまで農業・農村に関するビジネスに携わっていなかった事業者と農業・農村の活性化に関わる関係者とのマッチング機会を創出し、課題解決に協力可能な企業を農村に呼び込むこととしています。
また、中山間地域等において複数の集落の機能を補完して、農用地の保全活動や農業を核とした経済活動と併せて、生活支援等地域コミュニティ維持に資する取組を行う組織である農村RMO(*2)の形成を推進することとしています。
さらに、中山間地域等において棚田の振興を始め、地域に「活力」を創出するための社会貢献やビジネスの展開を図る企業の活動を後押しし、企業と地域との相互補完的なパートナーシップの構築を推進することとしています。
くわえて、中山間地域における農地保全のための地域ぐるみの話合い、農地の粗放的な利用、基盤・施設整備等にきめ細やかに取り組めるよう支援し、農村の持続的な「土地利用」を推進することとしています。
*1 第4章第2節を参照
*2 Region Management Organizationの略
(事例)地域課題の解決に向け、農業や観光等の街づくり事業を展開(山形県)

山形県鶴岡市(つるおかし)のYAMAGATA DESIGN(ヤマガタ デザイン)株式会社では、「官民共創」による地域課題の解決に向け、産学官連携による農業人材の育成・確保や観光・教育等の街づくり事業を展開しています。
同社は、庄内(しょうない)地域を拠点に地方都市の課題を希望に変える街づくり会社として、観光、教育、人材、農業の四つの事業で分野横断的な取組を展開しています。
また、同社が令和元(2019)年11月に設立した有機米(ゆうきまい)デザイン株式会社(*)では、有機米のマーケット拡大と有機農業に取り組む農業者の所得向上を目指した活動を推進しています。除草作業を省力化する自動抑草ロボット「アイガモロボ」の開発・製造では全国の農業者や地方公共団体、普及機関と連携し、有機農業の推進に向けた技術実証や有機農産物の販路確保に取り組んでいます。
また、令和4(2022)年8月には、一般社団法人ヴァンフォーレスポーツクラブ及び山梨県北杜市(ほくとし)と包括連携協定を締結し、農業や観光等の振興を始め、子供達を中心とした新たな食育の展開により、循環型社会の形成や地域の活性化を図る取組を推進しています。
さらに、令和5(2023)年8月には、宮城県大崎市(おおさきし)と「持続可能な農業推進に関する協定」を締結し、グリーンな栽培体系への転換に協働で取り組み、世界農業遺産「大崎耕土(おおさきこうど)」での有機農業や環境保全型農業の普及を図る取組を推進しています。
このほか、YAMAGATA DESIGN株式会社では、平成30(2018)年9月に、庄内(しょうない)平野の水田の上に浮かぶように建つホテル「スイデンテラス」を開業し、自社農園で栽培した野菜を用いた料理を始め、地域の魅力を体感できるサービスを提供しており、年間約5万人が宿泊しています。
同社では、「地方の希望であれ」という新たなビジョンを掲げ、令和6(2024)年4月から、創業の地を表す「株式会社SHONAI(ショウナイ)」に社名変更することとしており、庄内という起点を強化しながら、そこで生まれたモデルを通じて日本全国の地方都市の課題を希望に変えるアクションを創発していくこととしています。
* 令和6(2024)年4月から「株式会社NEWGREEN(ニューグリーン)」に社名変更し、農業のグリーン化を通じて農業者の所得を向上する取組を加速化することとしている。

宮城県大崎市との協定式
資料:YAMAGATA DESIGN株式会社

ホテル「スイデンテラス」
資料:YAMAGATA DESIGN株式会社
(農村の振興について、地域社会の維持を図っていく旨を位置付け)
農村振興の政策の方向性について、「基盤整備」、「生活環境整備」の二本柱に加え、農泊の推進等を念頭に農村との関わりを持つ者(農村関係人口)の増加に資する「産業の振興」や多面的機能支払を位置付けることとしています。また、農村RMOの促進を始めとして、中山間地域の振興等を念頭に「地域社会の維持」を図っていくほか、鳥獣害対策や農福連携等について明確化することとしています。
(カ) 多面的機能の発揮
(地域が一体となった共同活動により多面的機能の発揮を促進)
農業・農村は、国土の保全、水源の涵養(かんよう)、良好な景観の形成等の多面的機能を有しており、これを適切かつ十分に発揮させるためにも農業生産活動の継続に加えて、共同活動による地域資源の保全を図ることが重要です。
このため、日本型直接支払制度については、農業・農村の人口減少等を見据えた上で、持続可能で強固な食料供給基盤の確立が図られるよう、具体化を図ることとしています。このうち中山間地域等直接支払制度については、引き続き地域施策の柱として推進するとともに、農業生産活動の基盤である集落機能の再生・維持を図るため、農地保全やくらしを支える農村RMO等の活動を促進する仕組みを検討することとしています。
(事例)大学・企業と連携した棚田保全の取組を推進(香川県)
香川県小豆島町(しょうどしまちょう)の小豆島町(しょうどしまちょう)中山棚田協議会(なかやまたなだきょうぎかい)は、地域の文化や伝統の源である千枚田を守るため、大学・企業と連携した棚田保全の取組を推進しています。
小豆島のほぼ中央の中山間地域に位置する中山(なかやま)地区は、古くから棚田による稲作が行われてきていますが、特に「つなぐ棚田遺産」にも選ばれている「中山千枚田(なかやませんまいだ)」での米作りは、保水や生態系の保全、景観の形成だけにとどまらず、「農村歌舞伎」や「虫送り」等の伝統や文化が蓄積されており、地域文化の軸となっています。
一方、同地区では、地域の過疎化・高齢化の進行により、棚田の荒廃や水循環機能の低下、農作業効率の更なる悪化等のほか、地域文化の伝承にも影響が及んでいることから、地域住民が主体となって同協議会を立ち上げ、中山間地域等直接支払交付金を活用しながら、多様な保全活動を実施しています。
同協議会では、香川大学と連携し、用水路清掃等のボランティア活動や耕作体験、伝統行事への参加を通じて、様々な交流を行っています。大学生によるボランティア活動の受入れ等により、棚田での耕作が地域の活力づくりにつながり、耕作放棄地の解消にも寄与しています。
また、地元酒造会社と連携して、日本酒の原料となる酒米の作付けを平成27(2015)年度から実施しています。休耕田の解消・予防を図るとともに、収穫した酒米を使って醸造した酒を地酒として販売しています。
このような取組の結果、協議会の発足から約10年で水田面積は約1割増加しました。同協議会では、先人達が築き守ってきた美しい棚田と、棚田を中心に培われてきた文化・伝統を後世に残すため、今後とも大学や企業と連携し、担い手の確保、農産物の販売、伝統行事への参加等を促進していくこととしています。


つなぐ棚田遺産
「中山千枚田」

酒米の籾まき作業
資料:小豆島町中山棚田協議会
また、多面的機能支払制度については、草刈りや泥上げ等の集落の共同活動が困難となることに対応するため、市町村も関与して最適な土地利用の姿を明確にし、活動組織における非農業者・非農業団体の参画促進や土地改良区による作業者確保等を図る仕組みを検討することとしています。
さらに、環境保全型農業直接支払制度については、先進的な環境負荷低減への移行期の取組を重点的に後押しするとともに、これらの取組を下支えする農地周辺の雑草抑制等の共同活動を通じて面的な取組を促進する仕組みを検討することとしています。
これらとともに、地域計画を始めとする人・農地関連施策やみどり戦略との調和等を図っていくこととしています。
(2)食料安全保障強化政策大綱の改訂
(食料安全保障強化政策大綱を改訂)
食料安定供給・農林水産業基盤強化本部は、令和4(2022)年12月に、食料安全保障の強化に向けて構造転換を図るため、継続的に講ずべき対策とその目標を明らかにするものとして「食料安全保障強化政策大綱」(以下「政策大綱」という。)を策定しました。

政策大綱の改訂を発表する内閣総理大臣
資料:首相官邸ホームページ
その後、現行基本法の見直しに向けた検討が進められる中で、「食料・農業・農村政策の新たな展開方向」においては、平時から食料安全保障を抜本的に強化するための政策を確立することとされました。これらの食料安全保障の考え方を踏まえ、川上から川下までサプライチェーン全体の強靱化につながる構造転換を集中的に進めていく観点から、令和5(2023)年12月に政策大綱を改訂し、施策の拡充を図りました。
また、政策大綱においては、新しい資本主義の下、農林水産業・食品産業の生産基盤を強固にする観点から、食料安全保障の強化のための対策に加え、スマート農林水産業等による成長産業化、農林水産物・食品の輸出促進、農林水産業のグリーン化についても、改めてその目標等を整理し、その実現に向けた主要施策を取りまとめています。
(3)食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律案の国会提出
(第213回通常国会に食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律案を提出)

食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律案
新旧対照条文
URL:https://www.maff.go.jp/j/council/seisaku
/kensho/attach/pdf/18siryo-5.pdf
政府は、近年における世界の食料需給の変動、地球温暖化の進行、我が国における人口の減少その他の食料、農業及び農村をめぐる諸情勢の変化に対応し、食料安全保障の確保、環境と調和のとれた食料システムの確立、農業の持続的な発展のための生産性の向上、農村における地域社会の維持等を図るため、基本理念を見直すとともに、関連する基本的施策等を定める「食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律案」を、第213回通常国会に提出したところです(図表 特3-7)。
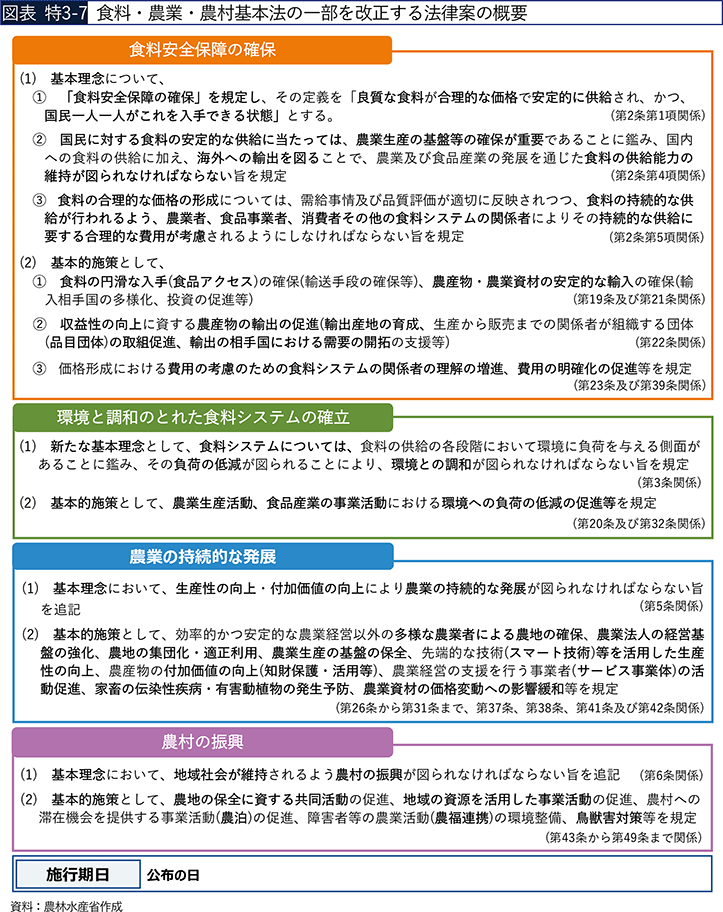
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883




