第2節 農村における所得と雇用機会の確保
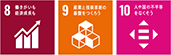
農山漁村を次の世代に継承していくためには、6次産業化の取組に加え、他分野との組合せにより農山漁村の地域資源をフル活用する「農山漁村発イノベーション」の取組により農村における所得と雇用機会の確保を図ることが重要です。
本節では6次産業化、農泊、農福連携(*1)等の農山漁村発イノベーションの取組について紹介します。
1 トピックス6を参照
(1)農山漁村発イノベーションの推進
(6次産業化の取組を発展させた農山漁村発イノベーションを推進)
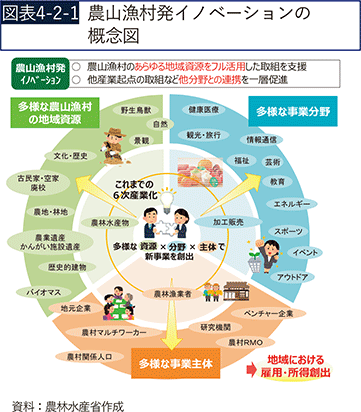

農山漁村発イノベーションの推進
URL:https://www.maff.go.jp/j/nousin/inobe/
農山漁村において人口減少・高齢化が進む中、農林漁業関係者だけで地域の課題に対応することが困難になってきており、これまで農林漁業に携わっていなかった多様な主体を取り込み、農山漁村の活性化を図っていくことが重要となっています。
農山漁村における所得向上に向けては、農林漁業所得と農林漁業以外の所得を合わせて一定の所得を確保できるよう、多様な就労機会を創出していくことが重要であることから、従来の6次産業化の取組を発展させ、農林水産物や農林水産業に関わる多様な地域資源を活用し、観光・旅行や福祉等の他分野と組み合わせて付加価値を創出する「農山漁村発イノベーション」の取組を推進しています(図表4-2-1)。
農林水産省では、農林漁業者や地元企業等多様な主体の連携を促しつつ、商品・サービス開発等のソフト支援や施設整備等のハード支援を行うとともに、全国及び都道府県単位に設けた農山漁村発イノベーションサポートセンター等を通じて、専門家派遣等の伴走支援や企業とのマッチング等を支援しています。また、現場の優良事例を収集し、全国への横展開等を図ることとしています(図表4-2-2)。
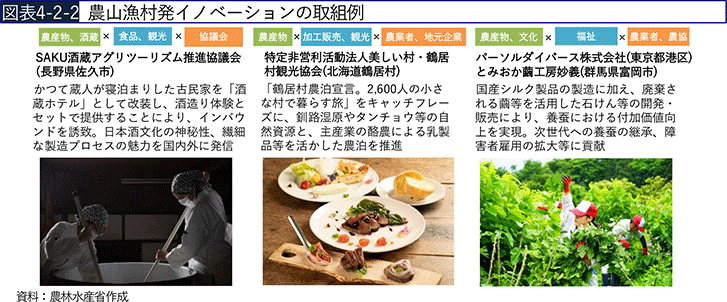
(事例)農山漁村発イノベーションの取組により、多様な事業を展開(岡山県)


いちご農園事業
資料:株式会社エーゼログループ

養蜂事業
資料:株式会社エーゼログループ
岡山県西粟倉村(にしあわくらそん)の地域総合商社である株式会社エーゼログループは、「未来の里山づくり」をテーマとして、地域の農林水産物、廃校、空き家等の様々な地域資源を活用し、その実現に資する取組を、経済資本事業、社会関係資本事業、自然資本事業として展開しています。
このうち自然資本の領域では、いちご農園や養蜂、ジビエのほか、養鰻(ようまん)、レストラン、木材加工流通等の事業を行っています。
いちご農園事業では、木材加工品を製造する過程で発生する樹皮やおが粉等の木くずを培土に使用し、甘みを豊富に蓄えた完熟いちごを栽培し、新鮮な朝採れいちごとして販売するとともに、ジャムや菓子等の加工品の商品化を積極的に進めています。同社では、農園でのいちご摘み体験を開催するとともに、併設するカフェにおいて、いちごをふんだんに使ったスイーツを提供するなど、家族で楽しめる場づくりにも取り組んでいます。
また、養蜂事業については、開墾した荒れ地や借り受けた山林を利用し、季節や場所を変えて採蜜を行うことで、味や香りが異なる蜂蜜作りを行っています。同社では、森から生まれ、森を産み出す自然蜂蜜を目指し、ギフト用として蜂蜜を商品化しているほか、蜂蜜グラノーラの開発・販売にも取り組んでいます。
さらに、ジビエ事業については、猟師と連携しながら、吉井川(よしいがわ)水系の最上流部で育つシカを捕獲し、迅速に処理を行うことにより、鮮度の高い「森のジビエ」として販売しています。
同社では、人や自然の本来の価値を引き出しながら、地域の所得と雇用の機会を確保していくことを目指しており、今後は、これまで蓄積してきたノウハウを活かし、全国各地に事業を展開していくこととしています。
(農山漁村の活性化に向けた起業を支援)
農村地域においては、急激な人口減少に伴う多様な課題がある中で、農村地域を将来にわたって維持していくためには、地域の「しごとづくり」を強化し、雇用や所得を確保する取組を推進していくことが必要です。
農林水産省では、地域資源を活用した多様なビジネスの創出を支援するため、起業促進プラットフォーム「INACOME(イナカム)」の運営を通じて、地域資源を活用したビジネスコンテストの開催、起業支援セミナーの開催、地域課題の解決を望む地方公共団体と企業とのマッチングイベント等の取組を実施しています。
(6次産業化による農業生産関連事業の年間総販売金額は2兆1,765億円)
地域の農林漁業者が、農林水産物等の生産に加え、加工・販売等を行う6次産業化の取組も引き続き推進しています。6次産業化に取り組む農業者等による加工・直売等の販売金額は、近年横ばい傾向で推移しています。令和4(2022)年度の農業生産関連事業の年間総販売(売上)金額は、農産加工等の増加により前年度に比べ1,099億円増加し2兆1,765億円となりました(図表4-2-3)。
また、六次産業化・地産地消法(*1)に基づく総合化事業計画(*2)の認定件数は、令和6(2024)年3月末時点の累計で2,642件となりました。
1 正式名称は「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」
2 六次産業化・地産地消法に基づき、農林漁業経営の改善を図るため、農林漁業者等が農林水産物や副産物(バイオマス等)の生産とその加工又は販売を一体的に行う事業活動に関する計画
(農村への産業の立地・導入を促進)
農林水産省では、農業と産業の均衡ある発展と雇用構造の高度化に向けて、農村地域への産業の立地・導入を促進するため、農村産業法(*1)に基づき、都道府県による導入基本計画、市町村による導入実施計画の策定を推進するとともに、税制等の支援措置の積極的な活用を促しています。
令和5(2023)年3月末時点の市町村による導入実施計画に位置付けられた計画面積は約1万8千haであり、同計画において、産業を導入すべき地区として定められた産業導入地区における企業立地面積は全国で約1万3,800ha、操業企業数は6,886社、雇用されている就業者は約46万人となっています。
1 正式名称は「農村地域への産業の導入の促進等に関する法律」
(地域の稼ぐ力の向上を促進)
近年、特定の地域に拠点を置き、地域の特産品や観光資源を活用した商品・サービスの域外への販売を主たる事業とする「地域商社」と呼ばれる事業体が全国各地で見られており、地域経済の活性化や地域の稼ぐ力の向上に重要な役割を果たしています。
内閣官房及び内閣府では、地域産品の販売等に携わる地域商社やこれから地域商社としての取組を始める者と金融機関等の支援者との連携を促進するため、ポータルサイトを開設し、経営課題の解決に向けた優良事例の横展開や情報共有を支援しています。
また、農林水産省では、平成30(2018)年に「GFP(*1)コミュニティサイト」を立ち上げ、農林漁業者・食品事業者と地域商社の販路拡大支援や商材の紹介等を行っています。
1 第1章第7節を参照
(コラム)農村地域の産品を売り込む地域商社の取組が拡大

栗製品の製造工場
「SHIMANTO ZIGURI FACTORY」
資料:株式会社四万十ドラマ
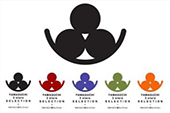
山口県の「山」を家紋風にした
ブランドマーク
資料:地域商社やまぐち株式会社
地域には、十分に活用されていない、あるいは、その価値を評価し得る市場に適切にアクセスできずに価値を発揮できていない地域資源(農林水産品、伝統工芸品、観光資源等)が数多く眠っています。このような地域資源の商材化やその販路開拓を行うことで、従来以上の収益を引き出し、そこで得られた知見や収益を生産者に還元していく地域商社事業の取組が拡大しています。
例えば高知県四万十町(しまんとちょう)の株式会社四万十(しまんと)ドラマは、地域資源を活用した栗・芋・茶等の商品開発のほか、地元生産者・事業者と連携した6次産業化にも取り組む地域商社であり、「ローカル・ローテク・ローインパクト」をコンセプトに、四万十川(しまんとがわ)に負担をかけないものづくりを実践しています。四万十川が有する「豊かな自然」等の良好なイメージをブランドの構築に活用するとともに、消費者の共感を呼ぶストーリーを発信することで、高付加価値の商品開発を行い、「しまんと地栗(じぐり)」等の力強い地域ブランドを育てています。
また、山口県下関市(しものせきし)の地域商社(ちいきしょうしゃ)やまぐち株式会社は、地方銀行が地元企業をサポートするために設立した地域商社であり、金融機関ならではのノウハウを活かした事業を展開しています。同県の産品が持つ小ロット・多品種という特性に対応し、複数の産品を束ね、統一コンセプトでのブランディングにより商品に磨きをかけ、高付加価値化を図るとともに、市場ニーズを的確につかみ、マーケティングを強化することで、首都圏市場と県内生産者を戦略的につなぐ取組を推進しています。
地域商社は、地方創生における「地域の稼ぐ力」向上の担い手として期待されており、政府においても、地域商社事業を地域に育て、根付かせるため、様々な角度から支援活動を行っています。
(2)農泊の推進
(農山漁村の所得向上と関係人口の創出を図る農泊を推進)
近年、農山漁村において農家民宿や古民家を活用した宿泊施設等に滞在し、我が国ならではの伝統的な生活体験や農村の人々との交流を通じて、その土地の魅力に触れる農山漁村滞在型旅行である「農泊」への関心が高まっています。
農林水産省では、農山漁村において「農泊」を持続的なビジネスとして推進し、農山漁村における所得の向上や雇用の増大を図るため、農泊に取り組もうとする地域に対し、体制整備、食事・体験に関する観光コンテンツの開発、古民家を活用した宿泊施設の整備等を支援しており、令和6(2024)年3月末までに全国で656の農泊地域(*1)を創出しています。
農泊を推進する狙いは、古民家・ジビエ・棚田といった農山漁村ならではの地域資源を活用した様々な観光コンテンツを提供し、農山漁村への長時間の滞在と消費を促すことにより、農山漁村における「しごと」を作り出し、持続的な収益を確保して地域に雇用を生み出すとともに、農山漁村への移住・定住も見据えた関係人口の創出の入口とすることにあります。
1 農山漁村振興交付金による農泊推進の支援に採択され、農泊に取り組んでいる地域
(農泊地域の延べ宿泊者数はコロナ禍以前を上回る水準)
令和4(2022)年度における農泊地域の延べ宿泊者数は、前年度に比べ163万人泊増加し611万人泊となり、コロナ禍以前を上回る水準となりました(図表4-2-4)。また、訪日外国人旅行者の延べ宿泊者数は前年度に比べ14万人泊増加し15万人泊となりましたが、依然としてコロナ禍以前の水準を下回っています。
政府の観光立国推進基本計画においては、「日本人の地方部延べ宿泊者数を3.0億人泊から3.2億人泊に約5%増」、「訪日外国人旅行者数の2019年水準超え」を目指していることから、農泊地域においても、新規に農泊に取り組む地域や訪日外国人旅行者の需要の増加を考慮して、令和7(2025)年度までに700万人泊とすることを目標としています。
(事例)「舟屋」の活用や「泊食分離」のビジネスモデル確立で農泊を推進(京都府)
京都府伊根町(いねちょう)の伊根浦地区農泊推進地区協議会(いねうらちくのうはくすいしんちくきょうぎかい)では、船の収納庫の上に居住スペースを備えた「舟屋(ふなや)」と呼ばれる建築物の活用や「泊食分離」のビジネスモデルの確立を進め、農泊の取組拡大を図っています。
同町では、空き家となっている舟屋を改修し、宿泊施設として開設する事業をリーディングモデルとして実施しており、地元の観光協会が運営を行っています。さらに、地域住民による新たな宿泊施設の開設には、食事提供が課題の一つとなっているため、同町が飲食施設を整備すること等により、泊食分離を推進しています。
また、観光協会は、国内外の宿泊予約に対応できるよう宿泊予約サイトの構築を行い、舟屋での宿泊と漁港ならではの旅行商品を販売する窓口として機能するとともに、インバウンド対応や宿泊予約の取次ぎを行っています。
このような取組により、令和4(2022)年の延べ宿泊者数は1万2,923人となり、平成29(2017)年の約2.1倍となっています。また、令和4(2022)年の宿泊消費額は約1億9千万円となっており、平成29(2017)年の約2.3倍となっています。
同協議会では、もともとの町の暮らしを保存し、地域ならではの海や山を活用した体験の提供を重視しながら、町の規模や民宿数を踏まえ、受入れ可能な範囲でプロモーションを展開していくこととしています。


舟屋の町並み
資料:伊根浦地区農泊推進地区協議会

舟屋を活用した宿泊施設
「伊根舟屋ステイ海凪」
資料:伊根浦地区農泊推進地区協議会
(農泊推進実行計画を策定)
コロナ禍以降の地域状況や観光需要の変化を踏まえ、これからの農泊推進の方向性について検討するため、有識者から構成される「農泊推進のあり方検討会」が開催され、令和5(2023)年6月に、農泊推進の取組の方向性を取りまとめた「農泊推進実行計画」が策定されました。
同計画では、地域自身が、地域の持続的な自立に資する事業を起こすことを目指す起業家精神「農山漁村アントレプレナーシップ」を持ち、「新規来訪者の獲得」、「来訪1回当たり平均泊数の延長」、「来訪者のリピーター化」に取り組むとともに、農林水産省が都道府県・事業者等と連携して広域的な課題解決に向けた支援を企画・実施することを通じ、目標の達成と農山漁村地域の持続性確保を目指すこととしています。
(3)農福連携の推進
(農福連携等応援コンソーシアムによる全国展開に向けた普及・啓発を推進)
農林水産省では、厚生労働省等の関係省庁と連携して、国・地方公共団体、関係団体等のほか、経済界や消費者等の様々な関係者が参画する「農福連携等応援コンソーシアム」による取組の輪の拡大や農業現場において障害者が働きやすい環境整備等に取り組んでいます。
同コンソーシアムは、イベントの開催、連携・交流の促進、情報提供等の国民的運動を通じた農福連携の普及・啓発を展開しています。また、農福関連の商品の価値をPRするノウフクマルシェや現場の課題解決を図るノウフク・ラボ等の取組を実施するとともに、令和6(2024)年2月には、農福連携に取り組む団体、企業等の優良事例24団体を「ノウフク・アワード2023」において表彰しました(図表4-2-5)。
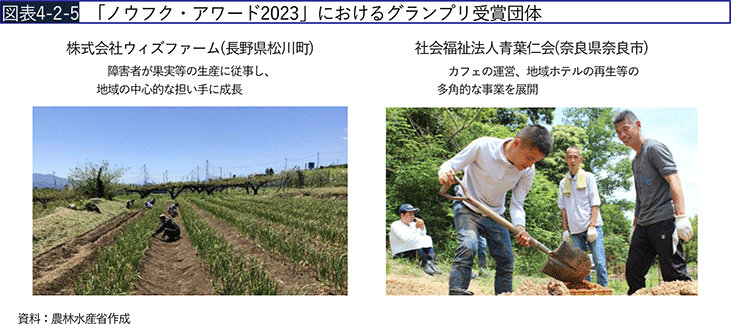
(初めての試みとしてノウフクウィークの取組を実施)

ノウフクウィークを
呼び掛けるポスター
農福連携の取組が全国に広がり、各地で定着していくためには、農福連携の取組が一般に広く認知され、農福連携で生産された商品が消費者や企業に選ばれるような環境を作ることが重要です。農林水産省では、農福連携等応援コンソーシアムによる「ノウフク・アワード」において、これまでの4年間で延べ88件(40都道府県)の優良事例を表彰し、各地に横展開すること等を通じて、認知度の向上に努めています。また、令和5(2023)年10月に、初めての試みとして、農福連携に関するマルシェやフォーラム等のイベントを集中的に行う「ノウフクウィーク」の取組を、農福連携の事業者等と連携して全国30か所で実施しました。
今後とも消費者や企業を巻き込みながら、国民的運動として農福連携を推進していくことが重要となっています。
(多世代・多属性の利用者が交流・参画するユニバーサル農園の整備・利用を推進)

ユニバーサル農園での農業体験
資料:特定非営利活動法人たかつき
「ユニバーサル農園」は、農業体験活動を通じて様々な社会的課題を解決するための取組であり、子供から高齢者までの多世代・多属性の者に対して、農業体験活動を通じた交流・参画する場の提供、高齢者や障害者の健康増進や生きがいづくり、精神的な不調を抱える若年層等の精神的健康の確保、生きづらさ・働きづらさを抱える者への職業訓練の場の提供等を目指すものです。このような取組を通じて、障害者等における農業現場での雇用・就労に対する意欲の高まりや農地の利用の維持・拡大効果も期待されています。
農林水産省では、障害者等の農林水産業に関する技術習得、障害者等が作業に携わる生産・加工・販売施設の整備への支援に加え、農業分野への就業を希望する障害者等に対し農作業体験を提供するユニバーサル農園の開設について支援を行っています。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883







